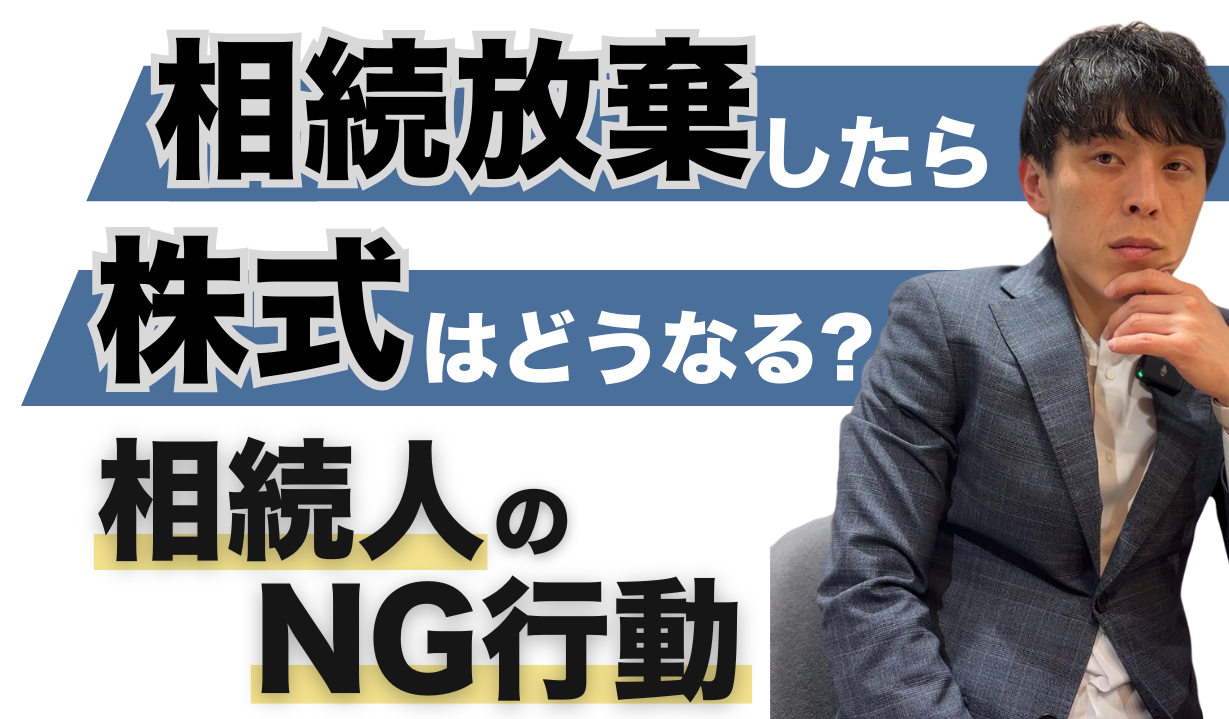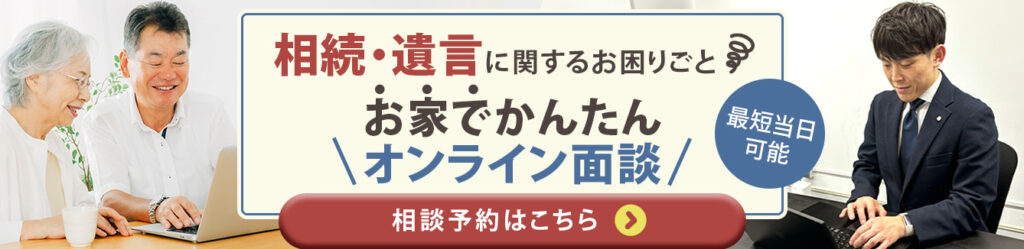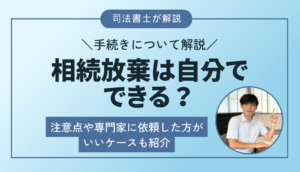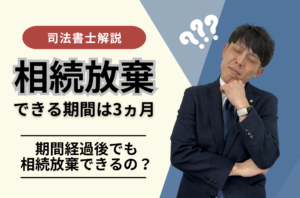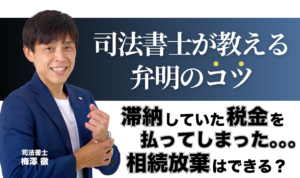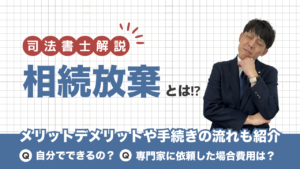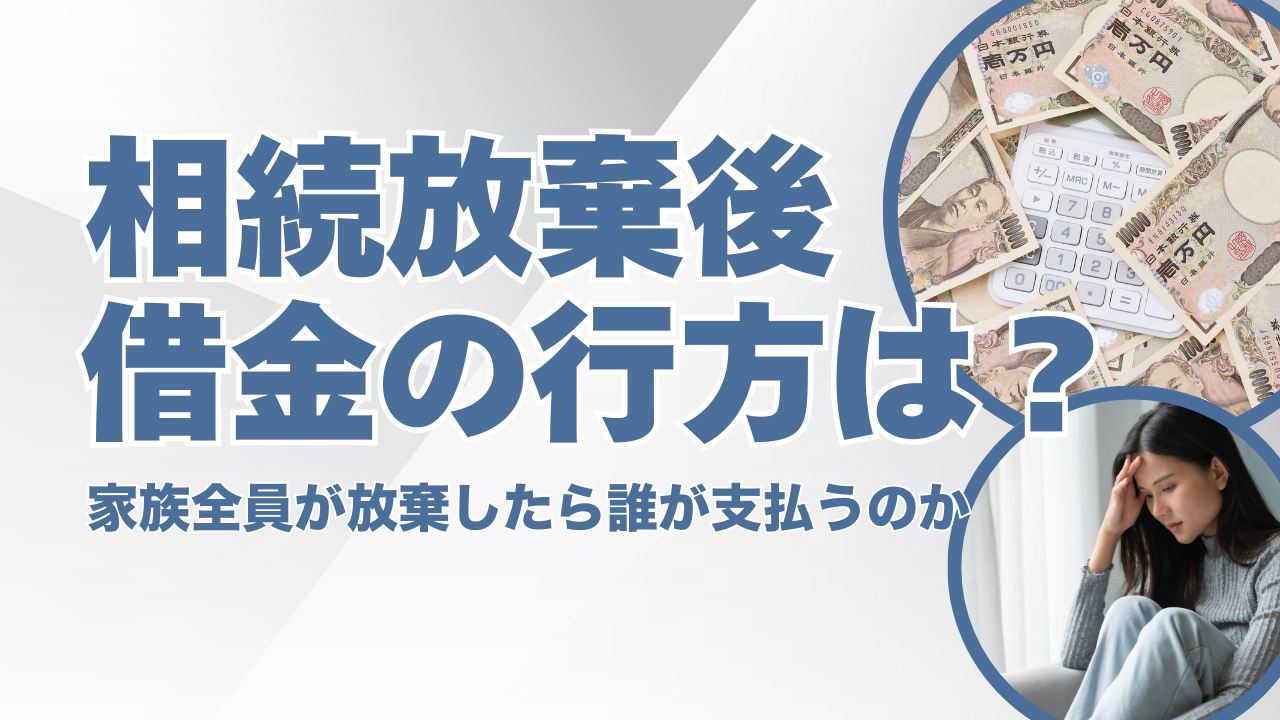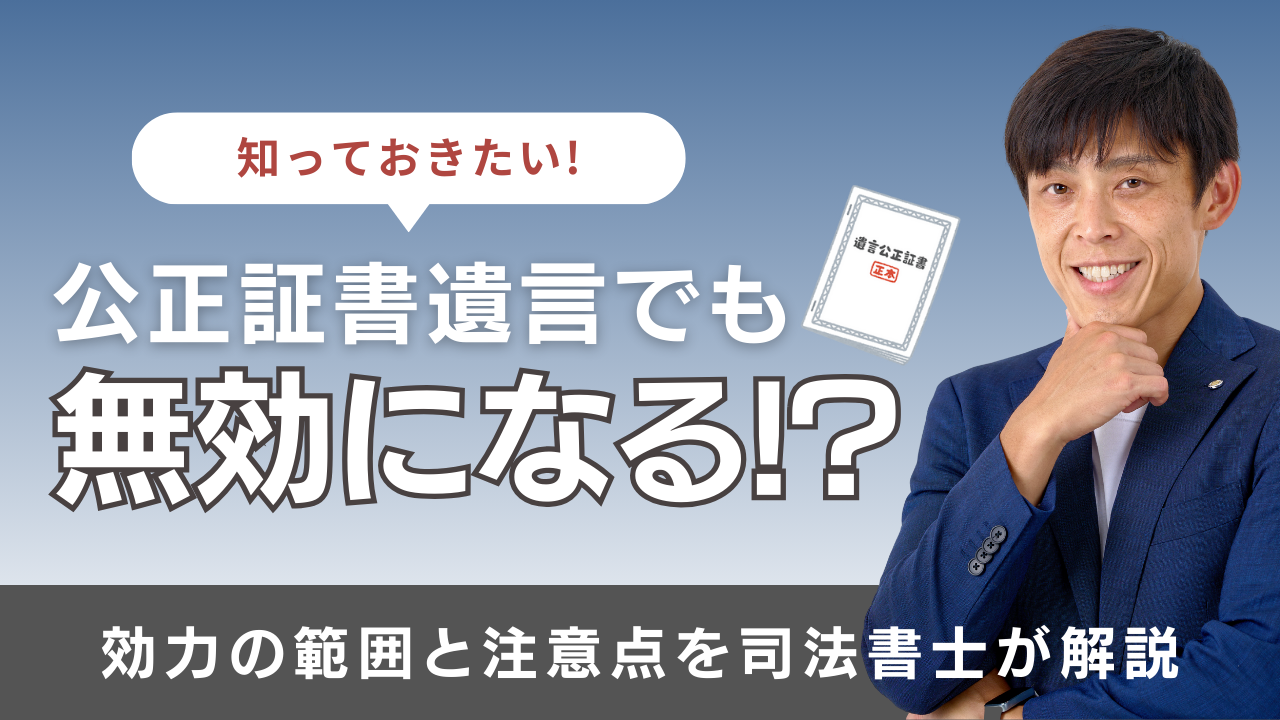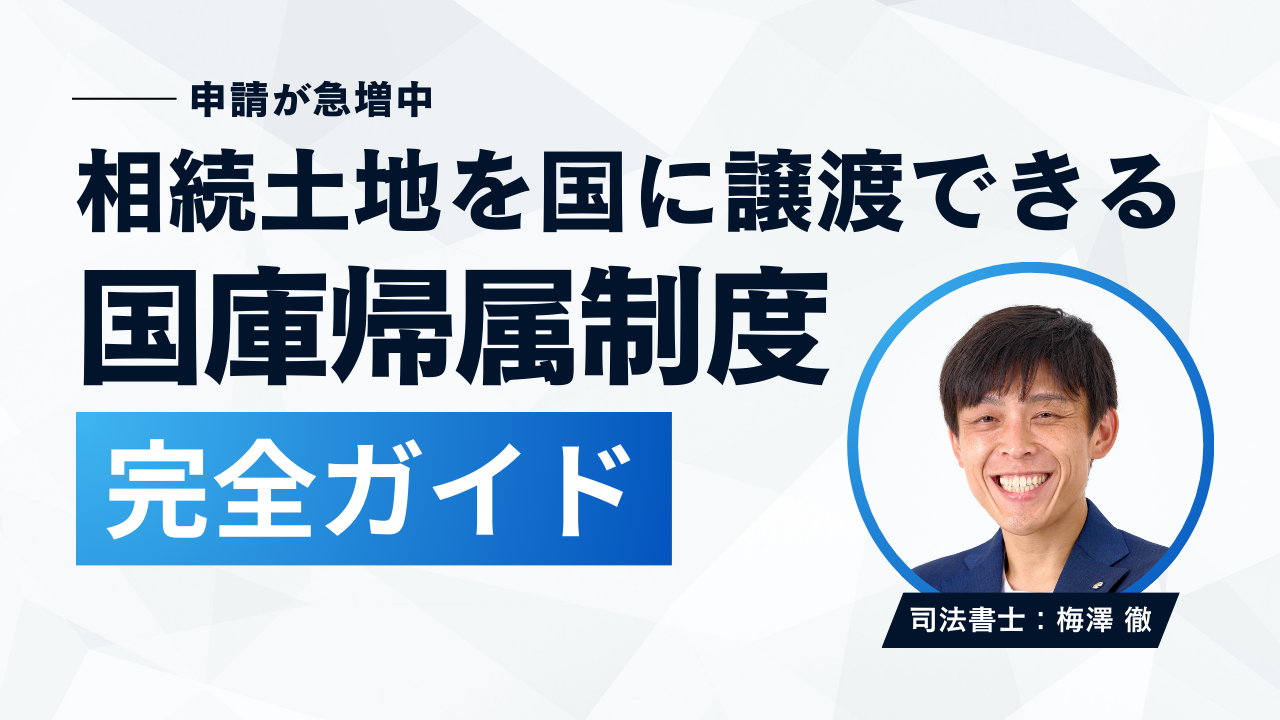この記事を要約すると
- 株式は種類により相続放棄時の処理方法が異なる
- 株式処分は単純承認となり相続放棄が不可能になる
- 3ヶ月以内の証券会社調査と適切な手順が必要
「親が亡くなって相続放棄したいけど、株式があるとどうなるの?」
「株式があるとき相続放棄できるの?」
こうしたお悩みを抱えているのは、あなただけではありません。
故人の債務が多い場合、相続放棄を検討されるのは自然なことですし、
そのお気持ち、本当によくわかります。
この記事では、相続放棄時の株式の取り扱いについて、
具体的な手順と注意点を分かりやすく解説します。
読み終わった後は、株式がある場合の相続放棄手続きを適切に進められるようになります。
この記事はこんな方におすすめ
- 相続人になったが株式も含めて相続放棄を検討している方
- 故人の株式の取り扱いで悩んでいる方
- 相続放棄の手続きで株式について不安を感じている方
目次
相続放棄で株式の扱いが決まる3つのパターン
相続放棄すると、故人が保有していた株式は 相続人によって取り扱いが大きく変わります。
株式の種類によって処理方法が異なるため、 まずは基本的な分類を理解しておきましょう。
| 株式の種類 | 相続放棄時の処理 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 上場株式 | ・次順位相続人へ自動承継 ・市場価値で評価 |
・証券取引所で売買 ・価値評価が明確 |
・株価変動リスクあり |
| 非上場株式 | ・評価額に関係なく放棄対象 ・次順位相続人へ承継 |
・中小企業の株式 ・評価が困難 |
・将来価値や責任が発生する可能性 |
| 持株会株式 | ・会社規定により処理 ・強制買取りの場合もあり |
・従業員持株会で購入 ・自社株式 |
・事前に会社への確認が必要 |
上場株式は次順位相続人へ自動承継される仕組み
上場株式※の場合、相続放棄すると 自動的に次順位の相続人に承継されます。
例えば、子供が相続放棄した場合
- 株式は配偶者と直系尊属(両親など)に承継される
- 直系尊属も放棄すれば兄弟姉妹に承継される
- すべての相続人が放棄すれば家庭裁判所が相続財産管理人※を選任
※相続財産管理人:相続人がいない場合に財産を管理・清算する裁判所が選任する人
※上場株式:証券取引所で取引される株式
上場株式は市場価値が明確なため、 相続財産の価値評価で問題になることはほとんどありません。
ただし、株価は常に変動していますので、
タイミングによっては、放棄した後の価値が変わることもあります。
非上場株式は評価額0円でも放棄対象となる理由
非上場株式※の場合、評価額に関係なく 相続放棄の対象となります。
よくある誤解として 「評価額0円の株式なら放棄しなくても大丈夫」 というものがありますが、これは間違いです。
※非上場株式:証券取引所で取引されない株式(主に中小企業の株式)
理由は以下の通りです。
- 将来的に価値が生まれる可能性がある
- 株主としての責任や義務が発生する場合がある
- 会社の債務に対して保証責任を負うケースもある
そのため、相続放棄を選択する場合は 評価額に関係なく、すべての株式を放棄することになります。
持株会株式は会社規定で処理方法が変わる
持株会株式※の場合、勤務先の会社規定により 処理方法が決まります。
※持株会株式:従業員持株会で購入した自社株式
一般的な処理パターン:
- 相続人が引き継ぎ可能な場合
- 会社による強制買取りが行われる場合
- 一定期間後に自動売却される場合
持株会株式がある場合は、 相続放棄前に必ず勤務先の人事部や総務部に 処理方法を確認しておくことが重要です。
あなたの家族の場合、どのような株式を保有しているでしょうか。
証券会社への確認から始めてみましょう。
個別の状況により最適解が異なるため、まずは無料相談で専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
FAQ
Q. 相続放棄で株式も放棄される?
A. はい、相続放棄すると株式も含めてすべての財産を放棄します。
Q. 上場株式と非上場株式の違いは?
A. 上場株式は市場で売買可能、非上場株式は評価が困難な株式です。
Q. 株式があると相続放棄できない?
A. 株式があっても相続放棄は可能ですが手続きが複雑になります。
相続放棄前に株式を処分すると取り返しがつかない
「株式を売って債務返済に充てた後で相続放棄したい」 このように考える方もいらっしゃいます。
しかし、これは絶対にやってはいけません。
株式の処分は単純承認※とみなされ、 相続放棄ができなくなってしまいます。
※単純承認:相続財産をすべて受け継ぐこと(プラスの財産も借金もすべて相続する)
株式売却は単純承認とみなされ放棄不可能になる
亡くなった後に故人の株式を売ってしまうと、 「財産を受け取った」と判断されてしまいます。
法律では 「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」 相続を承認したとみなすと決められています。
一度「相続する」と判断されてしまうとこのような事になります。
- 相続放棄の手続きができなくなる
- 借金もすべて背負うことになる
- 後から「やっぱり放棄したい」と言っても無理
株式の売却は明確な「処分行為」に該当するため、
相続放棄を検討している場合は絶対に行わないでください。
配当金受取りでも相続承認とみなされる落とし穴
またこういった落とし穴もあります。
それが、株式を売却しなくても、配当金をもらうだけで
「相続した」と判断されるケースです。
特に注意が必要なのは:
- 故人名義の配当金を相続人名義の口座で受け取った場合
- 配当金を使って債務の返済を行った場合
- 配当金を受け取った後で相続放棄を申し立てた場合
「配当金はわずかな金額だから大丈夫」 という認識は危険です。
金額が少なくても、「財産をもらった」として扱われる可能性があります。
配当金が支払われるタイミングも把握して、
受取り前に相続放棄の申述を完了させることが重要です。
株主名簿の名義変更手続きは絶対にやってはいけない
また以下のように考えたことはないでしょうか?
「名義変更だけなら処分にあたらないだろう」
こういった判断も注意が必要です。
実は株主名簿の名義変更も「財産をもらった」として 扱われる可能性があります。
名義変更をしてしまうと:
- 株主になったということになる
- 「相続したい」という意思があったと判断される
- 後で相続放棄をしようとしても難しくなる
特に非上場株式の場合、名義変更手続きが より厳格に扱われることが多いため注意が必要です。
相続放棄を検討している間は、 株式関連の一切の手続きを控えるのが安全です。
FAQ
Q. 株式売却すると相続放棄できない?
A. はい、株式売却は単純承認とみなされ相続放棄不可能になります。
Q. 配当金を受け取っても大丈夫?
A. 配当金受取りも相続承認とみなされる場合があり危険です。
Q. 名義変更だけなら問題ない?
A. 名義変更も相続財産の処分とみなされる可能性があります。
相続財産の中に株式がある場合で3ヶ月以内に相続放棄の手順
相続放棄には3ヶ月の期限があります。
参考:相続の承認又は放棄をすべき期間 – e-Gov法令検索
「3ヶ月あるのなら大丈夫だろう」 そう感じていらっしゃいませんか?
株式がある場合は、通常の相続放棄よりも 事前調査に時間がかかるため、
計画的に進める必要があります。
最高裁判所の統計によると、相続放棄の申述件数は 令和4年に約24万件となっており、
年々増加傾向にあります。
証券会社への照会で株式の有無と評価額を確認
まず、故人がどこの証券会社に口座を持っていたか調査します。
調査実施の流れ
調査はこのように実施します
- 故人の書類から証券会社の資料を探す
- 郵便物や通帳の取引履歴から証券会社を特定
- 証券保管振替機構(ほふり)※への照会
※証券保管振替機構(ほふり):全国の証券口座を一括管理する機関です。
2で特定できない場合の手段として考えて頂ければと思います。
証券会社を特定した後の流れ
証券会社が特定できたら以下を行なってください
- 残高証明書の発行を依頼
- 保有株式の種類と数量を確認
- 相続放棄予定であることを伝える
必要書類
必要な書類は下記の3つです。
- 故人の死亡証明書
- 相続人であることを証明する戸籍謄本
- 相続人の身分証明書
この調査には1〜2週間程度かかることが多いため、 相続開始後すぐに取りかかることが重要です。
家庭裁判所への申立書に株式情報を正確に記載
相続放棄の申請書には、株式についても きちんと書く必要があります。
申請書に書く内容
- どの会社の株式か
- 何株持っているか
- だいたいいくらぐらいの価値か
- どこの証券会社にあるか
書くときのポイント
- 「株式がある」「ない」をはっきりさせる
- まだ調べている最中なら「調査中」と書く
- 後で株式が見つかっても追加で報告できる
手続きに必要な書類
- 相続放棄の申請書
- 亡くなった方の戸籍謄本
- あなたの戸籍謄本
- 収入印紙800円分
株式の価値がまだよくわからない場合でも、
まずは3ヶ月以内に手続きを済ませることを優先してください。
放棄受理後の株式管理は次順位相続人に引き継ぎ
相続放棄が受理されたら、株式は次順位の相続人に承継されます。
引き継ぎ手順
- 次順位相続人に株式の存在を通知
- 証券会社に相続放棄受理証明書を提出
- 名義変更手続きは次順位相続人が実施
次順位相続人も放棄する場合
- 同様に3ヶ月以内の手続きが必要
- すべての相続人が放棄すると相続財産管理人が選任
- 管理人が株式の処分を行う
1つ注意点をお伝えします。 相続放棄後も、次の相続人が決まるまでは
「善良な管理者の注意をもって財産を管理する義務」があるということです。
ただし、株式については通常、 証券会社が適切に管理するため、
特別な管理は必要ありません。
手続きミスを避けるため、まずは無料相談を利用し、司法書士の専門的なアドバイスを受けてください。
FAQ
Q. 相続放棄の期限は?
A. 相続開始を知った日から3ヶ月以内です。
Q. 株式の調査に時間がかかる場合は?
A. 3ヶ月の期限内に申述することを優先してください。
Q. 相続放棄の費用は?
A. 家庭裁判所への申立てで収入印紙800円分が必要です。
まとめ:相続放棄成功のカギは株式の事前調査と適切な手順
相続放棄時の株式取り扱いは種類により大きく異なり、
上場・非上場・持株会株式それぞれに注意点があります。
特に株式売却や配当受取り、名義変更は単純承認とみなされ相続放棄ができなくなることは覚えておいてください。
株式がある相続放棄は通常より複雑で、証券会社への照会から申述書作成まで計画的な進行が必要です。
3ヶ月の期限内で適切に手続きを完了させるには、早期の調査開始と専門家のサポートが不可欠です。
相続放棄でお悩みの方は、まずは無料相談をご利用ください。
経験豊富な専門家が、あなたの状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。
この記事の監修者

遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。