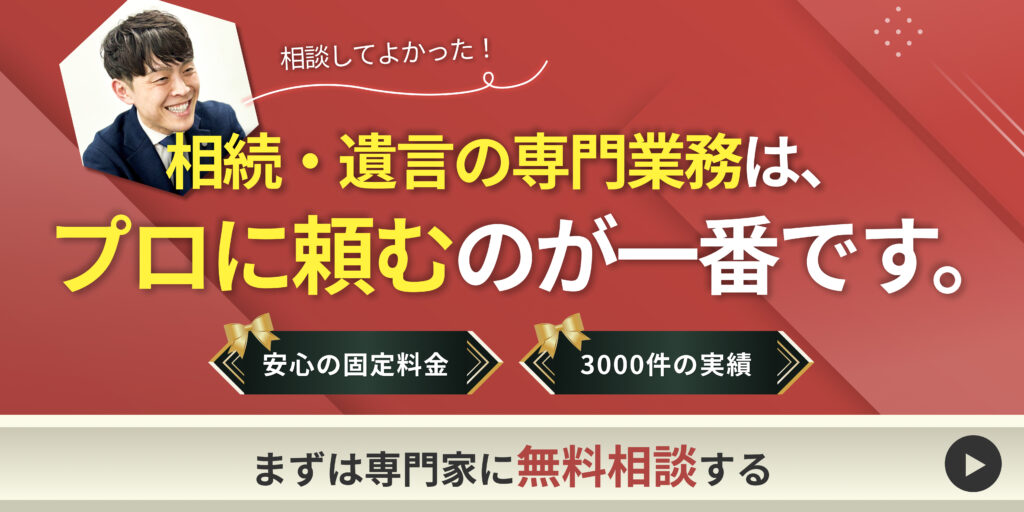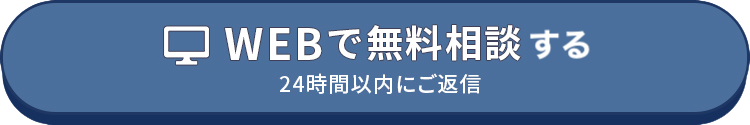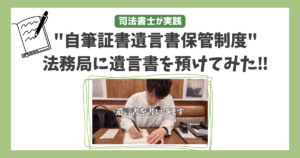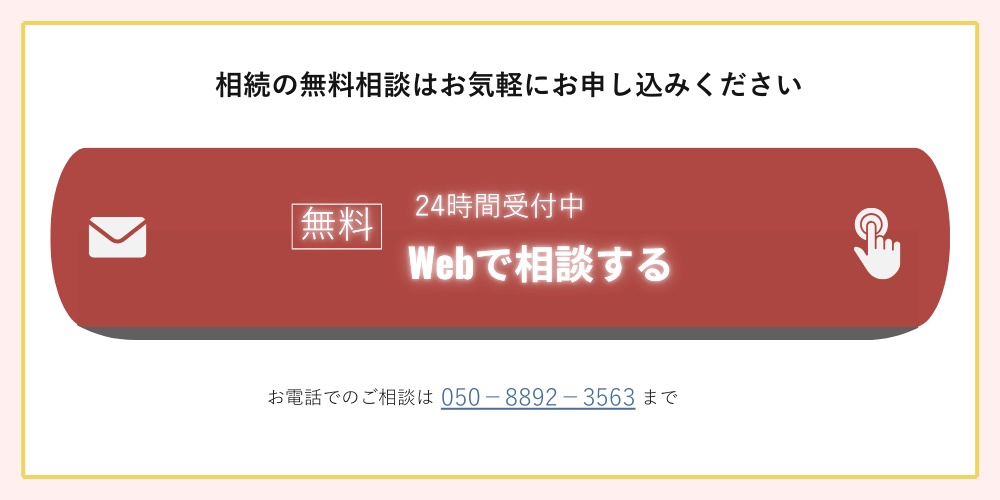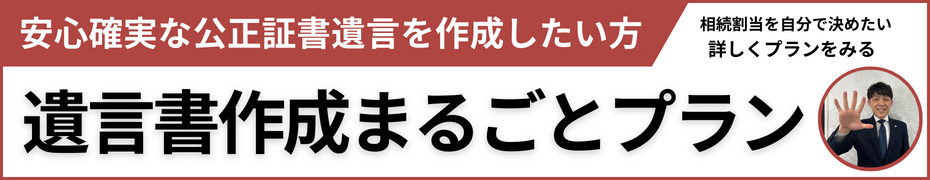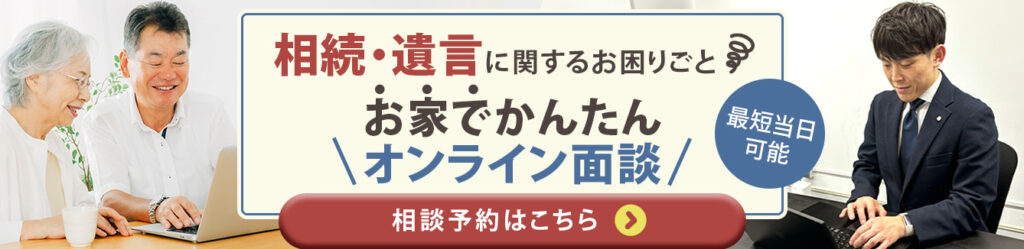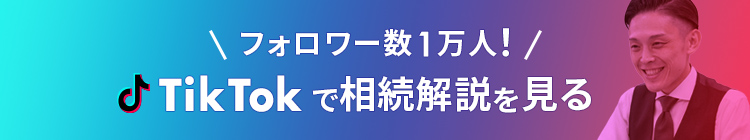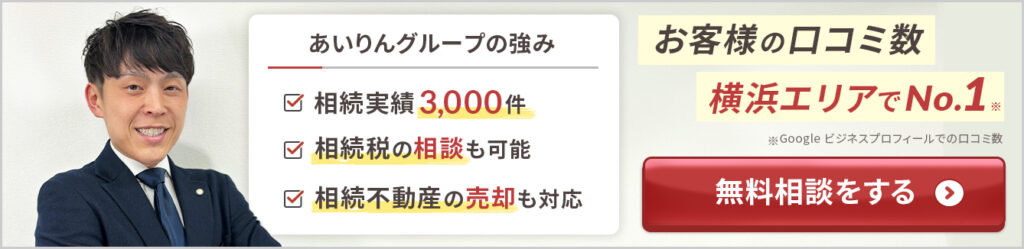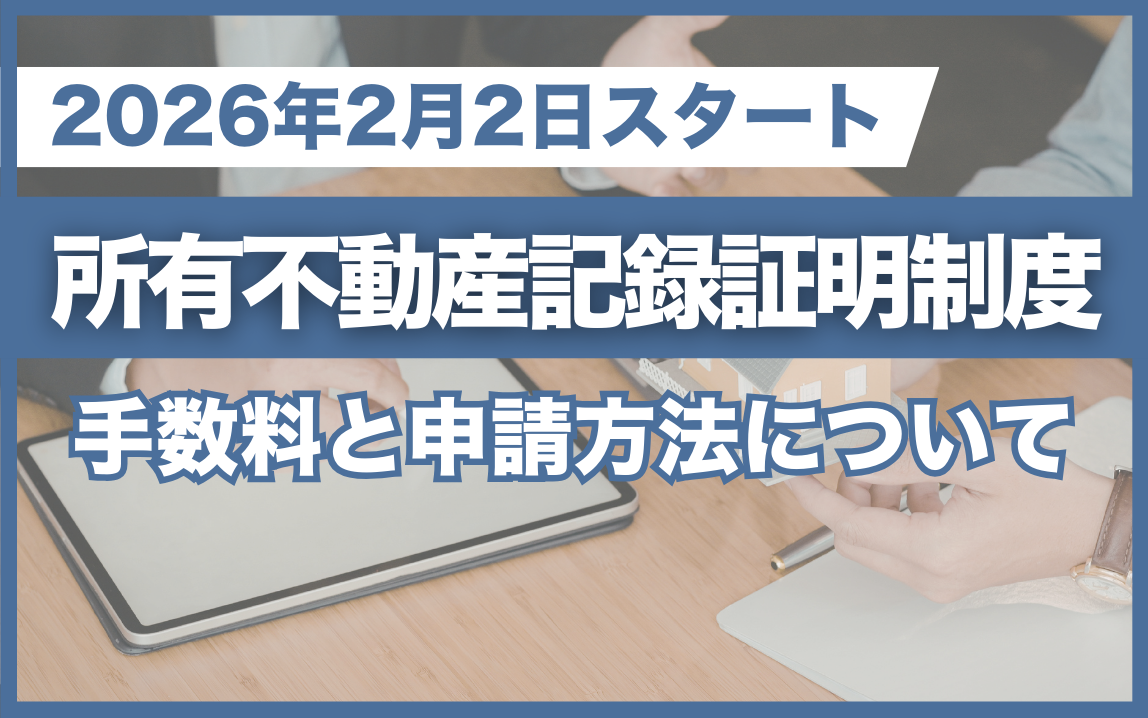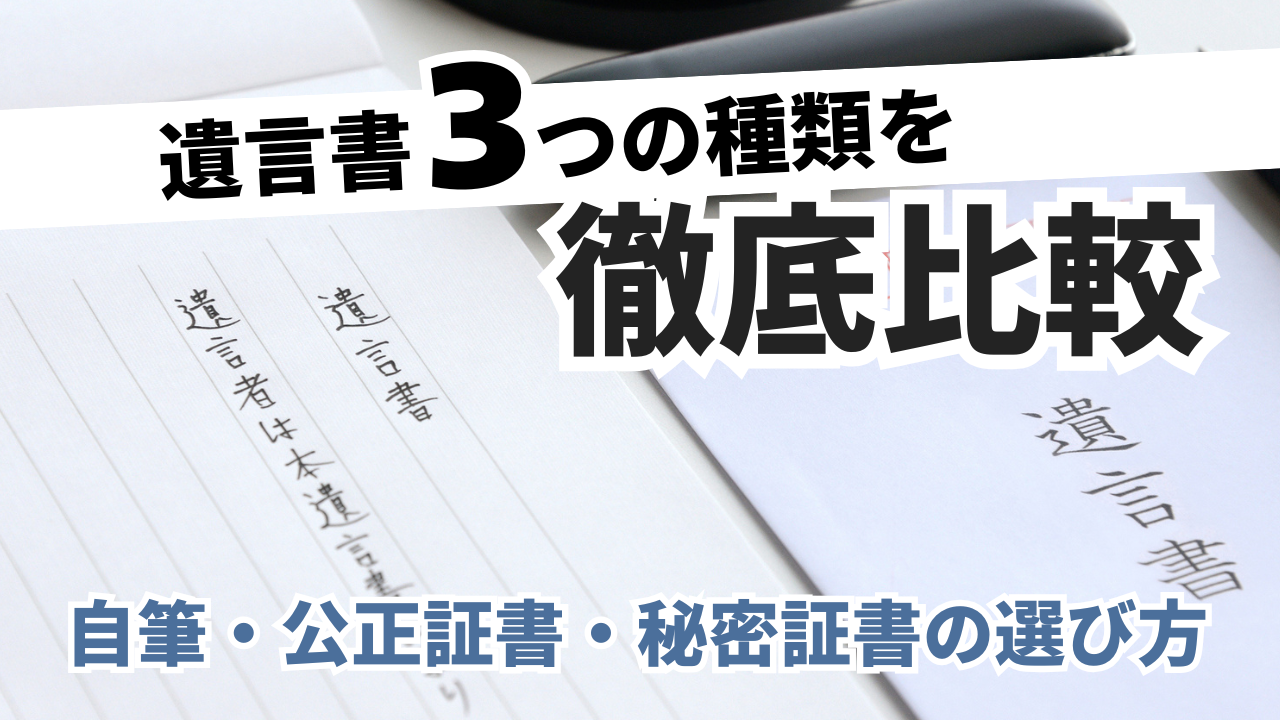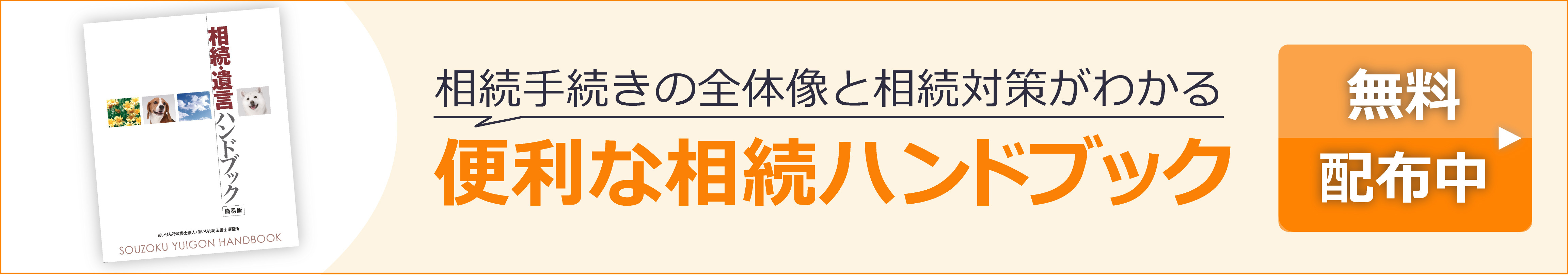この記事を要約すると
- 遺言書は15歳から作成できる
- 遺言を作成する最大のメリットは死後の争続を防ぐため
- 遺言書はできるだけ早めに作ったほうがいい
「遺言は何歳から作っておくべきだろか?」
この記事では、何歳から遺言を作るべきか、法律上は何歳から遺言を作れるか、遺言がないとどのような不都合が生じるか、などと合わせて解説します。
目次
遺言書は何歳から書けるのか

何歳から遺言書を作成すべきかを考える前に、何歳から遺言を作成することができる年齢なのか、その理由と要件について確認しましょう。
遺言の要件
遺言は15歳からできる
根拠は民法961条に「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」と定められているからです。契約や遺産分割協議は、成人してからでないと単独でできませんが、遺言は違います。
遺言というと、高齢者のものというイメージがあるでしょう。しかし、法律では遺言は若い時からできるようになっています。これは、若い人でも遺言を必要とすることが考えられるからです。
遺言ができる意思能力があること
民法963条では、遺言する際に、遺言ができるための意思能力を定めています。
遺言ができる意思能力とは遺言能力があることです。遺言能力とは自分の遺言内容と、遺言による結果が理解できる能力です。この遺言能力が無いまま作成された遺言は無効となります。
例えば、認知症や加齢などにより判断能力を失っていると遺言能力はないとされます。
遺言の方式と内容
遺言の方式と内容は、法律により厳格に定められています。
例えば、書式や遺言ができる内容などです。これを遵守しない遺言は無効となります。
なぜ15歳からなのか
例えば3歳の子供は意思能力を有する成人程度に自分の財産を把握し、他人にあげるというようなことはできません。つまり、遺言能力がないともいえます。
そうだとすると、民法が遺言できる年齢を15歳と定めた理由は、遺言の意味を理解できる年齢だからでしょう。
根拠の1つとして、明治民法とよばれる旧民法が関わっています。旧民法では、婚姻可能な年齢を男性17歳、女性15歳と定めていました。そして、婚姻できるなら、遺言もできるという考えで、年齢が低い方の15歳から遺言できると定めました。
現代民法ではこの流れを引き継いでいます。さらに、現代の考え方では義務教育を終えるのが15歳であり、遺言を理解できる一定の能力はもっているということです。
その上で、遺言は人の死に関わる極めて特殊な行為であり、人の最終意思をできるだけ尊重するという観点が含まれています。
法定代理人について
遺言には代理という制度が存在しません。遺言は契約行為と違い代理という制度はなじまないため、本人のみによってできる行為です。では、未成年者の場合はどうでしょうか。
前述のとおり、遺言行為は未成年者である15歳から可能です。契約行為ならば法定代理人の同意または代理が必要となる年齢です。
しかし、遺言は未成年者でも15歳以上であれば、法定代理人を必要とせず、完全に単独でできます。
最近の遺言書事情
遺言書のニーズは年々増えています。その大切さを示す情報として、遺言書作成に関するデータをご覧ください。
増えている遺言書
公正証書遺言を作成する人が非常に増えています。近年の作成件数推移は下記の通りです。
2007年は74,160件だったのに対し、2019年は113,137件と、12年間で1.5倍以上に増えています。
信頼性の高い公正証書遺言により、確実な遺言を作成するという高いニーズの現れです。自筆証書遺言の作成も、法務局による自筆証書遺言保管制度の拡充により増加が見込まれます。
なぜ遺言書作成が増えているのか
どうして遺言書作成が増えているのでしょうか。その理由は「争続」への対策です。
争続になる理由として、高齢社会および社会構造の複雑化と多様化、権利意識の高まりが挙げられます。例えば、長男なためので全部継げるというのを古い価値観であると考える人は多く、子として平等に遺産を取得したいと考える人が多いでしょう。
他にも高齢社会により、遺言者が長い介護期間を要することがあり、その場合は家族の誰かがお世話します。例えば、子が遺言者と同居して介護の世話をしても、他の別居している子は介護の世話をしないということがあります。
結果的に世話をした側はもっと遺産が欲しいといい、世話をしていない子は平等に相続したいといった相続人間の不仲や不満が生じるのです。
遺言者と一緒に暮らして生活費があまり掛からない独身者の子と、子供を持つ家庭でお金がかかる既婚者の子がいた場合、既婚者は現金を欲しがります。
他にも遺言者から結婚資金を出してもらった既婚者の子と、そうではない独身者の子がいるとき、何も考慮されずに平等に遺産分割が生じると独身者は不公平感を感じます相続人の意思だけで遺産分割協議すると揉める可能性が大きいのです。
そのため、争続対策として遺言は有効な手段となります。諸事情を理解している被相続人が遺言を作成すれば、実質的に平等な遺産分割を実現することも可能だからです。
遺言が無いとどうなるか

遺言が無い場合、法定相続人の間で分割の仕方を決めなければなりません。
民法では、分割の仕方の目安として法定相続分の規定が記されています。もし遺言が無かった場合、前項の争続以外にも以下のような問題があります。
財産の詳細がわからず、全ての調査が必要になる
相続人の知らない預金口座や有価証券、不動産が想定されます。
負債の有無がわからず、相続放棄するべきかの判断に迷う
マイナス財産を調査するのは、プラス財産以上に難しいことがあります。例えば、連帯保証債務も相続されるため注意が必要です。
相続人以外への遺贈ができなくなる
遺産分割は法定相続人の間で行います。もし、法定相続人以外に、生前お世話になったなどの理由で財産を渡したい人がいる場合は、遺言が無いと特別寄与料の請求ができる場合や特別縁故者として財産の請求をする場合でもない限り、難しいといえます。
各種手続きの時間が足りなくなる
相続税の申告納税期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続放棄・限定承認の申述期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内です。
これらは、役所や保険会社への保険金請求など他の手続きをしながら、期限内にすることが必要です。しかし、財産や負債の調査に時間が掛かると困難になります。
遺言の種類
遺言には、次のような種類があります。
一般方式
通常の遺言方式で、3つあります。
公正証書遺言
遺言者が専門家である公証人に遺言内容を伝え、公証人が法律の規定に従い作成する遺言の方式です。2人以上の証人が立会います。最後に遺言者と公証人および証人が署名捺印します。
遺言書の原本は公証役場で保管されます。手間と費用が掛かりますが、法律の専門家である公証人が法律の規定にのっとって作成するため、遺言方式の中では一番信頼性の高いものです。
自筆証書遺言
遺言者が自筆により、遺言書の全文と日付、氏名を書き捺印して行う遺言の方式です。一番手軽にできる遺言方式で、誰にも見られずに作成できます。
しかし、専門家の関与が無いため、法律に従わない遺言内容や様式不備で無効にならないよう注意が必要です。自己保管すると紛失や破棄の恐れがあるため、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することをおすすめします。
保管先は、全国各所にある法務局の遺言書保管所です。各地域の法務局はこちらから確認してください。
秘密証書遺言
遺言者が自筆またはワープロ等で遺言を作成し、封筒に入れて遺言書内で用いた印により封印します。
これに公証人が必要事項を書き留め、2人以上の証人が見届けます。最後に遺言者と公証人および証人が封筒に署名捺印します。
特別方式
一般方式ではできない状況である、緊急時にする遺言の方式です。
死亡の危急に迫った者の遺言
遺言者の臨終が近いときの遺言です。証人3人以上の立会いのもと、1人が口述された遺言書を筆記し、遺言者と立会人全員に読み聞かせて立会人全員が署名捺印します。
伝染病隔離者の遺言
遺言者が伝染病のため、行政処分により隔離された場合の遺言です。警察官および証人1人以上立会いのもと遺言書を作成し、遺言者と立会人全員が署名捺印します。
在船者の遺言
遺言者が航海中にする遺言です。船長または事務員1人および証人2人以上立会いの下、遺言書を作成し、遺言者と立会人全員が署名捺印します。
船舶遭難者の遺言
沈没しかけた船中や墜落しかけている航空機内でする遺言です。証人2人以上立会いのもと口頭で遺言し、立会人が筆記および署名捺印します。
遺言書は何歳から書くべきか
遺言は15歳からできますが、あまりに早いとそもそも譲り渡す遺産もありませんし、余りに遅いと正確な判断ができないで遺言をしてしまうことも考えられます。では、人によっていつ頃が適しているのかを解説いたします。
若年者・中年者の必要性
この年代の人達は、自分の相続というものが想像しにくい世代です。だからこそ、遺言について考えて、必要性に気付く価値が非常にある世代です。
想定できる相続の例として、突然の事故や病気があります。これは、ひと昔前と状況がかなり変化しています。万が一という状況が多種多様化しているのです。
交通事故はもちろん、震災や台風などの自然災害激増による被害、犯罪による被害も増えています。病気としては、現代社会によるストレスが若い人でも心臓発作や脳梗塞の危険性を増やし、命が脅かされる人も多くいます。相続が発生した時には争族の心配もあります。
独身の場合に子・孫もいなければ、親・祖父母と兄弟姉妹が法定相続人になります。昔と違い、兄弟間の疎遠や不仲も増えています。
その他にも既婚者で子がいない場合は相続が発生したとき、遺言がなければ、残された配偶者と亡くなった被相続人の親または兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。
もし、遺産分割協議でトラブルになったとき、配偶者が預金を引き出せないことや自宅を追い出されるなどのリスクがあるため、遺言しておく必要があります。若年者や中年者で若くても、不測の事態を想像して、遺言を考える必要はあります。
高齢者の必要性
高齢者の場合には、先が余り長くないため、遺言をするニーズは若い人よりも増します。遺言について、高齢者の人が考えるべきことは遺言能力です。遺言は、遺言者の周りの環境が変わることも関係します。
配偶者に先立たれる可能性が増え、その場合は相続人の構成が変わるため、新たな対策が必要になります。また、孫ができる年代でもあるため、孫への金銭支援や2次相続対策も考える必要があります。
遺言能力がなくなると、遺言するタイミングを無くしてしまうため、できるだけ早く元気なうちに行動することが大切です。
タイミングは何歳からが良いか
遺言するべきタイミングは人によりさまざまです。人によって生活環境や家族の状況が、その時々で違うからです。
そのため、ライフステージが変化した時は、遺言を考えるタイミングになります。言い換えれば、遺言するタイミングは家族構成や財産構成が変化した時です。例えば、再婚した際に、前妻との間に子がいるという状況はこれにあたります。
具体的なライフステージの変化としては、下記が挙げられます。
- 結婚や出産した時
- 住宅の購入をした時
- 転職や起業、定年退職した時
- 離婚や再婚、配偶者を亡くしたなど家族構成が変化した時
- 自分や家族が大病を患った時
他にも、生命保険に加入した時や見直しをした時は、死後の財産構成が変わるため、遺言を考えるタイミングといえます。
若いうちに遺言書を書くメリット・デメリット
若いうちに遺言書を書くメリットとデメリットは次のとおりです。
メリット
若いうちに遺言書を書くメリットには次の3つが挙げられます。
遺言するための行動が早くできる。
遺言はどちらかというと、ネガティブなイメージをもちやすく後回しにしがちです。遺言書を作るには体力と気力を要します。
先送りしているうちに、高齢になって面倒になり結局遺言書を書かない、または意思能力が低下して書けないということになりかねません。若い人は体力や気力もあり、行動を早くできます。
遺言への免疫ができる
若いうちに遺言することによって、以後の人生において遺言への免疫ができます。遺言書を、高齢になってから書き直す必要がでた時、抵抗なく取り組めるのではないでしょうか着手できます。
早くから相続に関する有益な情報を得られる
遺言を早くから意識することにより、遺言への積極性が増し、有益な情報も得られます。これらのことは、以後に状況変化のため遺言書の書き直しをする時、非常に役立ちます。
デメリット
状況変化によって遺言の内容が変化して手直しが必要
人生の先が長いため状況変化も多くなり、遺言内容が現実に合わなくなります。その場合、遺言内容を修正しないと意味が無くなる、または薄れます。
しかし、遺言書は何回でも書き直しができます。若い時に作成した遺言を何回か書き直す手間が増えるのは仕方がないことです。
遺言は書き直すことができる
遺言書作成に適した年齢は、人によりさまざまです。なぜなら、自分や身の回りの状況が変化するからです。
遺言書は何回でも書き直すことができます。この際、一度行った遺言は遺言の方式によって、その遺言の全部または一部を撤回する必要があります。
書き直す時の遺言方式は自由です。1回目の遺言は公正証書遺言で、2回目の遺言は公正証書遺言で撤回後に自筆証書遺言で作成しても大丈夫です。
遺言と併せて考えられる対策
対策には次のようなものがあります。
任意後見
任意後見とは、遺言者が信頼できる人に、自分の生前の財産管理を依頼する制度です。遺言者の意思能力が低下したときに家庭裁判所へ申述して、任意後見監督人が選任されたときに発動します。
もし、遺言書を作成した後に、認知症になったときの備えとして有効です。なぜならば、生前の財産管理がきちんと行われないと、遺言書に記した財産内容が維持できなくなる可能性があるからです。
自分が元気なうちに任意後見契約を結び、自分が望む財産管理を任意後見人に託すことができます。しかし、何でもできるわけではなく、財産の維持・管理から外れる投資行為などはできません。
家族信託
家族信託とは、遺言者が信頼できる人に、自分の財産管理を依頼する制度です。財産管理を依頼された人は受託者とよばれます。
遺言者の意思能力が低下する前でも、任意な時期に発動でき、生前だけではなく死後のことについても契約で定められます。認知症になったとき、自分が望む生前の財産管理を受託者に託せる点は任意後見制度と同様です。
しかし、財産管理の自由度が高く、投資行為や不動産購入のために借入することも可能です。
例えば、遺言者が認知症になった後に受託者が借入をして不動産を購入することにより、相続税の課税価格が圧縮できれば、相続税対策が可能です。遺言では遺言者の相続についてのみ財産処分方法が指定できます。家族信託では二次相続についても指定できます。
死後事務委任
遺言者が信頼できる人に、自分の死後の事務を依頼する契約です。遺言では対応できない事務を定めることができます。
遺言は何でも指定できるわけではないため、遺言を補完するものとして有効な手段です。例として、葬儀・納骨に関すること、行政手続きやクレジットカードの解約、知人への連絡などです。独身で兄弟がいないなど、身寄りのない方におすすめです。
生前贈与
遺言者が自分の財産を無償で相手に与えることを意思表示して、相手がこれを受諾する契約です。生前贈与は争族対策と相続税対策に有効です。
生前贈与は遺言と異なり、契約であるため成人してからでないと単独では行えません。争族対策として例えば、被保険者を遺言者、保険契約者および保険金受取人を法定相続人の1人とした生命保険契約を締結します。
この保険料相当額および贈与税相当額を遺言者から法定相続人の1人に贈与すると、法定相続人の金銭負担なく生命保険契約ができます。
遺言者の死亡後、受取死亡保険金により相続税の納税資金や、他の相続人への代償金の用意ができ、争族対策になります。相続税対策としては、遺言者から相続人へ生前贈与による財産移転をしつつ、遺言者の財産額が減るため、相続税を減らすことができます。贈与する際は、特別受益や遺留分に配慮することも大切です。
遺言書作成を専門家に依頼するメリット
遺言は15歳以上で意思能力があれば、誰でも作成できます。
しかし、誰でも有効な遺言が作成できるわけではありません。無効になってしまっては、全くの無意味になってしまいます。
専門家に相談するメリットは、無効にならない遺言書を作成できることです。さらには、自分が気付いていない潜在ニーズに、専門家ならではの助言をしてくれることもあります。
例えば、争族にならないための財産処分法などです。こういったメリットに時間と費用を使う価値はあります。
まとめ
この記事では、遺言書は何歳から書くべきか、を中心に法律の各種規定とあわせてお伝えしました。
遺言書を何歳から書くかは、人それぞれタイミングが違います。遺言書は15歳から書けますが、人生にはいつ何が起こるかわかりません。若いうちから不慮の事故に備えることは有益です。
遺言書の大切さを知るためにも、まずは専門家である司法書士に相談してみてください。
この記事の監修者

遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。