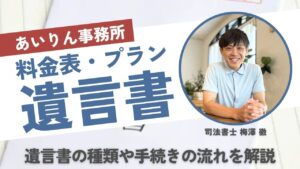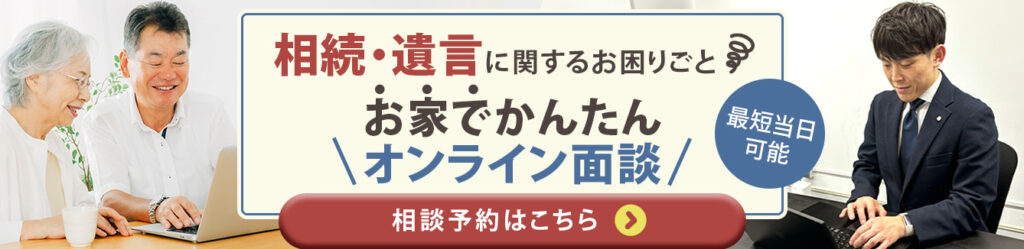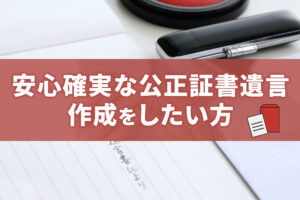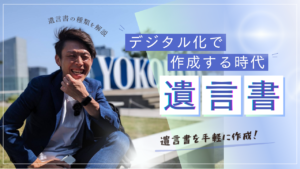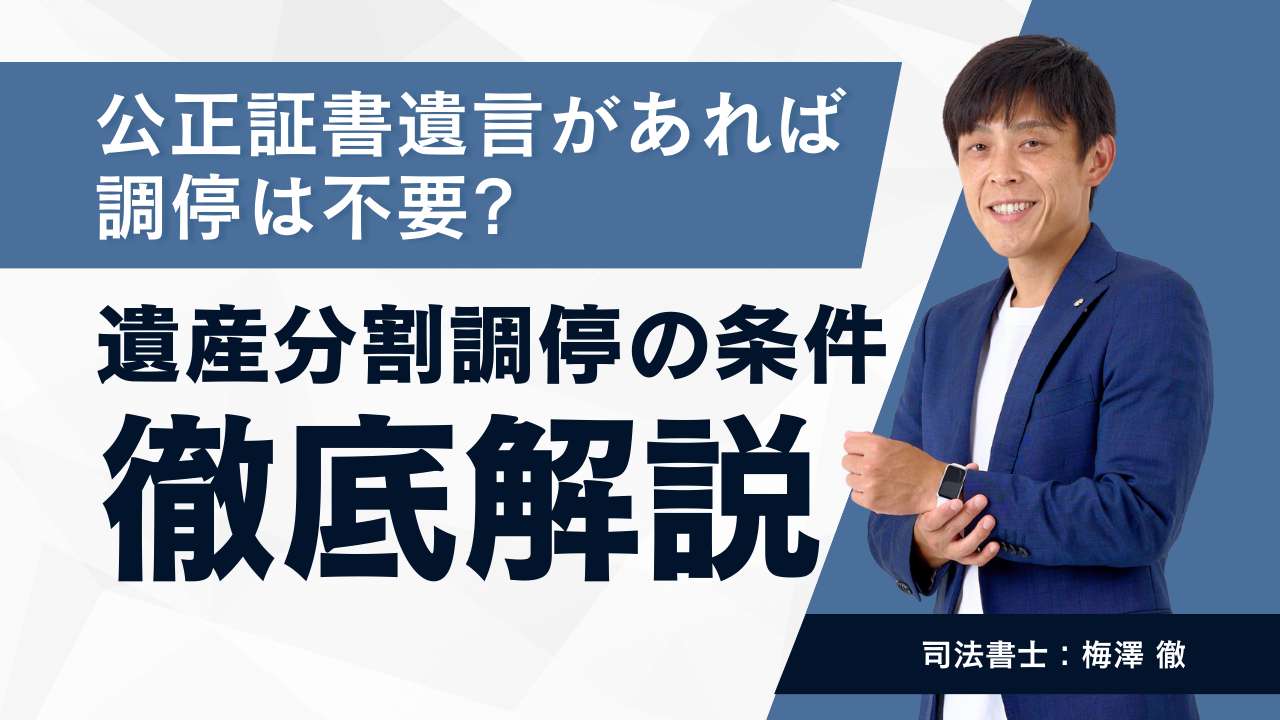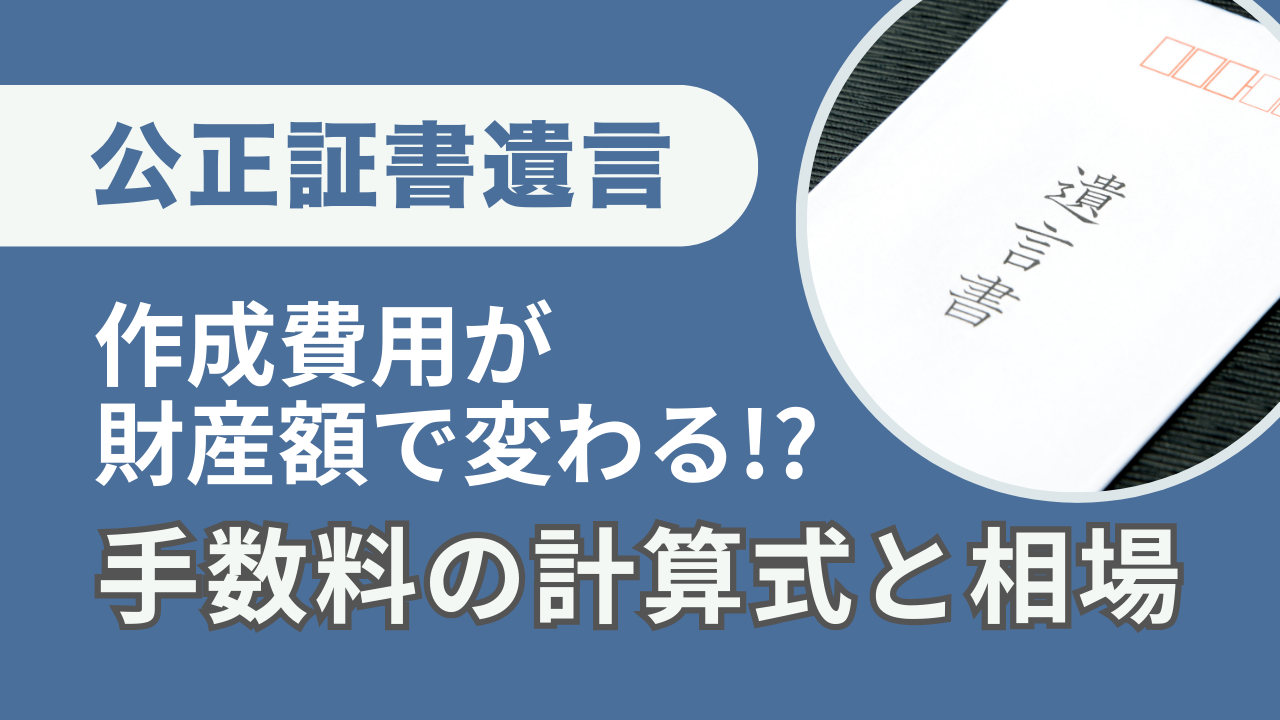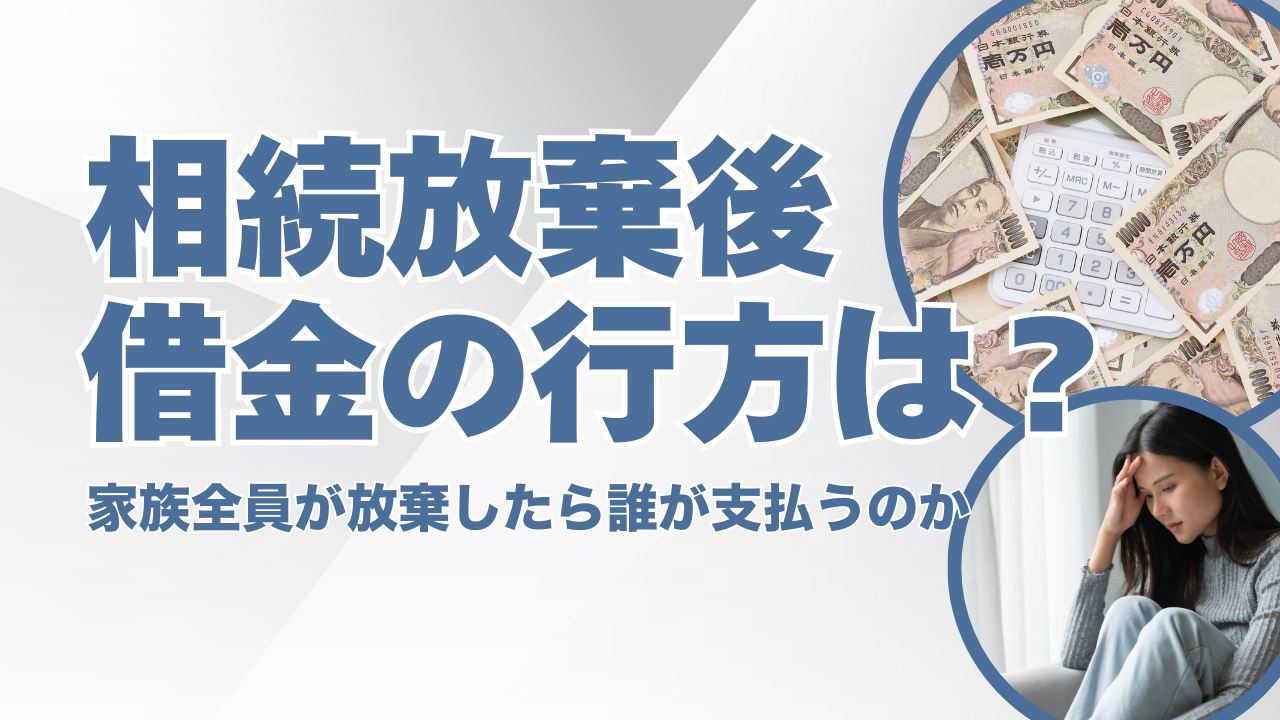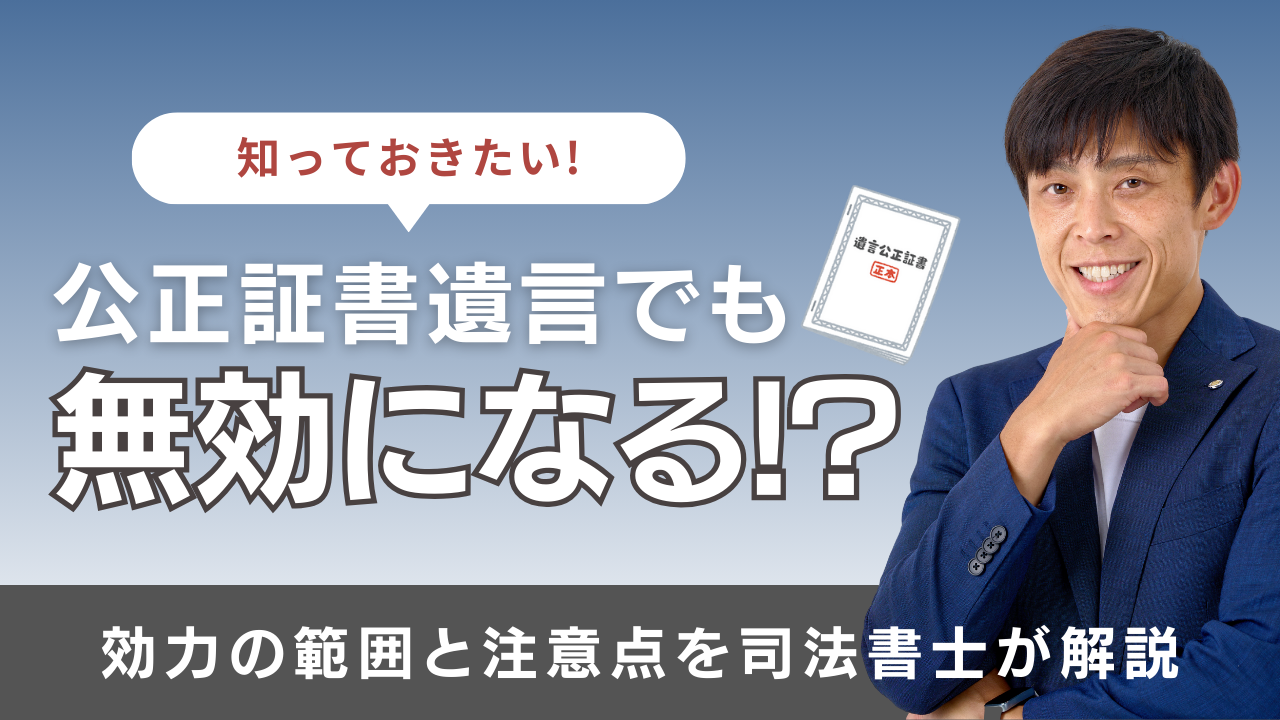この記事を要約すると
- 2025年10月から公正証書遺言が完全オンラインで作成可能になり、自宅や病院から手続きできる新制度がスタート
- 証人も別々の場所から参加でき、電子署名で完結するため移動時間や出張費が不要になる画期的な改正
- 法的効力は従来と同じで、パソコンとネット環境があれば誰でも利用でき、専門家のサポートも受けられる
目次
2025年10月から遺言作成についての変更点

梅澤先生、2025年10月から遺言書作成について制度が変わったと聞いたのですが、具体的に何が変わったのですか?

オンラインで遺言書が作成できるようになるという、重要な法改正についてお話しします。
この記事はこんな方におすすめ
- 公証役場まで行くのが困難で遺言書作成を諦めていた高齢者や入院中の方
- 平日は仕事で時間が取れず、公正証書遺言の作成を先延ばしにしていた方
- デジタル手続きに不安があるものの、自宅で安心して遺言書を作りたいとお考えの方
遺言書を作りたいけど、公証役場まで行くのが大変で諦めている方が多いのですが、実は2025年10月から、そんな心配をする必要がなくなったのはご存じでしょうか?
さて、今回の法改正で変わることにてついてですが、簡単に言うと、自宅から遺言書が作れるようになるという事です。
証人も別々の場所からOKで、全部デジタルで完結します。
でも、ちゃんとした準備をしないと失敗してしまうので、詳しい手順と注意点をお話しします。
今回の法改正における変更点とは

では、具体的に何ができるようになるのですか?

結論から言うと、2025年10月1日から、公正証書遺言が完全にリモートで作れるようになります。
公正証書遺言というのは、公証人が作成する法的に最も確実な遺言書のことです。
具体的にできることは3つです。
- 自宅や病院、介護施設からでも遺言書が作れます
- 証人2人も別々の場所から参加できます
- 署名も保管も全部デジタルで完結します
ただし、パソコンとネット環境、電子署名用の機材の準備が必要です。
これは本当に画期的な変化です。私も正直びっくりしました。
新制度になった理由、法改正の背景について

どうしてこんな制度ができたのですか?
法改正の背景を教えてください

なぜこんなことができるようになったのか解説しますね。
公証人法という法律が改正されました。
公証人法というのはなかなか馴染みがない法律ですが、この法律に公証人の手数料やルールが書いてあります。
ちなみに公証人というのもイメージしにくいですが、役所の人間と思っていただければ良いと思います。
簡単に言うと、これまでは法律で「本人と証人は必ず公証役場に来なさい」と決まっていたのですが、それが変わったのです。
実は、コロナ禍で「どうしても外出できない人が遺言を作れない」という問題がありました。
私のお客さんでも、入院中の方や車椅子の方が「公証役場まで行けない」と困っていました。
単純に病気や体の不自由で遺言が作れないのは不平等ですし、
もっと公平に作れる方法が必要でした。
銀行も最近はオンライン手続きが当たり前になっていますよね。
遺言書も同じように、時代に合わせて変わったのです。
遺言書だけではなく、もっとオンライン手続きができる領域が法律業務でも増えてきそうな潮目を感じますね。
重要なのは、法的効力は今までの紙の遺言書と全く同じということです。
ここが一番安心できるポイントです。便利になったからといって効力が弱くなるわけではありません。
手続きの流れについて

実際にはどんな流れで手続きが進むのですか?

実際にどんな流れで手続きが進むのか、詳しく説明していきますね。
事前準備(2週間〜1ヶ月)
まず、私たち司法書士や行政書士に相談して、遺言の内容を整理します。
これは今までと同じです。
次に、公証人と日程調整をして、遺言の草案を作ります。
ここまでが事前準備で、ケースバイケースですが2週間から1ヶ月かかります。
正直、これは今までと変わりません。
当日の進行(約1時間)
当日は、オンラインミーティングツールで全員がつながります。
- 本人確認:運転免許証やマイナンバーカードを画面に映して行います
- 内容確認:公証人が遺言の内容を読み上げて、本人の意思を確認
- 電子署名:画面上で指やタッチペンを使って名前を書いて完了
所要時間は約1時間で、これも今までとほぼ同じです。
必要書類
必要な書類はこういう物が挙げられます。
- 戸籍謄本
- 印鑑証明書
- 不動産の登記簿謄本
- 預金残高証明書など
最短で1日、通常であれば1週間程度で集められます。
戸籍法の改正などもあり、数年前と比べても書類集めはかなり楽になっています。
オンラインで遺言書作成ができるメリットとは

ここまで聞いていると、あまり変わりないような…
従来の方法と比べて、新制度にはどんなメリットがあるのですか?

実際にどんなメリットがあるのか、具体的にお話ししてきますね。
従来の方法
これまでなら「出張サービスで公証人に自宅に来てもらう」しか方法がありませんでした。
でも出張費は公証人や距離によって違って、数万円かかることもあります。
新制度のメリット
2025年10月以降なら、自宅からオンラインミーティングで約1時間で完了です。
つまり、
- 移動時間ゼロ
- 出張費もかからない
- 自宅で安心して手続きできる
ということです。
これって本当にすごい変化だと思います。
高齢の方が自宅で安心して手続きできるなんて、10年前は想像もできませんでした。
準備に必要な物と注意点について

準備には何が必要でしょうか?
また、注意点はありますか?

準備で一番大事なのは機材選びと、スケジュールの組み方です。
具体的には下記を見てください!意外とシンプルでしょう?
必要な機材4点
- ネットにつながるパソコン
- Webカメラとマイク(内蔵でOK)
- 電子署名用のタッチ画面かタブレット
- メールアドレス
私も最初聞いた時は、もっと複雑な機材が必要かと思っていましたが、意外とこれだけです。
スケジュールの重要性
実は、「来週すぐに作りたい」という方がいらっしゃいますが、これは難しいのです。
なぜかというと、必要書類の準備や郵送事故の可能性、公証人のアポイントの都合、
草案の確認など、色々な要因で時間がかかってしまうからです。
それから、遺言の内容をじっくり考えて、草案を作るのにも時間が必要です。
「誰に何を相続させるか」「遺言執行者はどうするか」など、大事な決断がたくさんあります。
だから、「遺言を作ろう」と思ったら、ケースバイケースですが2週間から1ヶ月くらい余裕を見てスケジュールを組むのがおすすめです。
オンラインで遺言が作成できる新制度はこんな方におすすめ

この新制度は、どんな方に特におすすめですか?

基本的には全ての人におすすめです。
ポイントなのは自宅や病院から動けないという方だけではなく、そもそも公証役場に行くのがめんどくさければこの制度を使えばよいということです。
こう考えると今後はほとんどの方がオンライン遺言を使うものと思われます。
例えば以下のような悩みを持っていたことは無いでしょうか?
- 「公証役場が遠い」
- 「平日は仕事がある」
- 「体調に不安がある」
私のお客さんでも「遺言書は大事だと思ってたけど、なかなか重い腰が上がらなかった」という方が多いです。
でもこの新制度なら、自宅で落ち着いて手続きできます。
手続きを進める上で、気をつけるべきポイントとは

手続きを進める上で、気をつけるべきポイントはありますか?

はい、いくつか気をつけていただきたいポイントがあります。
デジタルサポートについて
デジタルに慣れていない方は、お子さんやお孫さんにサポートしてもらうのがおすすめです。
ただし、遺言の内容は本人だけが決めることですから、そこは間違えないでください。
証人の手配方法
証人の手配も大切です。親族以外の人を2人用意する必要があります。
友人や知人にお願いするか、私たち専門家にお任せいただくか、どちらでも選べます。
準備期間の重要性
いくらオンラインになったからと言って、準備は早めにしておいた方がいいです。
なぜなら、書類集めや内容の検討、パソコンの設定など、意外と時間がかかるからです。
サポート内容について

梅澤先生のところではどんなサポートをしてもらえるのですか?

私のところでは、9月から事前準備のサポートを始めておりました。機材の選び方から、当日の流れの説明まで、しっかりお手伝いします。
「デジタルは苦手」という方でも大丈夫です。息子さんや娘さんと一緒に来てもらって、みんなで準備しましょう。
実際の手続きサポートでは、以下をトータルでお手伝いさせていただきます!
- 書類収集
- 機材設定
- 当日の立ち合い
また、無料相談も受け付けています。相続のこと、遺言のこと、何でも遠慮なく相談してください。
疑問に思ったことや、「こんな場合はどうなの?」という質問があったら、
ぜひお気軽にお問い合わせください。
この記事の監修者

遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。