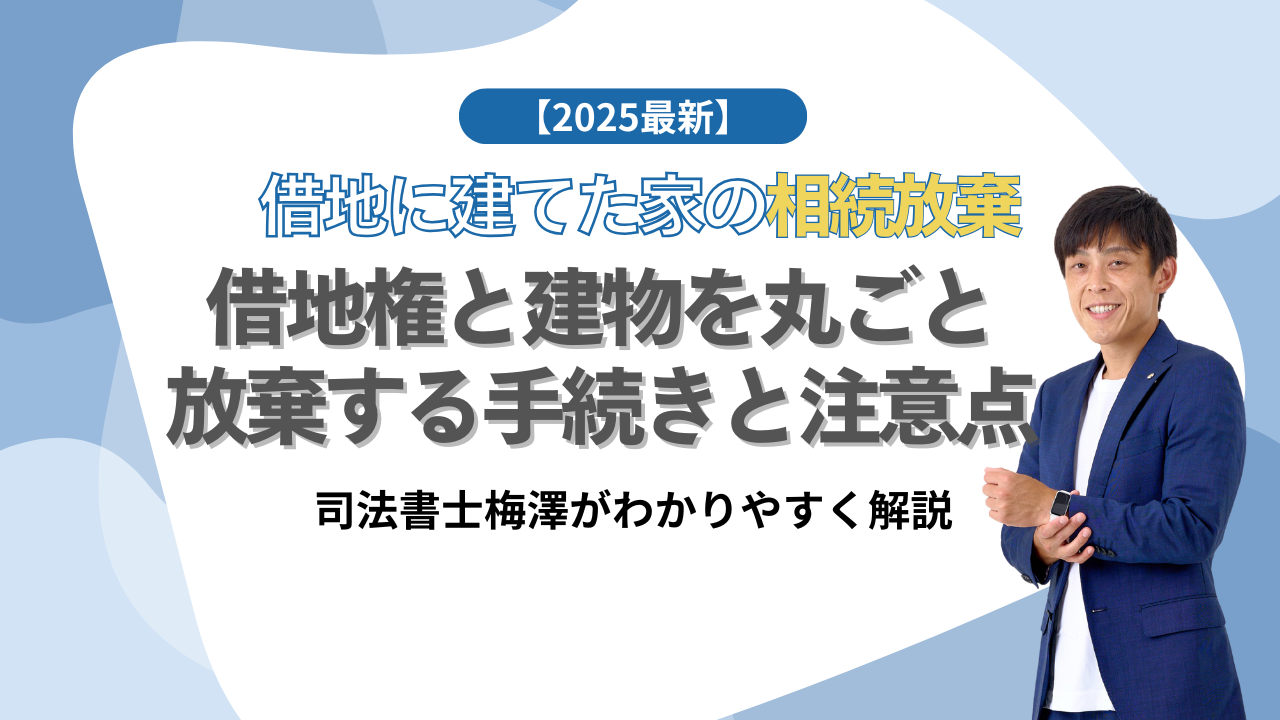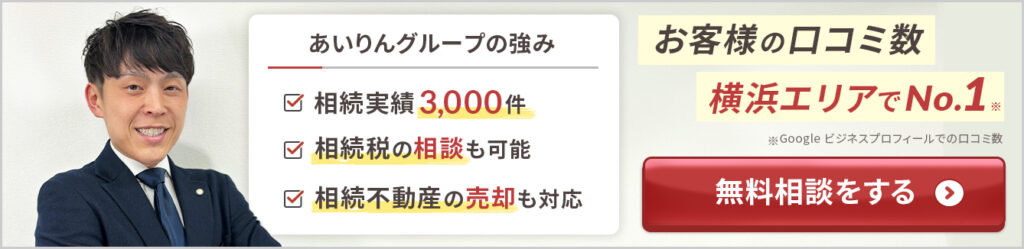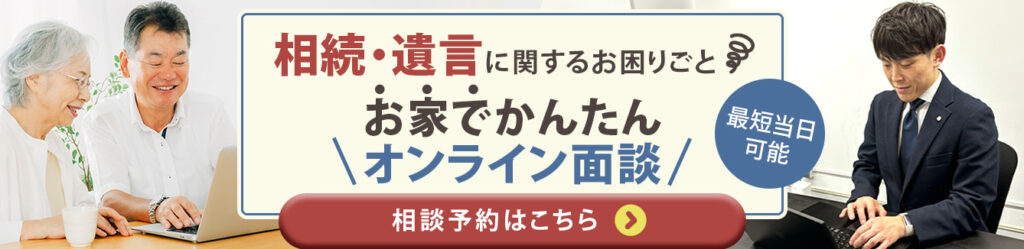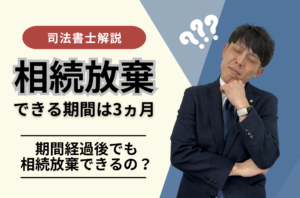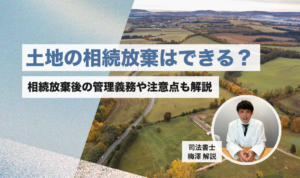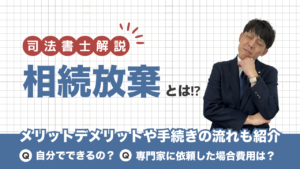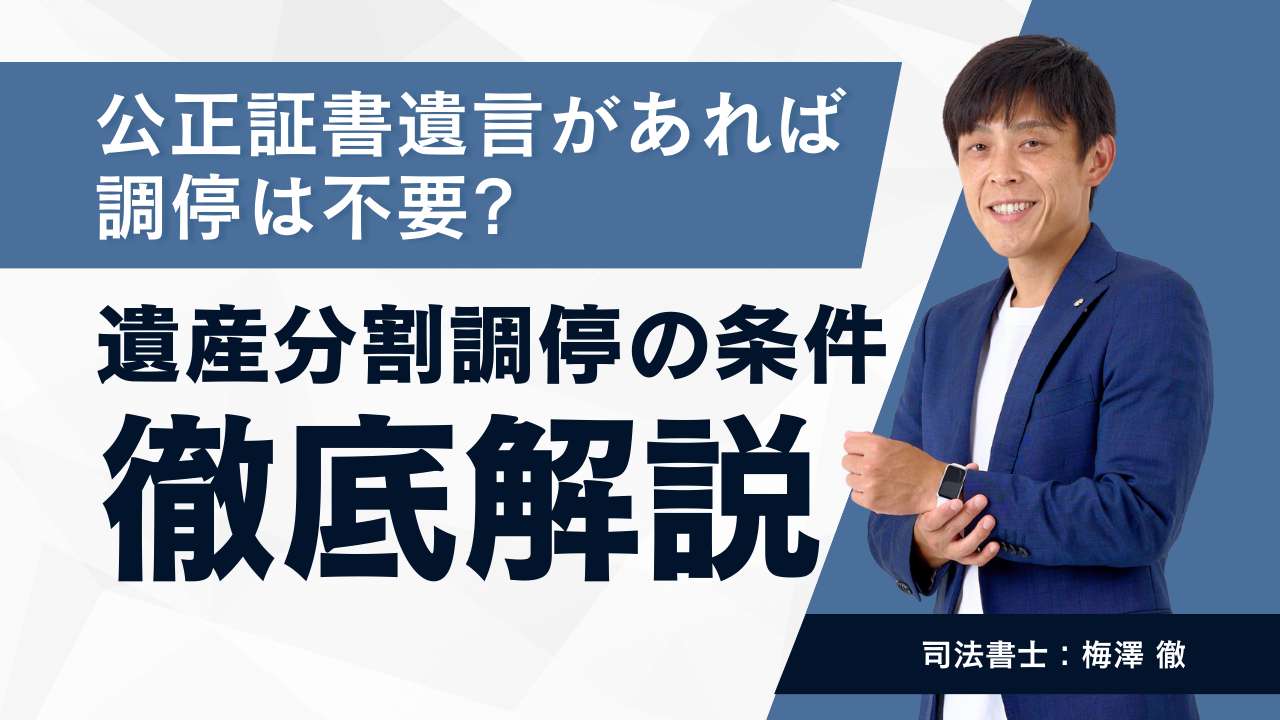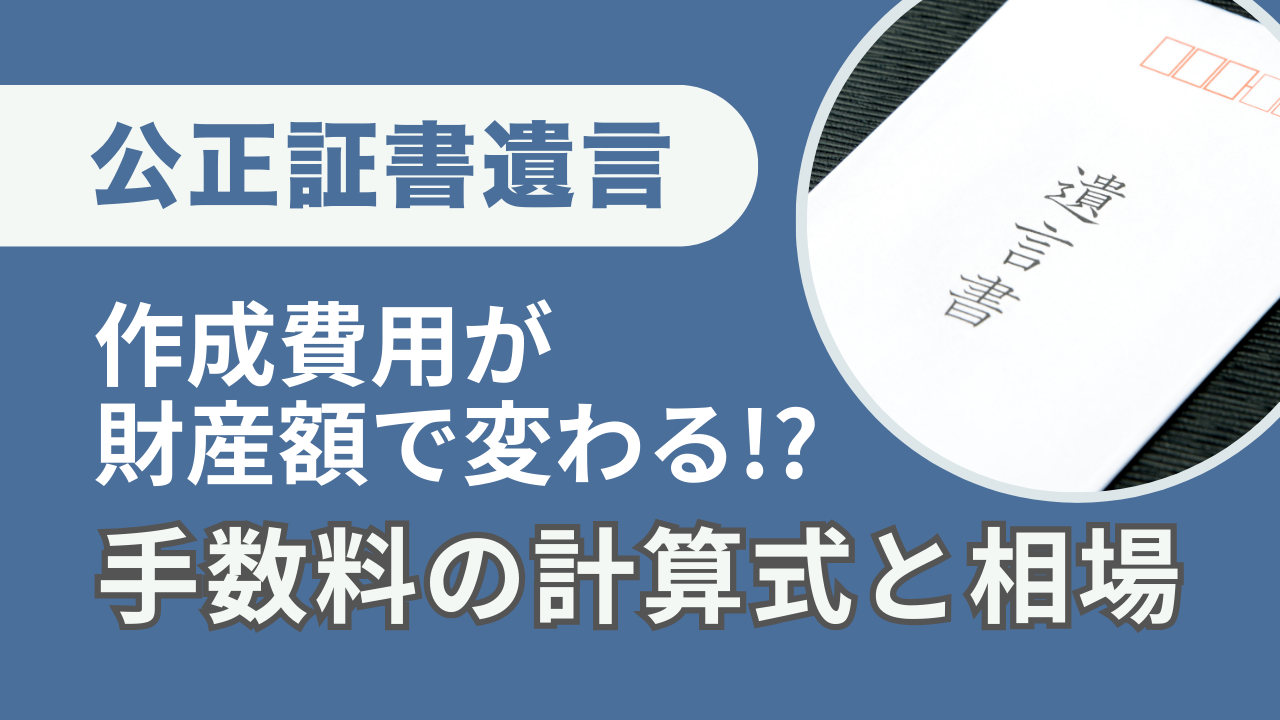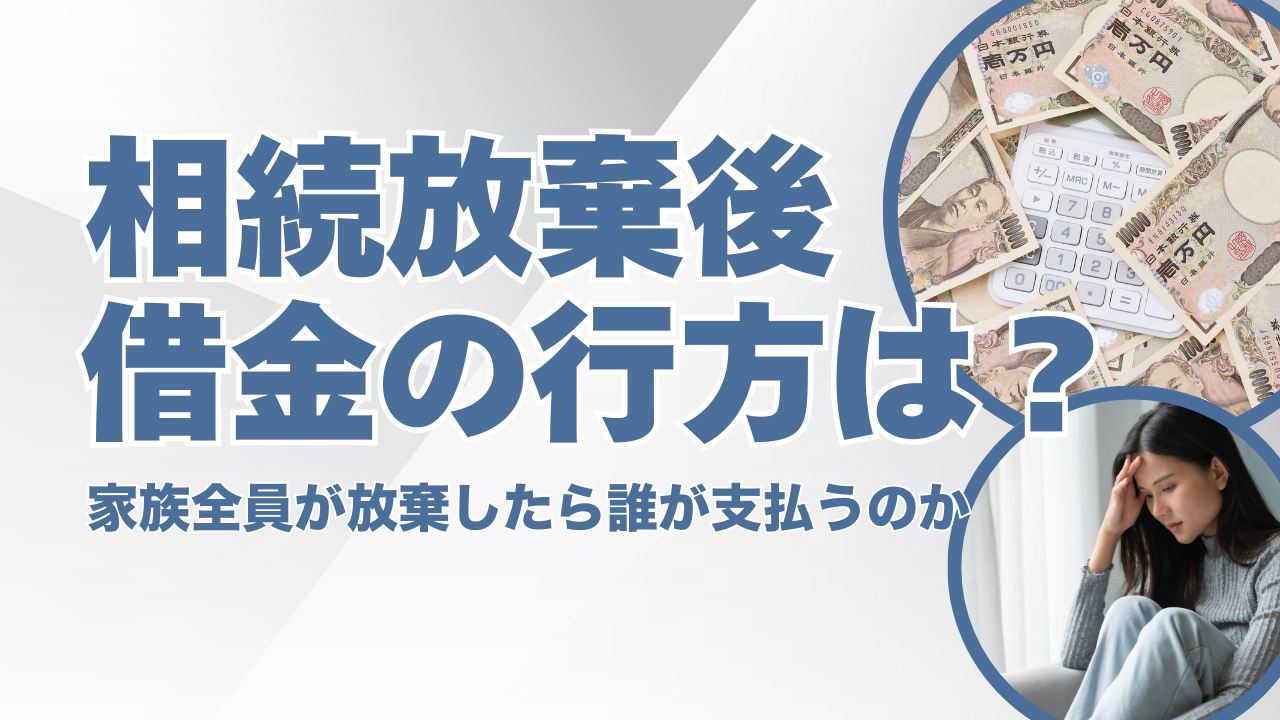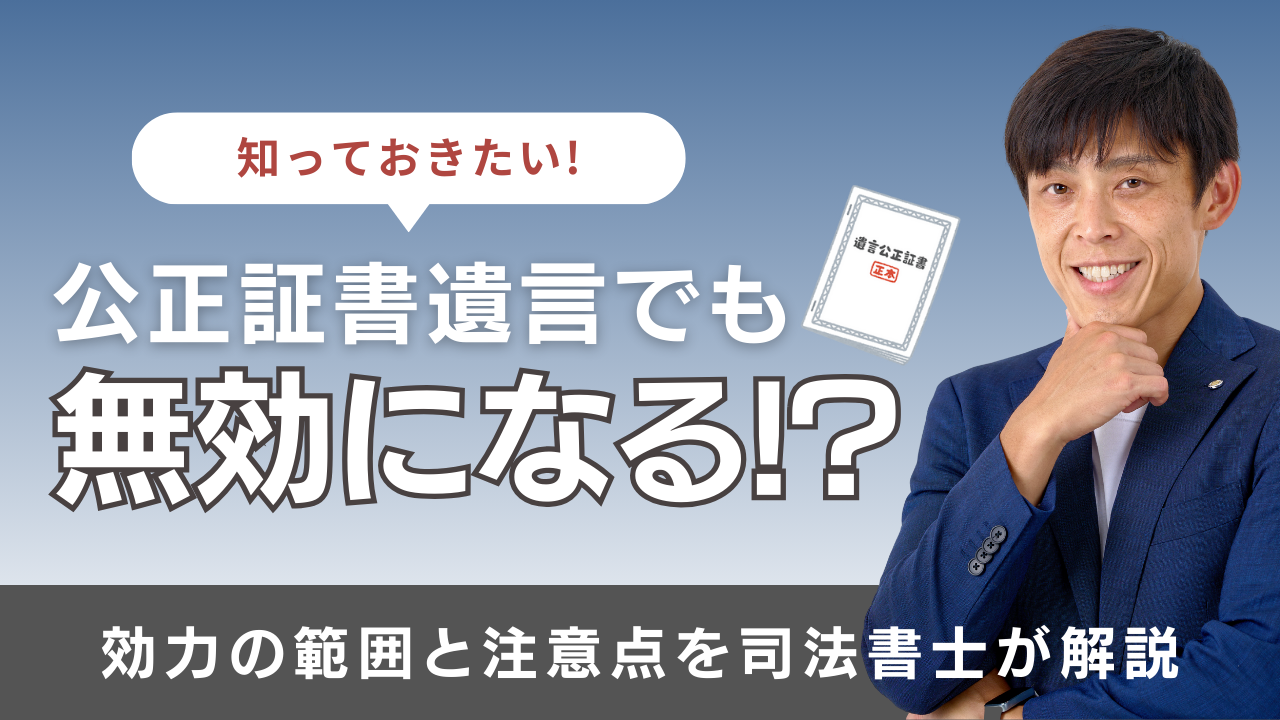この記事を要約すると
- 借地権と建物は一体扱いで別々の相続放棄は不可
- 相続放棄期限は相続開始を知った時から3ヶ月以内
- 限定承認や地主買取など代替案検討で収益確保可能
今回は、借地に建てた実家を相続したものの、
地代の負担や地主との関係を考えて相続放棄を検討している方に向けた記事です。
「借地権と建物は別々に放棄できるのか」「手続きの流れや費用はどのくらいか」など、
借地上の建物相続放棄に関する疑問にお答えします。
この記事を読むことで、借地上建物の相続放棄の正しい手続き方法と注意点が理解でき、適切な判断ができるようになります。
この記事はこんな方におすすめ
- 借地に建てた実家を相続したが地代負担を避けたい方
- 相続放棄の手続き方法と期限を正確に知りたい方
- 相続放棄以外の選択肢も含めて最適解を見つけたい方
目次
借地に建てた家の相続放棄で知るべき3つの基本知識
借地に建てた家の相続放棄を検討する際には、通常の不動産とは異なる特殊な事情があります。
一般的な不動産相続では土地と建物がセットで所有者に属しますが、借地上建物の場合は土地は地主のもの、建物のみが相続財産となる複雑な構造です。
また、借地契約に基づく地代の支払い義務や、地主との継続的な関係性も考慮しなければなりません。
「地主との関係で悩んでいる」「地代の負担が心配」「建物の維持管理費用を払いきれない」など、借地特有の複雑さで困っている方も多いのではないでしょうか。
さらに、相続後に地主との間でトラブルが発生するリスクや、将来的な建物の処分に関する制約も懸念材料となります。
このような借地上建物特有の問題を踏まえ、借地権と建物の関係性、相続放棄の期限と手続き、地主との関係性における注意点など、事前に理解しておくべき重要なポイントを3つ解説します。
借地権と建物は別々に相続放棄できない理由
借地に建てた家を相続する場合、借地権※と建物は一体として扱われるため、別々に相続放棄することはできません。
建物だけを相続放棄して借地権を相続する、または借地権だけを放棄して建物を相続することは法的に不可能です。
仮に建物だけを放棄しようとしても、借地権は自動的に放棄したものとみなされ、逆に借地権だけを放棄しようとしても、建物の所有権も同時に失うことになります。
※借地権:他人の土地を借りて建物を建てる権利
実際の相続放棄手続きでは、「借地権付建物一式」として一括で放棄の対象となります。
この点を理解せずに「建物は欲しいが地代は払いたくない」といった選択的な相続を考えていると、手続きの段階で混乱します。
借地上建物の相続を検討する際は、必ずこの一体性を前提として判断することが重要です。
相続放棄の3ヶ月期限と起算点の正確な計算方法
相続放棄の申立ては、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
最高裁判所の統計によると、相続放棄の申述件数は年々増加しており、2022年には約23万件と過去最多を記録しています。
これは高齢化社会の進展に伴い、負債が多い相続が増えていることも影響しています。
この3ヶ月の起算点は、単純に被相続人の死亡日ではありません。
相続人が「被相続人の死亡を知り、かつ、自分が相続人になったことを知った時」から計算します。
遠方に住んでいて死亡の事実を後から知った場合や、他の相続人が先に亡くなって順位が回ってきた場合は、それぞれのタイミングから3ヶ月となります。
借地上建物の場合、相続財産の調査が複雑になることが多く、期限内に判断するのが困難な場合があります。
借地契約の複雑さや財産状況の調査に時間がかかることを具体的に説明する必要があります。
このような場合は、期限を過ぎる前に家庭裁判所に期限延長の申立てを行うことができます。
申立てが認められると、通常3ヶ月程度の延長が可能です。
ただし、延長の申立てには「正当な理由」が必要で、「単に忙しかった」「手続きを忘れていた」といった理由では認められません。
借地契約の複雑さや財産状況の調査に時間を要することを具体的に説明する必要があります。
参考:相続の承認又は放棄をすべき期間 – e-Gov法令検索
地主への通知義務と建物撤去責任は誰にある?
相続放棄を行った場合でも、地主への通知義務や建物の管理責任が残る場合があります。
これは借地上建物の相続放棄において最も注意すべきポイントの一つです。
借地契約は通常、借地権者(建物所有者)の死亡によって自動的に終了するものではありません。
相続放棄により借地権を承継する者がいなくなった場合でも、契約関係は一定期間継続することになります。
相続放棄により相続人がいなくなった場合、建物は相続財産管理人※が管理することになります。
しかし、相続財産管理人が選任されるまでの間は、相続放棄した人が管理責任を負う可能性があります。
この管理責任には、建物の保全、地代の支払い義務、近隣への迷惑防止などが含まれます。
※相続財産管理人:相続人のいない財産を管理する裁判所が選任した人
地主に対しては、相続放棄の事実を速やかに通知し、借地契約の今後の取り扱いについて協議する必要があります。
建物の撤去時期や撤去費用の負担、撤去までの期間中の地代支払いなど、具体的な条件を取り決めることが重要です。
特に問題となりやすいのが建物撤去費用の負担です。
地主との契約によっては、借地契約終了時に借地権者が建物を撤去して更地にして返還する義務が定められている場合があります。
相続財産に十分な現金がない場合、この撤去費用が大きな問題となることがあります。
これらの手続きを怠ると、後から損害賠償請求される恐れがあるため、早めの対応が不可欠です。
借地の家を相続放棄する手続きと必要書類一覧
借地上建物の相続放棄手続きは、家庭裁判所への申立てから始まりますが、通常の不動産相続放棄よりも慎重な準備が必要です。
借地権付建物の場合、単純な所有権だけでなく、地主との契約関係、地代の支払い状況、建物の管理状況など、多角的な検討が必要になります。
また、申立て書類にも借地権付建物特有の記載事項があるため、正確な理解が必要です。
必要書類の準備から申立て後の注意点、さらに地主との調整まで、借地上建物特有の手続きの流れを詳しく解説します。
家庭裁判所への申立書類5点と記入例
借地上建物の相続放棄では、家庭裁判所への正確な申立てが重要になります。
手続きに不備があると受理されない可能性があるため、必要書類を確実に準備しましょう。
相続放棄の申立てには、以下の5点の書類が必要です。
書類の準備には1週間程度かかる場合があるため、期限に余裕を持って取り組むことが大切です。
必要書類一覧
- 相続放棄申述書(家庭裁判所で取得、またはWebサイトからダウンロード)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 収入印紙800円分と郵便切手(裁判所により異なる)
相続放棄申述書の記載で最も重要なのは、放棄する財産の具体的な記載です。
借地上建物の場合は「借地権付建物の相続を放棄する」旨を明記し、可能であれば土地の地番、建物の種類・構造・床面積、借地契約の概要なども記載することが推奨されます。
単に「全ての財産を放棄する」だけの記載では、後に地主や相続財産管理人との間でトラブルが生じる可能性があります。
特に借地権については、地主が相続放棄の事実を正確に把握する必要があるため、詳細な記載が重要になります。
記入例として、
「被相続人○○が所有していた○○市○○町○丁目○番○号所在の借地権(地主:○○)および同所在の木造2階建住宅(床面積○○㎡)に関する一切の権利義務を放棄いたします」
といった具体的な記載が望ましいです。
専門家へ依頼する時の手続き費用の相場
相続放棄の手続き費用は、自分で行う場合と専門家に依頼する場合で大きく異なります。
借地上建物の場合は、通常の相続放棄よりも複雑な事前調査や書類準備が必要になることが多く、専門家報酬も若干高くなる傾向があります。
費用の内訳
- 収入印紙:800円
- 郵便切手代:500円程度
- 戸籍謄本等取得費:2,000円~5,000円
- 専門家報酬(司法書士):5万円~10万円
- 借地契約書等の調査・整理費用:1万円~3万円(専門家依頼の場合)
自分で手続きを行う場合の実費は3,000円~6,000円程度ですが、借地契約の内容確認、地主との事前協議、申述書への詳細記載など、専門知識を要する作業が多いのが実情です。
書類の作成ミスや地主との調整不備により手続きが長期化するリスクを考慮すると、専門家への依頼を検討することが賢明です。
特に以下のようなケースでは専門家のサポートが特に有効です
- 地代滞納がある場合
- 地主との関係が悪化している場合
- 借地契約書が紛失している場合
- 建物に抵当権がついている場合
などです。これらの複雑な状況では、法的な判断や地主との交渉が必要になることが多く、専門家の経験と知識が大きな助けとなります。
FAQ
Q. 相続放棄に必要な書類は?
A. 申述書、戸籍謄本、住民票除票など5点が必要です。
Q. 申立て費用はいくら?
A. 収入印紙800円と郵便切手代500円程度です。
Q. 専門家に依頼すべき?
A. 借地権の複雑なケースでは専門家サポートが有効です。
相続放棄後の建物管理義務と地主トラブル回避法
相続放棄が受理された後も、建物の管理義務や地主との調整が必要になります。
「相続放棄すればすべて終わり」と思っていたのに、実はそうではないんですよね。
相続放棄により建物の所有者がいなくなると、相続財産管理人※の選任が必要になる場合があります。
この選任申立てには20万円~30万円の予納金が必要になることが多く、追加の費用負担が発生します。
※相続財産管理人:相続人のいない財産を管理する裁判所が選任した人
地主とのトラブルを避けるためには、相続放棄の手続きと並行して、建物の今後の処理について早めに相談することが重要です。解体や売却の方向性について、事前に合意を得ておくことで円滑な解決が可能になります。
地主との関係や建物管理の問題も含めて、まずは無料相談で司法書士の専門的なアドバイスを受けてください。
借地の家を相続放棄する前に検討すべき代替案
相続放棄以外にも、借地上建物の処理方法はいくつか存在します。
完全に放棄してしまう前に、あなたの状況でも収益を得られる可能性があるのではないでしょうか。
収益を得られる可能性がある代替案を検討してみましょう。
| 選択肢 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 相続放棄 | 借地権と建物を完全に放棄 | ・債務から完全に解放 ・地代負担なし |
・収益の可能性を失う ・管理責任が残る場合 |
| 限定承認 | 相続財産の範囲内で債務を支払い | ・手残り50万円の可能性 ・借地権売却収入 |
・手続きが複雑 ・時間がかかる |
| 地主買取 | 地主に借地権を直接売却 | ・地代36回分の収入 ・関係性良好維持 |
・地主の同意が必要 ・交渉が必要 |
| 国庫帰属 | 国に土地を帰属させる制度 | ・国が管理 ・処分の悩み解決 |
・審査6ヶ月 ・借地は対象外多数 |
限定承認で借地権売却|手残り50万円の可能性
限定承認※を選択することで、相続財産の範囲内で債務を支払い、余剰があれば相続する方法があります。
※限定承認:相続財産の範囲内で借金も含めて相続する方法
借地権付建物の場合、建物の築年数や立地条件によっては、借地権を第三者に売却できる可能性があります。
一般的な住宅地の借地権売却価格は、更地価格の40%~60%程度が相場となっています。
例えば、更地評価額が500万円の土地の場合、借地権売却で200万円~300万円の収入が見込めます。
債務や諸費用を差し引いても50万円程度の手残りがある場合は、限定承認の検討価値があります。
相続土地国庫帰属法の活用|審査期間6ヶ月の注意点
2023年4月に開始された相続土地国庫帰属制度の利用も検討できます。
ただし、借地権付建物の場合は、建物を解体して更地にした状態で申請する必要があります。
また、地主の同意が必要になるケースが多く、手続きが複雑になる傾向があります。
審査期間は標準的に6ヶ月程度かかり、承認されても10年分の管理費相当額(土地の種類により異なる)の納付が必要です。
借地の場合は対象外となることも多いため、事前に制度の適用可能性を確認することが重要です。
地主への借地権譲渡交渉|地代36回分の買取相場
地主に直接借地権を買い取ってもらう交渉も有効な選択肢です。
地主にとっては、借地権を買い取ることで完全な土地所有権を取得でき、将来的な活用の自由度が高まります。
買取価格の相場は、月額地代の24回分~48回分程度が一般的で、平均的には36回分程度となることが多いです。
月額地代が5万円の場合、180万円程度での買取が期待できます。
この方法なら相続放棄よりも経済的メリットが大きく、地主との関係も良好に保てます。
交渉の際は、建物の解体費用の負担割合についても併せて話し合うことが重要です。
FAQ
Q. 限定承認のメリットは?
A. 借地権売却で50万円程度の手残りが期待できます。
Q. 国庫帰属制度は使える?
A. 借地の場合は対象外となることが多いです。
Q. 地主買取の相場は?
A. 月額地代の36回分程度が一般的な相場です。
まとめ:借地の家の相続放棄は専門家と相談して慎重判断を
借地に建てた家の相続放棄は、通常の不動産相続よりも複雑な手続きと注意点があります。
借地権と建物は一体として扱われるため、別々に放棄することはできず、相続放棄の手続きには3ヶ月の期限があります。
相続放棄以外にも限定承認での借地権売却(手残り50万円の可能性)や地主への買取交渉(地代36回分の収入)など、経済的メリットのある選択肢も存在します。
2022年の相続放棄申述件数は約23万件と増加傾向にあり、借地権付建物の複雑なケースも増えています。
借地権が関わる複雑なケースでは、司法書士などの専門家に相談することで、適切な判断とスムーズな手続きが可能になります。
まずは無料相談で専門家のアドバイスを受け、あなたの状況に最適な選択肢を見つけましょう。
おすすめ記事:借地に建てた家を相続放棄する手続きの流れ|解体費用が払えない・相続したくない時の選択肢を紹介|株式会社ブリリアント
この記事の監修者

遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。