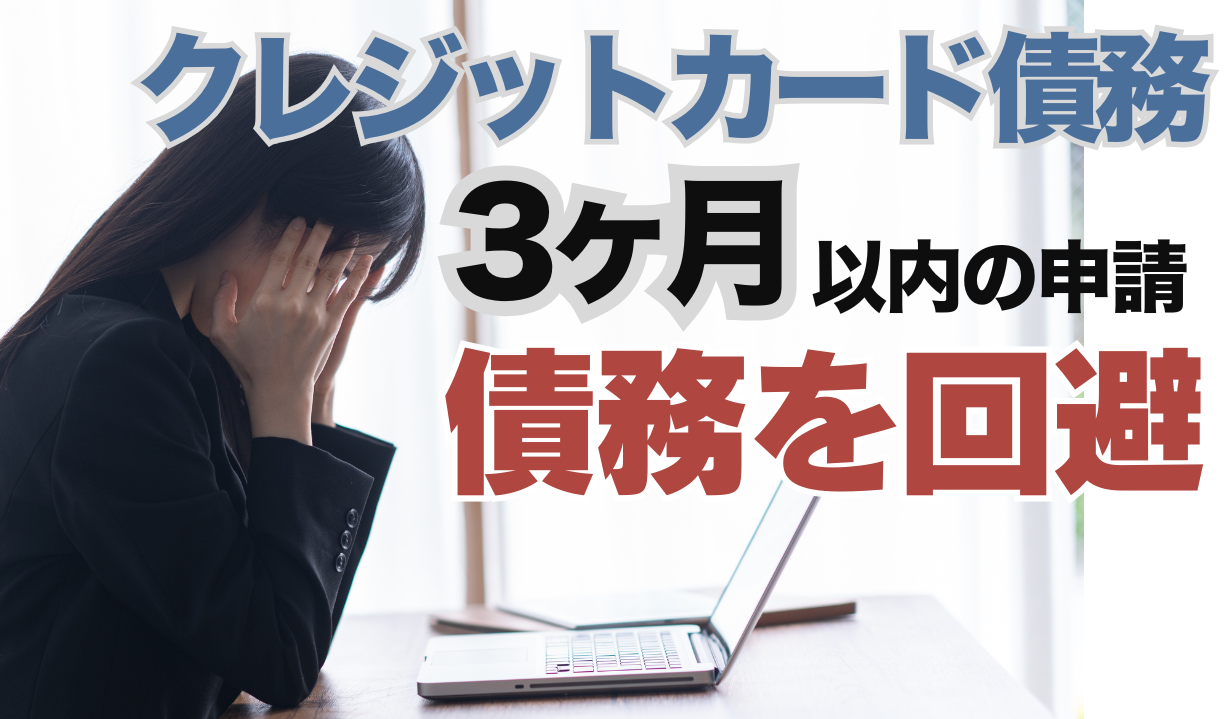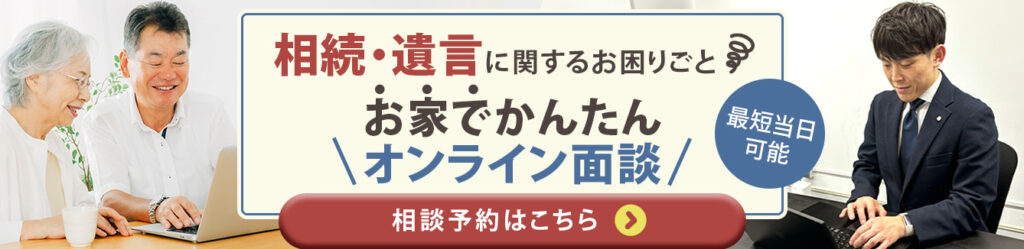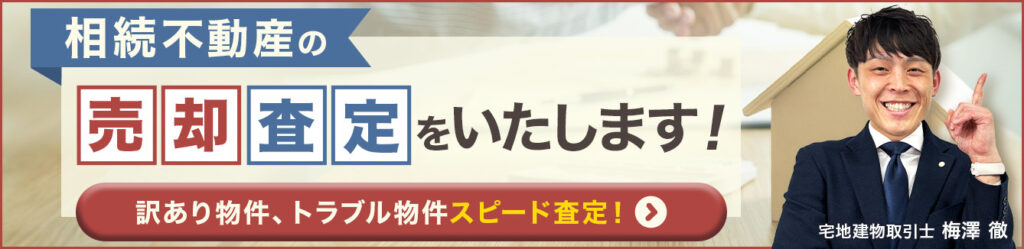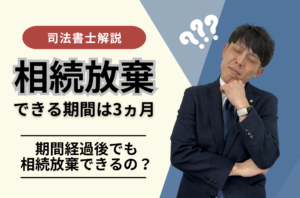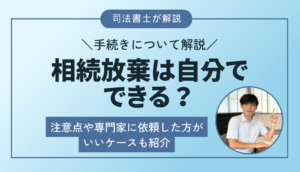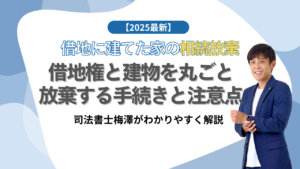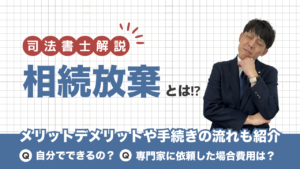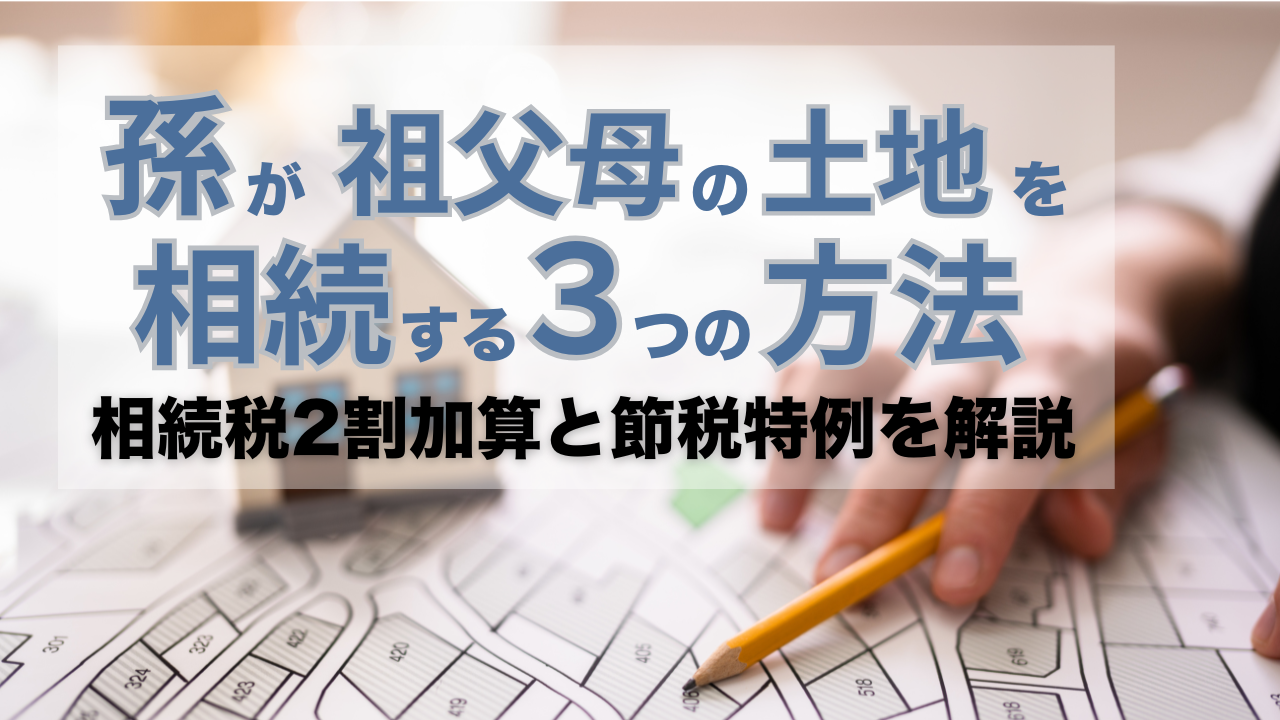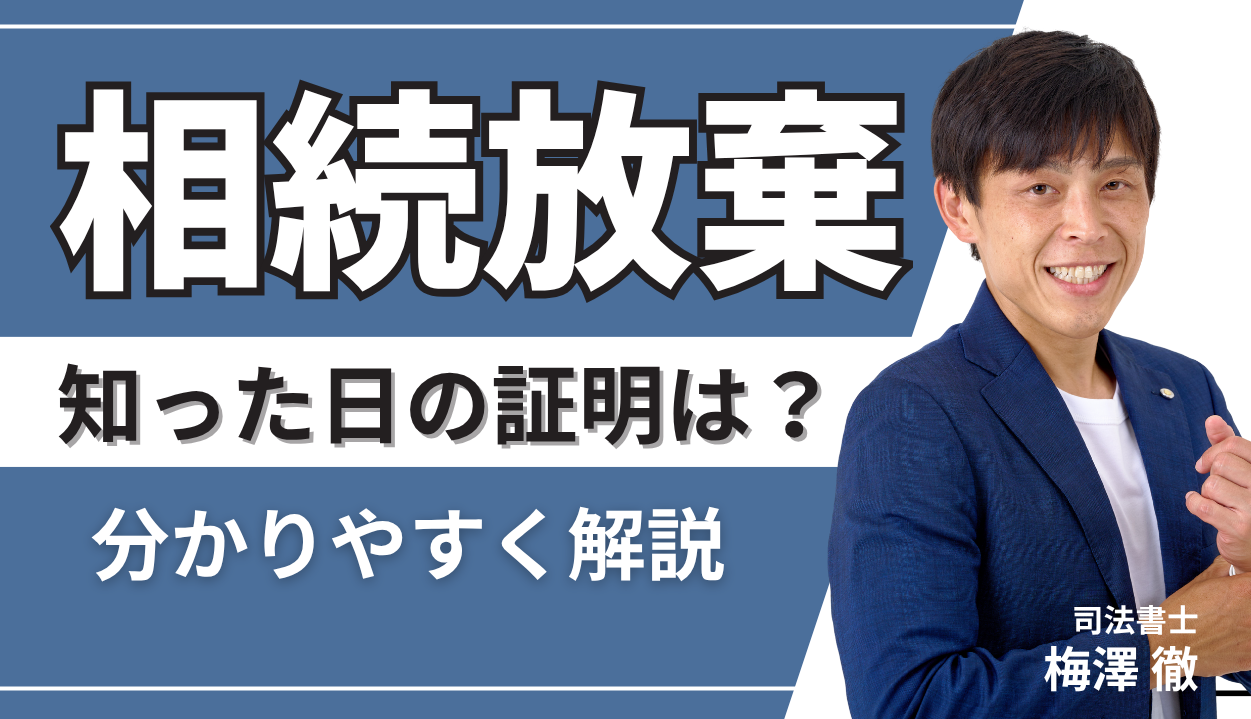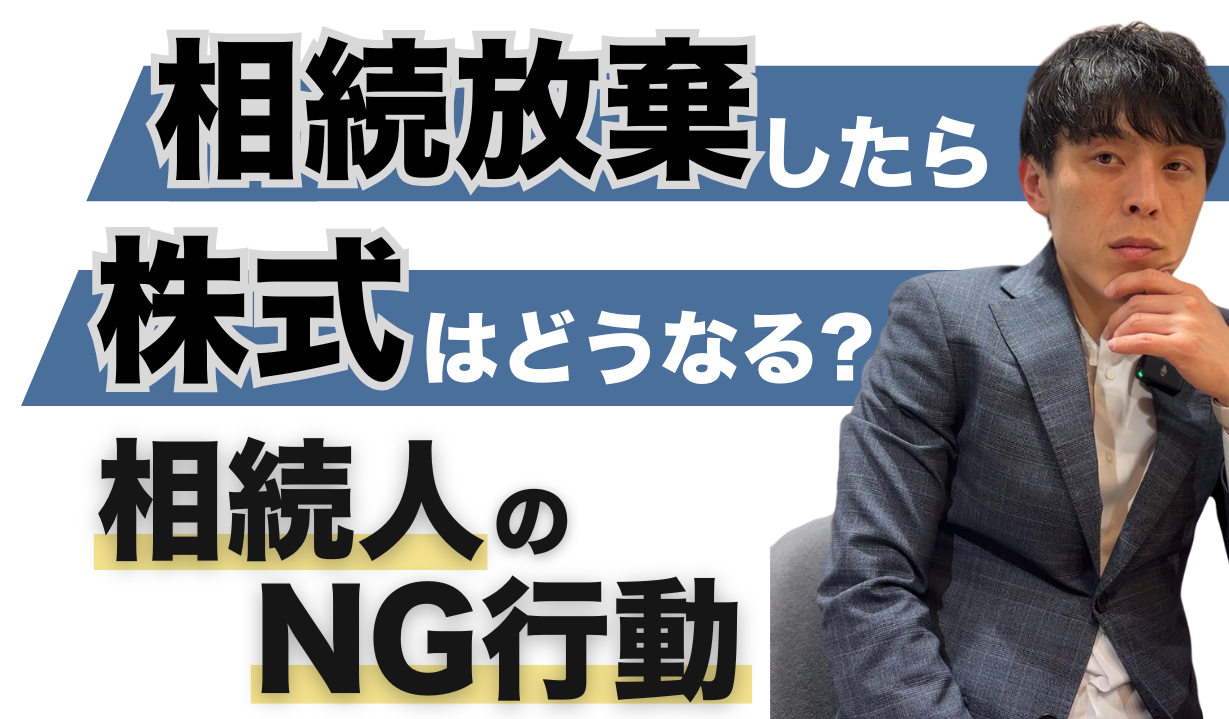この記事を要約すると
- クレジットカード債務は相続されるが相続放棄で回避可能
- 相続放棄は死亡を知った日から3ヶ月以内に申立て必須
- 債務調査と早期のカード会社連絡が成功の重要ポイント
家族が亡くなったとき、悲しみに暮れる間もなく、さまざまな手続きに追われますよね。
その中でも心配なものの一つが故人のクレジットカード債務の扱いです。
「借金まで相続してしまうの?」「どうすれば債務を引き継がずに済むの?」という不安を抱える方も多いでしょう。
こうした心配を抱えているのは、あなただけではありません。
この記事では、クレジットカード債務の相続放棄について、手続きの期限から必要書類まで詳しく解説します。
記事を読み終える頃には、適切な対応方法が分かり、安心して手続きを進められるようになります。
この記事はこんな方におすすめ
- 家族が亡くなってクレジットカード債務があることが分かった方
- 相続放棄でクレジットカードの借金を回避したい方
- 相続放棄の手続き方法や期限を知りたい方
- クレジットカード会社への対応方法を知りたい方
クレジットカード債務の相続基本知識
死亡後のクレジットカード債務はどうなる?継承される仕組み
クレジットカードの名義人が亡くなった場合、その債務は自動的に消滅するわけではありません。
法律上、故人の借金や債務は相続財産の一部として扱われ、相続人が引き継ぐこととなります。
これは「包括承継※プラス財産とマイナス財産をすべてまとめて相続する仕組み」という考え方によるものです。
例えば、故人がクレジットカードで50万円の未払い残高があった場合、配偶者や子どもなどの相続人が法定相続分
※法律で定められた相続割合に応じて債務を負担することになります。
ただし、相続人には「相続を承認する」「相続放棄をする」「限定承認※相続財産の範囲内でのみ債務を負担する手続き」の
3つの選択肢があり、必ずしも債務を引き継ぐ必要はありません。
家族カードと本人カードの債務の違いと相続への影響
家族カードと本人カードでは、債務の責任範囲が大きく異なります。
本人カード(主契約者のカード)の場合、カード名義人の死亡により、
その未払い債務はすべて相続財産となります。
リボ払いの残高、分割払いの未払い分、キャッシングの借入残高などが対象です。
一方、家族カードの場合は少し複雑です。
家族カードの利用分も最終的には主契約者の責任となるため、
主契約者が亡くなった場合は本人カードと同様に相続の対象となります。
ただし、家族カードの利用者が亡くなった場合は、
主契約者(配偶者など)が引き続き支払い義務を負うため、相続の問題にはなりません。
この違いを理解することで、適切な対応方法を選択できるでしょう。
年会費・リボ払い・キャッシング債務の相続パターン
クレジットカードの債務には、さまざまな種類があり、それぞれ相続時の扱いが異なります。
年会費については、故人の死亡時点で既に発生している分は相続債務となりますが、
死亡後に発生する分は通常免除されます。ただし、カード会社によって取り扱いが異なるため、早めの連絡が重要です。
リボ払いの残高は、最も注意が必要な債務です。
毎月の支払い額が少ないため残高が高額になりやすく、利息も継続して発生します。
相続放棄を検討する際の重要な判断材料となります。
キャッシング債務は、消費者金融からの借入と同様に扱われ、元本と利息すべてが相続の対象です。
これらの債務の合計額が相続財産のプラス分を上回る場合は、相続放棄を検討することが賢明です。
あなたの家族の場合はどのような状況でしょうか。
FAQ
Q. 相続でクレジットカード債務も引き継ぐの?
A. はい、債務も相続財産として引き継がれますが相続放棄で回避できます。
Q. 家族カードの債務は誰が負担する?
A. 主契約者が亡くなった場合は家族カードの債務も相続対象になります。
Q. リボ払いの残高はどうなる?
A. 元本と利息すべてが相続債務となるため注意が必要です。
相続放棄で債務を回避する方法
相続放棄の申請期限3ヶ月以内の具体的手続きの流れ
相続放棄には厳格な期限があり、「相続があったことを知った日」から3ヶ月以内に手続きを完了する必要があります。
「もう時間がない」と焦っている方もいらっしゃるかもしれませんが、適切な手順を踏めば大丈夫です。
参考:相続の承認又は放棄をすべき期間-民法第九百十五条 – e-Gov法令検索
手続きの流れは次の通りです
- 相続財産の調査(1〜2週間)
- 必要書類の収集(1週間程度)
- 家庭裁判所への申立書提出
- 裁判所からの照会書への回答(約2週間後)
- 相続放棄受理証明書の交付
重要なのは、この3ヶ月間に相続財産を処分したり、債務の一部でも支払ったりすると
「単純承認※相続を受け入れたとみなされる行為」とみなされ、
相続放棄ができなくなることです。
そのため、相続放棄を検討している間は、
故人のクレジットカード債務の支払いや相続財産の処分は一切行わないよう注意が必要です。
期限に余裕を持って手続きを進めるため、できれば死亡から1〜2ヶ月以内には申立てを行うことをお勧めします。
クレジットカード債務の相続放棄申立てに必要な書類と費用800円の内訳
相続放棄の申立てには、以下の書類と費用が必要です。
必要書類
- 相続放棄申述書(家庭裁判所で入手可能)
- 故人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
- 申述人の戸籍謄本
- 故人の住民票除票または戸籍附票
費用の内訳
- 収入印紙:800円
- 連絡用の切手代:約500円程度(裁判所により異なる)
申述書には、相続放棄をする理由を明確に記載する必要があります。
「債務が財産を上回るため」という理由が一般的です。
書類は故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
郵送でも受け付けてもらえるため、遠方の場合でも手続き可能です。
申立て後、約2週間で裁判所から照会書が送られてくるので、
内容を確認して返送すれば手続き完了です。
相続放棄が認められない7つのケースと回避策
| 却下されるケース | 具体例 | 回避策 |
|---|---|---|
| 期限超過 | ・3ヶ月期限を過ぎている | ・期間伸長申立てを活用 ・早めの手続き着手 |
| 財産処分 | ・相続財産を処分している ・債務の一部を支払っている |
・財産に一切手をつけない ・支払いは避ける |
| 不正行為 | ・相続財産を隠匿している ・申述書の記載に虚偽がある |
・正直な申告 ・適切な書類作成 |
| 手続き参加 | ・遺産分割協議に参加済み ・相続財産から利益を得ている |
・協議前に放棄手続き ・利益受領は避ける |
相続放棄は必ず認められるわけではありません。
以下の7つのケースでは申立てが却下される可能性があります:
- 3ヶ月の期限を過ぎている
- 相続財産を処分している
- 債務の一部を支払っている
- 相続財産を隠匿している
- 申述書の記載に虚偽がある
- 既に遺産分割協議に参加している
- 相続財産から利益を得ている
回避策として最も重要なのは、相続放棄を検討している間は
故人のクレジットカード債務の支払いや相続財産の処分を一切行わないことです。
また、葬儀費用の支払いについては、社会通念上相当な範囲であれば相続放棄に影響しないとされていますが、高額な場合は問題となる可能性があります。
期限の延長が必要な場合は、3ヶ月の期限内に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを行うことで、
さらに3ヶ月程度の延長が可能です。
個別の状況により最適解が異なるため、まずは無料相談で専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
FAQ
Q. 相続放棄の期限は?
A. 相続開始を知った日から3ヶ月以内です。
Q. 相続放棄の費用は?
A. 収入印紙800円と切手代約500円程度です。
Q. 相続放棄が却下されることはある?
A. 財産処分や期限超過など7つのケースで却下される可能性があります。
時期別の対応手順と注意点
死亡直後7日以内にすべきクレジットカード会社への連絡
家族が亡くなったら、可能な限り早くクレジットカード会社に連絡することが重要です。
連絡の際に伝える内容
- 契約者の死亡年月日
- 連絡者と故人との関係
- カードの利用停止依頼
- 債務残高の照会依頼
多くのカード会社では、死亡の連絡を受けると即座にカードの利用を停止し、それ以降の利息や延滞損害金の計算を止めてくれます。
また、家族カードがある場合も同時に利用停止となるため、家族に事前に知らせておくことが大切です。
連絡が遅れると、不正利用の可能性もあるため、カードの発見次第、
速やかに連絡を取りましょう。カスタマーセンターは24時間対応している会社が多いので、
深夜早朝でも連絡可能です。
この段階では、まだ債務の承継について決める必要はありません。
まずは利用停止と残高確認が最優先です。
1ヶ月以内の債務調査と相続財産の把握方法
相続放棄を適切に判断するため、故人の財産と債務を正確に把握する必要があります。
債務調査の方法
- 信用情報機関への照会(CIC、JICC、KSCの3機関)
- 郵送物の確認(請求書、明細書など)
- インターネットバンキングやアプリの確認
- 金融機関への残高照会
財産調査の方法
- 預貯金通帳の確認
- 不動産の権利証や固定資産税納税通知書の確認
- 有価証券や保険証券の確認
- 貸金庫の有無確認
この調査により、相続財産全体でプラスかマイナスかを判断できます。
債務が財産を大きく上回る場合は相続放棄、僅差の場合は限定承認を検討します。
最高裁判所の統計によると、相続放棄の申述件数は年々増加傾向にあり、
令和4年には約24万件に達しています。
これは、相続債務の問題に直面する家庭が増加していることを示しています。
調査には時間がかかるため、並行して相続放棄の準備も進めておくことをお勧めします。
3ヶ月期限前の最終確認事項と手続き完了のポイント
相続放棄の申立て前に、最終確認すべき事項があります。
確認事項
- すべての債務と財産の把握が完了しているか
- 相続放棄する相続人全員の意思統一ができているか
- 次順位の相続人への影響を検討したか
- 必要書類がすべて揃っているか
特に重要なのは、次順位相続人への配慮です。例えば子ども全員が相続放棄をすると、
故人の両親や兄弟姉妹が相続人となり、債務を負担する可能性があります。
事前に関係者全員で話し合い、必要に応じて全員が相続放棄をするよう調整することが大切です。
手続き完了後は、相続放棄受理証明書をクレジットカード会社に提出し、債務の免責を正式に通知します。
これにより、法的にクレジットカード債務から解放されます。
手続き前の財産調査から申立て後の対応まで、専門家によるサポートを受けることで安心して進められます。
FAQ
Q. 死亡直後にすべきことは?
A. 7日以内にクレジットカード会社へ連絡して利用停止を依頼します。
Q. 債務調査はどのように行う?
A. 信用情報機関への照会と郵送物確認で全債務を把握します。
Q. 次順位相続人への影響は?
A. 子どもが放棄すると両親や兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
まとめ:クレジットカード債務の相続放棄で家族を守る方法
クレジットカード債務の相続放棄は、適切な手順を踏めば確実に債務を回避できる有効な方法です。
最重要ポイントは3ヶ月の期限厳守、債務の支払いや相続財産の処分を行わないこと、そして早期のカード会社連絡の3つです。
手続きには専門的な知識と正確な判断が必要であり、一度の失敗が家族全体の将来に大きな影響を与える可能性があります。
相続放棄の可否判断、書類作成、裁判所対応など、複雑な手続きをスムーズに進めるためには、
相続に精通した司法書士のサポートが不可欠です。
当事務所では、クレジットカード債務の相続放棄に関する無料相談も承っております。
お一人で悩まず、まずは専門家にご相談いただき、ご家族にとって最適な解決策を一緒に見つけていきましょう。
適切な判断と迅速な対応で、安心できる未来を築くお手伝いをいたします。
この記事の監修者

遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。