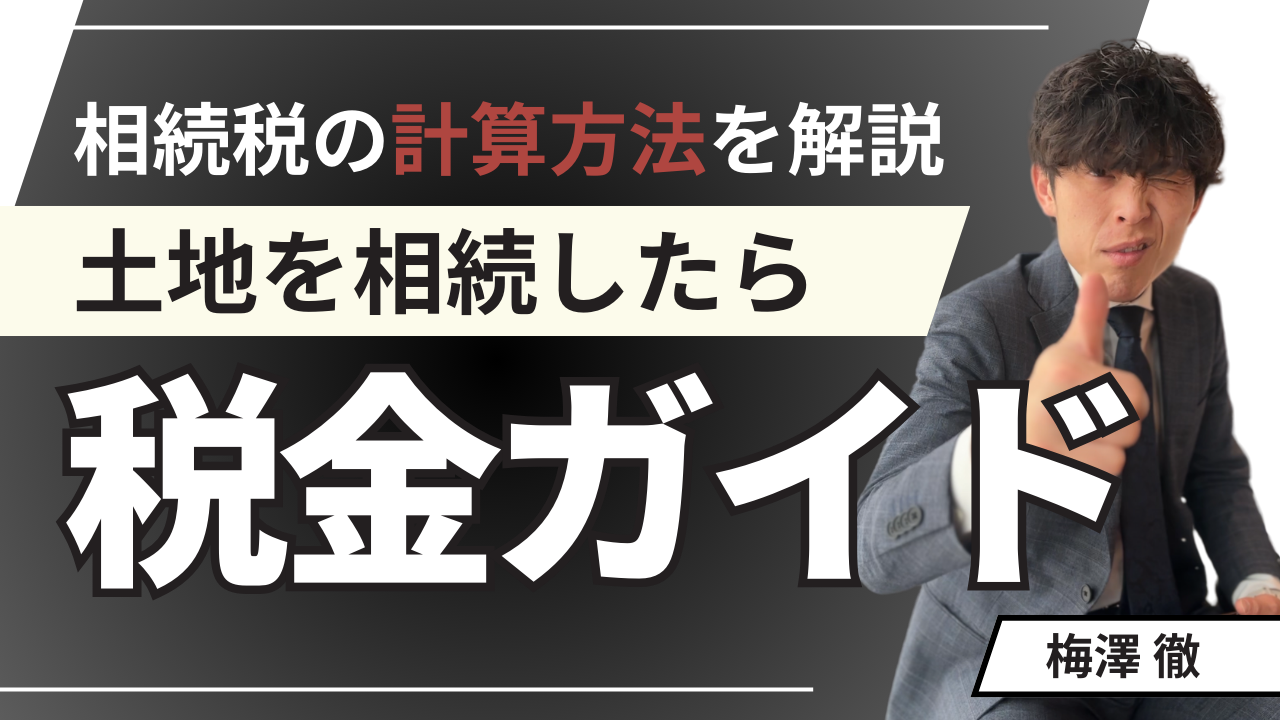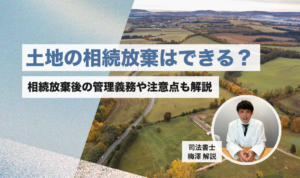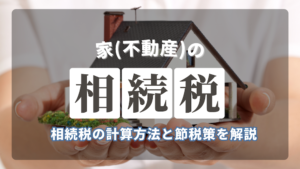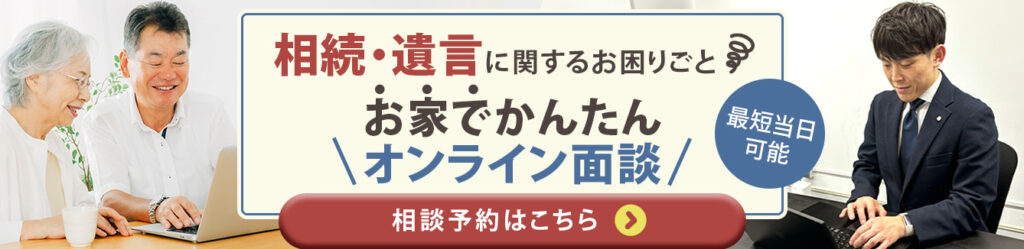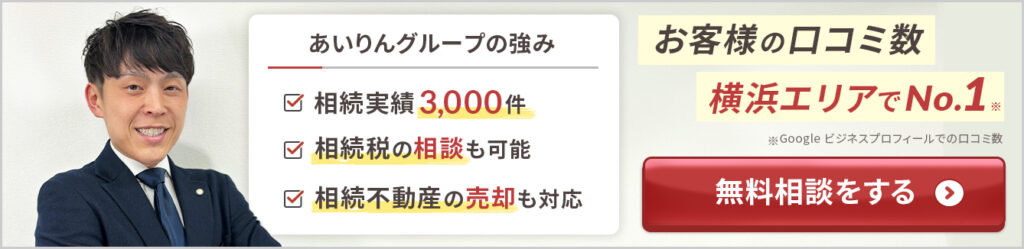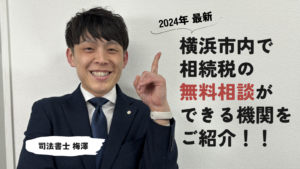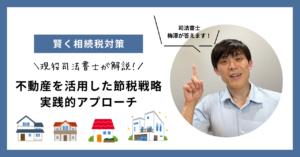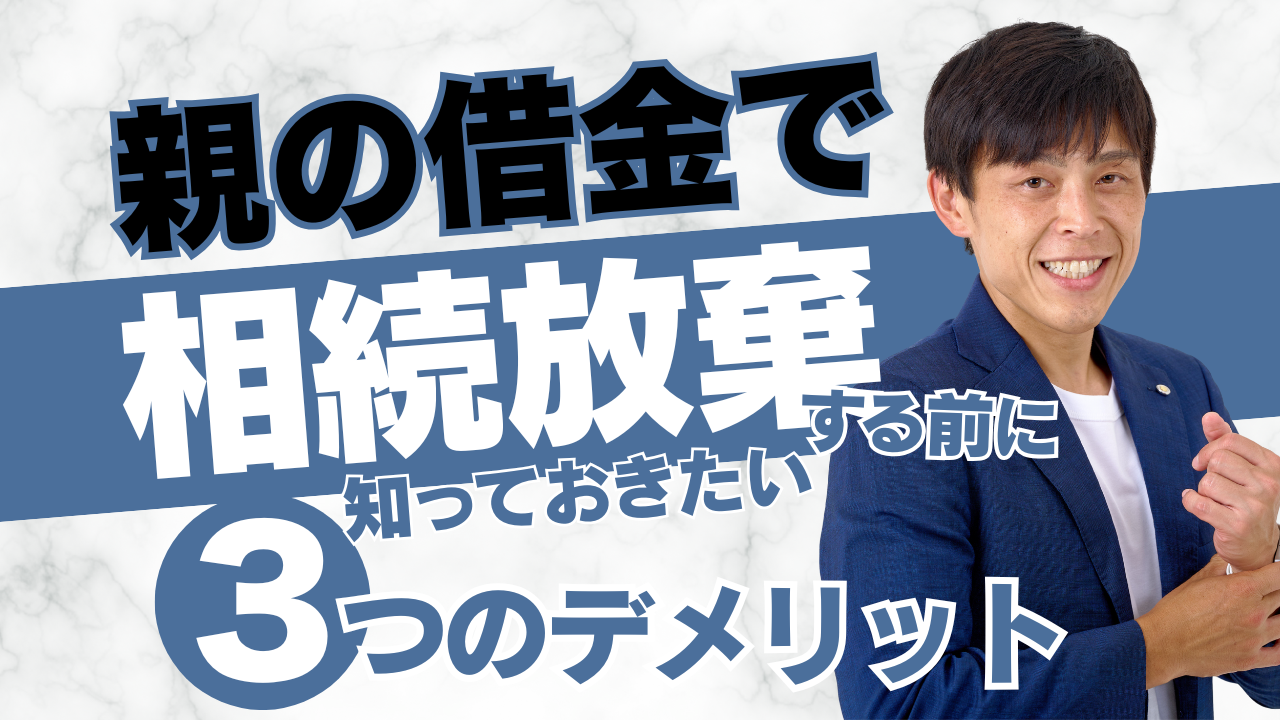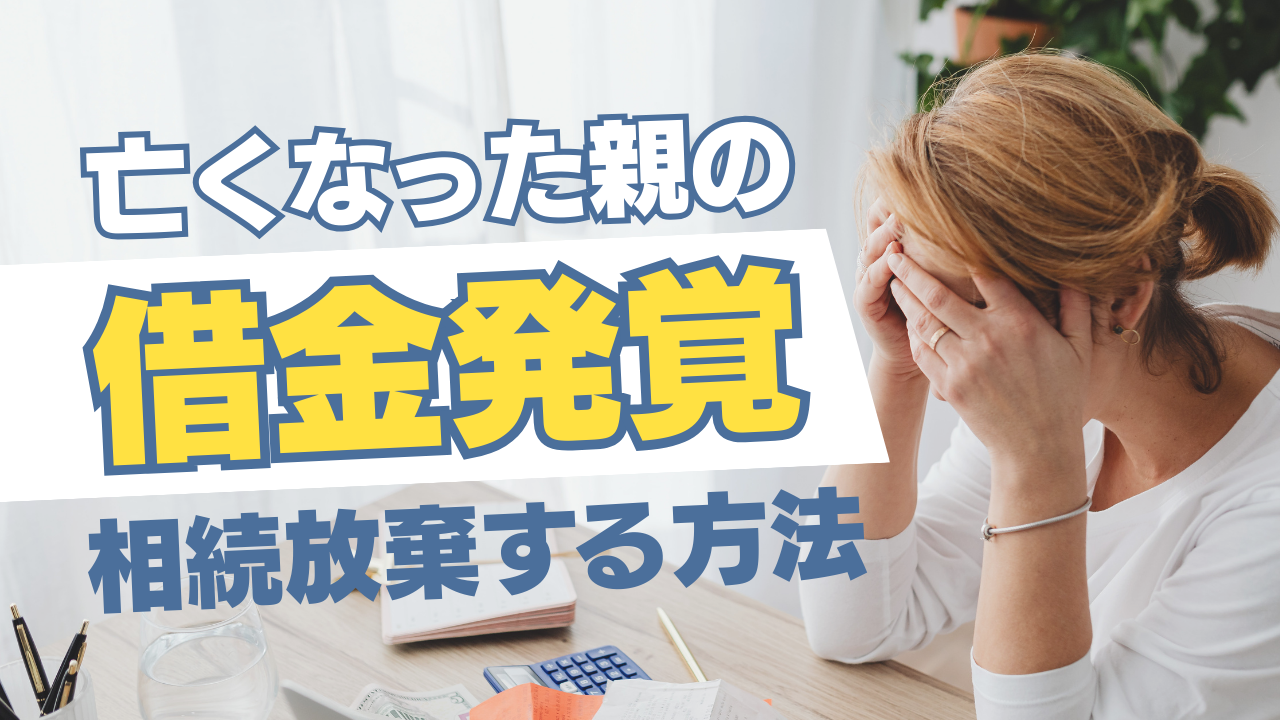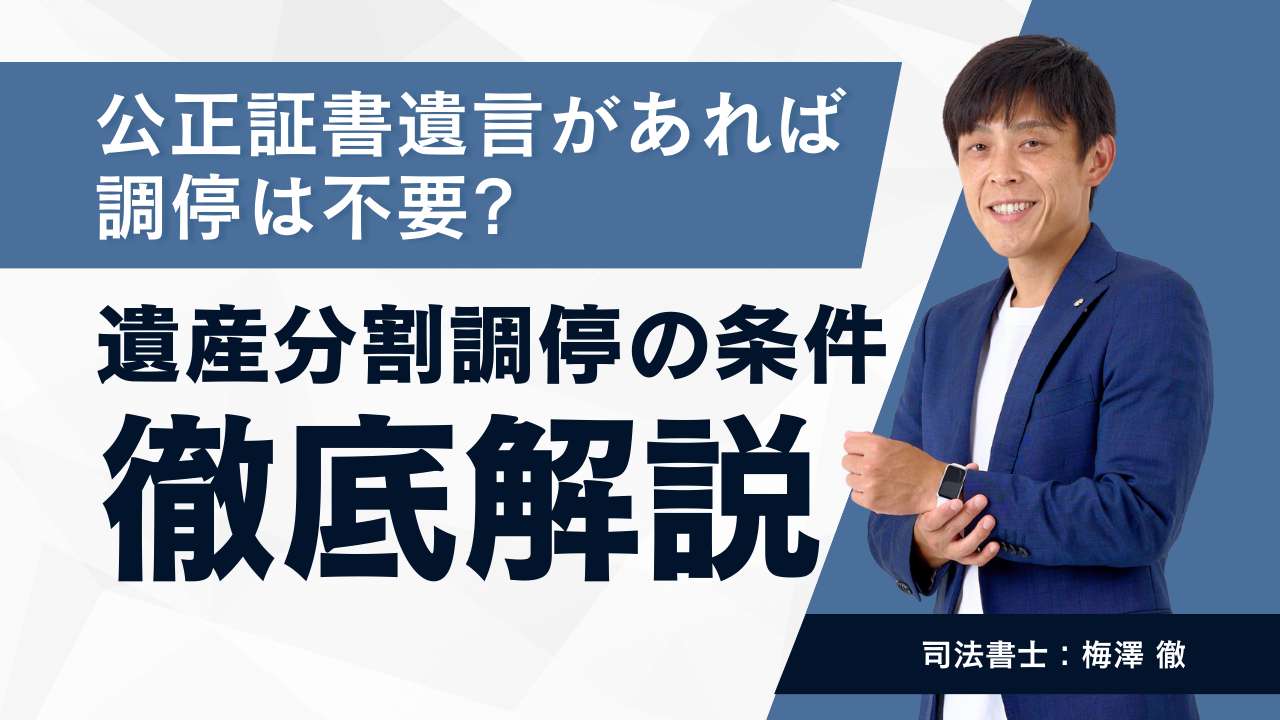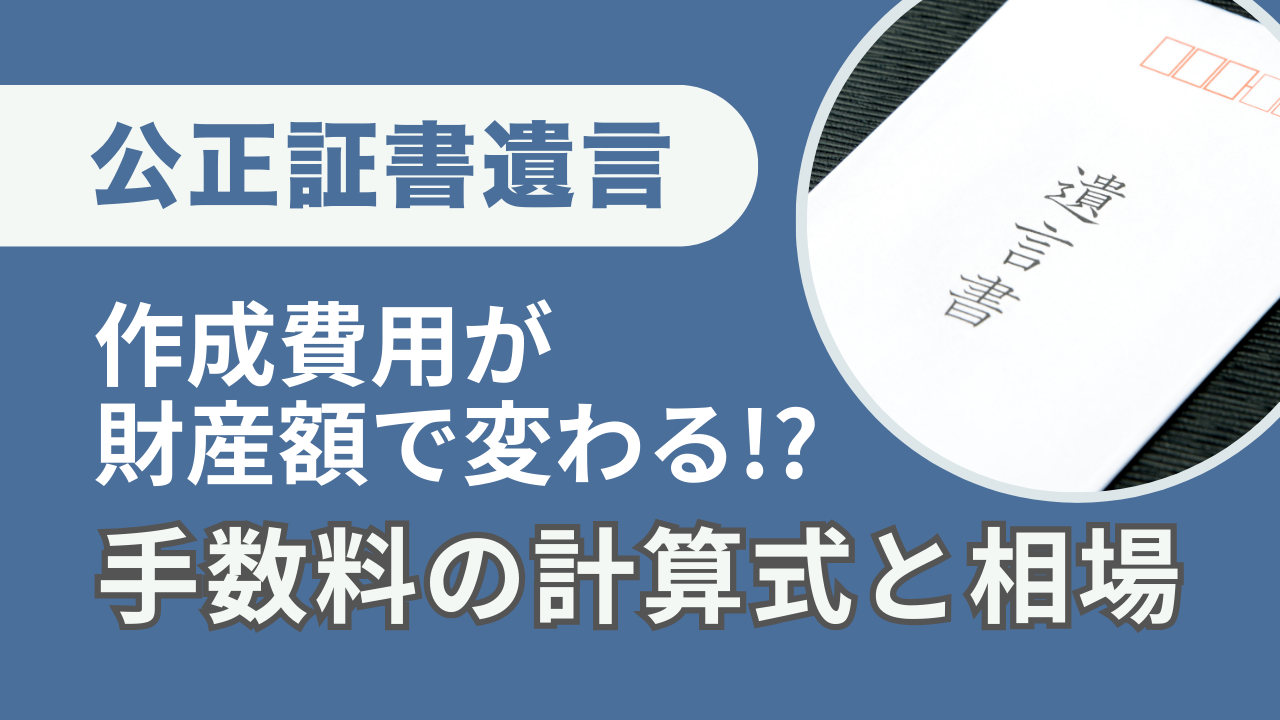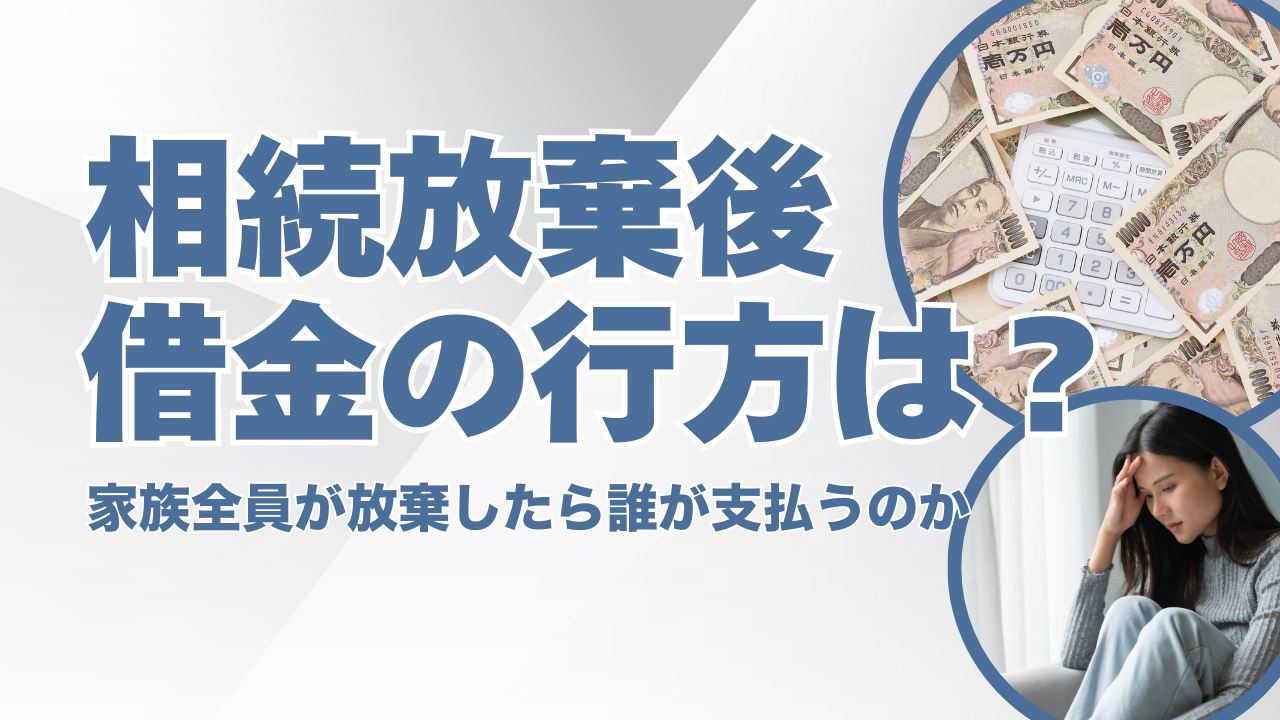この記事を要約すると
- 土地の相続した場合、相続税は土地を含む相続財産の全てに対して課税される
- 土地を相続すると、相続税の節税になる場合がある
- 相続した土地を売却せずに活用するのも、相続税対策として有効である
「親から土地を相続したけど、税金のことが全くわからない…」そんな不安を抱えていませんか?相続税は複雑で難しそうに感じますが、基本を押さえれば対策も可能です。
本記事では、土地の相続税の基本と節税のポイント、相続後の土地活用法までわかりやすく解説します。知っているか知らないかで、数百万円の差が出ることもあるのが相続税です。
相続税を正しく理解して、“損をしない相続”を目指しましょう。
土地を相続したらまず確認!相続税で損しない3ステップ
土地の相続は人生において何回もあるものではありません。そのため「どこから手を付けたらよいかわからない」という方も少なくないでしょう。
相続税の概要を知らないと、手続き方法がわからないだけではなく、相続税で損をしてしまう可能性もあります。
ここでは、親や知人などから土地を相続したらまず確認すべき3つのステップをご紹介します。相続税で損をしないためにも正しく理解しましょう。
1.土地の相続税は誰が払う?課税対象と相続人をチェックしよう
相続税とは、遺産を受け継いだ相続人が支払う税金のことです。相続税が課税される財産には、現金や株などの有価証券だけでなく、土地や建物などの不動産も含まれます。
被相続人が所有していた土地も相続税の課税対象です。
土地の相続税を支払うのは、相続によって土地の所有権を取得した相続人だけではありません。相続税は、土地にかかる相続税を他の相続財産にかかる相続税と分けて課税するのではないためです。
土地を含む相続財産を全て合計した総額をもとに、課税対象となる遺産額を出し、そこから算出した相続税額を相続人で按分して納税します。
そのため、相続税を算出する際は、課税遺産の総額の算出方法と相続人の法定相続割合を把握しておくと安心です。
課税遺産の総額を算出するには、以下の手順でおこないます。
- 相続する全ての遺産を足して総額を算出する
- 遺産額の総額から葬儀費用や債務、非課税財産、経費などを差し引いて、課税遺産の総額を算出する
法定相続割合の主な例は、以下のとおりです。
| 相続人 |
法定相続分の割合 | |
| 子がいる場合の相続人 | 配偶者 | 遺産の2分の1 |
| 子 | 遺産の2分の1を子の人数で分ける | |
| 子がいない場合の相続人 | 配偶者 | 遺産の3分の2 |
|
父母 |
遺産の3分の1を父母で分ける | |
| 子も父母もいない場合の相続人 | 配偶者 | 遺産の4分の3 |
|
兄弟姉妹 |
遺産の4分の1を兄弟姉妹の人数で分ける |
|
参考:国税庁ホームページ|財産を相続したとき|法定相続分の主な例
例えば、相続財産が3000万円で、相続人が配偶者と子ども2人だった場合、配偶者が財産の2分の1なので1500万円、子ども2人がそれぞれ財産の4分の1の750万円ずつを相続します。
2.土地の相続税の税額はこう計算する!基礎控除・評価額・税率の仕組みを知ろう
具体的に土地の相続税を計算する方法を解説しましょう。土地の相続税の算出には、次の4つの項目を理解することが重要です。
- 基礎控除
- 評価額
- 相続税の税率
- 税額の計算方法
ひとつずつ詳しく解説しますので、しっかり理解して相続税の税額を計算する際に参考にしてください。
基礎控除
財産を相続しても、必ず相続税が課税されるわけではありません。相続税には基礎控除があるため、相続した財産の総額より基礎控除額が多い場合は相続税は課税されません。
| 相続財産の総額<基礎控除額 | 相続税は課税されない |
| 相続財産の総額=基礎控除額 | |
| 相続財産の総額>基礎控除額 | 相続税が課税される |
相続税の基礎控除額は以下のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人だった場合の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×3=4,800万円」となり、相続財産の総額が4,800万円より多い場合に相続税が課税されます。遺産総額が6000万円だった場合、6000万円-4800万円=1200万円が課税相続財産です。
評価額
土地の相続税を計算する際に基準となる土地の価格は、市場で売買される際の売却価格(時価)ではなく、土地の相続税評価額です。
相続税評価額の算出方法には、路線価方式と倍率方式の2種類があります。
・路線価方式
路線価方式では、路線価をもとに土地の評価額を算出します。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、設定されているのは主に市街地です。
路線価は、国税庁のHPに公表されている「財産評価基準書」の「路線価図」から確認できて、千円単位で表示されています。例えば、200と表示されている場合の路線価は20万円です。
路線価方式による土地の相続税評価額の計算方法は以下のとおりです。
土地の相続税評価額=路線価×持分割合×土地面積×補正率
例えば、路線価が20万円、持分割合1/1、土地面積150㎡、補正率が1.0の場合の評価額は「20万円×1×150㎡×1.0=3,000万円」となります。補正率は土地の形状などにより設定されており、国税庁のホームページより確認できます。
・倍率方式
路線価が設定されていない地域では、「固定資産税評価額」に国が定めた評価倍率をかけて、相続税評価額を算出します。評価倍率は国税庁のHPに掲載されています。
倍率方式による相続税評価額の計算方法は以下のとおりです。
土地の相続税評価額=固定資産税評価額×評価倍率
例えば、固定資産税評価額が3,000万円で評価倍率が0.9だった場合の評価額は「3,000万円×0.9=2,700万円」となります。
相続税の税率
相続税の税率は、法定相続分に応じて取得した遺産の金額により異なります。以下に、主な税率を表にまとめました。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | – |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
※参照:国税庁ホームページ|財産を相続したとき|相続税の速算表
例えば、法定相続分に応じて按分した課税相続財産が800万円だった場合の税率は10%、4500万円だった場合の税率は20%で控除額が200万円となります。
税額の計算方法
土地を含む相続財産の相続税の税額は、次の6つのステップで算出できます。
| ステップ1 | 土地の相続税路線価と現金や株などの有価証券など相続した財産を足して総額を出し、葬儀費用などを差し引いて、相続財産の総額を算出する |
| ステップ2 | 相続財産の総額から基礎控除を差し引いて、課税相続財産を算出する |
| ステップ3 | 課税相続財産の総額を、法定相続分に応じて按分する |
| ステップ4 | 按分された課税相続財産に税率税額をかけて、法定相続人ごとの相続税額を算出する |
| ステップ5 | 4で算出した法定相続人の相続税額を合計する |
| ステップ6 | 5で合計した相続税額の相続を実際の相続割合に応じて、按分する |
例として、土地の評価額が3000万円、現金と株の価額の合計が1億8000万円、葬儀費用などの経費1000万円、相続人が配偶者と子ども2人だった場合の相続税額を計算しましょう。
| ステップ1 | 3000万円+1億7000万円-1000万円=2億円(相続財産の総額) |
| ステップ2 | 2億円-基礎控除(3000万円+600万円×3)=1億5200万円(課税相続財産) |
| ステップ3 | 1億5200万円×2分の1=7600万円(配偶者) 1億5200万円×4分の1=3800万円(子ども1人目) 1億5200万円×4分の1=3800万円(子ども2人目) |
| ステップ4 | 7600万円×30%-700万円=1580万円(配偶者の相続税額) 3800万円×20%-200万円=560万円(子ども1人目の相続税額) 3800万円×20%-200万円=560万円(子ども2人目の相続税額) |
| ステップ5 | 1580万円+560万円+560万円=2700万円(相続税額の総額) |
| ステップ6 | 2700万円×2分の1=1350万円(配偶者が支払う相続税額) 2700万円×4分の1=675万円(子ども1人目が支払う相続税額) 2700万円×4分の1=675万円(子ども2人目が支払う相続税額) |
ただし、配偶者は「配偶者控除」の特例により、取得した課税遺産額が相続財産の2分の1または1億6,000万円のどちらか大きい額まで相続税がかかりません。
そのため、相続税額が軽減され、実際に支払う税額は0円となります。
3. 相続税の申告・納税の期限は10ヶ月以内!延滞リスクを避けよう
相続税の申告・納税の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に相続税の申告をし、相続税を納税します。
被相続人が亡くなった直後は葬儀などで慌ただしく、相続税の申告期限を忘れてしまうケースも少なくありません。また、土地を相続する場合は、相続登記に時間がかかる可能性もあります。
生前から、土地の権利証をどこに保管しているかを確認しておいたり、土地が時価でいくらなのか査定を受けておいたりして、前もってできる準備を進めておくことをおすすめします。
そうすれば、相続が始まってからの限られた期間でもスムーズに手続きを進められて、相続税の延滞リスクを避けられるでしょう。
最大80%も節税できる?!土地相続で得する3つの実践ワザ
土地の相続税は、要件に合えば節税できる場合があります。この章では、土地相続で得をする3つの方法をご紹介します。
1. 評価額8割減も可能?「小規模宅地の特例」の条件と使い方
相続した土地の評価額を下げる特例として「小規模宅地の特例」があります。要件を満たしていれば、土地の相続税評価額を50〜80%減額することができます。ただし、減額の対象となるのは土地のみで、建物は対象になりません。
また、特例の適用を受けるには要件を満たす必要があります。うっかりして特例を受けられず損をしないために、前もって要件を把握しておくことが大切です。
2. 相続税対策になる生前贈与とその落とし穴
相続税対策として耳にする機会が多いのが「生前贈与」です。
生前贈与とは、生きている間に相続人に財産を贈与してしまうことです。生前贈与には「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」の2種類があります。
贈与により財産が減れば、相続が開始したときに相続財産を減らせるため、相続税対策として効果的です。
ただし、生前贈与のしくみを正しく理解していないと、思いがけない失敗をして損をしたりトラブルになったりする可能性があります。
例えば、生前贈与は控除額を超えてしまうと贈与税がかかります。贈与税は累進課税であるため、高額な税金がかかってしまうため注意しなければなりません。
また、親が子どもの名義で預金している場合は、名義預金とみなされると相続税の課税対象となります。預金があることを子どもにも知らせておくことが必要です。
さらに、生前贈与はひとりの相続人に贈与が片寄ってしまうとトラブルになる場合もあります。生前贈与をする場合は、相続人全員に承諾を得ておきましょう。
3. 土地のまま相続すると節税になる?土地を複数の相続人で相続する3つの分割方法
土地の相続において、相続人が複数いる場合は3つの方法があります。
- 「現物分割」でひとりが土地を相続する
- 「共有分割」で複数の相続人が共有で土地相続する
- 「換価分割」で土地を売却して現金で相続する
ひとりの相続人だけで相続すると、将来的に土地を売却する際に手続きしやすいですが、他の相続人との間に不公平感が生まれる可能性があります。
一方、複数の相続人で共有すると、公平に分割できてトラブルになりにくいです。しかし、将来土地を売約する際に相続人全員の承諾が必要となり手続きが煩雑になってしまいます。
換価分割だけが、土地のままではなく、現金に換えて分割する方法です。売却して手元に残った金額を相続人で分けられるため、金額がわかりやすくトラブルを避けられるメリットがあります。
ただし、土地を売却して現金で相続すると、相続税で損をする可能性があります。土地のまま相続する場合、土地の価格は売却する際の価格(時価)ではなく、相続税評価額で計算します。
一般的に、相続税評価額は時価の約80%程度が目安とされているため、相続税評価額で土地の価格を算出するほうが時価より安くなるのです。
土地を売却すると、相続税以外に譲渡所得税や印紙税、その他の経費などがかかる場合もあります。どちらが得になるのかを総合的に判断することが重要です。
売らずに活かす!相続土地のおすすめ活用法
相続した土地を売却する場合、利益が出ると譲渡所得税が課税されます。税金を節約するには、相続した土地を売却せずに活用するのもひとつの方法です。ここでは、相続した土地を売らずに活用する方法をご紹介します。
また、売却したときの譲渡所得税を節税する方法も併せて紹介するので、相続した土地を有効活用するための参考にしてください。
空き家を賃貸にして家賃収入を得る
実家など建物が建っている場合は、建物を解体せず空き家のままにして、賃貸物件として貸し出す方法があります。
家賃収入があれば、固定資産税の支払いや建物の修繕費用などに充当できるだけでなく、本業以外の収入として貯金したり生活費の足しにしたりすることもできます。
ただし、建物の築年数が経っていて大きな修繕だと出費がかさんで損をするかもしれません。最低限の修繕をすれば建物が使用できる状態であれば、賃貸物件にすることを検討しましょう。
農地として貸して税制優遇を受ける
農地を貸し出すと、固定資産税の軽減措置や相続税の納税猶予など、税制の優遇措置を受けられます。農地として貸し出して得た賃料は、建物を賃貸にするのと同様に、副収入として固定資産税の支払いや生活費などに活用できます。
優遇措置を受けるためには要件をみたしている必要があるため、間違いのないように概要を把握しておくことが大切です。
売却時の「譲渡所得税」を節約する2つの特例
土地を売却して利益が出ると、譲渡所得税が課税されます。相続した不動産の場合、譲渡所得税を節約する方法があります。
- 相続税の取得費加算の特例
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
いずれも、要件に当てはまれば譲渡所得税を節税できる特例です。特例が適用されるにはチェックすべきポイントがあります。
- 相続が開始してから売却するまでの期間
- 相続が開始する直前に被相続人が居住していたか
- 第三者に賃貸していたことがないか
- 相続開始から売却まで空き家だったか
2つの特例は併用できないため、それぞれの特例の要件に当てはまっているかを確認したうえで、どちらの特例が適用できるかを検討しなければなりません。
どちらも大きな節税効果のある特例ですので、生前から適用要件を確認し、間違いなく特例を受けられるように準備しておくことも大切です。
まとめ
土地を相続すると、必ず相続税がかかるわけではありません。しかし、場合によっては高額の相続税を支払う可能性もあり、相続税の正しい知識がないと不安になったり損をしたりするでしょう。
また、相続税には税額を節約できる特例や控除などがあり、申告や納税の期限も決められています。
土地の評価額の正しい算出方法や、相続税の税額の算出方法など、相続税の基本を前もって知っておくことによって、いざというときに慌てず適切に対応できます。
土地の相続には専門的な知識も必要です。失敗を避けてスムーズに手続きするためには、専門家に相談するのもひとつの方法です。
「あいりん司法書士・行政書士事務所」は、相続の専門家として、土地の相続の複雑な手続きをおこないます。まずはお電話または問合せフォームから無料相談をご予約ください。
この記事の監修者

遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。