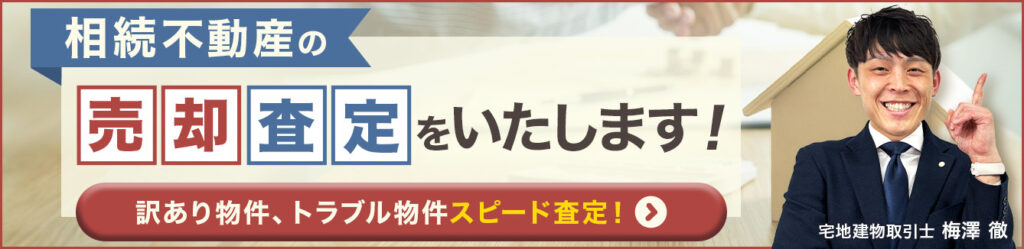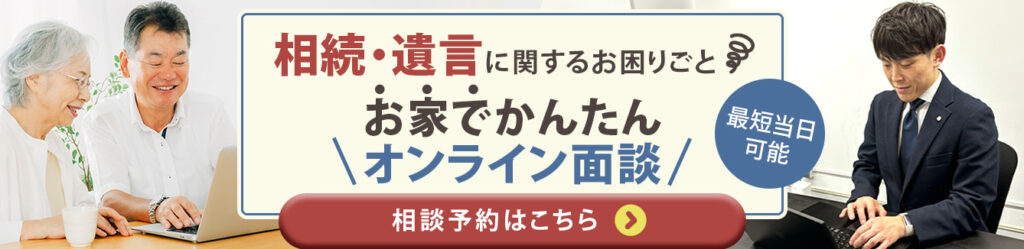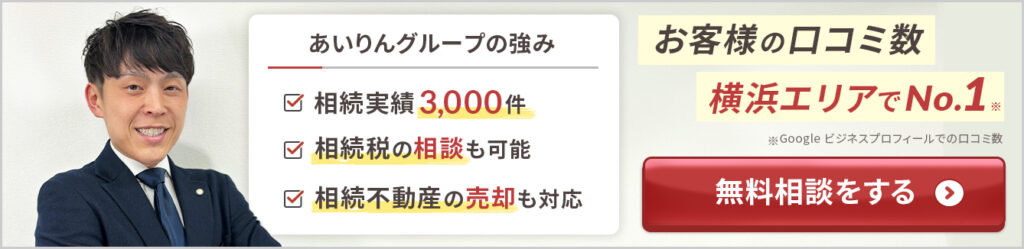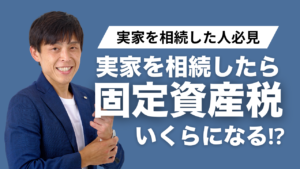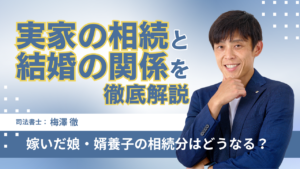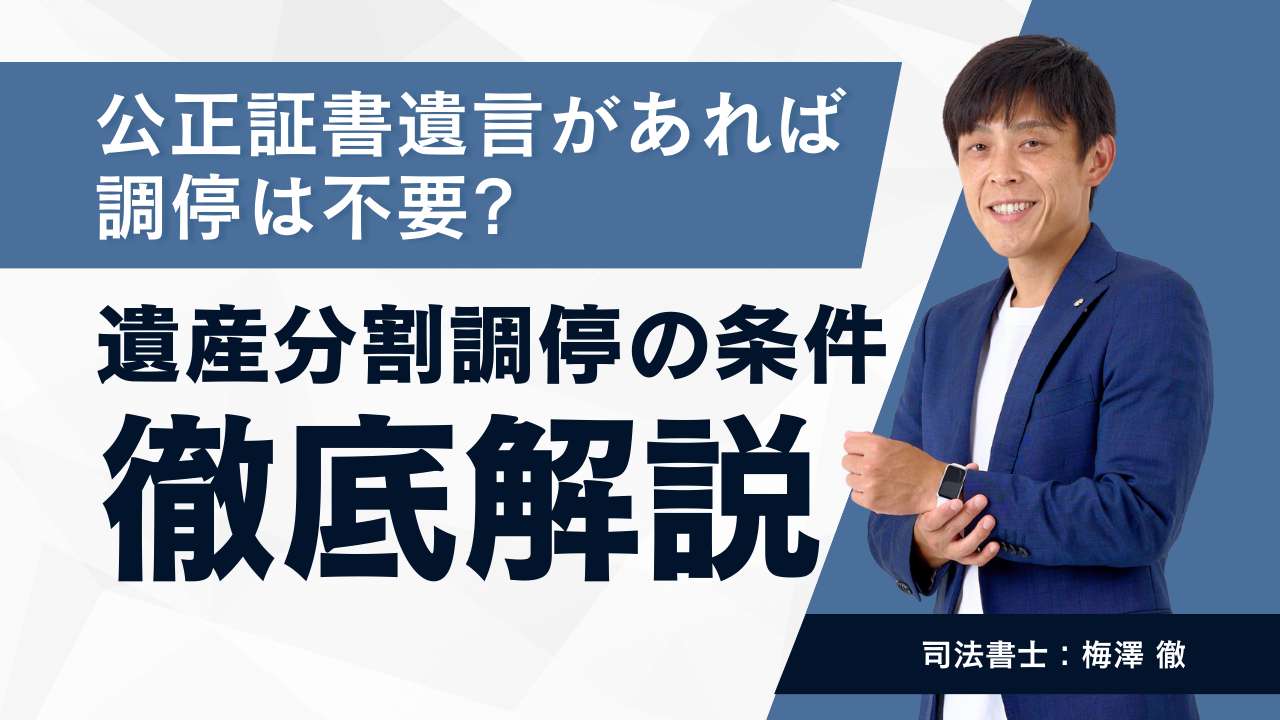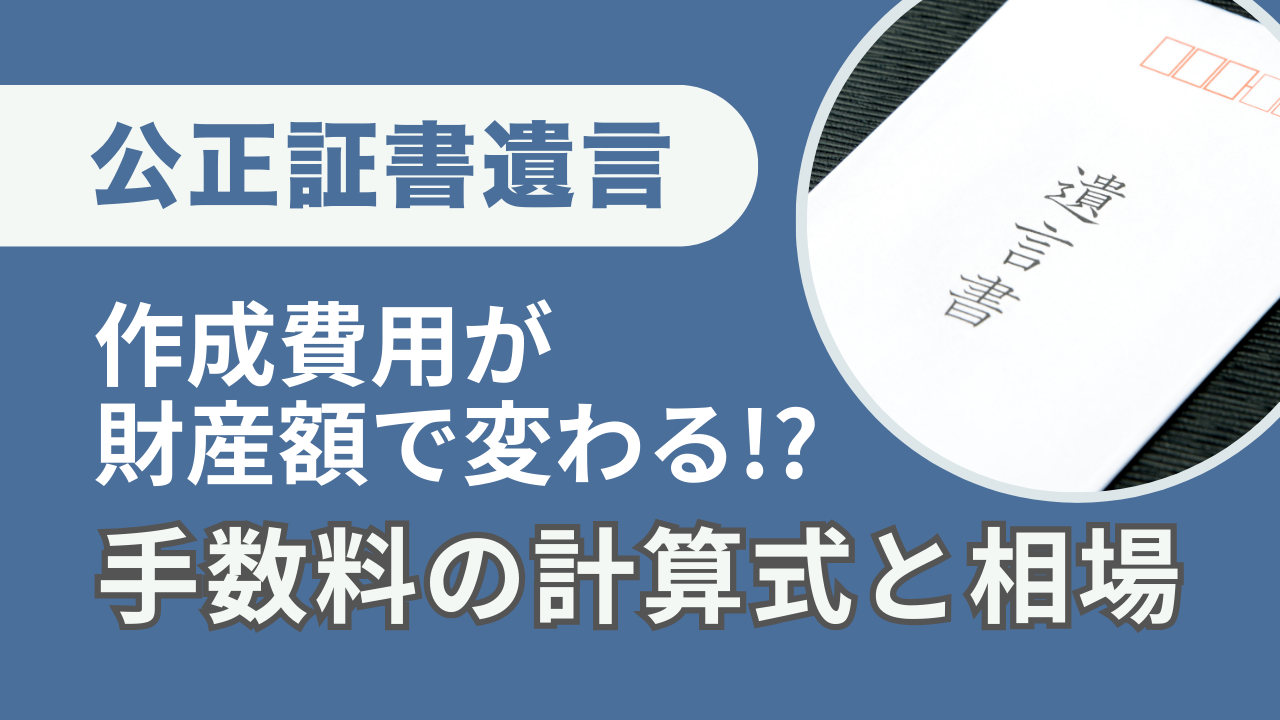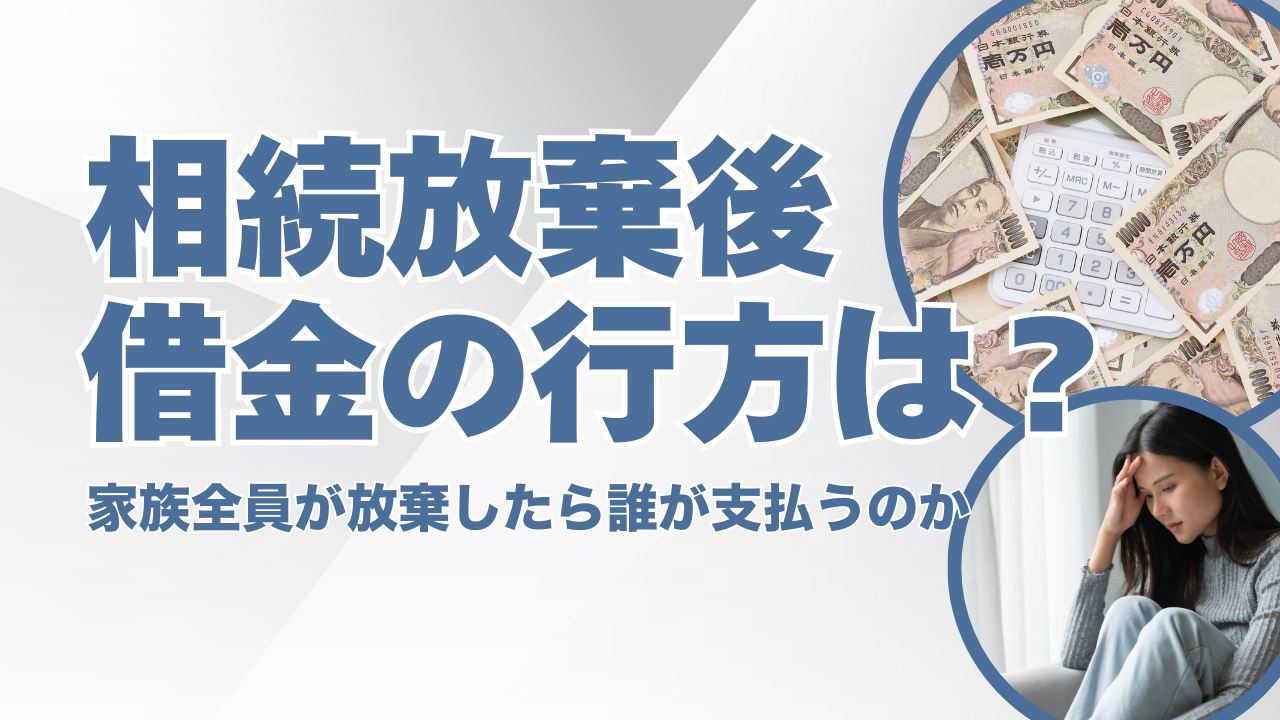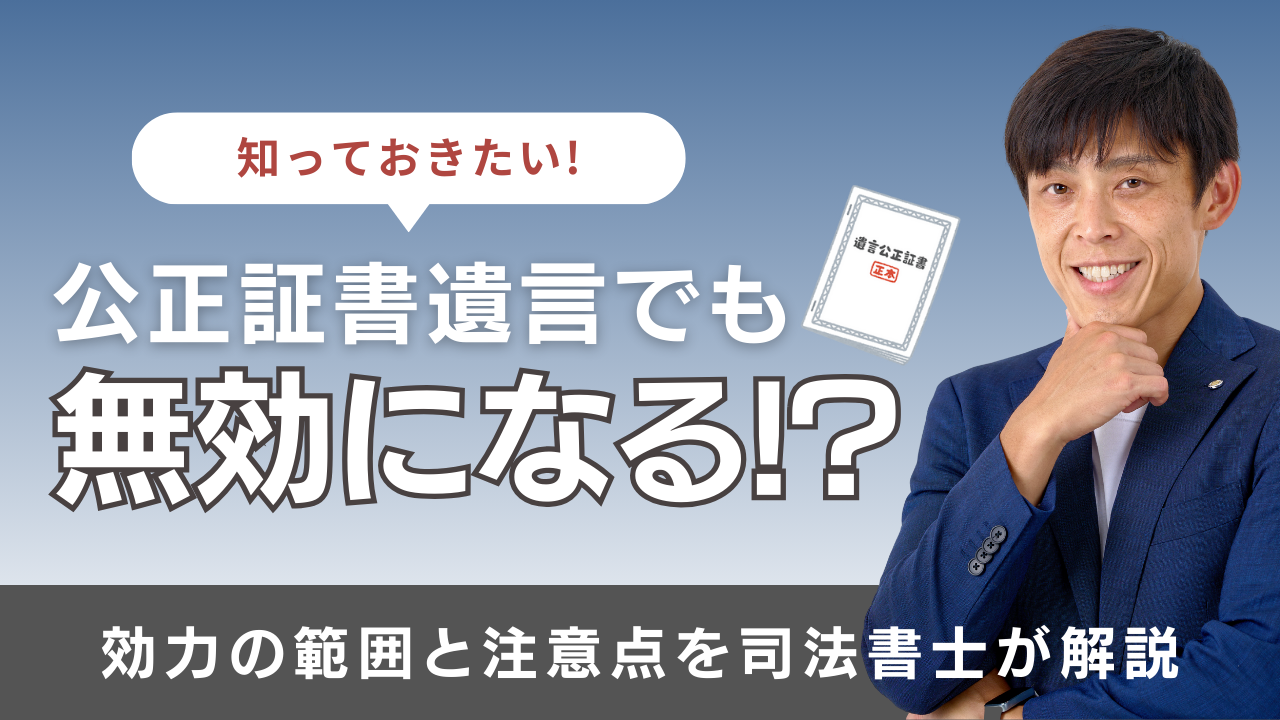この記事を要約すると
- 実家相続後は売却・住居利用・賃貸活用の3つが基本選択肢
- 戸建て賃貸なら年利回り4〜10%の収益が期待できる
- 地域活用なら社会貢献しながら安定収入を得ることが可能
実家を相続したものの「住む予定もないし、どうしよう…」と悩んでいませんか?
維持費だけで年間数十万円かかる実家を、ただ保有しているだけではもったいないですよね。
この記事では、相続した実家の7つの活用方法を具体的な数値とともに詳しく解説します。
読み終える頃には、あなたの実家に最適な活用方法が見つかり、将来的な収益性まで把握できるでしょう。
この記事はこんな方におすすめ
- 実家を相続したが住む予定がない方
- 相続した実家の維持費に悩んでいる方
- 実家を有効活用して収益化したい方
- 売却以外の選択肢を知りたい方
実家相続の全体の流れについては以下の記事で解説していますので、参考にしてください。
実家相続のメリット/デメリットについて
実家を相続することには、様々なメリットとデメリットがあります。相続後の活用方法を決める前に、まずは実家を相続することに対する、メリットとデメリットを見ておきましょう。
実家相続の5つのメリット
資産価値の継承
実家という不動産資産を受け継ぐことで、将来的な資産形成の基盤を得ることができます。
土地の価値は立地によって異なりますが、都市部や駅近物件であれば将来的な値上がりも期待できます。
住居費の大幅削減
実家に住むことを選択すれば、月々の家賃や住宅ローンの負担がなくなります。
一般的な賃貸住宅の家賃が月7〜15万円であることを考えると、年間100万円以上の住居費削減効果があります。
収益源としての活用可能性
賃貸に出すことで安定した家賃収入を得られます。立地条件にもよりますが、戸建て賃貸の年利回りは4〜10%程度が期待でき、月々の収入源として活用できます。
思い出の場所の保持
生まれ育った実家を手放さずに済むため、家族の思い出や精神的なよりどころを維持できます。
お盆や正月などの家族団らんの場としても活用できます。
相続税対策としての効果
小規模宅地等の特例を活用することで、相続税評価額を最大80%減額することが可能です。
これにより相続税の負担を大幅に軽減できる場合があります。
実家相続の5つのデメリット
年間維持費の負担
実家を保有する限り、以下のような維持費が継続的に発生します。
| 費用項目 | 年間費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 固定資産税・都市計画税 | 10〜30万円 | 評価額による |
| 火災保険料 | 2〜5万円 | 補償内容による |
| 水道・電気基本料金 | 3〜6万円 | 使用しなくても発生 |
| 庭木の手入れ・清掃 | 5〜15万円 | 年2〜3回実施 |
| 修繕・メンテナンス費 | 10〜50万円 | 築年数による |
年間の維持費用は、平均的な戸建て住宅で30〜100万円程度となります。
管理の手間と責任
空き家として保有する場合、定期的な換気、清掃、草刈りなどの管理業務が必要です。
管理を怠ると建物の劣化が進み、近隣住民とのトラブルの原因となることもあります。
相続人間での権利関係の複雑化
実家を複数の相続人が共有している場合、売却や活用方法について全員の合意が必要となります。
意見が分かれると、長期間にわたって利活用できない状況が続く可能性があります。
市場価値下落のリスク
特に地方や過疎地域では、人口減少により不動産価値が下落する傾向があります。
将来的に売却を検討する際、購入時や相続時の価値を下回る可能性があります。
災害リスクへの対応
地震、火災、台風などの自然災害により建物が損壊した場合、修繕費用や近隣への損害賠償責任が発生する可能性があります。
特に築年数の古い建物では、耐震性に不安がある場合もあります。
メリット・デメリットを踏まえた判断基準
実家相続のメリット・デメリットを踏まえ、以下の判断基準を参考に今後の方向性を検討しましょう。
実家の保有・活用をおすすめする場合
- 立地が良く、賃貸需要が見込める
- 家族の誰かが将来住む予定がある
- 年間維持費を上回る収益が期待できる
- 相続人全員が保有に合意している
実家の売却をおすすめする場合
- 誰も住む予定がなく、管理が困難
- 年間維持費の負担が重い
- 相続税の納税資金が必要
- 市場価値の下落が懸念される
個別の状況により最適解が異なるため、まずは無料相談で専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
FAQ
Q. 実家相続の維持費はいくら?
A. 年間30〜100万円程度で、築年数や立地により変動します。
Q. 相続した実家に住むべき?
A. ライフスタイルと維持費を総合的に判断しましょう。
Q. 実家の管理が大変な場合は?
A. 管理会社への委託や売却も選択肢として検討できます。
収益化を目指す4つの活用方法
相続した実家、またはその土地を人に貸し出すことで、安定した収入を得ることができます。
”貸す”といっても賃貸に出す以外にも実は色々な方法があります。
立地や建物の状態に応じて、適切な方法は変わってきますので、以下の表で各活用方法の特徴を比較してみてください。
| 分類 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 戸建て賃貸 | ファミリー向け長期賃貸 | ・安定収入(年利回り4~10%) ・管理の手間が少ない |
・初期リフォーム費用大 ・空室リスク |
| シェアハウス | 若者向け個室+共用部 | ・高収益(月15~17万円) ・需要が安定 |
・入居者管理が複雑 ・トラブル対応必要 |
| 民泊運営 | 短期宿泊サービス | ・高単価(月6~30万円) ・観光需要を活用 |
・許可申請が複雑 ・営業日数制限 |
| 駐車場経営 | 月極・コインパーキング | ・低リスク・低管理 ・初期投資少 |
・収益性は限定的 ・税軽減措置なし |
戸建て賃貸の利回り相場と初期投資額
戸建て賃貸は、ファミリー層をターゲットにした安定収入が期待できる活用方法です。
マンションと比べて管理組合費がかからず、庭付きの物件なら他の賃貸物件との差別化も図れます。
戸建て賃貸の利回り相場
- 都市部:年利回り4〜6%
- 郊外・地方:年利回り6〜10%
- 駅近物件:年利回り3〜5%(安定性は高い)
立地条件によって大きく利回りが変わるのが特徴です。
駅から徒歩10分以内の物件なら入居者が見つかりやすく、長期入居も期待できます。
一方、郊外の物件でも学校や商業施設が近くにあれば、子育て世帯からの需要が見込めます。
初期投資額の目安
- リフォーム費用:100〜500万円
- 不動産会社への仲介手数料:家賃1ヶ月分
- 火災保険料:年間2〜5万円
リフォーム費用は建物の築年数や状態によって大きく変動します。
水回りの交換だけなら200万円程度ですが、全面改装なら500万円以上かかる場合もあります。
例えば、月額家賃10万円で貸し出せる物件なら、年間収入120万円となります。
利回り(※投資した金額に対する年間収益の割合)6%なら投資回収期間は約16年、維持費を考慮すると実質利回りは4〜5%程度になります。
シェアハウス運営で月収20万円を目指す
若者や単身者をターゲットにしたシェアハウス運営は、高い収益性が魅力です。
近年、都市部を中心にシェアハウスの需要が高まっており、特に駅近物件や設備の充実した物件は人気が高い状況です。
シェアハウス運営の収益構造
- 4部屋×家賃5万円=月収20万円
- 共用部分の光熱費:月2〜3万円
- 清掃・管理費:月1〜2万円
- 実質月収:15〜17万円
通常の戸建て賃貸と比較すると、同じ物件でも1.5〜2倍の家賃収入が期待できます。
これは個室ごとに家賃を設定できるためで、入居率が高ければ非常に効率的な収益源となります。
初期投資費用
- 個室への間仕切り工事:50〜150万円
- 共用キッチン・バスルームの改修:100〜300万円
- 家具・家電の購入:50〜100万円
初期投資は通常の賃貸より高額になりますが、共用設備を充実させることで入居者の満足度向上と長期入居につながります。
Wi-Fi環境の整備や防犯システムの導入も重要な投資項目です。
シェアハウス運営は通常の戸建て賃貸より1.5〜2倍の収益が期待できますが、入居者管理やトラブル対応などの手間もかかります。
「管理が大変そう…」と心配になりますよね。確かに手間はかかりますが、適切な管理会社を選ぶことで負担を軽減できます。
入居者同士のルール作りや定期的な清掃、設備メンテナンスなど、きめ細やかな対応が成功の鍵となります。
民泊・宿泊業での収益性と許可申請
観光地や都市部の物件なら、民泊運営で高収益を期待できます。
民泊の収益性
- 1泊単価:3,000〜15,000円
- 稼働率(※年間の利用率):40〜70%(立地による)
- 月収例:6万円〜30万円
必要な許可申請
- 住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出
- 旅館業法の許可(簡易宿所営業)
- 建築基準法や消防法への適合
参考:住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて 国土交通省
民泊運営には年間営業日数180日以内の制限があるため、通年営業を希望する場合は旅館業許可(※簡易宿所営業の許可)が必要です。
許可取得には建物の改修工事が必要な場合があり、初期投資額は200〜800万円程度となります。
個別具体的に回答が異なるため、まずは無料相談をお申し込みください。
駐車場経営なら初期投資10万円で開始
いわゆる賃貸とは少し毛色が違いますが、 建物を解体して駐車場にすることで、低リスクで安定した収入を得られます。
駐車場経営の収益構造
- 月極駐車場:1台月額5,000〜20,000円
- コインパーキング:1台日額500〜2,000円
- 5台分の駐車場なら月収2.5〜10万円
初期投資費用
- 建物解体費:100〜300万円
- 舗装工事:50〜150万円
- コインパーキング設備:100〜200万円
駐車場経営は管理の手間が少なく、土地活用の入門編として人気があります。
FAQ
Q. 賃貸の利回りはいくら?
A. 都市部4〜6%、郊外・地方6〜10%程度です。
Q. シェアハウスの管理は大変?
A. 管理会社を利用して負担を軽減できます。
Q. 駅車場経営の初期費用は?
A. 解体・舗装工事で300〜800万円程度です。
地域活性化に貢献する3つの社会的活用法
相続した実家を地域のために活用することで、社会貢献しながら収益も得られます。
公的な補助金を活用できる場合もあり、安定した運営が期待できます。
高齢者向けデイサービス施設への転用
高齢化が進む地域では、デイサービス施設のニーズが高まっています。
総務省の調査によると、2025年には65歳以上の人口が全人口の30%を超え、介護サービスの需要がさらに拡大すると予測されています。
出典:人口推計(総務省統計局)
デイサービス施設の収益構造
- 介護保険収入:1人1日8,000〜12,000円
- 定員15名×稼働率80%で月収約200万円
- 人件費・運営費を除いた利益率:10〜20%
必要な設備投資
- バリアフリー改修工事:300〜800万円
- 介護用設備・備品:200〜500万円
- 指定申請・許可取得費用:50〜100万円
デイサービス事業は介護保険制度(※日中に高齢者の生活支援を行うサービス)に基づく安定した収入源ですが、有資格者の確保や行政手続きが複雑な点がハードルとなります。
地域コミュニティスペースとしての活用
地域住民の交流拠点として活用することで、地域活性化に貢献できます。
コミュニティスペースの活用例
- 子育て支援センター
- 高齢者向けサロン
- 趣味・文化活動の拠点
- 地域イベント会場
収益化の方法
- 自治体からの委託料:月10〜30万円
- 利用料金:1時間500〜2,000円
- イベント開催料:1回5,000〜20,000円
- カフェ・軽食の提供
コミュニティスペース活用の実践例
- 子育てサロン・学習塾:月額5〜15万円の賃料収入
- 高齢者サロン・健康教室:地域包括支援センターとの連携
- 文化教室・趣味サークル:利用料収入で運営費をカバー
- 防災拠点:自治体との協定で維持費補助
地域のニーズに合わせた柔軟な運営が可能で、NPO法人や地域団体との連携により持続可能な運営体制を構築できます。
また、地域密着型の活用により、近隣住民との良好な関係を維持でき、将来的な売却時にも地域に愛された物件として付加価値を生み出すことができます。
地域のニーズに応じた柔軟な運営により、月収5〜20万円程度の収益が期待できます。
農業体験・田舎暮らし体験施設運営
郊外の実家を相続した場合に限りますが、都市部からの移住希望者や農業体験希望者をターゲットにした施設運営も有効です。
体験施設の運営内容
- 農業体験プログラム:1回3,000〜8,000円
- 田舎暮らし体験宿泊:1泊5,000〜15,000円
- 農産物の直売:売上の20〜30%が利益
必要な初期投資
- 農地の整備:50〜200万円
- 体験用農機具・設備:100〜300万円
農業体験施設運営の具体的な収益構造
- 区画貸し:年額20,000〜50,000円/区画
- 体験教室:1回3,000〜5,000円/人
- 収穫祭イベント:参加費2,000〜3,000円/家族
- 農産物直売:収穫物の販売収入
- 宿泊設備の整備:200〜500万円
都市部に近い立地なら、週末農業を楽しみたいファミリー層からの需要が見込めます。
また、保育園や小学校の食育プログラムと連携することで、安定した利用者を確保できる可能性があります。
初期投資は比較的少なく、土づくりと基本的な農機具があれば開始できるため、リスクを抑えながら地域貢献できる魅力的な選択肢です。
農業体験施設は季節による収入変動がありますが、リピーターを獲得できれば安定した収益源となります。
年間を通じた運営で月収10〜40万円程度の収益が期待できます。
FAQ
Q. デイサービスの許可は必要?
A. 介護保険法に基づく指定申請が必要です。
Q. 地域活用のメリットは?
A. 社会貢献と安定収入の両立が可能です。
Q. 公的補助金はある?
A. 地域活性化関連の補助金が利用できる場合があります。
まとめ:実家相続の最適な活用方法は立地条件で決まる
相続した実家の活用方法は、立地条件や建物の状態によって最適解が変わります。
都市部や駅近の物件なら年利回り4~10%の賃貸経営や民泊での高収益が期待でき、郊外や地方の物件なら駐車場や地域活用が現実的な選択肢となります。
活用方法を決める際は、初期投資額・維持費・期待収益を総合的に検討することが重要です。
売却なら一度に現金化できますが、賃貸なら長期的な安定収入、地域活用なら社会貢献と収益の両立が可能です。
ただし、相続登記や各種許可申請、税務上の特例適用など法的手続きが複雑で、個別の状況によって最適な判断が異なります。
一人で悩まず、相続や不動産の専門家に相談することで、あなたの実家に最も適した活用方法を見つけることができるでしょう。
相続した実家を有効活用して、将来の安定した収入源として育てていきませんか?
まずは無料相談で、あなたの状況に合った具体的なプランを一緒に考えてみましょう。
無料相談のご案内
実家相続の活用方法でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
経験豊富な司法書士が、あなたの状況に合わせた最適なアドバイスをいたします。
無料相談はこちら
相続トラブルにまつわるご相談は、東京新宿法律事務所も参考にしてみてください。
この記事の監修者

遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。