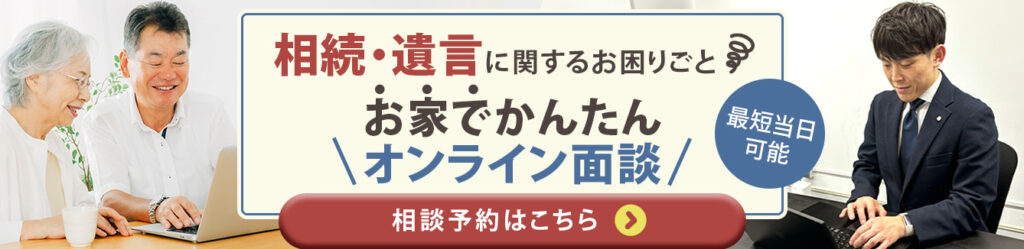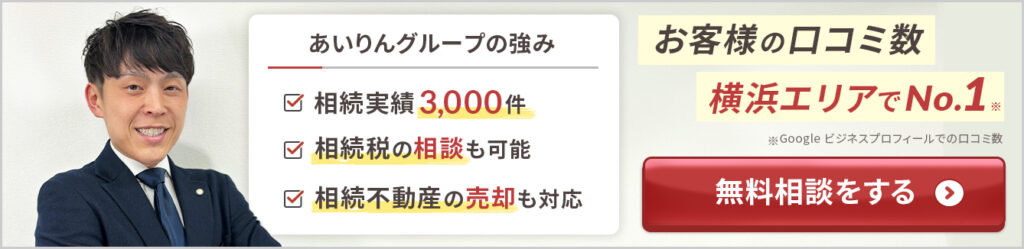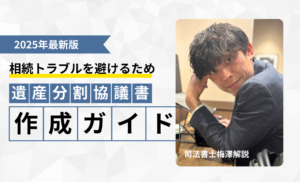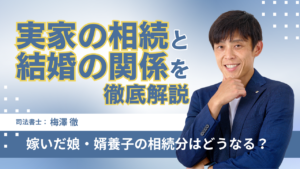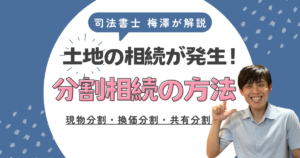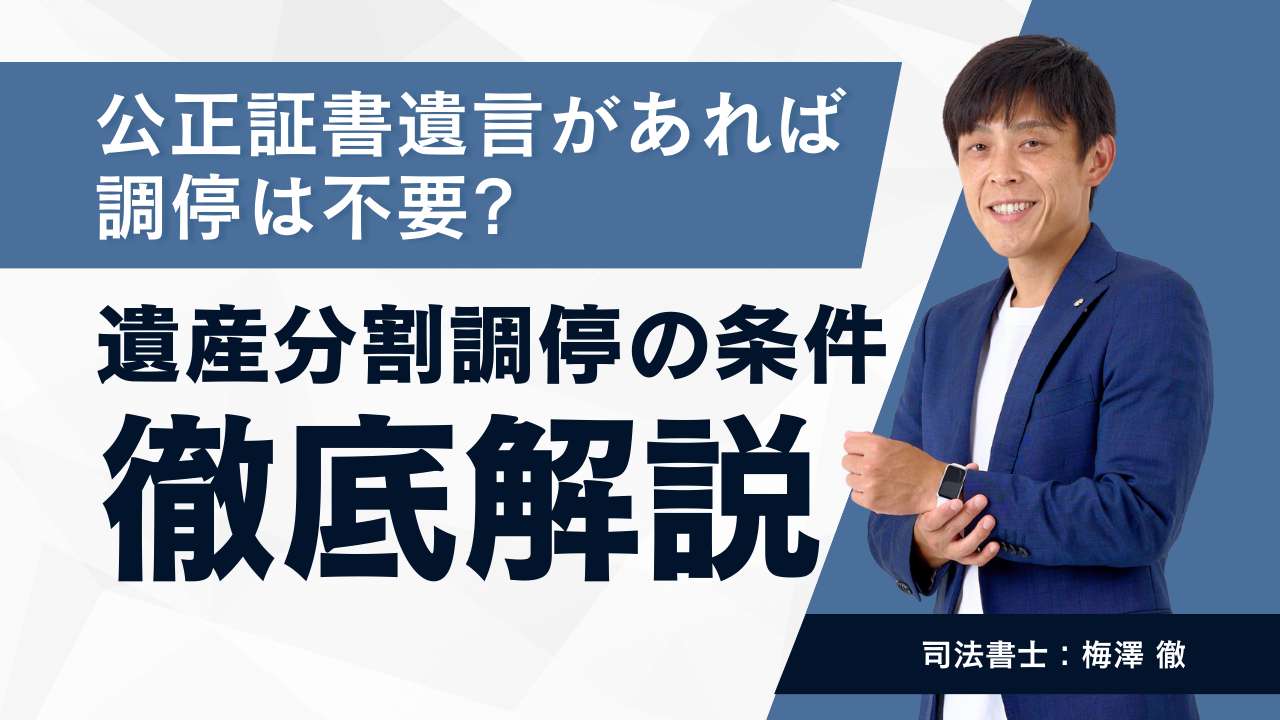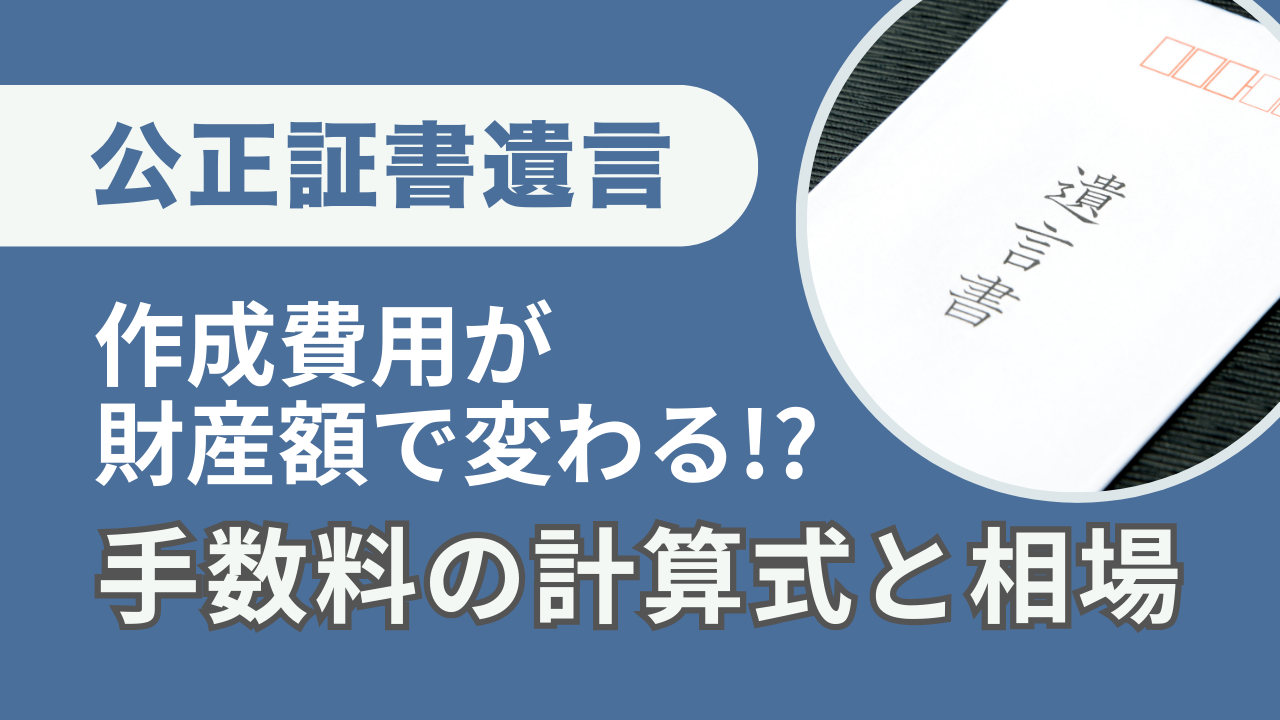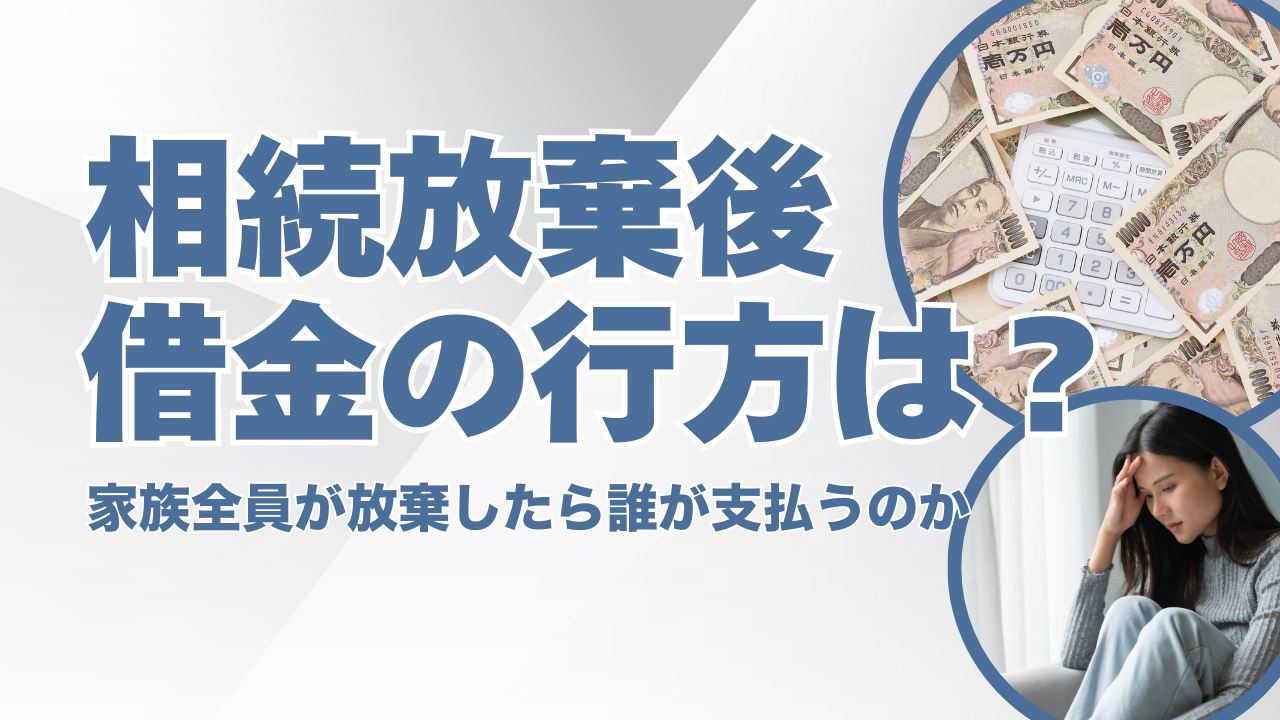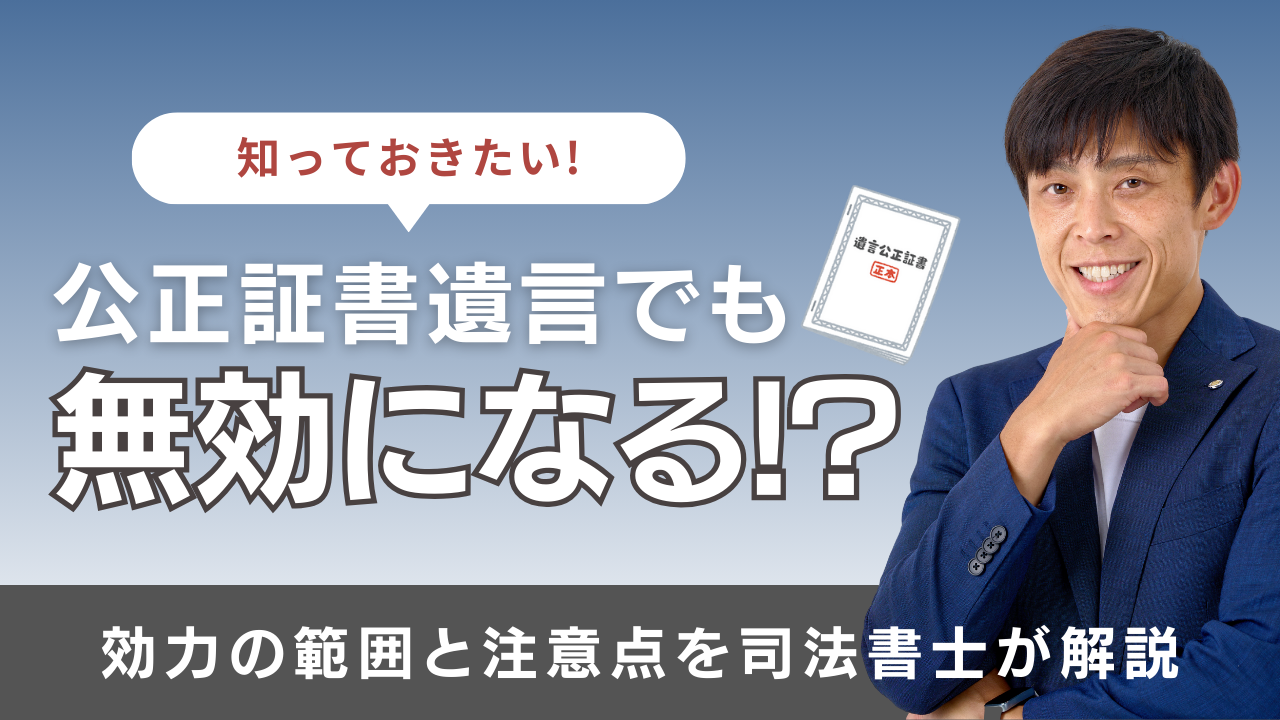この記事を要約すると
- 相続登記の義務化により3年以内の手続きが必要
- 年間120万円の住居費削減効果がある一方でリフォーム費用の想定が大切
- 通勤利便性と家族の同意が重要な判断基準
親が亡くなり実家を相続したとき、「この家に住むべきか、それとも売却すべきか」で
悩む方は多いでしょう。そのお気持ち、よくわかります。
実家に住むことは経済的にお得な面もありますが、手続きや維持費など考慮すべき点も多くあります。
この記事では、相続した実家に住む場合の手続きから費用まで、知っておくべきポイントを詳しく解説します。
この記事はこんな方におすすめ
- 相続した実家に住むかどうか悩んでいる方
- 実家に住む場合に何を準備すればよいか不安な方
- 実家に住むメリットやデメリットを比較したい方
実家相続の全体の流れについては以下の記事で解説していますので、参考にしてください。
目次
実家を相続して住む場合の基本手続きと注意点
実家を相続して住む際には、まず法的な手続きを適切に行うことが重要です。
相続登記は2024年4月から義務化されており、期限内に手続きを済ませる必要があります。
相続登記の必要性と期限|2024年義務化で罰則も
相続登記※とは、亡くなった方から相続人に不動産の名義を変更する手続きのことです。
※相続登記:相続により取得した不動産の所有権を法務局に届け出て、登記簿上の名義を変更する手続き
2024年4月1日から相続登記が義務化され、
相続を知った日から3年以内に登記しなければ10万円以下の過料が課されます。
参考:相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日制度開始) – 法務省
実家に住む場合でも、名義変更を行わないと将来の売却や担保設定ができなくなるリスクがあります。
総務省の統計によると、全国の空き家率は13.6%となっており、
適切な管理と活用が重要な社会課題となっています。
相続登記の費用は登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と
司法書士報酬(10万円程度)で、合計15~20万円程度が一般的です。
必要書類には戸籍謄本一式、印鑑証明書、固定資産税評価証明書などがあり、
早めの準備をおすすめします。
個別具体的に対応が異なります。
期限内に適切な手続きを完了するためにも、まずは無料相談をお申し込みください。
兄弟がいる場合の遺産分割協議のポイント
相続手続きは、遺言書、遺産分割協議、法定相続の3つの方法から選択して進めます。
兄弟がいて、そのうちのひとりが実家を相続して住む場合、
遺言書がなければ遺産分割協議を行うのが一般的です。
遺産分割協議とは、相続人全員が話し合い、どの財産を誰が相続するかを決める手続きです。
法定相続では兄弟が均等に相続する権利を持つため、
実家に住みたい人が他の相続人全員の同意を得る必要があります。
実家をひとりが相続する際は、他の兄弟との間で不公平にならないよう、
代償分割という方法がよく使われます。
これは、実家を取得した人が、その価値に見合う現金を他の相続人に支払うことで
公平に分割する方法です。
実家の評価額は、不動産鑑定士に依頼すると20~30万円かかりますが、
近隣の取引事例や固定資産税評価額を参考に、話し合って決めるケースも多くあります。
話し合いで合意した内容は、遺産分割協議書にまとめます。
この書類には、相続人全員の署名と実印が必要で、後のトラブルを避けるためにも、
詳細な内容を記載しておくことが大切です。
実家に住宅ローンが残っている場合の対処法
「実家に住宅ローンが残っているけれど、相続したら毎月の返済をしなければならないの?」と心配される方も多いでしょう。
実家に住宅ローンが残っている場合、団体信用生命保険※によりローンが完済されることが一般的です。
※団体信用生命保険(団信):住宅ローン契約者が死亡・高度障害時にローン残高が保険金で完済される制度
ただし、団信に加入していない場合や、リフォームローンなどは残債を引き継ぐ必要があります。
住宅ローンの残債は相続放棄の判断材料にもなるため、
金融機関に残高証明書を請求して正確な金額を把握しましょう。
相続人が住宅ローンを引き継ぐ場合、金融機関の承諾が必要で、収入証明などの審査を受けることになります。
住宅ローンが残っている不動産の相続登記には、銀行の抵当権抹消手続きも必要になる場合があるため専門家への相談をおすすめします。
適切な手続きを行うためにも、まずは無料相談をお申し込みください。
FAQ
Q. 相続登記の期限は?
A. 相続を知った日から3年以内に申請が必要です。
Q. 相続登記の費用は
A. 登録免許税と司法書士報酬で15-20万円程度です。
Q. 兄弟での分割方法は?
A. 現物・換価・代償・共有の4つの方法があります。
実家に住むことの経済的メリット・デメリット
実家に住むかどうかを判断する際、経済面での影響を正確に把握することが重要です。
住居費の削減効果は大きなメリットですが、一方でリフォーム費用や維持費なども発生するため、総合的な視点での検討が必要となります。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 住居費 | ・家賃0円(年間120万円節約) ・住宅ローン支払い不要 ・更新料・引越し費用不要 |
・固定資産税継続(年間10-30万円) ・火災保険料 ・修繕費用 |
| 心理面 | ・慣れ親しんだ環境 ・思い出を大切にできる ・近所付き合い既築 |
・親の死を思い出すつらさ ・古い設備によるストレス ・家族の馴染み問題 |
| リフォーム | ・自由に改装可能 ・介護保険制度活用可能 |
・築20年で平均300万円 ・水回り交換200万円 ・一括支払い必要 |
実家に住むことで得られる経済的効果は大きいですが、同時に維持費用も発生します。
長期的な収支を考慮して判断することが重要です。
住居費削減効果
実家に住む最大のメリットは住居費の大幅削減です。
例えば、月10万円の家賃を払っていた方が実家に住めば年間120万円の節約になり、10年間で1,200万円もの差が生まれます。
住宅ローンの支払いがなくなることで、その分を教育費や老後資金に充てることができるのは大きなメリットです。
ただし、固定資産税や火災保険料、修繕費などの維持費は継続して発生するため、
年間30~50万円程度は見込んでおく必要があります。
賃貸住宅の更新料や引越し費用なども不要になるため、トータルでの経済効果は非常に大きいと言えるでしょう。
思い出の実家で暮らす心理的メリットとストレス
実家で暮らすことには経済面以外にも心理的なメリットがあります。
慣れ親しんだ環境で過ごせる安心感や、家族の思い出を大切にできる充実感は、お金では買えない価値があります。
近所付き合いも既に築かれているため、新しい土地での人間関係構築の負担がないことも大きな利点です。
ただし、心理的な面では課題もあります。親の死を日常的に思い出してしまうつらさや、
古い設備に対するストレスを感じる方もいます。
配偶者や子どもが実家の雰囲気に馴染めず、家族関係に影響を与えるケースもあるため、
家族全員の気持ちを確認することが重要です。
リフォーム費用の現実|築20年で平均300万円
実家に住む場合、築年数に応じたリフォームが必要になることが多く、築20年の住宅では平均300万円程度の費用がかかります。
水回りの設備交換(キッチン・浴室・トイレ)だけで200万円程度、
内装や外壁の修繕を含めると500万円を超えるケースもあります。
老朽化した配管や電気設備の更新は安全面からも重要で、見えない部分の工事費用も考慮する必要があります。
バリアフリー化を検討する場合は追加で100~200万円の費用がかかりますが、
介護保険の住宅改修費給付制度を活用できる場合もあります。
リフォーム費用は一度にまとめて支払う必要があるため、
相続時に十分な現預金を確保しておくことが大切です。
FAQ
Q. 実家に住むメリットは?
A. 住宅費の大幅節約と精神的安定感が得られます。
Q. リフォーム費用はいくら?
A. 築20年の住宅で平均300万円程度かかります。
Q. 心理的負担はある?
A. 親の死を思い出すつらさや古い設備のストレスがあります。
実家に住む前に検討すべき現実的な問題点
実家に住むことを決める前に、日常生活に関わる現実的な問題を十分に検討する必要があります。
あなたの現在の生活環境と実家での生活を具体的に比較して想像してみてください。
特に通勤や家族関係への影響は、長期的な生活の質に大きく関わる重要な要素です。
通勤・通学の利便性|職場との距離を慎重に判断
実家に住む場合、現在の職場や学校への通勤・通学時間が大幅に変わる可能性があります。
通勤時間が1日2時間延びた場合、年間で約500時間もの時間ロスが発生し、生活の質に大きな影響を与えます。
交通費の増加も考慮すべきポイントで、月3万円の交通費増加は年間36万円の負担になります。
リモートワークが可能な職種であれば実家住まいのメリットを最大限活用できますが、
毎日の通勤が必要な場合は慎重な判断が必要です。
子どもの学校や習い事への影響も考慮し、教育環境の変化が家族に与える影響を十分に話し合いましょう。
老朽化した実家の安全性とメンテナンス費用
築年数が古い実家では、耐震性や断熱性能などの安全性に問題がある場合があります。
1981年以前に建築された住宅は旧耐震基準のため、耐震診断(10~20万円)を受けて
必要に応じて耐震補強工事(100~300万円)を検討する必要があります。
老朽化した設備の故障リスクも高く、給湯器の交換(20~40万円)、エアコンの交換(10~20万円)など突発的な出費が発生しがちです。
定期的な外壁塗装(100~150万円/10年毎)や屋根の修繕(50~100万円)なども必要で、
年間換算で20~30万円の維持費を見込んでおくべきです。
住宅の瑕疵や欠陥が後から発見された場合の修繕費用も大きな負担になるため、
住む選択をとるのであれば事前の建物診断をおすすめします。
配偶者の同意と家族関係への影響を事前に確認
実家に住むことは家族全員に影響するため、配偶者や子どもの同意を得ることが不可欠です。
配偶者にとって義理の両親の家で生活することは心理的負担が大きく、
充分な話し合いなしに進めると夫婦関係に亀裂が生じる可能性があります。
子どもの友人関係や学習環境の変化も考慮し、転校が必要な場合は子どもの意見も聞いて慎重に判断しましょう。
実家のしきたりや生活習慣の違いが原因でストレスを感じる家族もいるため、
住む前に家族のルールを話し合っておくことが大切です。
最終的には家族全員が納得できる形で決断を下し、
住み始めてからも定期的に家族会議を開いて問題がないか確認することをおすすめします。
FAQ
Q. 耐震診断は必要?
A. 1981年以前の建物は耐震診断を推奨します。
Q. 配偶者が反対したら?
A. 充分な話し合いで理解を得ることが重要です。
まとめ:実家相続後の住居選択を成功させる3つのポイント
実家を相続して住むかどうかは、経済面だけでなく家族の生活全体に影響する重要な決断です。
まず法的手続きを適切に行い、特に2024年から義務化された相続登記は期限内に完了させることが必要です。
経済的には年間120万円の住居費削減というメリットがある一方で、
リフォーム費用や維持費も含めた長期的な収支計算が重要となります。
また、通勤の利便性や家族の同意など、お金では解決できない問題についても十分に検討することが大切です。
実家に住むという選択が家族全員にとって最適になるよう、
時間をかけて慎重に判断することをおすすめします。
相続手続きや実家活用でお悩みの方は、専門家による無料相談をご活用ください。
あなたの状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。
相続・実家活用の無料相談はこちら
https://souzoku-yokohama.net/contact/
この記事の監修者

遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。