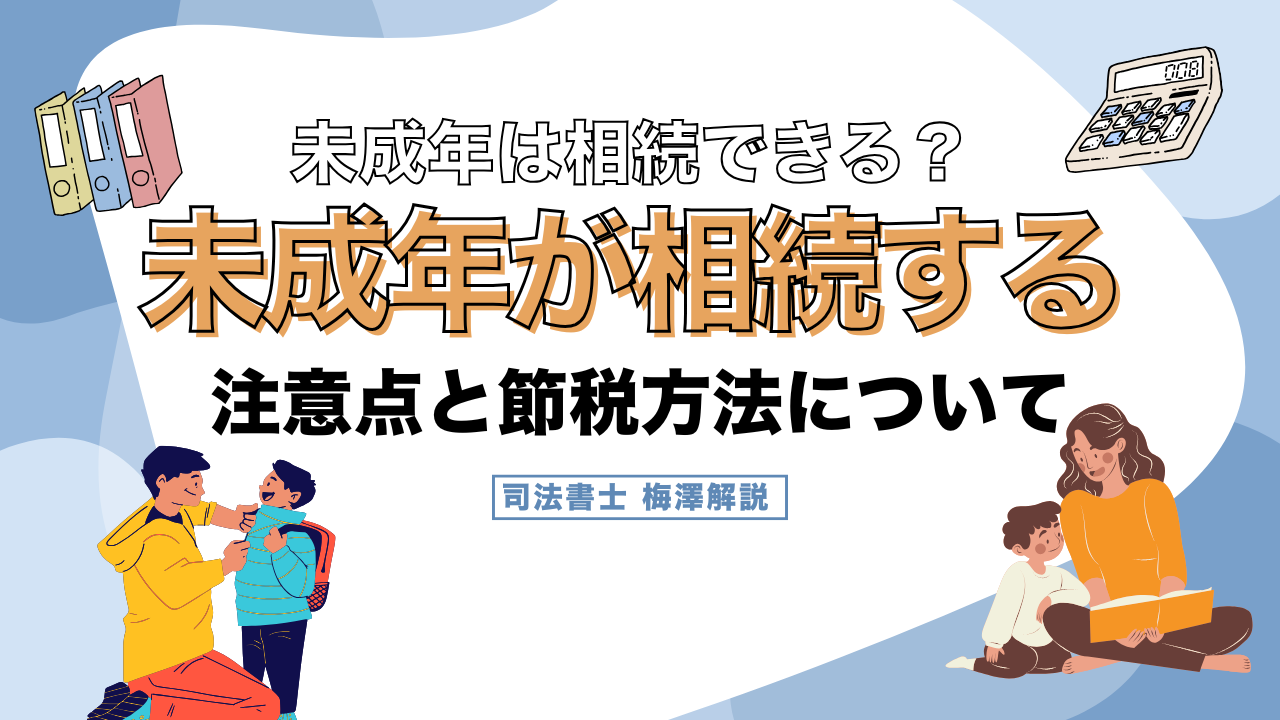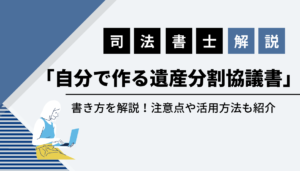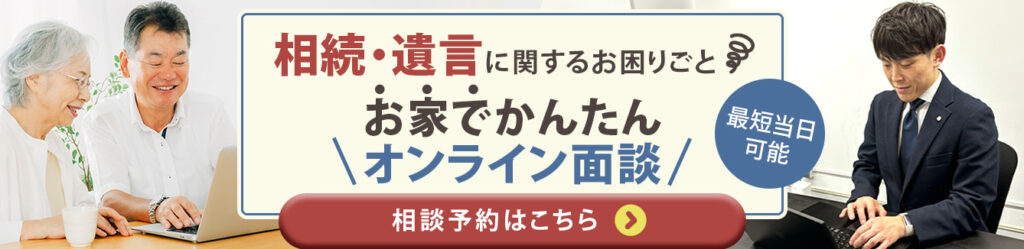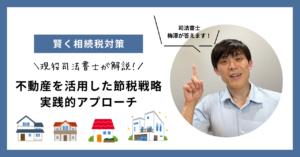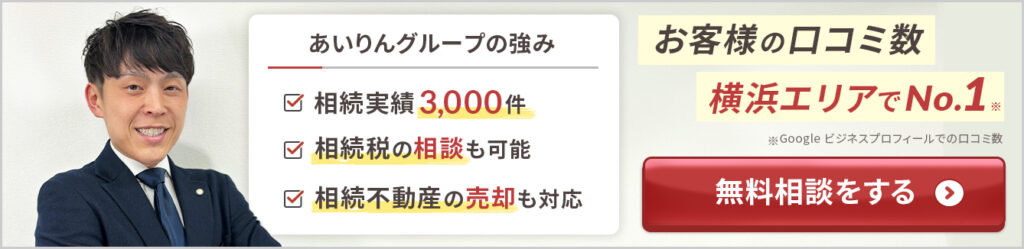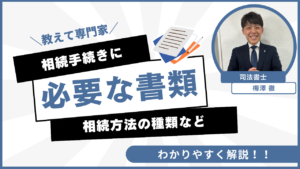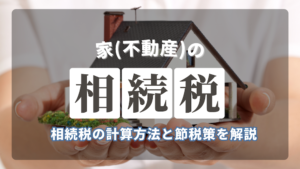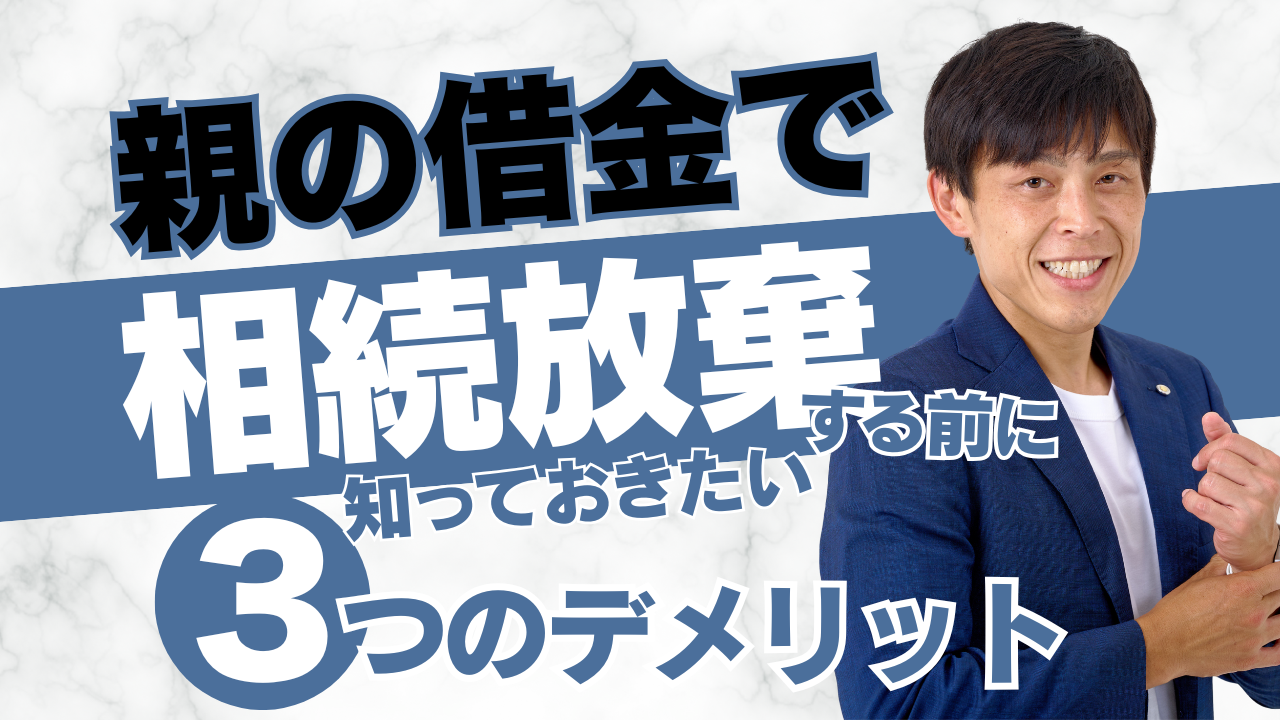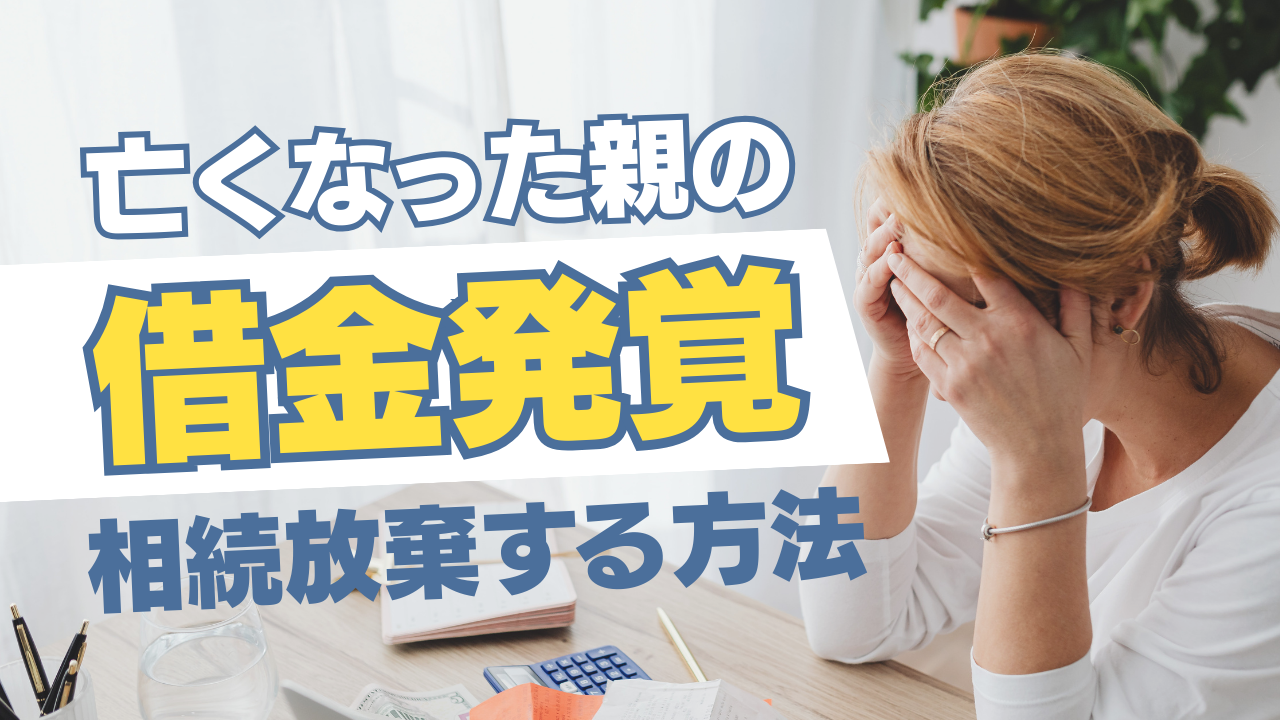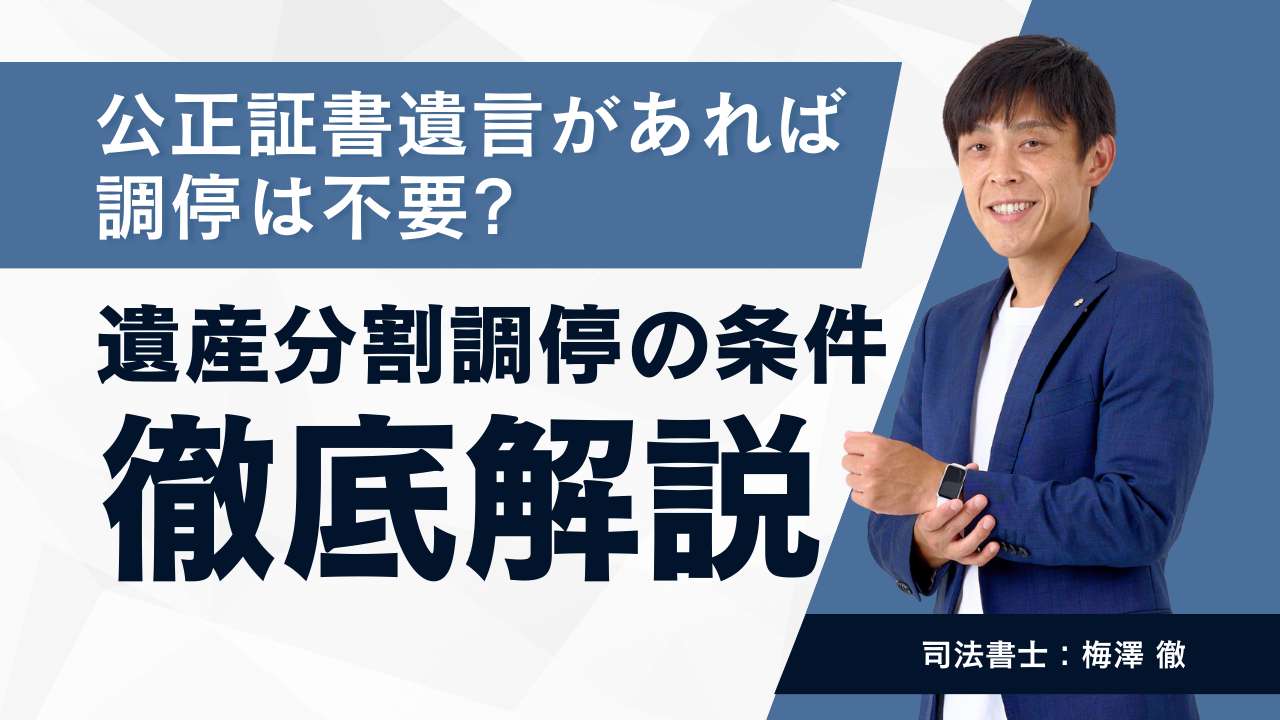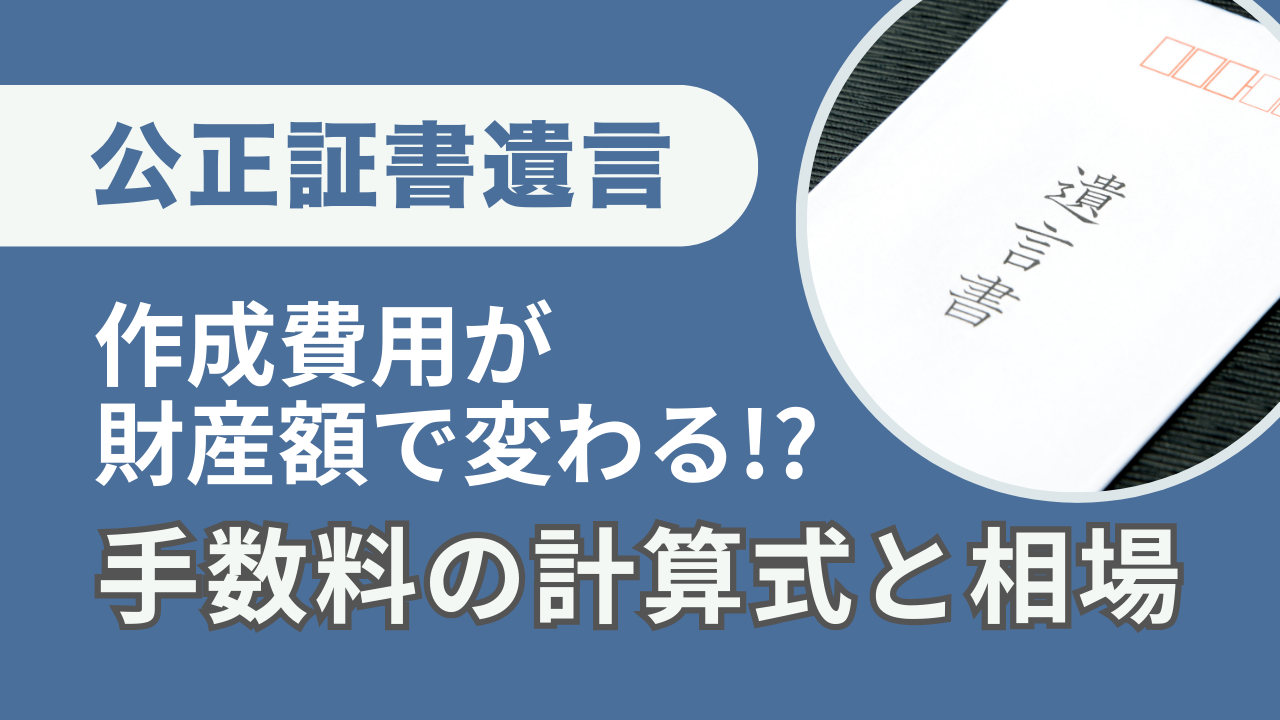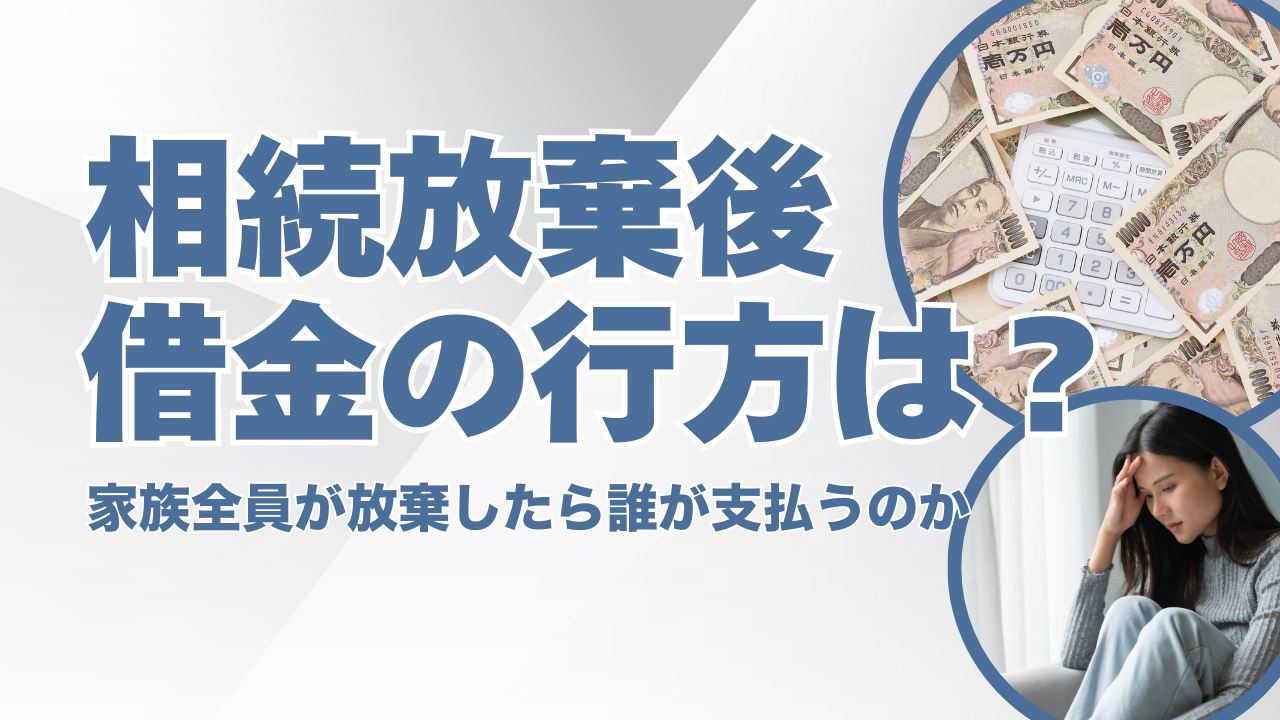この記事を要約すると
- 子どもが相続人になった場合には法定代理人が必要
- 未成年者控除を活用すれば最大で180万円もの税額控除に!
- 未成年者を含む不動産相続では通常の手続きと異なるので注意!
未成年者が相続人になる場合に知っておくべき制度があります、「未成年者控除」です。この控除を活用すれば、最大で一人あたり180万円もの節税が可能です。
例えば5歳の子どもなら130万円、15歳なら30万円の控除が受けられ、さらに控除しきれない分は親の税額からも差し引けるという驚きの制度です。
本記事では、この節税メリットを最大化する方法と、未成年者が相続人となる場合の特有の手続きを、実例を交えて詳しく紹介します。10分ほどの短い時間で読める内容ですので、スキマ時間を使って数百万円をお得に節税しましょう!
未成年者の相続手続きに注意すべきポイント
相続が発生すると、相続人同士で遺産分割協議※を行いますが、相続人に未成年者がいる場合は注意が必要です。
こういった声をよく聞きます。
「子どもが相続人になると手続きが複雑になって、どうすればいいのか途方に暮れてしまいますよね。私も経験しましたが、最初は何から手をつければいいのか本当に悩みました…」
未成年者は単独で法律行為を行うことができないため、代理人が必要になります。ここでは、その基本的な仕組みについて説明します
未成年者の法律行為の制限と相続時の対応方法
民法第5条では、未成年者は法定代理人の同意がなければ有効な法律行為ができないと定められています(民法第5条第1項)。
これは相続手続きにも適用され、未成年者単独での遺産分割協議への参加や相続放棄などの手続きはできません(民法第764条)。
遺産分割協議は相続財産を決める重要な契約行為です。未成年者がこれに参加しても、法的には無効となります。
そのため、未成年者の代わりに誰かが代理人となって手続きを行う必要があります。通常は親権者である親が法定代理人として対応します。
⚠️ 注意点 未成年者を含めて行った遺産分割協議は、適切な代理人なしでは無効になる可能性があります。必ず法的に有効な手続きを踏みましょう。
親権者が代理人になれない利益相反ケースと特別代理人の選任
一般的には親権者が未成年者の法定代理人となりますが、親権者と未成年者の利益が相反する場合は例外となります。
例えば、父親が亡くなり、母親と子どもが相続人になるケースでは、母親の相続分が増えると子どもの相続分が減る関係になります。
利益相反とは、簡単に言えば「一人の人が複数の立場で関わり、それぞれの利益が衝突してしまう状態」のことです。例えるなら、サッカーの試合で一人の審判が両チームの監督を務めるようなもの。公平な判断ができなくなりますよね。
このような「利益相反」の状況では、親権者は子どもの代理人になることができず(民法第826条)、特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人の選任手続きは以下の通りです
| 手続き | 内容 |
| 申立先 | 家庭裁判所 |
| 必要書類 | 申立書、戸籍謄本、財産目録など |
| 費用 | 収入印紙 800円程度+郵便切手代 |
| 処理期間 | 通常1〜2ヶ月程度 |
📌 参考リンク:最高裁判所 特別代理人選任申立ての手続き(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_17/index.html)
特別代理人には、未成年者の利益を守る立場から、弁護士や司法書士などの法律の専門家が選任されることが多いです。
また、親族が選任されることもありますが、その場合も利益相反関係にない人物である必要があります。
未成年者を含む遺産分割協議の進め方と必要書類
未成年者を含む遺産分割協議を有効に進めるためには、以下のステップを踏むことが重要です(民法第907条、家事事件手続法第200条)。
【遺産分割協議の進め方】
- 相続人の確定:戸籍謄本を収集して、法定相続人を確定します
- 相続財産の調査:預貯金、不動産、有価証券など遺産の全容を把握します
- 代理人の選任:未成年者のために適切な代理人を選任します
- 遺産分割協議の実施:すべての相続人(未成年者は代理人)が参加して協議します
- 遺産分割協議書の作成:合意内容を書面にまとめます
- 必要な登記手続き:不動産の名義変更などを行います
特に不動産を含む相続の場合は、以下の書類が必要になります
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 固定資産評価証明書
- 不動産の登記簿謄本
- 遺産分割協議書(実印の押印と印鑑証明書が必要)
未成年者が相続人に含まれる場合は、これらに加えて特別代理人選任の審判書なども必要になることがあります。
💡 専門家のアドバイス
未成年者を含む相続手続きは複雑になりがちです。早い段階で弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
未成年者相続で活用できる未成年者控除と節税方法とは
未成年者が相続人となる場合、「未成年者控除」という税額控除を利用できます。これを活用することで、相続税を大幅に節税することが可能です。
未成年者控除の具体的事例
「私の甥が5歳の時に相続人になった時は、税理士さんから未成年者控除の説明を受けて本当に助かりました。それまで相続税の節税なんて考えたこともなかったんです。」
確かに、専門家のアドバイスで大きく税負担が変わることは多いですよね。皆さんも早めに確認しておくと安心です。
未成年者控除は、以下の計算式で求められます(相続税法第19条の3):
(18歳-相続した時の年齢)× 10万円
📌 参考リンク:国税庁 No.4155 相続税の未成年者控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
例えば、8歳の子どもが相続した場合の未成年者控除額は: (18歳-8歳)× 10万円 = 10年分 × 10万円 = 100万円
この控除額は相続税額から直接差し引かれるため、大きな節税効果があります。
実際の計算例を見てみましょう:
【事例】父親が亡くなり、母親と子ども2人(15歳と5歳)が相続人となったケース
相続税計算後の税額が各人150万円だった場合:
- 母親:150万円(控除なし)
- 15歳の子:150万円-30万円(未成年者控除)= 120万円
- 5歳の子:150万円-130万円(未成年者控除)= 20万円
3人合計で150万円の節税になります。特に年齢が低いほど控除額が大きくなるため、幼い子どもがいる場合は大きなメリットがあります。
ここで、未成年者控除を活用した場合としなかった場合の違いを具体的に見てみましょう。先ほどの事例を、相続財産が1億円で法定相続分(母1/2、子ども各1/4)で分けた場合で考えます:
【未成年者控除を活用しなかった場合】
- 母親(5,000万円相続):相続税約1,250万円
- 15歳の子(2,500万円相続):相続税約450万円
- 5歳の子(2,500万円相続):相続税約450万円
- 家族全体の税負担:約2,150万円
【未成年者控除を活用した場合】
- 母親(5,000万円相続):相続税約1,250万円
- 15歳の子(2,500万円相続):相続税約450万円 – 30万円(控除) = 約420万円
- 5歳の子(2,500万円相続):相続税約450万円 – 130万円(控除) = 約320万円
- 家族全体の税負担:約1,990万円
差額は約160万円となり、何も対策をしないまま相続するよりも、未成年者控除を適切に活用することで、家族全体で大きな節税効果が得られることがわかります。
「私の知人は未成年者控除の存在を知らずに相続してしまい、後から『もったいないことをした』と悔やんでいました。正しい知識があれば防げたことなんですよね」。
こういった事例は実際によく聞きますので、早めに専門家に相談することをおすすめします。
控除しきれない分を扶養義務者の税額から控除する方法
未成年者の相続税額が未成年者控除額より少ない場合、控除しきれない分は未成年者の扶養義務者(通常は親)の相続税額から控除できます(国税庁通達による一般的解釈)。
例えば、5歳の子どもの相続税額が50万円、未成年者控除額が130万円の場合:
- 子どもの相続税:50万円-50万円(控除)= 0円
- 残りの控除額:130万円-50万円 = 80万円
- この80万円を扶養義務者(母親など)の相続税から控除できます
この仕組みを活用すれば、家族全体での相続税負担を効果的に減らすことができます。
💡 税理士からのアドバイス
未成年者控除を最大限に活用するためには、相続財産の配分を工夫することも大切です。専門家に相談して、最適な相続プランを立てましょう。
未成年者控除を受けるための要件は以下の通りです:
- 相続開始時に18歳未満であること
- 相続または遺贈により財産を取得したこと
- 法定相続人であること
- 原則として相続開始日に日本に住所があること
これらの条件をすべて満たす必要があります。
📌 参考リンク:国税庁 相続税の申告と納税 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm
未成年者が相続した不動産の管理方法
未成年者が不動産を相続した場合、その管理は親権者または後見人が行います。ただし、不動産の売却や担保設定などの処分行為には、家庭裁判所の許可が必要になる場合があります(民法第824条の制限行為能力者の保護に関する通説)。
不動産の管理においては、以下の点に注意しましょう:
- 固定資産税などの税金の支払い
- 空き家になる場合は防犯・防災対策
- 賃貸に出す場合の契約管理
- 修繕費用の確保と計画的な修繕
また、未成年者が成人するまでの長期的な視点での管理計画も重要です。
【不動産管理の選択肢】
| 管理方法 | メリット | デメリット |
| 親権者が管理 | 柔軟な対応が可能 | 管理負担がかかる |
| 信託銀行に管理委託 | 専門的な管理が受けられる | 手数料がかかる |
| 不動産管理会社に委託 | 賃貸経営がスムーズ | 管理コストがかかる |
| 売却して金融資産化 | 管理の手間がなくなる | 将来の資産価値上昇の機会を失う |
未成年者が成人した後のことも考え、教育資金や独立資金としての活用なども視野に入れた管理計画を立てることが大切です。
⚠️ 重要ポイント 未成年者名義の不動産を勝手に売却したり、収益を親が使ったりすることは、法的に問題になる可能性があります。必ず適切な手続きを踏んで管理しましょう。
まとめ
未成年者を含む不動産相続では、通常の相続とは異なる手続きや注意点がありますが、未成年者控除を活用すれば大きな節税メリットを得ることも可能です。本記事で解説したように、最大で180万円もの税額控除が実現できます。
「知っているか知らないかで数百万円の差が出る可能性がある」のが相続税の世界です。特に未成年者が相続人に含まれるケースでは、適切な知識と対応が不可欠です。この記事が、未成年者を含む相続に直面されているご家族の一助となれば幸いです。
専門家のサポートを受けながら、未成年者の将来も見据えた相続対策を行うことをおすすめします。相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)に余裕をもって、早めの準備を始めましょう。
まずは無料相談を活用して、ご自身の状況に合った専門家に相談することから始めてみてください。
この記事の監修者

遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。