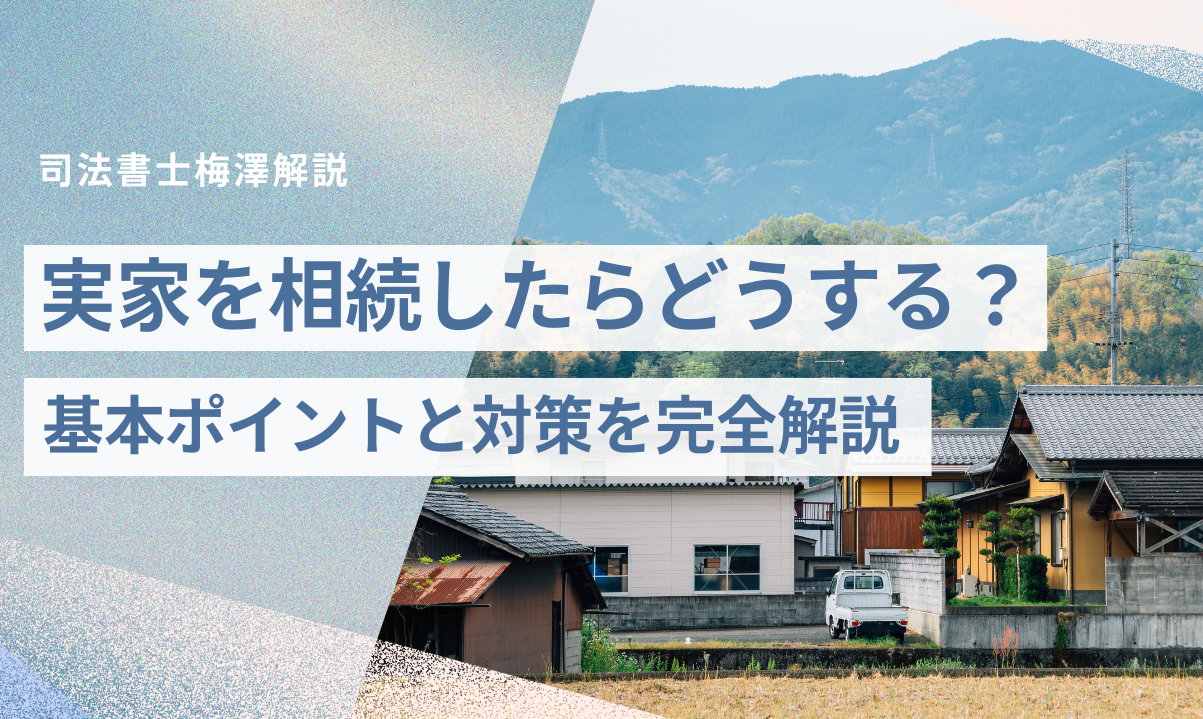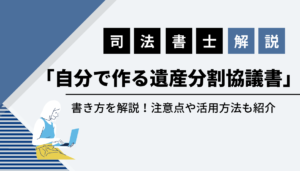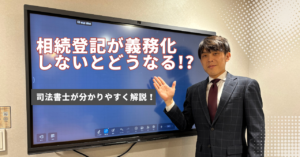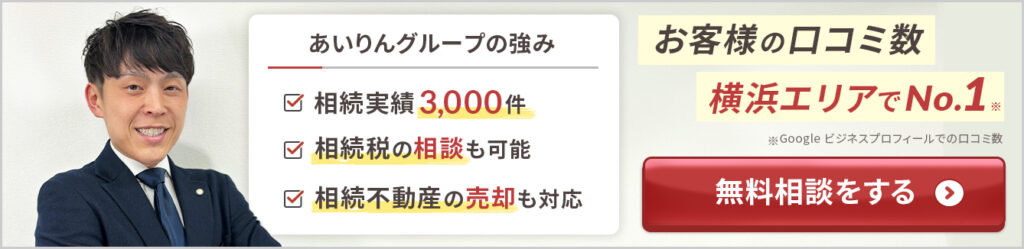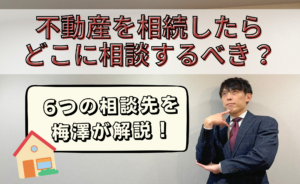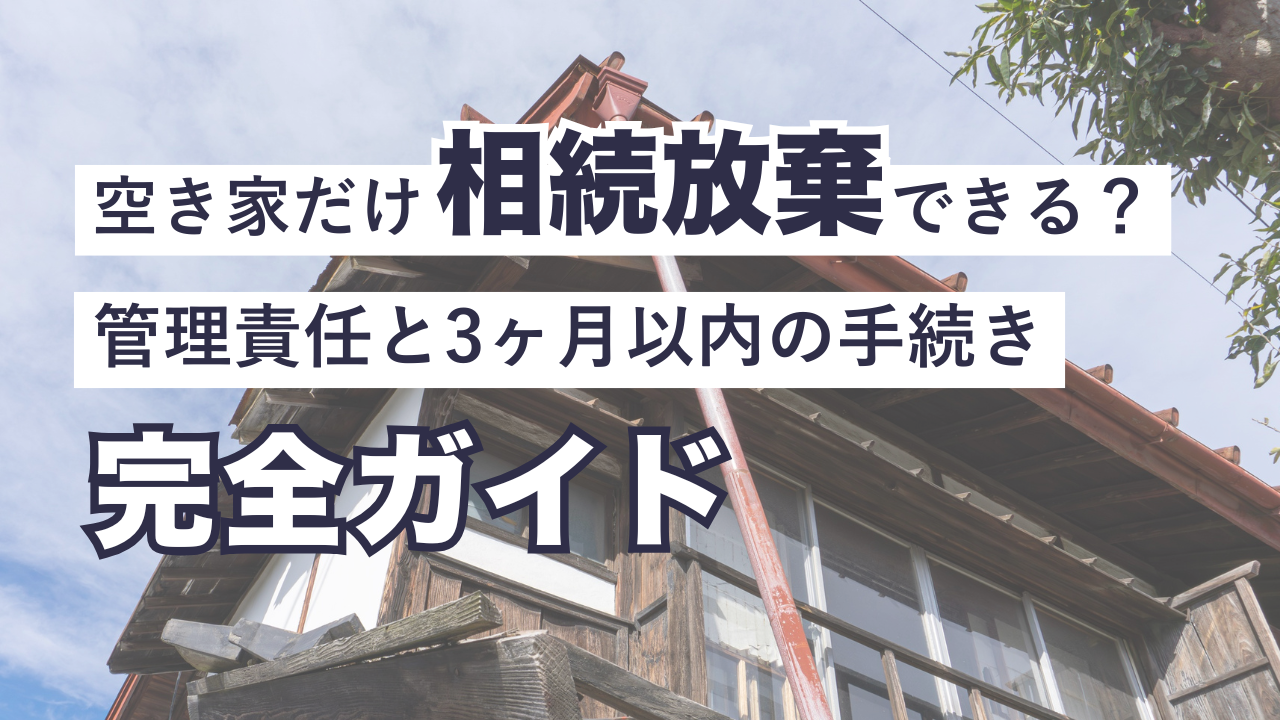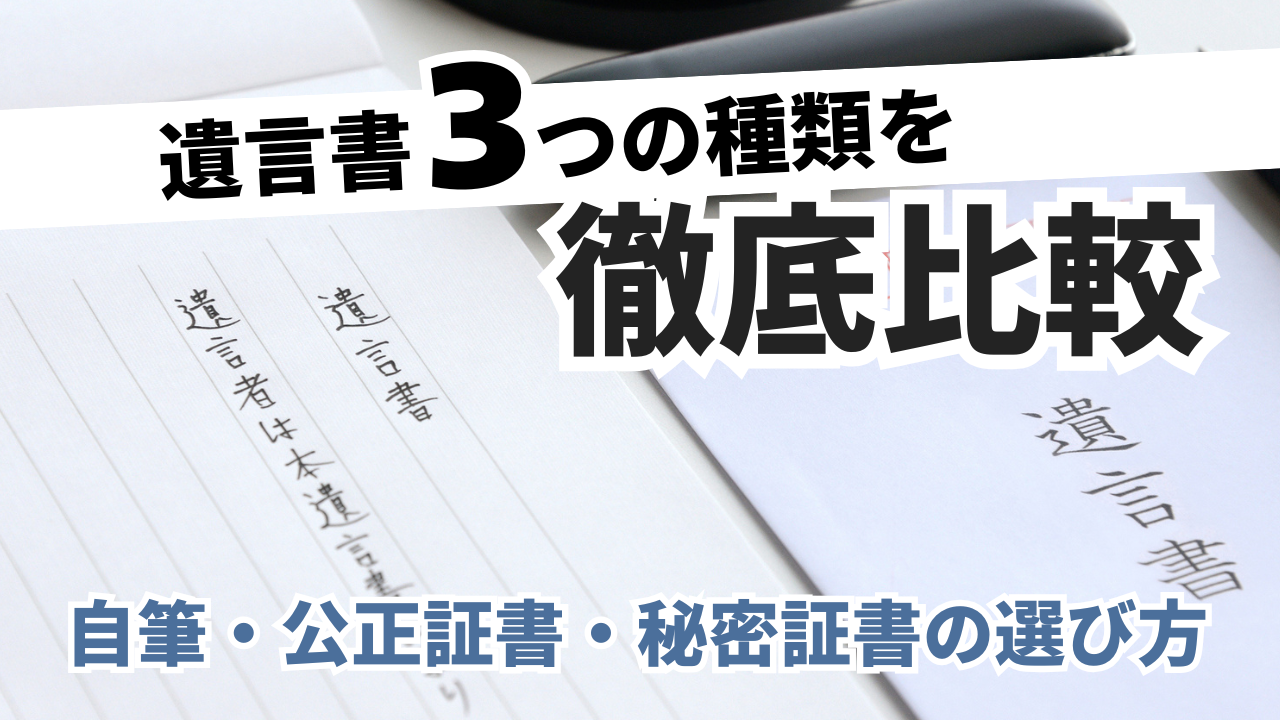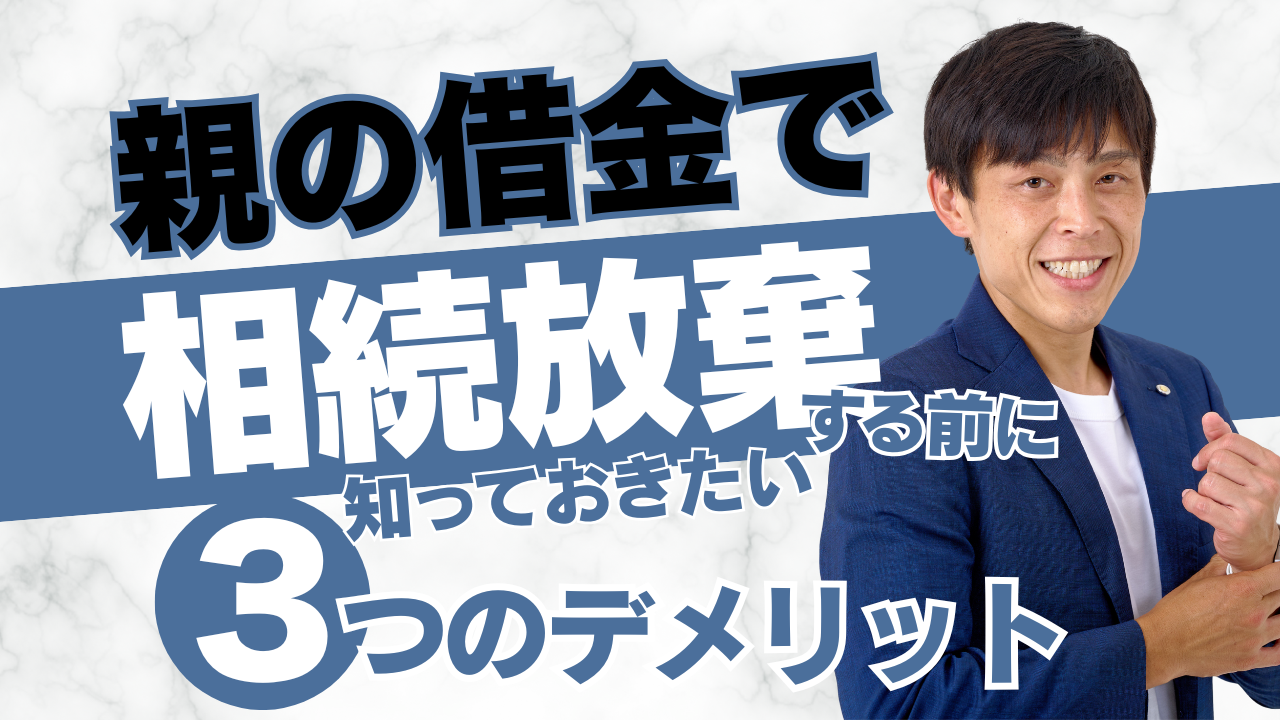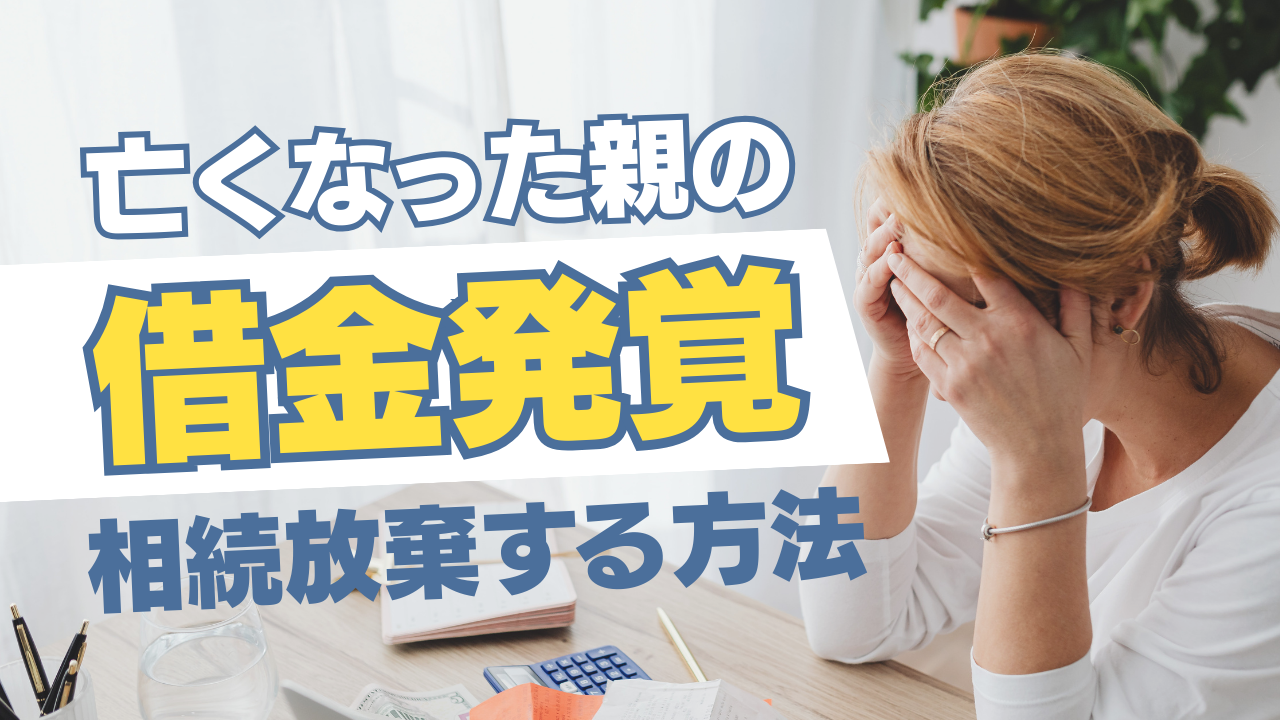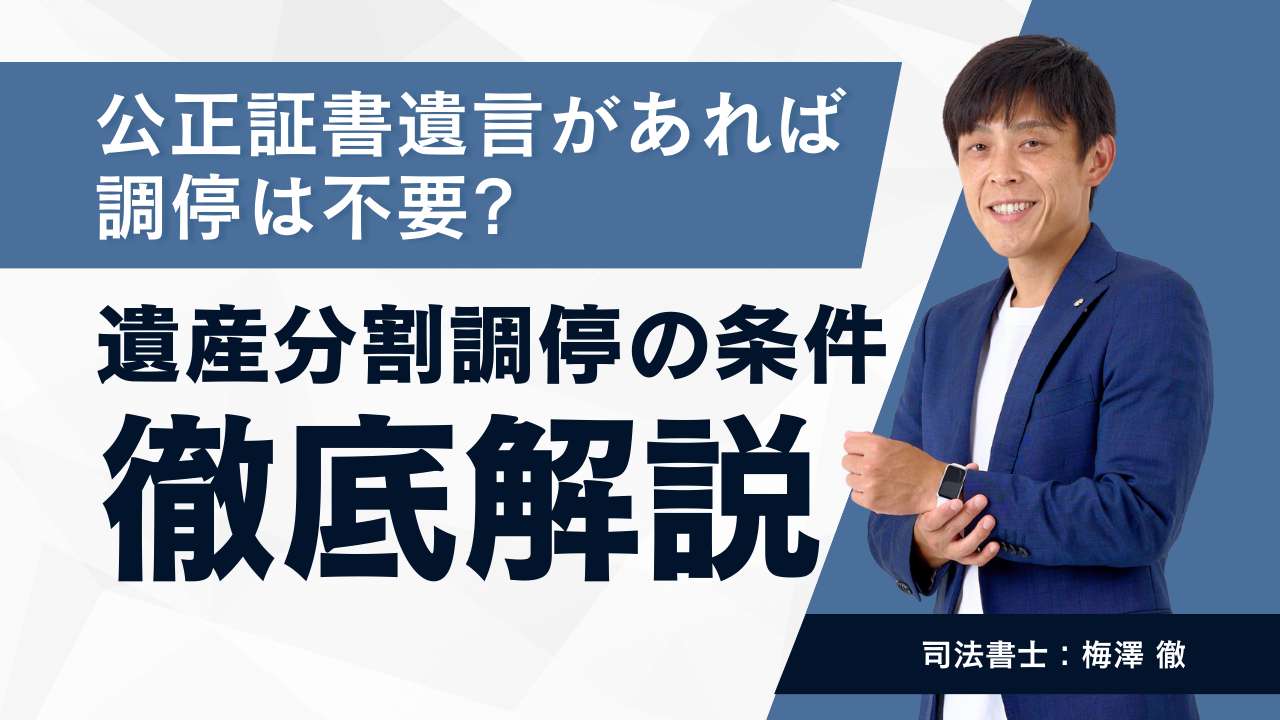この記事を要約すると
- 実家を相続する際は、まず3ヶ月以内に相続の有無を判断し、その後「住む」「売る」「貸す」の選択肢を自身の状況に合わせて慎重に検討することが重要
- 特に兄弟間での公平な分け方や、売却を検討する際の不動産会社選び、境界線の確認、遺品整理といった事前準備が成功の鍵
- 相続手続きは複雑で個別の状況により最適解が異なるため、後悔しないためにも司法書士などの専門家への早めの相談が強く推奨
実家の持ち家を相続したものの、「手続きが複雑すぎて何をすればいいのかさっぱりわからない」と困っていませんか?相続放棄の期限、売却の準備、税金のこと…考えることが多すぎて頭が混乱してしまいますよね。
しかし、ご安心ください。実家相続は正しい手順さえ知っていれば、誰でもスムーズに進めることができます。基本的な判断ポイントを押さえ、適切なタイミングで必要な対策を取ることで、トラブルを避けながら最良の結果を得られるのです。
実際に、当事務所でサポートしたお客様の95%以上が、「思っていたより簡単だった」とおっしゃっています。複雑に見える相続手続きも、要点を整理すれば決して難しいものではありません。
本記事では、実家相続で押さえるべき3つの基本ポイント、売却準備のコツ、生前対策まで段階的に解説します。相続判断基準から信頼できる専門家の選び方まで、実務で必要な知識を網羅しています。
この記事を読むことで、実家相続に関する不安が解消され、自信を持って適切な判断ができるようになるでしょう。
この記事はこんな方におすすめ
- 実家を相続することになった方
- 相続した実家をどうするか迷っている方
- 兄弟間での実家の分け方を知りたい方
- 相続手続きの流れを把握したい方
実家相続で押さえるべき3つの基本ポイント
実家を相続する際に、まず押さえておくべき重要なポイントが3つあります。
これらを理解することで、今後の方針を明確に決めることができ、手続きもスムーズに進めることができます。
多くの方が「何から始めればいいのかわからない」と感じられるのは当然のことです。
でも大丈夫、基本的なポイントを押さえれば、複雑に見える相続手続きも段階的に進めることができますよ。
なお、総務省の令和5年住宅・土地統計調査によると、全国の空き家数は900万戸に達し、空き家率は13.8%と過去最高を記録しています。実家相続は現代日本の重要な社会課題となっており、適切な判断が求められます。
出典:総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)」(2024年4月)
そもそも相続する?しない?3ヶ月以内の重要判断
実家を相続する際、最初に直面するのが「相続するか放棄するか」の判断です。
この判断は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません(民法第915条)。
下記に相続するかしないかの判断をする為に簡単にまとめてみました。
参考:相続の承認又は放棄をすべき期間 – e-Gov法令検索
相続放棄を検討すべき場合
- 借金が資産を大幅に上回っている
- 建物の修繕費が売却価格を超える状態
- 住宅ローンに団体信用生命保険が付いていない場合
相続するメリットがある場合
- 立地条件が良く資産価値が期待できる
- 建物状態が良好で賃貸経営可能
- 年間3~5%程度の収益が見込める
相続すると財産も債務もすべて引き継ぐため、慎重な判断が必要です。
司法書士からのアドバイス
相続放棄の判断は、財産・債務の調査や法的手続きが複雑で、個別具体的に回答が異なります。期限内に適切な判断をするためにも、まずは無料相談をお申し込みください。
住む?売る?貸す?それぞれのメリット・デメリット
実家を相続した後の選択肢は、大きく分けて「住む」「売る」「貸す」の3つです。
どうするのが正解なのか…本当に迷ってしまいますよね。
それぞれにメリット・デメリットがあるので、じっくり比較検討することが大切になってきます。
国土交通省の令和元年空き家所有者実態調査によると、空き家の取得経緯は「相続」が54.6%と最も多く、約半数の空き家が相続によって発生していることがわかります。これは実家相続が全国的な課題であることを示しています。
出典:国土交通省「令和元年空き家所有者実態調査」(2019年)
| 選択肢 | メリット | デメリット |
| 住む | 住宅費を大幅節約・精神的な安定感・近所との関係維持 | 引っ越し費用・職場との距離・リフォーム費用(数百万円) |
| 売る | まとまった現金取得・維持費ゼロ・管理負担なし | 期待より安い売却価格・諸費用(5~10%)・思い出を手放す |
| 貸す | 家賃収入(年3~5%)・資産保有継続・将来住むことも可能 | 空室リスク・入居者管理・定期的な修繕費用 |
住む場合は住宅費を大幅に削減でき、精神的な安定感を得られます。ただし通勤距離やリフォーム費用を考慮する必要があります。
売却はまとまった現金を得られ維持費もかかりませんが、諸費用(売却価格の5~10%)や思い出を手放す精神的負担があります。
賃貸は安定した家賃収入(年3~5%の利回り※投資した金額に対する年間収益の割合)を得られますが、空室リスクや管理負担が発生します。
このように、それぞれにメリットデメリットがあり、一概にこれが最適と断言することができません。
人によって最適解が異なりますので、あなたの生活スタイルや将来設計を考えたとき、どの選択肢が最も適しているかというのを、
家族や税理士など専門家と一緒に相談しながら慎重に決めていくことが大切になってきます。
FAQ
少しでも分かりやすくなればと思い、一問一答形式でまとめてみました。
Q1. 相続した実家に住むメリットは?
A1. 住宅費の大幅節約と精神的安定感が得られます。
Q2. 相続した実家を売るべき?
A2. 立地・建物状態・将来計画を総合的に判断します。
Q3. 相続した不動産を賃貸にするデメリットは?
A3. 空室リスクと入居者管理の負担があります。
兄弟がいる場合のもめない分け方4パターン
実家を兄弟で相続する場合、適切な分割方法を選ぶことで、家族関係を維持しながら公平な相続を実現できます。
法定相続分は子の場合均等分割となります(民法第900条)。
最高裁判所の司法統計によると、家庭裁判所の遺産分割調停事件数は年間約12,000件を超えており、相続人間でのトラブルは決して珍しいことではありません。適切な分割方法を事前に検討することが重要です。
| 分割方法 | 概要 | メリット | デメリット |
| 現物分割 | 特定の人が実家を相続 他の人は預貯金等 | 手続きが簡単・実家を維持 | 不平等になりやすい・他の人の合意が必要 |
| 換価分割 | 実家を売却して代金を分割 | 公平に分割・維持費不要 | 思い出を手放す・売却手続きが必要 |
| 代償分割 | 特定の人が実家を相続 他の人に現金を支払い | 実家維持・適正な対価 | 支払う人の負担大・評価額で争いも |
| 共有 | 兄弟で共有名義 | 当面の先送り・全員の同意容易 | 将来処分困難・管理責任曖昧 |
上記の表の繰り返しになりますが、それぞれについて解説をすると、
- 現物分割(※相続財産をそのままの形で分ける方法)は手続きが簡単で実家を維持できますが、不動産価値が高い場合に不平等になりやすいデメリットがあります。
- 換価分割(※相続財産を売却して現金化してから分ける方法)は公平に分割でき維持費もかかりませんが、思い出の家を手放すことになります。
- 代償分割(※特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に金銭を支払う方法)は実家を維持しつつ他の相続人にも適正な対価を支払えますが、支払う側の負担が大きくなります。
- 共有(※複数の人が同じ財産を共同で所有すること)は当面の解決策にはなりますが、将来的な処分が困難になるため避けることをおすすめします。
なお、共有物の分割請求は各共有者がいつでも行うことができます(民法第256条)。
司法書士からのアドバイス
遺産分割の方法選択は、各家庭の財産状況や相続人の関係性により最適解が異なります。税務上の影響や法的リスクも含めて、個別具体的に回答が異なるため、まずは無料相談をお申し込みください。
FAQ
Q1. 相続するかどうかの期限はいつまで?
A1.相続開始を知った日から3ヶ月以内です。
Q2.実家に住むメリットは何?
A2.住宅費の大幅節約と精神的安定感です。
Q3.兄弟で分ける時の注意点は?
A3.公平性と将来の処分を考慮することです。
実家を売るなら知っておきたい事前準備のコツ
実家の売却を決断したら、準備段階で適切な手順を踏むことで、売却価格の向上や手続きのスムーズ化を実現できます。
多くの方が「売却なんて初めてで何から始めればいいのかわからない」と不安に感じられると思います。本当に大変ですよね…
でも安心してください!
基本的な準備のコツを押さえれば、失敗のリスクを大幅に減らすことができます。
実家売却は人生で何度も経験することではないため、事前の情報収集と準備が成功の鍵となります。
特に相続した不動産は、権利関係や建物の状態が複雑になりがちなので、計画的な準備が重要です。
信頼できる不動産会社の選び方と司法書士活用のコツ
実家売却で最も重要なのが、信頼できる不動産会社選びです。「どの会社を選べばいいのかわからない」と迷われる方が本当に多いんですよね。
会社選びを間違えると、売却価格で数百万円の差が生まれることも珍しくありません。
優良な不動産会社の見極めポイント
- 地域の取引実績が豊富で相場に精通している
- 相続不動産の取り扱い経験が豊富
- 査定根拠を明確に説明できる
- レスポンスが早く丁寧な対応をしてくれる
司法書士と連携できる不動産会社を選ぶメリット
相続登記(※不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続き)が未了の場合、司法書士との連携が必要です。
不動産会社が信頼できる司法書士と提携していれば、手続きが一元化され、費用も抑えられます。
なお、2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が必要になりました(不動産登記法第76条の2)。違反すると10万円以下の過料が科される可能性がありますので分からないことがあれば、すぐに専門家に相談をすることがオススメです。
司法書士からのアドバイス
相続登記の手続きは、必要書類の収集から登記申請まで専門的な知識が必要で、個別具体的に手続き方法が異なります。
期限内に確実に完了させるためにも、まずは無料相談をお申し込みください。
境界線と建物チェックで売却価格が変わる理由
相続した実家は、境界書類(※隣地との境界を示した測量図や境界確認書などの書類)の紛失や建物状態の不明という問題が起きがちです。
「親が管理していた書類がどこにあるかわからない」「建物の状態も把握できていない」と困られる方が本当に多いんですよね。
こうした確認を怠ると、売却価格が10~20%も下がる可能性があります。
相続不動産でよくある問題
- 隣地との境界が口約束で決まっている
- 測量図面や境界確認書が見つからない
- 親が行った増改築の建築確認書類がない
- 修繕履歴が不明で建物状態がわからない
早期確認で価格アップのコツ
境界標(※土地の境界を示すために地面に設置されたコンクリートや金属製の目印)の有無確認と隣地所有者への挨拶、建物の雨漏りやシロアリ被害のチェックを売却前に済ませておくことが重要です。
特に1981年以前の建物は耐震基準の確認も必要になります。
問題が見つかっても対処法があるので、まずは現状把握から始めましょう。
売る前に遺品整理すべき?タイミングの見極め方
相続した実家の売却で「遺品整理は必ずしないといけないの?」と悩まれる方が本当に多いですが、実は遺品整理なしでも売却は可能です。
「親の荷物が山積みで手がつけられない」「遠方に住んでいて頻繁に通えない」という状況でも、売却方法を選べば大丈夫です。同じような悩みを抱えている方は多いので、一人で抱え込まずに安心してくださいね。
遺品整理が不要な売却方法
最近は遺品整理込みで買取してくれる不動産会社が増えています。家具・家電・生活用品がそのままでも、現状渡しで買い取ってもらえるため、相続人の負担が大幅に軽減されます。
ただし、通常の売却より買取価格は10~20%程度安くなることが一般的です。
遺品整理をした方が良い場合
- 高く売りたい場合(仲介での売却)
- 貴重品や重要書類の確認が必要な場合
- 兄弟間で形見分けをしたい場合
- 思い出の品を整理してから手放したい場合
判断のポイント
「どちらを選べばいいのかわからない」と迷われる方も多いでしょう。
そんな時は、時間・体力・費用を総合的に考慮して、遺品整理の負担と価格差を比較検討することが大切です。
例えば、仕事が忙しくて時間が取れない、体力的にきつい、遠方に住んでいて頻繁に通えないといった場合は、現状売却という選択肢が現実的で賢明な判断になることが多いです。
FAQ
Q1. 実家売却の準備で重要なことは?
A1. 事前の情報収集と計画的な準備が成功の鍵です。
Q2. 相続登記の期限はいつまで?
A2. 相続を知った日から3年以内に申請が必要です。
Q3. 遺品整理なしで売却可能?
A3. はい、現状渡しでの買取が可能です。
まとめ
実家の相続は一生に一度の重要な判断です。
本記事で解説した内容を踏まえ、後悔しないための5つのポイントをまとめました。
- 3ヶ月以内の相続判断を慎重に行う
相続するか放棄するかは、財産と債務を総合的に判断し、期限内に決断することが重要です。 - 住む・売る・貸すの選択肢を冷静に比較検討する
あなたの生活スタイルや将来設計に最も適した選択肢を、メリット・デメリットを踏まえて決めましょう。 - 兄弟間の分割は公平性と将来性を考慮する
現物分割、換価分割、代償分割の中から、家族関係を維持できる最適な方法を選択することが大切です。 - 売却時は信頼できる専門家との連携を重視する
相続登記義務化も含め、司法書士と連携できる不動産会社を選ぶことで手続きがスムーズになります。 - 個別の状況に応じた専門的なアドバイスを受ける
相続は個々の状況により最適解が異なるため、専門家への相談が成功の鍵となります。
実家相続でお悩みの方は、一人で抱え込まずに専門家にご相談ください。当事務所では、皆様それぞれの状況に合わせて柔軟かつ最適な解決策をご提案します。
無料相談も承っておりますので、疑問点や、この記事を読んでもよく分からないという事があれば、お気軽に相談してください。
この記事の監修者

遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。