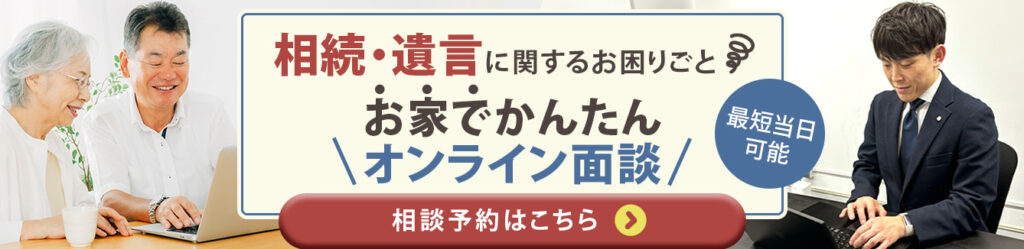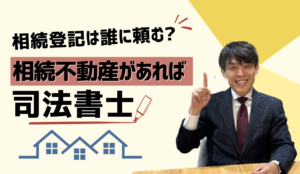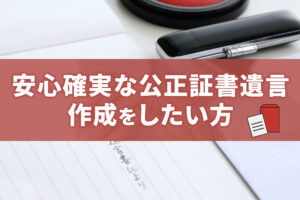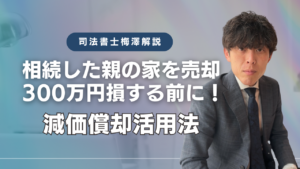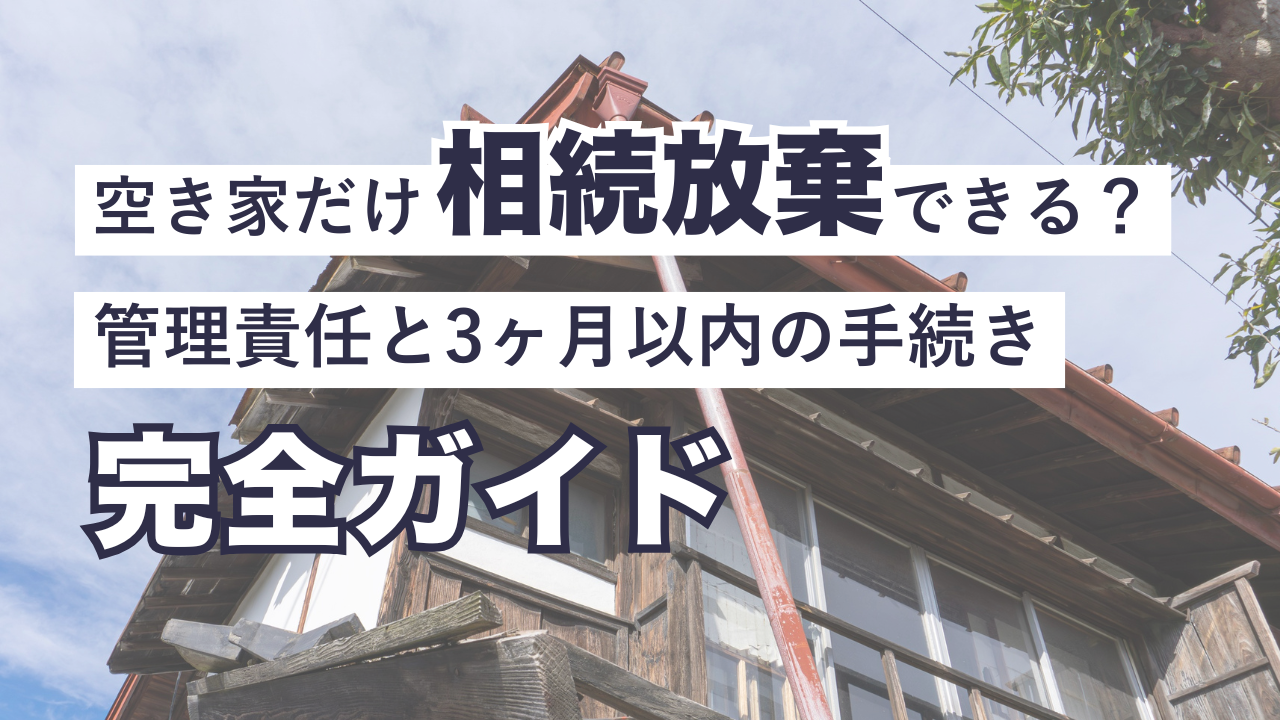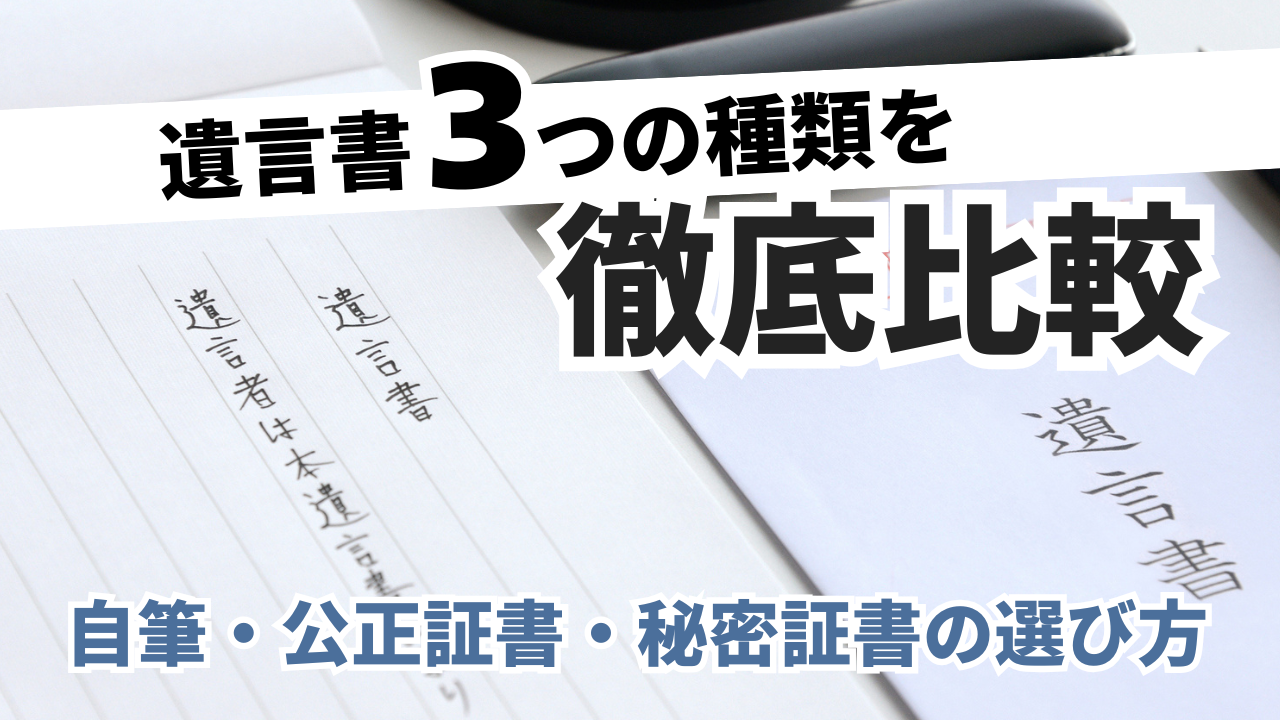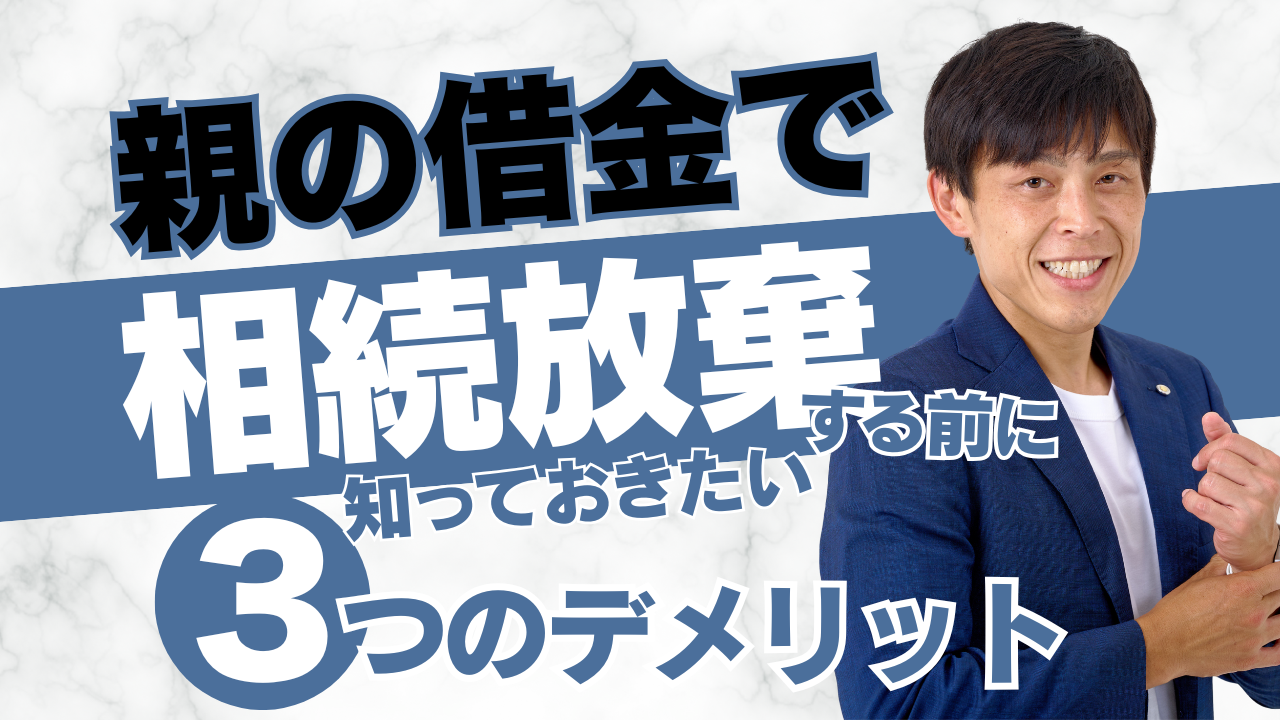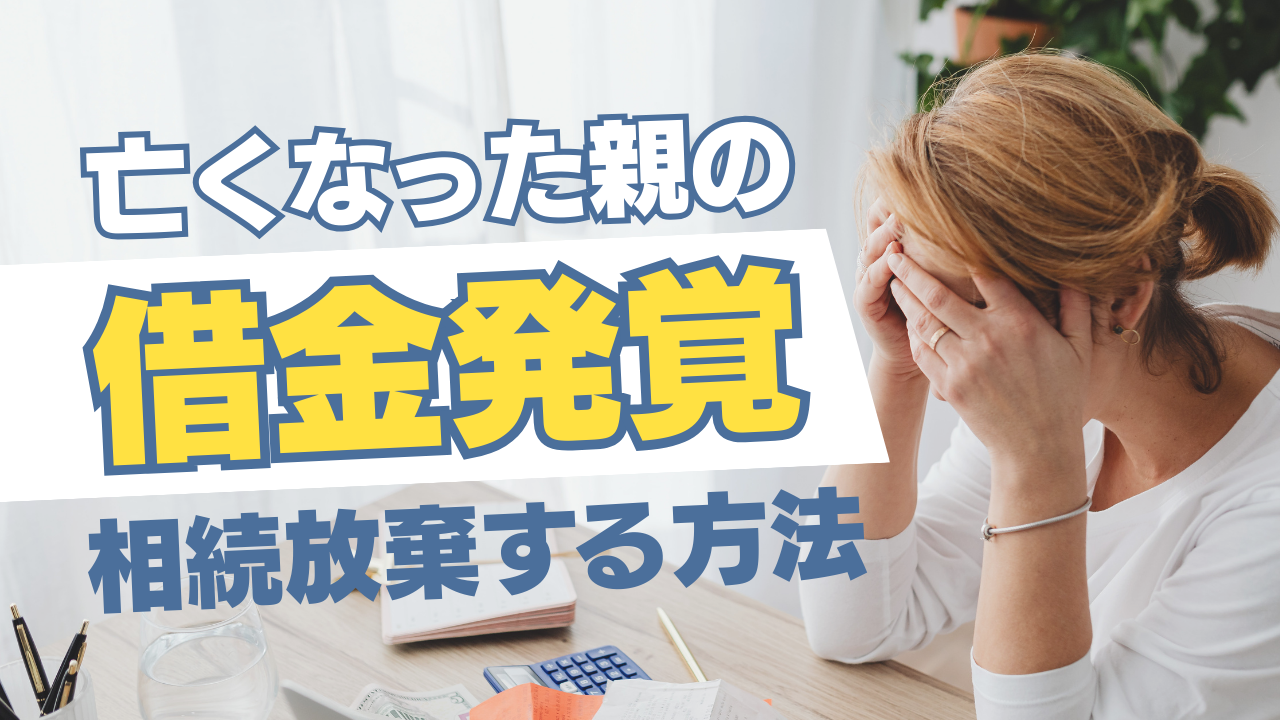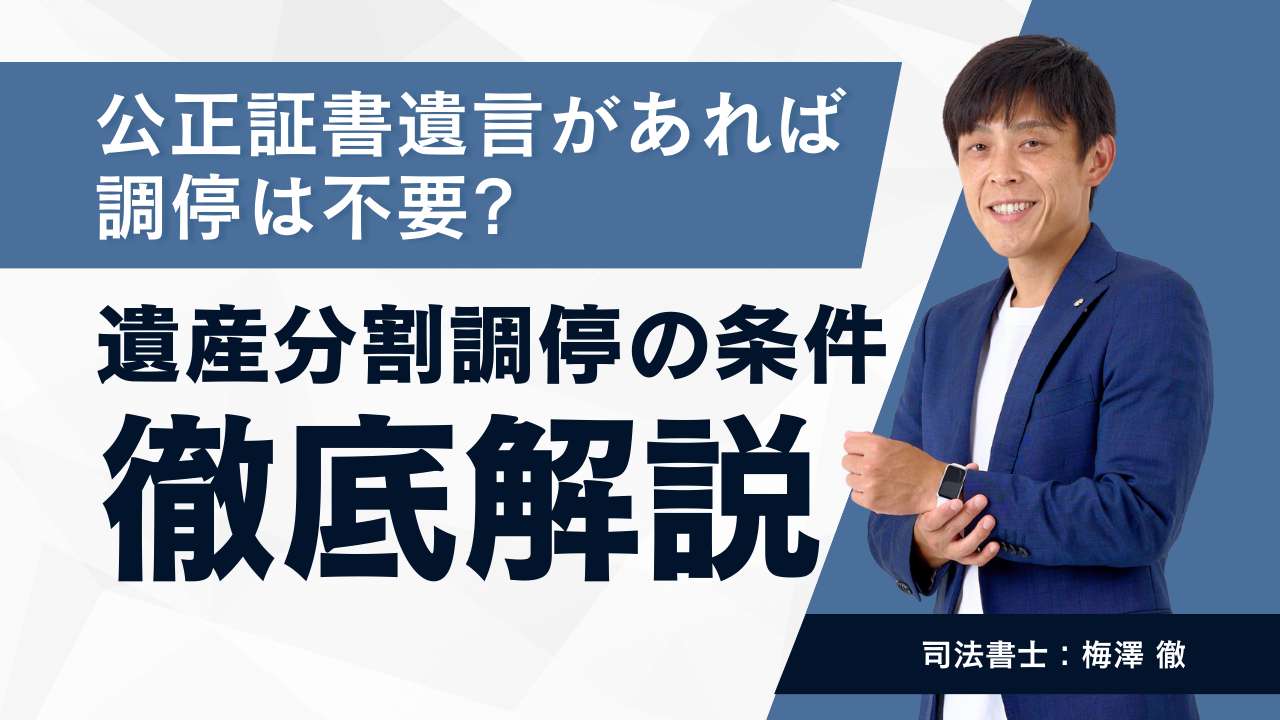この記事を要約すると
- 認知症により意思能力を失うと不動産の売買契約や遺産分割協議ができなくなる
- 成年後見制度・任意後見契約・家族信託の3つの方法で対処可能
- 親が元気なうちに遺言書作成や家族会議で事前対策を講じることが重要
親が認知症になると、不動産の売買契約や遺産分割協議ができなくなり、相続手続きに大きな支障が出ます。
この記事では、認知症による不動産相続のリスクと、事前に準備しておくべき対策を司法書士の視点から分かりやすく解説します。
読み終えた後は、認知症対策として何をすべきか明確になり、家族の財産を守るための具体的な行動を起こせるようになります。
この記事はこんな方におすすめ
- 親が高齢で認知症の兆候があり、不動産の相続対策を検討している方
- 認知症の親が所有する不動産の売却や管理で困っている方
- 成年後見制度や家族信託など事前対策の方法を知りたい方
目次
認知症になると不動産の相続手続きに支障が出る理由
認知症になると、法律上の「※意思能力」が失われるため、不動産の売買契約や相続手続きに大きな制約が生じます。
高齢化社会が進む中、親が認知症を発症してから不動産の処分や相続で困る家族が急増しています。
ここでは、認知症が不動産相続に与える具体的な影響を3つの観点から解説します。
※意思能力:自分の行為の結果を判断できる精神的能力のこと
意思能力喪失で売買契約・遺産分割協議ができない
認知症により意思能力を失うと、不動産の売買契約や※遺産分割協議など、法律行為が一切できなくなります。
民法では意思能力を欠く状態で行った契約は無効とされています(民法3条の2)。
参考:意思能力 – e-Gov法令検索
例えば、親が認知症になった後に実家を売却する契約を結んでも、その契約は法的に無効となり、買主とのトラブルに発展するリスクがあります。
また、親が亡くなった後の遺産分割協議においても、相続人の中に認知症の方がいると、その方は協議に参加できないため、相続手続きが進められません。
このような状況を避けるには、親が元気なうちに不動産の処分方針を決めておくか、後述する※成年後見制度や※家族信託などの対策を講じる必要があります。
※遺産分割協議:相続人全員で遺産の分け方を話し合って決める手続き
※成年後見制度:判断能力が不十分な方を法的に保護する制度
※家族信託:財産を信頼できる家族に託して管理してもらう仕組み
成年後見制度を利用しても不動産売却に制限がある
認知症の親のために成年後見制度を利用しても、不動産の売却には厳しい制限があります。
成年後見制度では、家庭裁判所が選任した※成年後見人が本人に代わって財産管理や契約を行います。
成年後見人が本人の居住用不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要となり(民法859条の3)、売却の必要性や本人の利益を厳格に審査されます。
参考:成年後見制度 – 裁判所
例えば、「相続税対策のために売却したい」「子どもの事業資金に充てたい」といった理由では許可が下りず、本人の介護費用や施設入居費用など、本人のための明確な必要性が求められます。
また、成年後見制度の利用には、家庭裁判所への申立費用や後見人への報酬は、専門職後見人(弁護士・司法書士など)が就任した場合、月額2万円〜6万円程度が目安です。
親族が後見人の場合は無報酬となるケースもありますが、家庭裁判所の決定に基づき継続的なコストがかかる点にも注意が必要です。
※成年後見人:家庭裁判所から選任され、本人に代わって財産管理や契約を行う人
認知症発症後は遺言書の作成が原則として無効
認知症を発症した後に作成された※遺言書は、意思能力が欠如しているとして無効と判断されるリスクが高くなります。
遺言書は本人の真意に基づいて作成される必要があり、※遺言能力(遺言の内容や効果を理解する能力)がなければ法的に有効とは認められません。
実際の裁判例では、認知症の診断後に作成された遺言書について、医師の診断書やカルテを証拠として遺言能力の有無が争われ、無効と判断されるケースが多く見られます。
特に※公正証書遺言は、公証人が遺言能力を確認するため、自筆証書遺言に比べ遺言能力が争われるリスクは大幅に軽減されます。
ただし、作成時の診断書やカルテなど、公証人の確認を覆すような明確な証拠がある場合は、例外的に無効となるリスクも残ります。
そのため、親に遺言書を作成してもらいたい場合は、認知症の兆候が現れる前、できれば70歳前後までに準備しておくことが望ましいです。
遺言書の作成が間に合わなかった場合でも、後述する※任意後見契約や家族信託などの代替手段を検討することができます。
※遺言書:自分の財産を誰にどのように残すかを書面で示したもの
※遺言能力:遺言の内容や効果を理解できる判断能力
※公正証書遺言:公証役場で公証人が作成する法的に強い遺言書
※任意後見契約:本人が元気なうちに将来の後見人を指定しておく契約
親が元気なうちにどのような対策が最適か、まずは無料相談で司法書士のアドバイスを受けることをおすすめします。
FAQ
Q. 認知症になると契約はできない?
A. 意思能力を欠くと契約は無効となり法律行為ができません。
Q. 成年後見制度の費用は?
A. 申立費用と月額2万円〜6万円程度の後見人報酬がかかります。
Q. 認知症後の遺言書は無効?
A. 遺言能力がないと判断されると無効になるリスクが高いです。
認知症の親が所有する不動産を処分する3つの方法
認知症の親が所有する不動産を処分する必要がある場合、主に3つの方法があります。
それぞれメリット・デメリットがあるため、家族の状況や不動産の内容に応じて最適な方法を選択することが重要です。
あなたのご家族の場合、どの方法が最適でしょうか。
ここでは、成年後見制度、任意後見契約、家族信託という3つの方法について、実務的な観点から詳しく解説します。
| 方法 | 開始時期 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 成年後見制度 | 認知症発症後 | ・法的保護が手厚い ・裁判所の監督あり ・既に認知症でも利用可能 |
・居住用不動産売却に裁判所許可必要 ・後見人報酬が継続的に発生 ・柔軟な財産管理が困難 |
| 任意後見契約 | 認知症発症前に契約 | ・後見人を自分で選べる ・契約内容を柔軟に設計可能 ・本人の意思を反映しやすい |
・認知症発症前の契約が必須 ・後見監督人の選任が必要 ・裁判所の監督あり |
| 家族信託 | 認知症発症前に契約 | ・認知症後も柔軟な財産管理可能 ・受託者の判断で迅速に売却可能・裁判所の許可不要 |
・契約設計が複雑 ・専門家への報酬が高額 ・金融機関の理解不足 |
成年後見制度の利用|家庭裁判所の許可で売却可能
既に親が認知症になっている場合、成年後見制度を利用することで不動産の売却が可能になります。
成年後見制度では、家庭裁判所に申立てを行い、選任された成年後見人が本人に代わって不動産の管理や売却を行います。
ただし、本人が居住している(または居住していた)不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可が必要となり(民法859条の3)、以下のような条件を満たす必要があります。
- 本人の生活費や医療費
- 介護費用の捻出など、本人の利益のための売却であること
- 売却価格が適正であること
- 他に本人の利益を守る方法がないこと
申立てから成年後見開始の審判が確定するまで、通常2〜4ヶ月程度(事案により変動)かかります。その後、居住用不動産売却の許可申立てが必要となるため、急いで売却したい場合には不向きです。
また、成年後見人には家族が選任されるとは限らず、弁護士や司法書士などの※専門職後見人が選ばれることも多く、その場合は継続的に報酬を支払う必要があります。
※専門職後見人:弁護士や司法書士など法律の専門家が後見人となるケース
任意後見契約|認知症になる前の契約で柔軟に対応
任意後見契約は、本人が元気なうちに、将来認知症になった場合に備えて後見人を指定し、財産管理の内容を契約で定めておく制度です。
成年後見制度との大きな違いは、本人が信頼できる家族や専門家を自ら選んで契約できる点と、財産管理の方針を自由に設計できる点です。
任意後見契約は公正証書で作成する必要があり、本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に※任意後見監督人の選任を申し立てることで効力が発生します。
参考:任意後見制度 – 法務省
任意後見監督人は裁判所が選任し、任意後見人の業務を監督する役割を担うため、不正な財産管理を防ぐ仕組みになっています。
不動産の売却についても、任意後見契約の内容に含めておけば、認知症発症後でも比較的柔軟に対応できますが、成年後見制度と同様に裁判所の監督下にあるため、一定の制約はあります。
契約の作成には公証人手数料や専門家への相談費用がかかりますが、将来の安心を得るための有効な選択肢です。
※任意後見監督人:任意後見人の業務を監督するため家庭裁判所が選任する人
家族信託の活用|認知症後も受託者が管理・売却可能
家族信託は、親が元気なうちに不動産を子どもなど信頼できる家族(※受託者)に託し、認知症になった後も受託者が管理・売却できる仕組みです。
家族信託では、財産の所有権は受託者に移転しますが、その利益は親(※委託者兼※受益者)が受け取るため、実質的には親の財産として活用できます。
最大のメリットは、親が認知症になった後でも、受託者の判断で迅速に不動産を売却できる点です。
成年後見制度や任意後見契約のように家庭裁判所の許可は不要で、相続税対策や不動産の組み替えなど、柔軟な財産管理が可能になります。
ただし、家族信託の契約設計は複雑で、信託の目的や財産の範囲、受託者の権限などを詳細に定める必要があるため、専門家のサポートが不可欠です。
また、信託契約の作成費用や専門家への報酬は、成年後見制度よりも高額になることが一般的です(初期費用として30万円〜100万円程度)。
さらに、金融機関によっては家族信託への理解が不十分で、※信託口口座の開設や融資に対応できないケースもあるため、事前の確認が必要です。
※受託者:財産を託されて管理・運用する人
※委託者:財産を託す人
※受益者:信託財産から生じる利益を受け取る人
※信託口口座:信託財産を管理するための専用口座
個別の事情に応じた判断が必要なので、まずは無料相談で司法書士の専門的なアドバイスを受けることをおすすめします。
FAQ
Q. 成年後見制度の申立期間は?
A. 申立てから許可まで通常2〜4ヶ月程度かかります。
Q. 任意後見契約の費用は?
A. 公証人手数料と専門家への相談費用が必要です。
Q. 家族信託のメリットは?
A. 認知症後も受託者が柔軟に不動産を管理・売却できます。
認知症による不動産相続トラブルを防ぐ事前対策
認知症による不動産相続トラブルを防ぐには、親が元気なうちに事前対策を講じることが何よりも重要です。
対策を先延ばしにすると、親が認知症を発症してから選択肢が大幅に制限されてしまいます。
本当に大変かとは思いますが、今から準備すれば間に合います。
ここでは、遺言書の作成、生前贈与、家族会議という3つの事前対策について、実務的なポイントを解説します。
遺言書の作成で相続人間の争いを未然に防ぐ
遺言書を作成しておくことで、親の意思を明確にし、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。
特に不動産は分割が難しい財産であるため、遺言書で「誰が不動産を相続するか」を明確に指定しておくことが重要です。
遺言書には※自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、認知症対策としては公正証書遺言の作成をおすすめします。
公正証書遺言は公証役場で※公証人が作成するため、形式の不備で無効になるリスクが少なく、原本が公証役場に保管されるため紛失の心配もありません。
また、遺言書作成時に公証人が本人の意思能力を確認するため、後日遺言能力を争われるリスクも軽減できます。
ただし、遺言書で特定の相続人に不動産を集中させる場合は、他の相続人の※遺留分を侵害しないよう配慮する必要があります(民法1042条)。
参考:遺留分 – e-Gov法令検索
遺留分とは、法律で保障された最低限の相続分のことで、配偶者や子どもには遺留分が認められており、侵害された場合は※遺留分侵害額請求ができます。
不動産以外の現金や預貯金で遺留分に相当する財産を用意しておくなど、バランスの取れた遺言内容にすることが、円満な相続のカギとなります。
※自筆証書遺言:本人が全文を自分で手書きする遺言書
※公証人:公証役場で法律文書を作成する公務員
※遺留分:法律で保障された最低限の相続分 ※遺留分侵害額請求:遺留分を侵害された相続人が金銭を請求できる権利
生前贈与で不動産を次世代へ移転|税金の注意点
※生前贈与を活用して、親が元気なうちに不動産を子どもに移転する方法もあります。
生前贈与のメリットは、親の意思がはっきりしているうちに財産を移転できるため、相続時の争いを回避できる点です。
また、親が認知症になる前に贈与を完了させることで、後々の不動産管理の負担を軽減できます。ただし、不動産の生前贈与には以下のような税金がかかる点に注意が必要です。
参考:贈与税 – 国税庁
このように、生前贈与は相続に比べて税負担が重くなるケースが多いため、税理士に相談して税額をシミュレーションすることが重要です。なお、※相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となり、相続時に相続財産として清算する方法もあります(相続税法21条の9)。
参考:相続時精算課税制度 – 国税庁
ただし、この制度を一度選択すると、同じ贈与者からの贈与について110万円の基礎控除が使えなくなるため、慎重な判断が必要です。
※生前贈与:生きているうちに財産を贈与すること
※相続時精算課税制度:2,500万円まで贈与税非課税で相続時に精算する制度
定期的な家族会議で財産状況と意思を共有する
認知症対策として最も基本的で重要なのが、定期的な家族会議を開いて財産状況と親の意思を共有することです。 親の財産がどこにどれだけあるのか、不動産の所在や評価額、預貯金の口座情報などを家族で把握しておくことで、万が一の際にスムーズに対応できます。
また、親自身が「将来認知症になったら不動産をどうしたいか」「誰に財産を残したいか」といった意思を明確にし、家族と共有しておくことも大切です。 家族会議では、以下のような内容を話し合うことをおすすめします。
- 不動産や預貯金など、親の財産の全体像
- 遺言書の作成や成年後見制度、家族信託などの対策の必要性
- 将来の介護方針や施設入居の希望
- 葬儀や墓の希望
- 財産の分け方についての親の意向
こうした話し合いは、親が元気なうちだからこそできるもので、認知症が進行してからでは手遅れになります。
また、家族会議には司法書士や税理士などの専門家を同席させることで、法的に有効な対策や税務面のアドバイスを受けることができます。
親子で話しにくいテーマだからこそ、第三者である専門家が入ることで冷静に話し合いを進めることができるでしょう。
ご家族の状況に応じた最適な対策を知るために、まずは無料相談で司法書士にご相談ください。
FAQ
Q. 遺言書作成の適齢期は?
A. 認知症の兆候が出る前、70歳前後までの作成が望ましいです。
Q. 生前贈与の税負担は?
A. 贈与税・不動産取得税・登録免許税で相続より高額になります。
Q. 家族会議で話すことは?
A. 財産の全体像・対策の必要性・介護方針・相続の意向などです。
まとめ:認知症対策は早めの準備が財産を守る鍵
認知症による不動産相続のリスクは、事前の準備によって大幅に軽減できます。
親が認知症になると、不動産の売買契約や遺産分割協議ができなくなり、成年後見制度を利用しても売却には厳しい制限がかかります。
そのため、親が元気なうちに遺言書の作成、任意後見契約、家族信託などの対策を講じておくことが何よりも重要です。
また、定期的な家族会議で財産状況と親の意思を共有し、認知症への備えを家族全体で考えることが、円満な相続への第一歩となります。
「まだ大丈夫」と思っているうちに、認知症は突然進行することもあります。
当事務所では、認知症対策としての遺言書作成、家族信託の設計、成年後見制度の申立てなど、不動産相続に関する総合的なサポートを提供しております。
ご家族の状況に応じた最適な対策をご提案しますので、まずは無料相談をご利用ください。
初回相談は無料ですので、親の財産や認知症対策でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
認知症の人が忘れる順番について専門家がわかりやすく解説|静岡老人ホーム紹介タウンYAYA
この記事の監修者

遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。