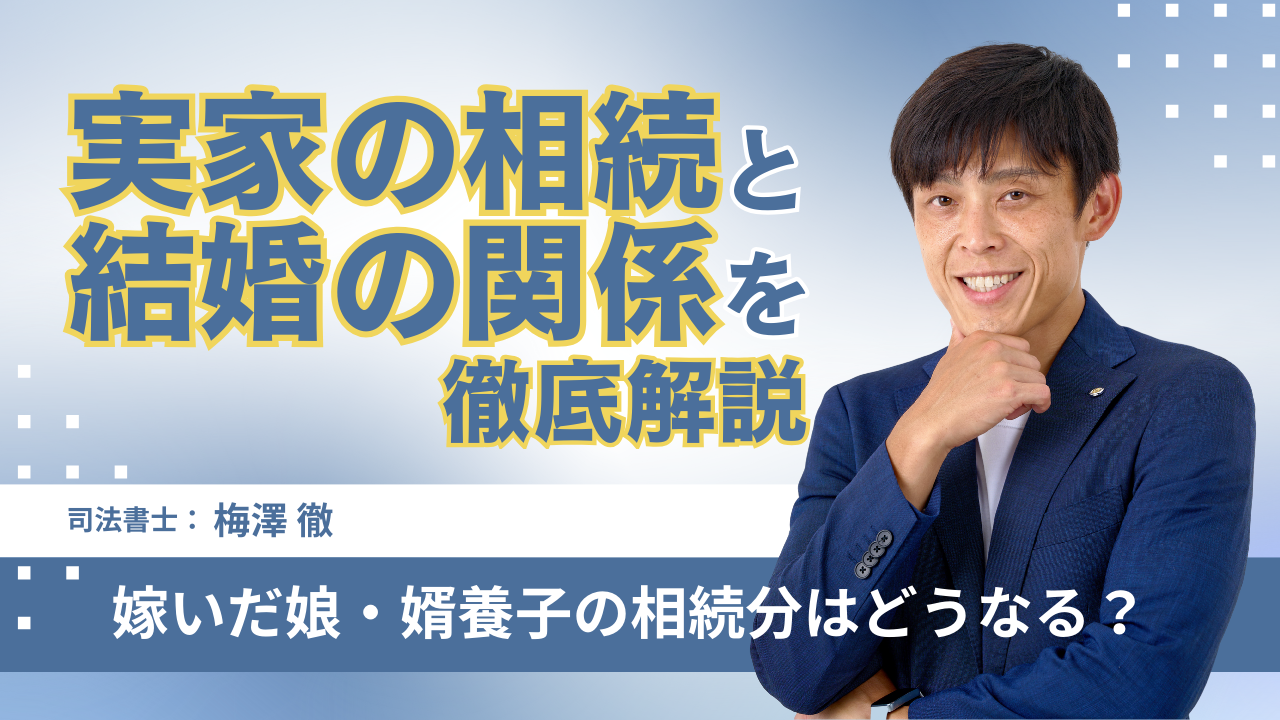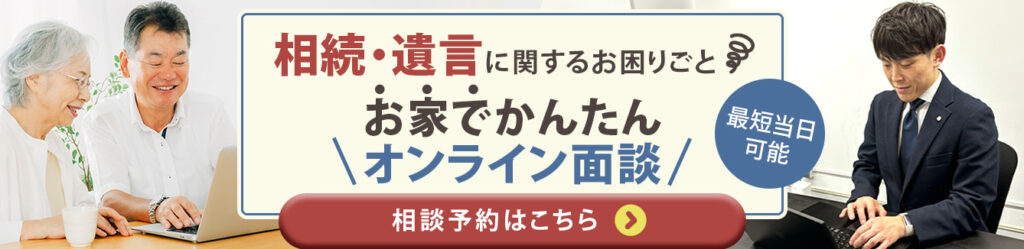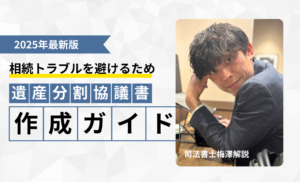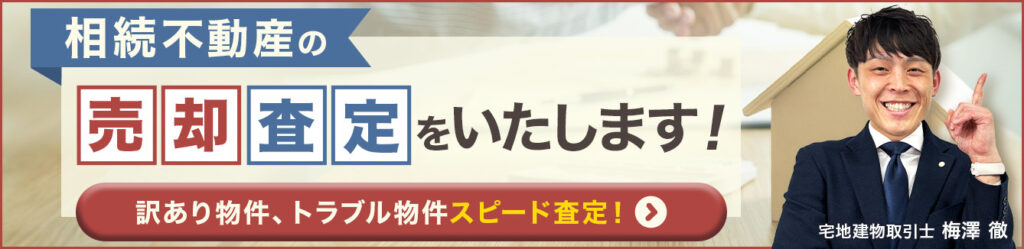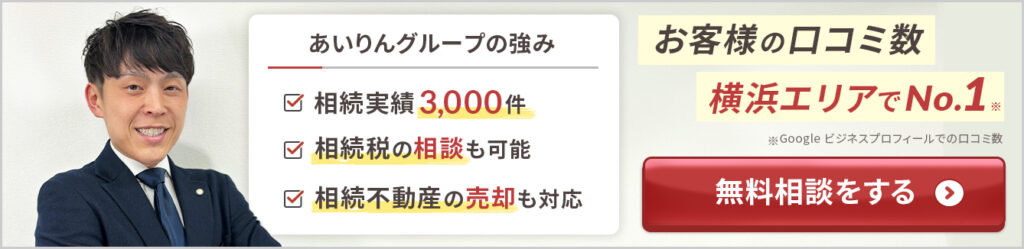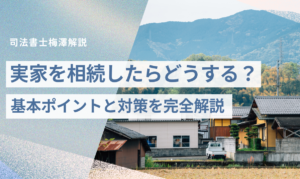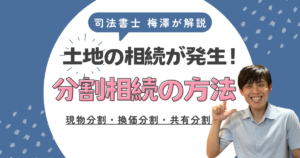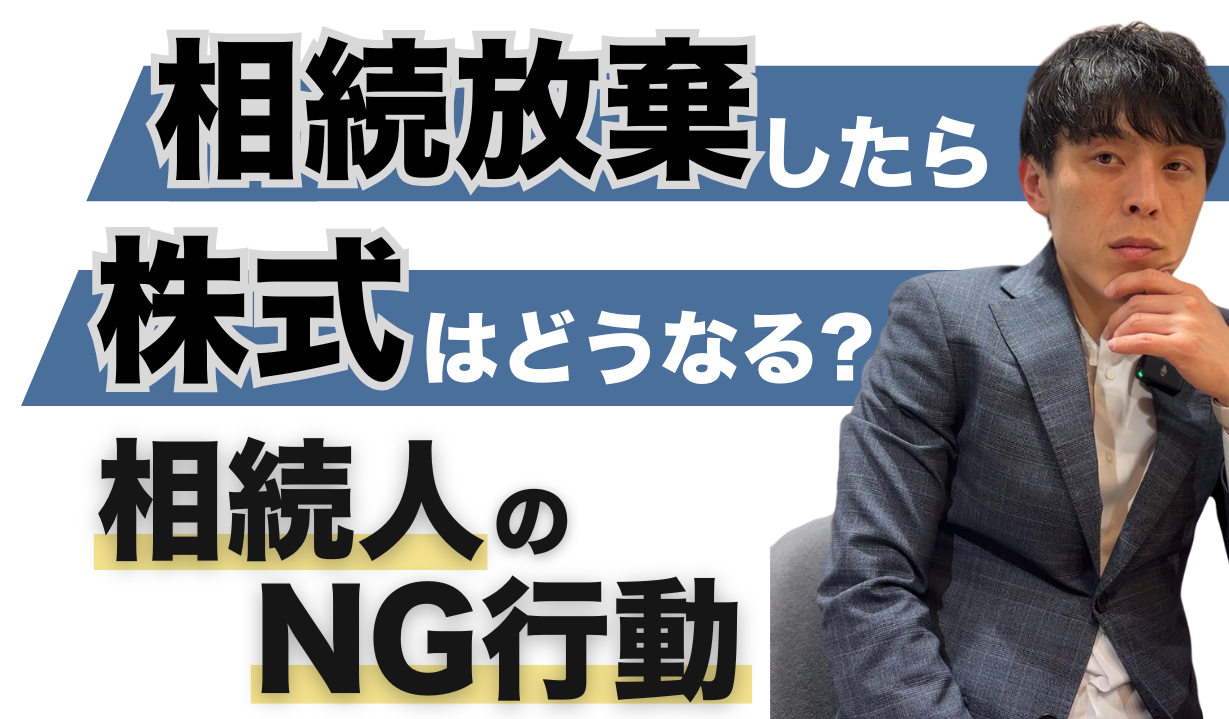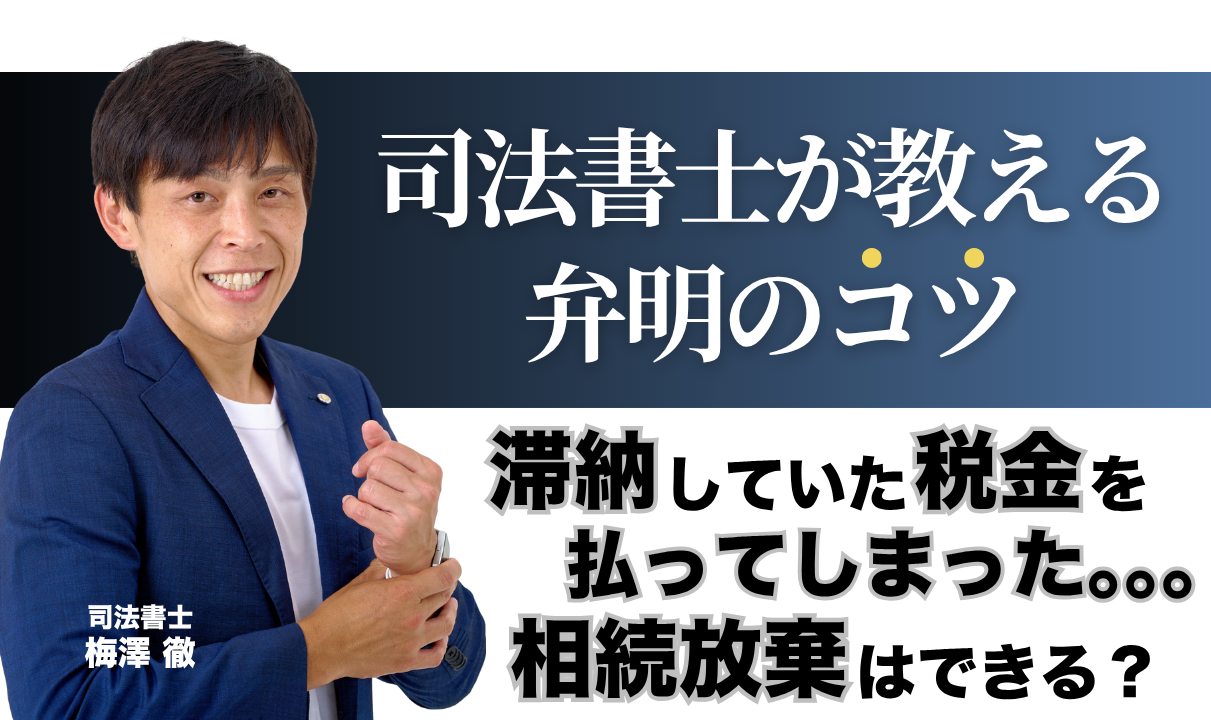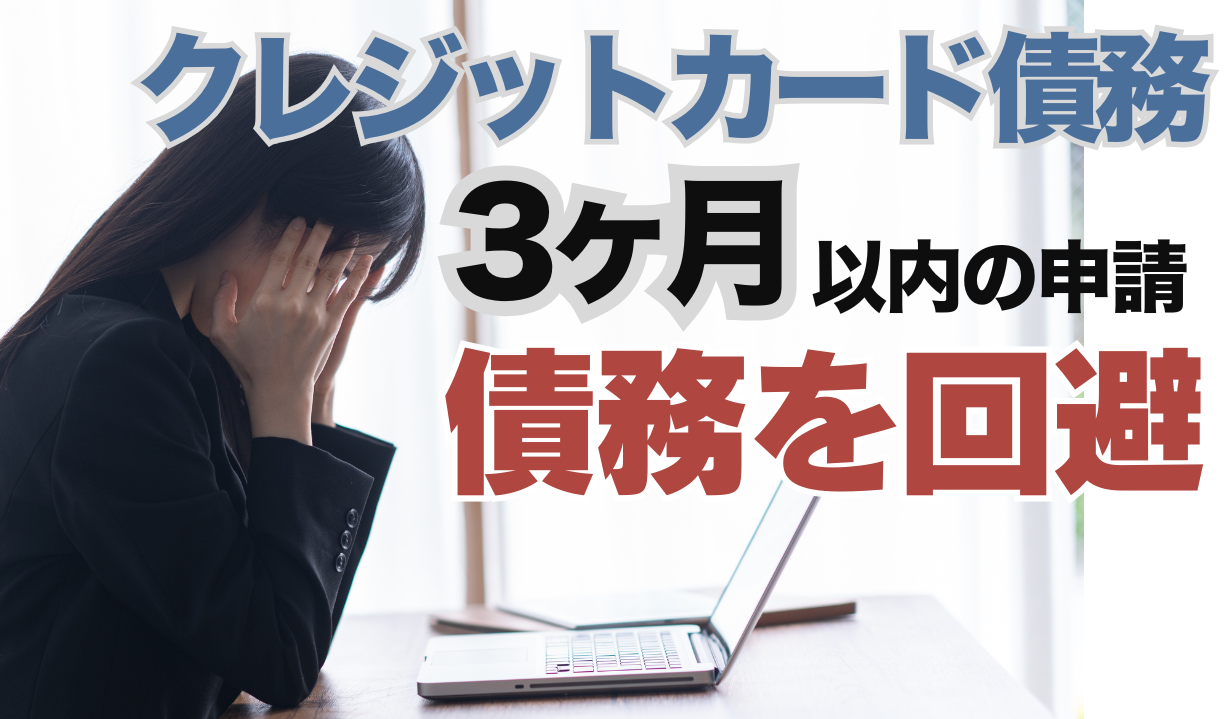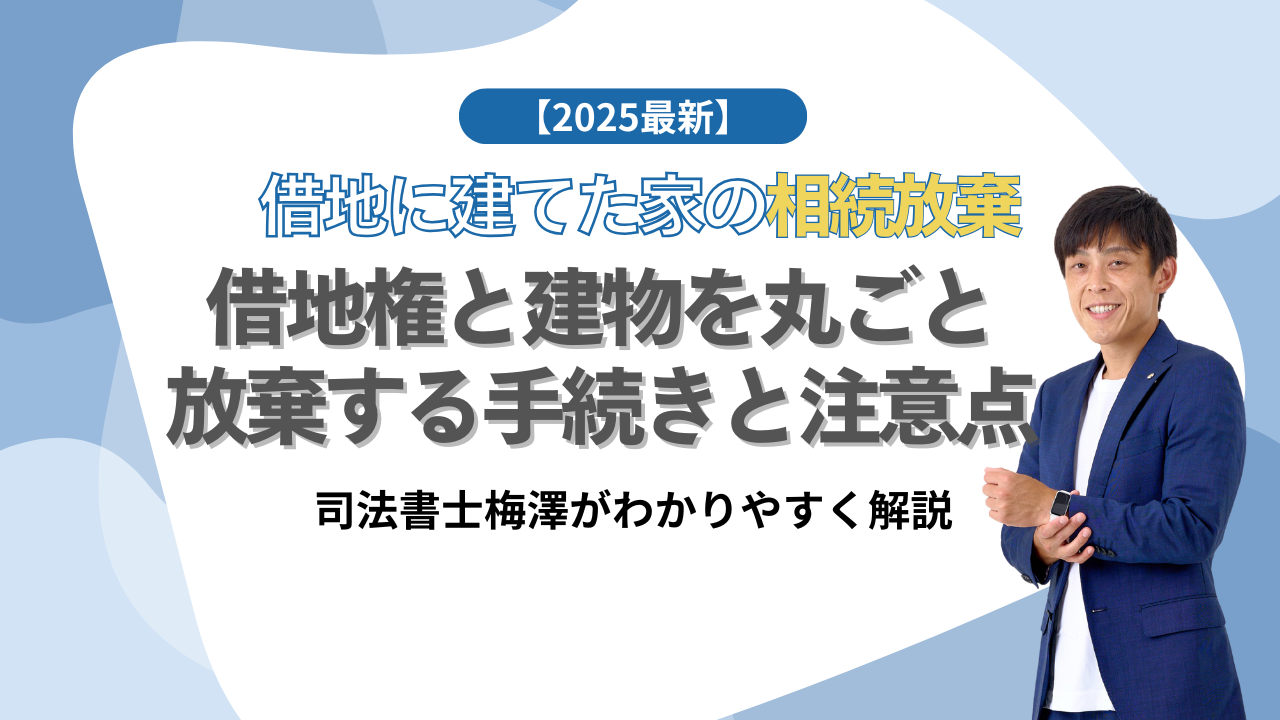この記事を要約すると
- 実家の法定相続人地位は、結婚後も変わらず兄弟間で平等
- 配偶者との利害対立、実家の管理責任、兄弟間の調整など様々な課題がある
- 遺産分割の方法選択、相続税の計算、法的期限の管理などは複雑な為、専門家への相談が推奨
結婚して実家を出ると「もう相続権がないのでは」と不安に思う方もいらっしゃいますが、
実はそんなことはありません。
法律では結婚後も変わらず、実家の相続権が守られています。
この記事を読むことで、結婚による住所変更や姓の変更が相続権に与える影響、
具体的な相続手続きの流れ、そして円滑な相続を実現するための対策方法を詳しく理解できます。
読み終えた頃には、実家の相続について自信を持って対応できるようになるでしょう。
この記事はこんな方におすすめ
- 結婚して実家を離れたが、親の相続について不安に感じている方
- 兄弟姉妹の中で自分だけが家を出ており、相続権があるのか疑問な方
- 配偶者から「実家の相続には関わりたくない」と言われている方
- 実家の跡取りではないが、正当な相続分を知りたい方
実家相続の全体の流れについては以下の記事で解説していますので、参考にしてください。
結婚後の実家相続権の法的根拠3つ
法定相続人の地位は婚姻で変わらない
結婚して姓が変わったり住所が変更されても、
法定相続人※としての地位は一切変わりません。
※法定相続人:法律で定められた相続する権利を持つ人
民法第887条では、子は第1順位の相続人として明確に規定されています。
この法律の「子」には、結婚した子も未婚の子も区別なく含まれます。
参考:民法第887条(子及びその代襲者等の相続権) – e-Gov法令検索
実際の相続現場では、「跡取りの長男以外は相続できない」という誤解が多く見られますが、
これは法的根拠のない思い込みです。
たとえば、3人兄弟の家庭で長女が結婚して県外に住んでいる場合でも、
長女の相続分は長男・次男と同等に保障されています。
民法900条が定める相続分の保障
民法第900条では、同順位の相続人間での相続分を具体的に定めています。
参考:民法第900条(法定相続分) – e-Gov法令検索
子同士の相続分は、性別や婚姻状況、居住地に関係なく平等です。
例えば、両親が亡くなった際の子3人の相続分は以下の通り平等です。
| 相続人 | 相続分 | 備考 |
|---|---|---|
| 長男(実家在住) | 1/3 | 跡取りでも相続分は同じ |
| 次男(結婚して県外在住) | 1/3 | 婚姻・居住地は無関係 |
| 長女(嫁いで姓変更) | 1/3 | 姓の変更は相続分に影響なし |
この法定相続分※は、遺言書がない限り必ず適用される法的な権利です。
遺言書に別途記載があった場合はこの限りではありません。
※法定相続分:民法で定められた各相続人の取り分の割合
相続欠格・相続廃除以外で権利が失われない
相続権を失うケースは、法律で厳格に限定されています。
相続欠格の事由(民法第891条)は以下の5つのみです
- 故意に被相続人や他の相続人を死亡させた場合
- 被相続人が殺害されることを知りながら告発しなかった場合
- 詐欺や強迫で遺言の作成を妨害した場合
- 詐欺や強迫で遺言の取り消しを妨害した場合
- 遺言書を偽造・変造・隠匿した場合
参考:民法第891条(相続人の欠格事由) – e-Gov法令検索
また、相続人の廃除(民法第892条)も、
被相続人に対する重大な侮辱や虐待がある場合に限られます。
参考:民法第892条(推定相続人の廃除) – e-Gov法令検索
単に「実家を出た」「跡取りではない」「親の面倒を見ていない」といった理由では、
相続権は失われません。
FAQ
Q. 結婚で姓が変わったら相続権はなくなる?
A. いいえ、姓の変更は相続権に一切影響しません。
Q. 実家を出たら相続人ではない?
A. 居住地は相続権に関係ありません。法定相続人の地位は変わりません。
Q. 相続権を失う場合とは?
A. 相続欠格や廃除など法律で限定された場合のみです。
嫁いだ娘・婿に出た息子の実家相続権
娘が結婚後も実家の相続分を持つ理由
娘が結婚した場合は、かつては実家の相続が出来ないし、
親子関係に何かしらの変化が生じるという慣習が一部の地域ではあったかもしれません。
しかし、現行の民法では、女性が結婚しても実家との法的な親子関係は継続します。
姓が変わることと相続権は全く別の問題です。
具体的なケースとして、田中家の長女が佐藤家に嫁いだ場合を考えてみましょう。
- 戸籍上:田中花子→佐藤花子(姓の変更)
- 相続権:田中家の相続人として権利継続
- 相続分:他の兄弟と同等(法定相続分)
実際の相続手続きでは、戸籍謄本で親子関係を証明できれば、
姓が変わっていても何の問題もありません。
むしろ最近では、実家の介護や相続に積極的に関わる娘が増えており、
「跡取り娘」として期待される事例も多くなっています。
跡取りでない息子の実家相続権は?
長男以外の息子が結婚して家を出た場合も、相続権は完全に保護されています。
「家督相続制度」は戦後に廃止されており、現在は男女・出生順に関係なく平等相続が原則です。
次男や三男であっても
- 法定相続分は兄弟間で平等
- 遺産分割協議※での発言権あり
- 相続放棄するかどうかは本人の意思
※遺産分割協議:相続人全員で遺産の分け方を話し合うこと
ただし、実家の維持や親の介護負担を考慮して、遺産分割で実家不動産を長男が多く相続し、その代わりに他の財産を次男・三男が相続するケースが一般的ではあります。 実際にどうするかはその家次第と言えます。
これは法的な義務ではなく、あくまで相続人同士の話し合いによる調整です。
配偶者が実家相続に関与できる範囲
配偶者(夫や妻)は、配偶者の実家の相続について直接的な相続権はありません。
しかし、夫婦の財産関係に影響するため、一定の範囲で関与する権利があります
下記にまとめてみました。
| 分類 | 関与できる場面 | 関与できない場面 |
|---|---|---|
| 財産管理 | ・相続した財産の管理方法 ・実家不動産の売却や活用 |
・法定相続分の変更 ・相続放棄の強要 |
| 手続き参加 | ・相続に伴う借金の処理 | ・遺産分割協議への直接参加 |
特に注意すべきは、相続した実家の不動産を売却する際です。
原則、相続で取得した自分名義の居住用不動産は配偶者の同意なく売却可(民法206・762)です。
ただし、例外として共有名義の場合や(被相続人死亡後に)配偶者居住権が設定されているケース、
処分禁止の仮処分がある場合、
または実務上銀行や仲介が同意書を求める場面などがありますので、注意してください。
FAQ
Q. 嫁いだ娘に相続権はある?
A. はい、結婚しても実家の相続権は完全に保護されています。
Q. 跡取りでない息子の相続分は?
A. 兄弟間で平等です。出生順や性別は相続分に影響しません。
Q. 配偶者が相続に関与できる?
A. 直接的な相続権はありませんが財産管理などで一定の関与権があります。
結婚後の実家相続で発生する3つの問題
結婚した後に実家を相続する場合によくある問題を3つに厳選して整理してみました。
配偶者と実家相続の利害対立
まず1つ目です。 結婚後の実家相続では、配偶者との間で利害対立が生じることがあります。
よくある対立パターンは以下のとおりです:
- 配偶者:「実家の相続には関わりたくない」
- 本人:「親の遺産は正当な権利として受け取りたい」
この対立の背景には、相続に伴う責任への不安があります。
本当に大変ですよね。
実家を相続すると、固定資産税の支払いや建物の維持管理が必要になるためです。
解決策としては、事前の話し合いが重要です
- 相続予定の財産内容を配偶者に説明
- 相続後の活用方針を夫婦で検討
- 必要に応じて相続放棄も選択肢として検討
相続は夫婦の将来設計に大きく影響するため、
一方的な判断ではなく夫婦で協力して進めることが大切です。
結婚後の新居と実家、二重の住居負担
そして、結婚して実家を相続する場合、新居と実家の二重の住居負担が大きな問題となることもあります。
結婚後特有の負担
- 現在の住居:住宅ローンや家賃
- 実家:固定資産税、管理費、修繕費
- 配偶者の理解:「なぜ使わない家にお金を払わないといけないの?」
特に結婚したばかりの夫婦や子育て世帯では、この二重負担は家計に深刻な影響を与えます。
結婚後の実家活用パターン
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 週末利用 | ・親との思い出を大切にできる ・配偶者も実家に慣れる |
・交通費がかさむ ・年間維持費が高額 |
| 二世帯住宅化 | ・配偶者も納得しやすい ・将来の住居問題解決 |
・改修費用が高額 ・配偶者の職場との距離 |
| 賃貸収入確保 | ・家計の足しになる ・建物の劣化防止 |
・配偶者が管理業務を嫌がる ・入居者トラブルのストレス |
| 早期売却 | ・二重負担から解放 ・結婚生活に集中できる |
・配偶者が「冷たい」と感じる ・将来後悔する可能性 |
配偶者との将来設計を考慮して、夫婦で納得できる選択をすることが重要です。
結婚した子と実家に残った子の立場の違い
結婚して実家を出た子と、独身で実家に残った子(または結婚後も実家にいる子)との間で、
立場の違いによる感情的な対立が生じることがあります。
これも事前に考えるべき問題の1つです。
家庭裁判所の統計では、令和4年の遺産分割事件(審判+調停)の新受は16,687件。
近年は高止まりの傾向です。 原因の1つに、兄弟姉妹間での感情的な対立があるとも考えられています。
結婚後特有の対立パターン
- 実家に残った兄弟:「結婚して出て行ったのに相続だけは主張するのか」
- 結婚して出た本人:「実家にいるからといって多く相続するのは不公平」
- 配偶者の影響:「配偶者にそそのかされて強欲になった」
- 経済格差:「結婚して生活が苦しいから実家の財産に頼ろうとしている」
特に親の介護を実家に残った兄弟が一手に担っていた場合、感情的な溝は深くなります。
結婚した子が気をつけるべきポイント
- 感謝の気持ちを示す:実家に残った兄弟への介護負担に対する感謝
- 配偶者の理解を得る:配偶者が相続争いに巻き込まれないよう事前説明
- 建設的な提案:単に「権利を主張」するのではなく、みんなが納得できる解決策を提案
- 法的制度の活用:寄与分※や代償分割※で実質的な公平を図る
※寄与分:被相続人の財産維持や増加に特別の貢献をした相続人の加算分
※代償分割:特定の相続人が多く相続する代わりに他の相続人に金銭を支払う方法
結婚後も家族の絆を大切にし、相互理解に努めることが円満な相続の鍵となります。
あくまで、このような問題には感情も大きな要因ですので、
文学的なアドバイスのように聞こえるかもしれないですが、他者の理解や感謝の言葉なども実際に重要な要素です。
税務上の影響や法的リスクも含めて、個別具体的に回答が異なるため、まずは無料相談をお申し込みください。
FAQ
Q. 配偶者との相続対立を避ける方法は?
A. 事前の話し合いで相続内容と活用方針を夫婦で共有することです。
Q. 結婚後の実家維持費が家計を圧迫する?
A. 二世帯住宅化、賃貸活用、売却など配偶者と相談して決めましょう。
Q. 実家に残った兄弟との対立を避けるには?
A. 感謝の気持ちを示し、配偶者も含めて事前に話し合うことです。
まとめ
結婚すると実家の相続権を失う?と誤認している方もいらっしゃるかとは思いますが、
実際には、結婚して実家を出た子でも、法定相続人としての権利は完全に保護されています。
姓の変更や住所の移転は、相続権に何の影響も与えません。
最後に重要なポイントをまとめると下記の5点です。
- 法定相続分は兄弟間で平等(婚姻状況無関係)
- 相続欠格・廃除以外で権利を失うことはない
- 配偶者の理解と協力が円滑な相続の鍵
- 実家の管理方法は4つの選択肢から検討
- 兄弟間の不公平感は法的制度で調整可能
ただし、実際の相続では配偶者との利害対立、実家の管理責任、兄弟間の調整など様々な課題が生じます。
これらの問題は法律の専門知識が必要で、一般の方が独力で解決するのは困難です。
特に遺産分割の方法選択、相続税の計算、法的期限の管理などは、個別具体的に最適解が異なります。
間違った判断をしてしまうと、後で取り返しのつかない問題に発展する可能性もあります。
相続に関する疑問や不安を抱えている方は、まずは専門家にご相談ください。
無料相談では、あなたの状況に合わせた具体的なアドバイスを受けることができます。
早めの準備で、あなたの正当な相続権を確実に守りましょう。
この記事の監修者

遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。