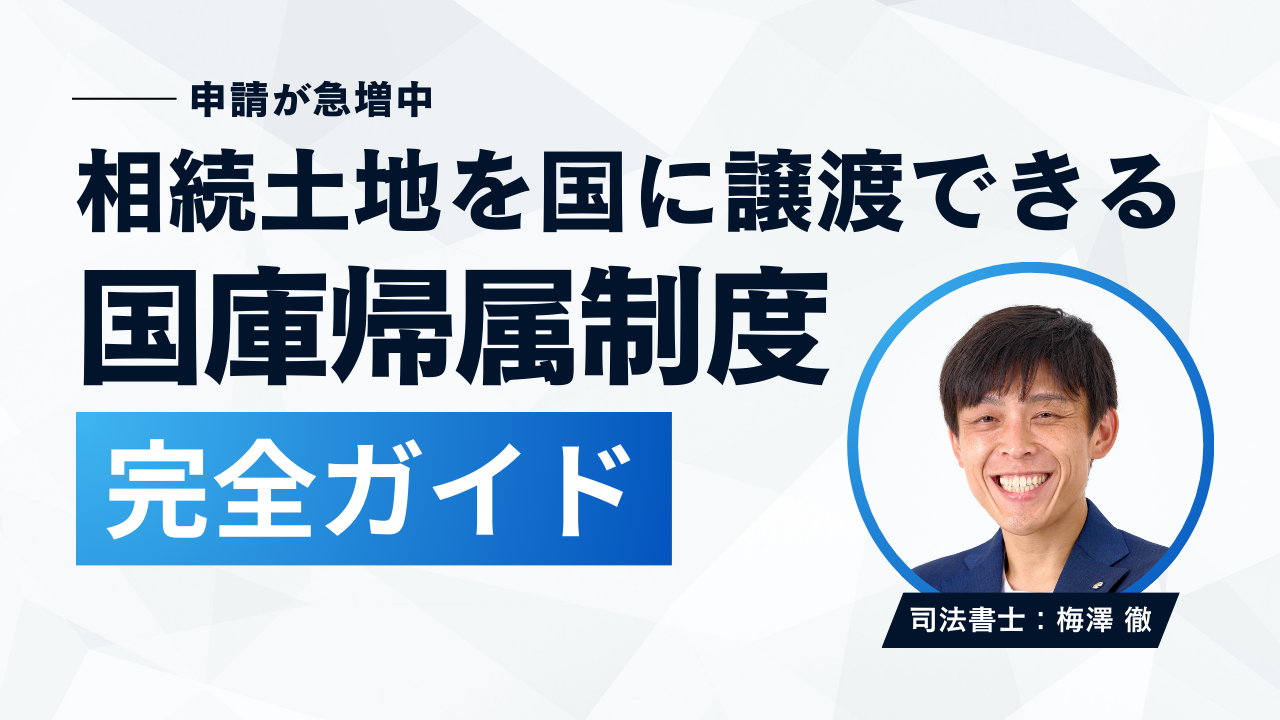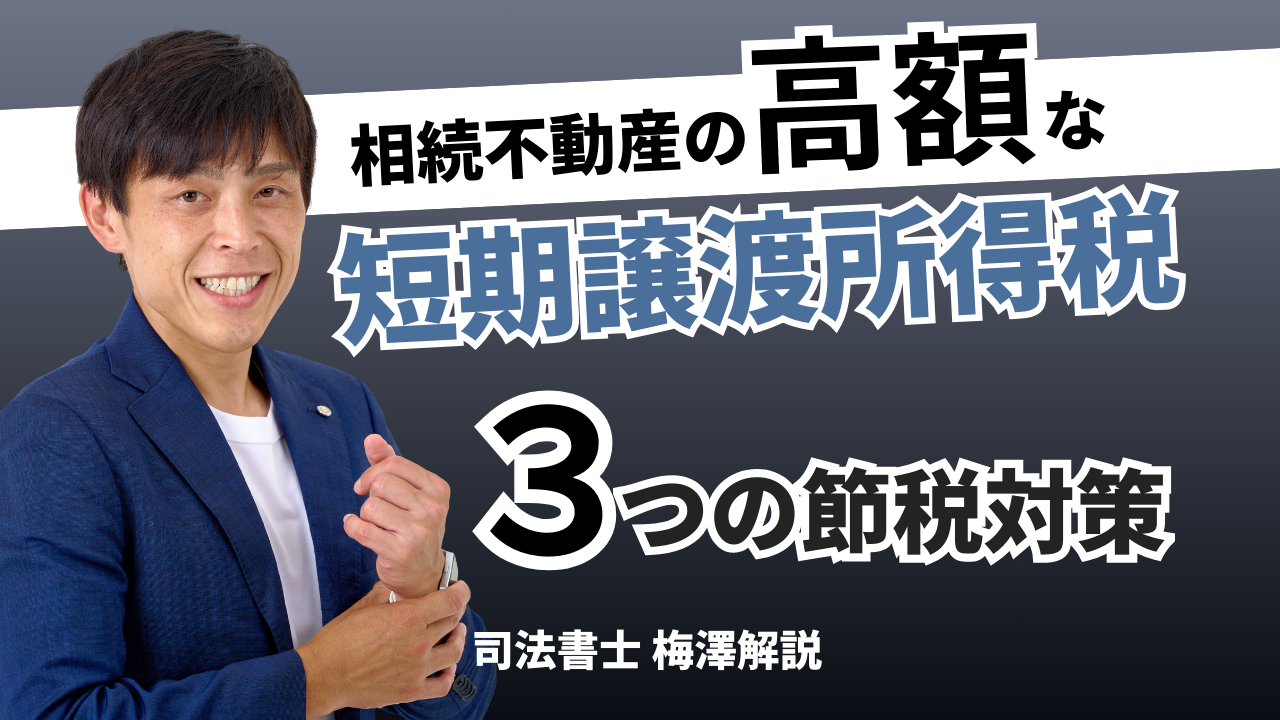この記事を要約すると
- 親から相続した家を売却する際、減価償却を知っておかないと数百万円もの税金を損する可能性があります
- 正しい税金計算では親が家を購入した時の価格から減価償却を適用し、特に木造住宅や居住用物件は大きな節税効果が期待できます
- 親の購入時の契約書確認や建物構造の把握が重要で、専門家への相談が不要な税金支払いを避ける鍵となります
親から相続した家を売却する際、「相続時の評価額で計算すればいい」と思っていませんか?実は、この考え方で税金を計算すると、本来払う必要のない数百万円もの税金を支払うことになってしまいます。
正しくは、親が家を購入した時の価格から「減価償却」を計算することで、大幅な節税が可能になります。
実際に当事務所でサポートした田名さん(仮名)は、この方法で本来なら100万円かかるはずだった税金を0円にすることができました。
同じような条件でも、知識があるかないかで300万円もの差が生まれるケースも珍しくありません。
この記事では、減価償却の仕組みから具体的な計算方法、建物の構造別の節税効果まで、実際の事例を交えながら詳しく解説します。
木造住宅なら築20年で1,000万円以上、マンションでも数百万円の節税効果が期待できる理由も明らかになります。
記事を読み終える頃には、あなたの相続した家でどれだけの節税効果が見込めるかが分かり、税務署に余計な税金を払わずに済む正しい手続きの進め方が身につきます。
親の家を売って大損した人、節税できた人の違いとは一体なんなのでしょうか?一緒に見ていきましょう。
この記事はこんな方におすすめ
- 親から相続した家の売却を検討している40代以上の方
- 不動産売却時の税金について心配な方
- 会計の知識はないが損はしたくない方
- 実際の事例を通して学びたい方
親から相続した家を売却する時、多くの方が「減価償却」という仕組みを知らずに高額な税金を支払っています。
実際に、同じような条件の家を売却したにも関わらず、一方は300万円の税金、もう一方は50万円の税金という大きな差が生まれたケースがあります。
この差を生むのが「減価償却」という計算方法です。難しそうに聞こえますが、要は「建物は年月が経つと価値が下がる」という考え方で、この仕組みを理解しているかどうかで税金が大きく変わります。
相続した不動産を売却して利益が出た場合、その利益に対して「譲渡所得税」という税金がかかります。この利益の計算で重要になるのが減価償却です。
親から受け継いだ家を売る時の「見えない税金の罠」
多くの人が間違える「家の価値は今の相場で計算」の勘違い
「親から相続した家だから、相続時の価値で計算すればいい」
税金の計算なんて普段考えませんから、そう思うのは当然ですよね。実際に、このように考えている方はとても多いです。
しかし実際には、相続した不動産の譲渡所得税の正しい計算方法は親が、家を購入した時の価格から計算する必要があります。
実際に、国税庁の統計によると、相続財産に占める不動産の割合は約38%となっており、
多くの方が不動産の相続税計算で悩んでいる現状があります。
出典:令和4年分の相続税の申告状況について – 国税庁(2023年12月)
例えば、田中さん(仮名)のケースを見てみましょう。
田中さんの事例
- 不動産の詳細:親が30年前に3,000万円で購入した木造住宅
- 相続時の評価額:1,500万円
- 売却価格:2,000万円
多くの人は「1,500万円で相続したから、2,000万円で売れば500万円の利益」と考えがちです。普通はそう思いますよね、わかります。
しかし、実際の計算では親が購入した3,000万円から始まります。どちらの計算方法が得なのでしょうか?
実は、田中さんの場合、正しい計算方法の方が圧倒的に有利になります。
- 間違った計算: 2,000万円 – 1,500万円 = 500万円の利益
- 正しい計算: 2,000万円 – 3,000万円 = 1,000万円の損失
正しい計算では損失が出ているため、税金は一切かかりません。一方、間違った計算では500万円に対して約100万円の税金がかかってしまいます。
つまり、正しい知識があるだけで約100万円もの税金を節約できるのです。
親が昔買った時の価格で税金が決まる意外なルール
では、なぜ親が購入した時の価格が重要になるのでしょうか。これには相続税法の特別なルールがあります。
相続した不動産の税金計算では、被相続人(※亡くなった親)が取得した価格を引き継ぐというルールがあります。
これは「取得費の引き継ぎ(※不動産を購入した時にかかった費用を相続人が受け継ぐこと)」と呼ばれる制度で、相続税法で決められています。
つまり、あなたが相続したタイミングではなく、親が購入したタイミングが計算の基準になるのです。
ただし、単純に物件購入時の金額を引くだけではないです。他にも考慮するべきポイントがあります。あなたの親が家を購入したのは何年前でしょうか?
30年前、40年前という方も多いのではないでしょうか。
実はこの購入時期によっても、減価償却の効果は大きく変わってきます。
なぜなら、総務省の住宅・土地統計調査によると、現在の住宅ストックの約3割が築30年以上の建物となっており、多くの方が築年数の古い家を相続している状況だからです。
築年数が古いほど、減価償却による税額軽減効果も大きくなります。これは売る側にとって大きなメリットです。
築年数が古い建物ほど、減価償却で差し引ける金額が大きくなり、結果として課税対象となる利益が少なくなります。
つまり、古い家ほど税金が安くなるのです。
例えば、築10年の家と築40年の家では、同じ売却価格でも数百万円の税額差が生まれることも珍しくありません。
親が購入した時の契約書が見つからない場合は、売却価格の5%を取得費として計算する概算法(※正確な購入価格が分からない時の簡易計算方法)もありますが、多くの場合、不利になります。古い書類を探すのは本当に大変ですが、見つけるかどうかで税額が大きく変わるので頑張って探してみてください。
住んでいた家と貸していた家で税金が10倍変わる現実
減価償却による税額軽減効果は、建物の築年数だけでなく、
その「使い方」によっても大きく変わります。居住用物件なのか事業用なのかの違いです。
| 分類 | 概要 | メリット | デメリット |
| 住んでいた家(居住用) | ・売却時に減価償却を計算 ・法定耐用年数の1.5倍適用 |
・減価償却効果が大きい ・建物価格の90%まで適用 |
・計算が複雑 ・契約書などの書類が必要 |
| 貸していた家(事業用) | ・毎年確定申告で計上済み ・通常の法定耐用年数適用 |
・毎年の節税効果あり ・計算が明確 |
・売却時の効果は限定的 ・既に減価償却済み |
同じ家でも、親が住んでいた家と人に貸していた家では、減価償却の計算方法が大きく異なります。
住んでいた家(居住用)の場合
- 売却時にのみ減価償却(※建物の価値が年数とともに減っていく分の計算)を計算
- 法定耐用年数(※税法で決められた建物の使用可能年数)の1.5倍で計算
- 建物価格の90%まで減価償却可能
貸していた家(事業用)の場合
- 毎年確定申告で減価償却を計上済み
- 通常の法定耐用年数で計算
- 既に減価償却済みの分は控除済み
この違いにより、同じ築年数でも税金が大きく変わることがあります。
特に、親が長年住んでいた実家を売却する場合は、大きな節税効果を期待できることが多いのです。
司法書士からのアドバイス
相続した不動産の売却に伴う減価償却の計算は、建物の使用用途や取得時期により複雑になり、個別具体的に回答が異なります。税務上の特例適用や適切な手続きを行うためにも、まずは無料相談をお申し込みください。
FAQ
ここまでの内容を元に質問形式で整理しました。
内容の理解チェックや確認にご活用ください。
Q. 不動産相続における減価償却とは何ですか?
A. 建物の価値が年数とともに減っていく分を計算する税務上の仕組みです。
Q. 親の購入価格が分からない場合は?
A. 売却価格の5%を概算法で計算しますが多くの場合不利になります。
Q. 居住用と事業用で相続時の税金に違いはある?
A. 計算方法が異なり居住用の方が減価償却の効果が大きくなります。
家の造りと古さで決まる「税金の重さ」
| 構造 | 法定耐用年数 | 償却率 | メリット |
| 木造 | 22年(33年) | ・減価償却効果が最大 ・早期に価値減少を計上 |
・実際の建物劣化が早い ・維持管理費がかかる |
| 鉄骨造 | 27年(40年) | ・木造より耐久性が高い ・適度な減価償却効果 |
・建築コストが高い ・税制効果は中程度 |
| 鉄筋コンクリート | 47年(70年) | ・建物の耐久性が最高 ・長期間価値を維持 |
・減価償却効果が限定的 ・売却時の節税効果小 |
※()内は居住用の1.5倍適用後の年数 居住用は年数が長くなるため、償却率が下がり減価償却効果も小さくなります。
木造の実家:築20年で1,200万円も税金が安くなった話
佐藤さん(仮名)は親から相続した築20年の木造住宅を売却しました。建物の購入価格は2,000万円でした。
「木造だから古くて価値がないかも…」そんな風に思われる方も多いですが、
実は税制上はとても有利なんです。
佐藤さんも最初は心配されていましたが、計算結果を見て安心されました。
実際に計算してみましょう。
減価償却の計算
- 木造住宅の法定耐用年数(※税法で決められた建物の使用可能年数):22年
- 居住用なので1.5倍:33年
- 償却率(※1年間で減らす価値の割合):0.031
- 経過年数:20年
減価償却費 = 2,000万円 × 0.9 × 0.031 × 20年 = 1,116万円
この計算により、建物の取得費は約884万円(2,000万円 – 1,116万円)となり、1,116万円分も税金の対象から外れました。
つまり、佐藤さんは木造住宅という構造のおかげで、大幅な節税効果を得ることができたのです。
マンション:築40年でも800万円しか安くならない理由
一方、鈴木さん(仮名)が相続した築40年のマンションは、同じ2,000万円で購入されていましたが、減価償却の効果は限定的でした。
「えっ、40年も経っているのに木造より効果が少ないの?」と驚かれる方が本当に多いんです。
同じように疑問に思われた鈴木さんも、最初は納得がいかない様子でした。
では、なぜこのような違いが生まれるのでしょうか。実際の計算を見てみましょう。
鉄筋コンクリート造マンションの場合
- 法定耐用年数:47年
- 居住用なので1.5倍:70年
- 償却率:0.015
- 経過年数:40年
減価償却費 = 2,000万円 × 0.9 × 0.015 × 40年 = 1,080万円
木造住宅とほぼ同じ金額ですが、ここに注目してください。
築20年の木造住宅と築40年のマンションの減価償却費がほぼ同じ! ということです。
- 木造住宅(築20年):1,116万円の減価償却費
- マンション(築40年):1,080万円の減価償却費
つまり、築年数が2倍も違うのに、減価償却の効果はほとんど変わらないのです。
これは構造が頑丈なマンションほど、税法上の価値の減り方が遅く設定されているためです。
このように、鉄筋コンクリート造は「建物としては長持ちするが、税制上の恩恵は限定的」という特徴があります。
実際に、国土交通省の住宅着工統計によると、新築住宅のうち木造住宅が約57%、鉄筋コンクリート造が約11%となっており、多くの方が木造住宅を相続する状況にあります。
つまり、税制上有利な構造の家を相続している方が多いということです。
店舗付き住宅:商売部分のおかげで年180万円節税できた事例
これまでは純粋な住宅の事例でしたが、中には店舗と住宅が一体になった建物を相続される方もいらっしゃいます。
山田さん(仮名)が相続した店舗兼住宅は、1階が店舗、2階が住宅という造りでした。
建物価格3,000万円のうち、店舗部分が1,800万円、住宅部分が1,200万円でした。
店舗部分(事業用)の特徴
- 毎年確定申告で減価償却を計上可能
- 年間の節税効果:約180万円
- 売却時には累積した減価償却費(※これまでに計上した減価償却の合計額)を控除
このように、事業用部分がある不動産は、毎年の所得税軽減効果も大きく、相続した方にとって有利な面があります。
ところで、あなたが相続した家はどのような構造でしょうか?木造、鉄骨造、それとも鉄筋コンクリート造でしょうか。
上記で説明した通り、この構造の違いだけで減価償却の効果が大きく変わってくるため、まずは建物の構造を確認することが重要です。
| 構造 | 法定耐用年数 | 居住用(1.5倍) | 償却率 |
| 木造 | 22年 | 33年 | 0.031 |
| 鉄骨造 | 27年 | 40年 | 0.025 |
| 鉄筋コンクリート | 47年 | 70年 | 0.015 |
参考:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 – e-Gov法令検索
司法書士からのアドバイス
建物構造による減価償却の計算や税務上の特例適用は、建築年度や用途により複雑になり、個別具体的に回答が異なります。正確な節税効果を確認し適切な手続きを行うためにも、まずは無料相談をお申し込みください。
FAQ
Q. 木造とマンションでは相続する際の税金に違いはある?
A. 木造の方が減価償却効果が大きく税額軽減につながりやすいです。相続するなら基本的には木造のほうが税制上はお得と覚えておきましょう。
Q. 築年数が古いと税金は安くなる?
A. はい。築年数が古いほど減価償却費が多くなり税金が安くなります。
Q. 建物の構造はどこで分かる?
A. 登記簿謄本や建築確認申請書で構造を確認できます。
まとめ
親から相続した家の売却で大損しないためには、減価償却の仕組みを理解することが重要です。
知識の有無で数百万円の税額差が生まれる現実があります。繰り返しになりますが、今すぐ確認すべき3つのポイントです。
- まず、親の購入時の契約書を探しましょう。
- 次に、建物構造を確認してください。木造住宅なら減価償却効果が最も大きくなります。
- 最後に、親が住んでいた家か貸していた家かを整理しましょう。
ただし、減価償却の計算は複雑で個別判断が必要です。大切な財産を守るため、専門家の診断をお勧めします。
分からないことを分からないままで手続きをすると知らないうちに損をすることになってしまうかも知れません。
当事務所では相続不動産の売却に関する無料相談を実施していますので、困ったことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
この記事の監修者

遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。

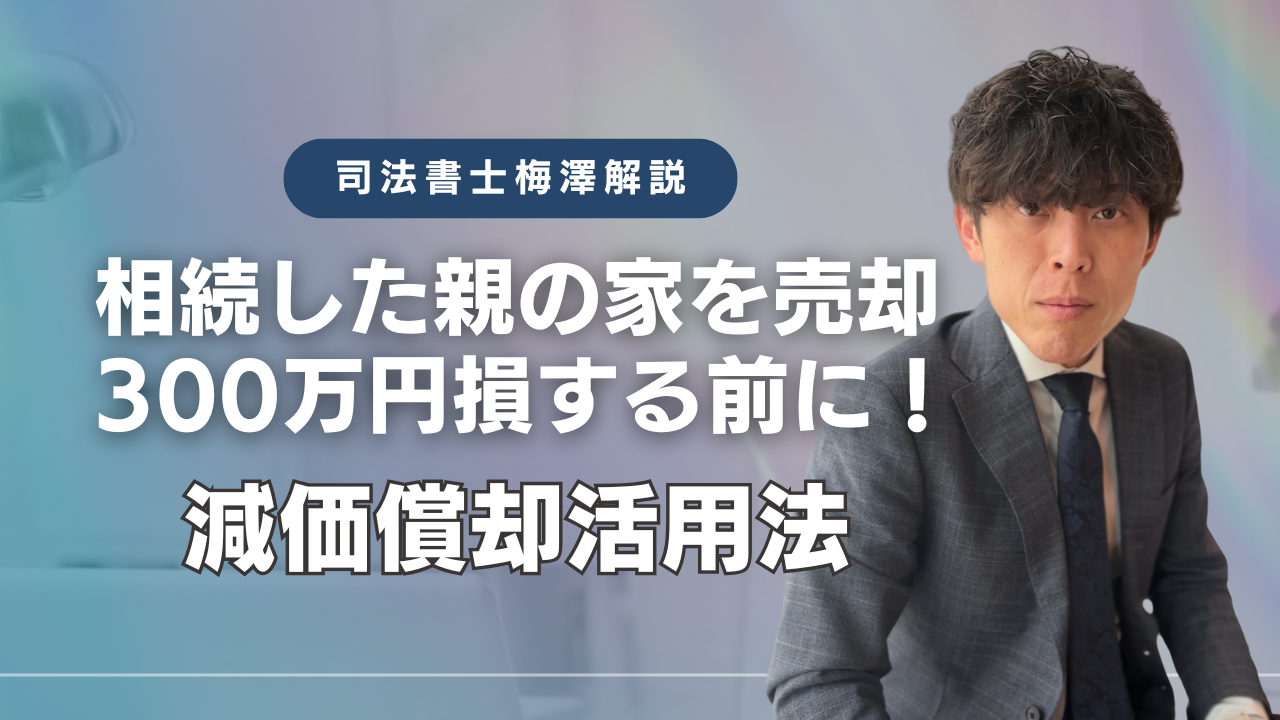




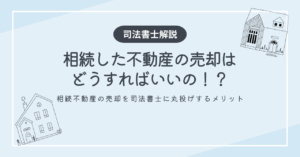
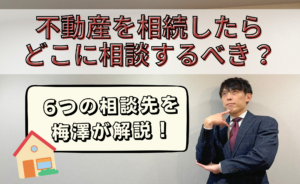
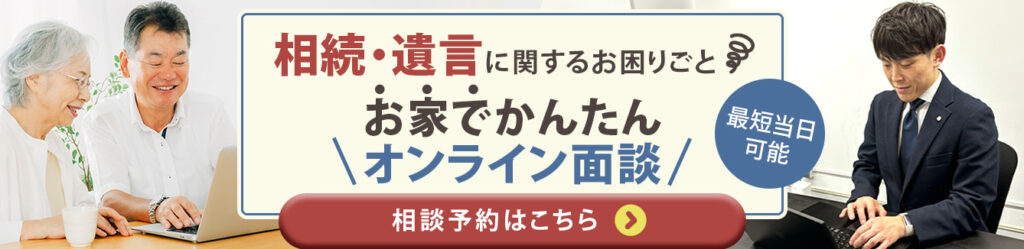


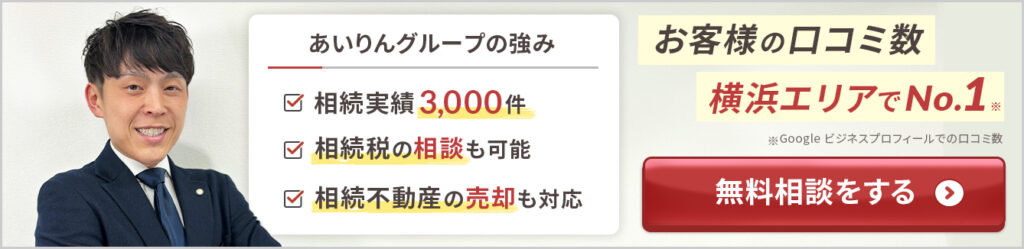

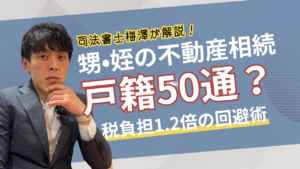
相続を現金化で解決-300x169.png)