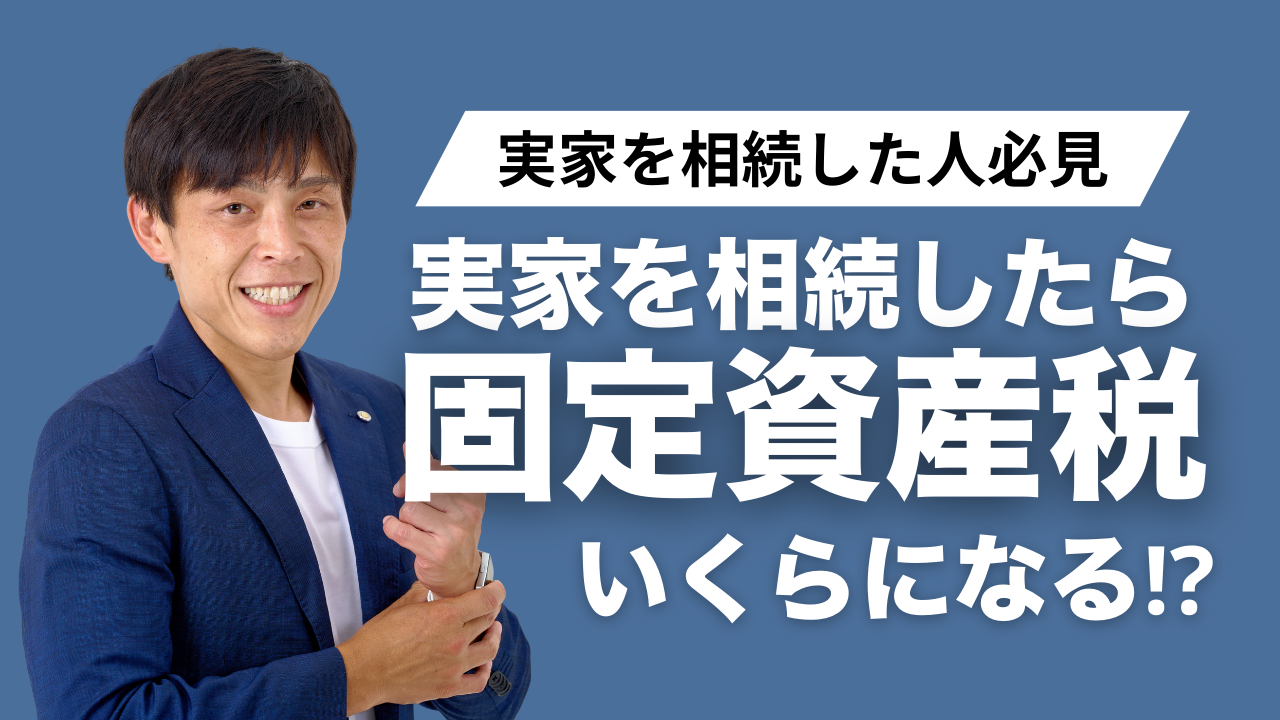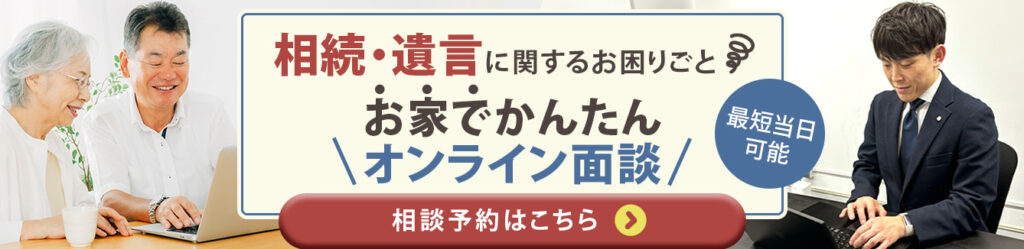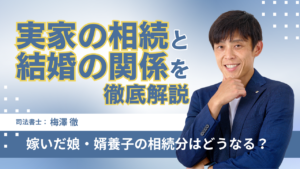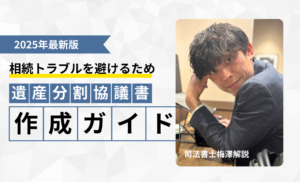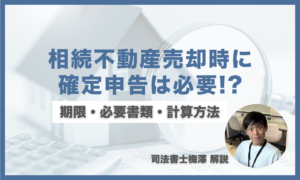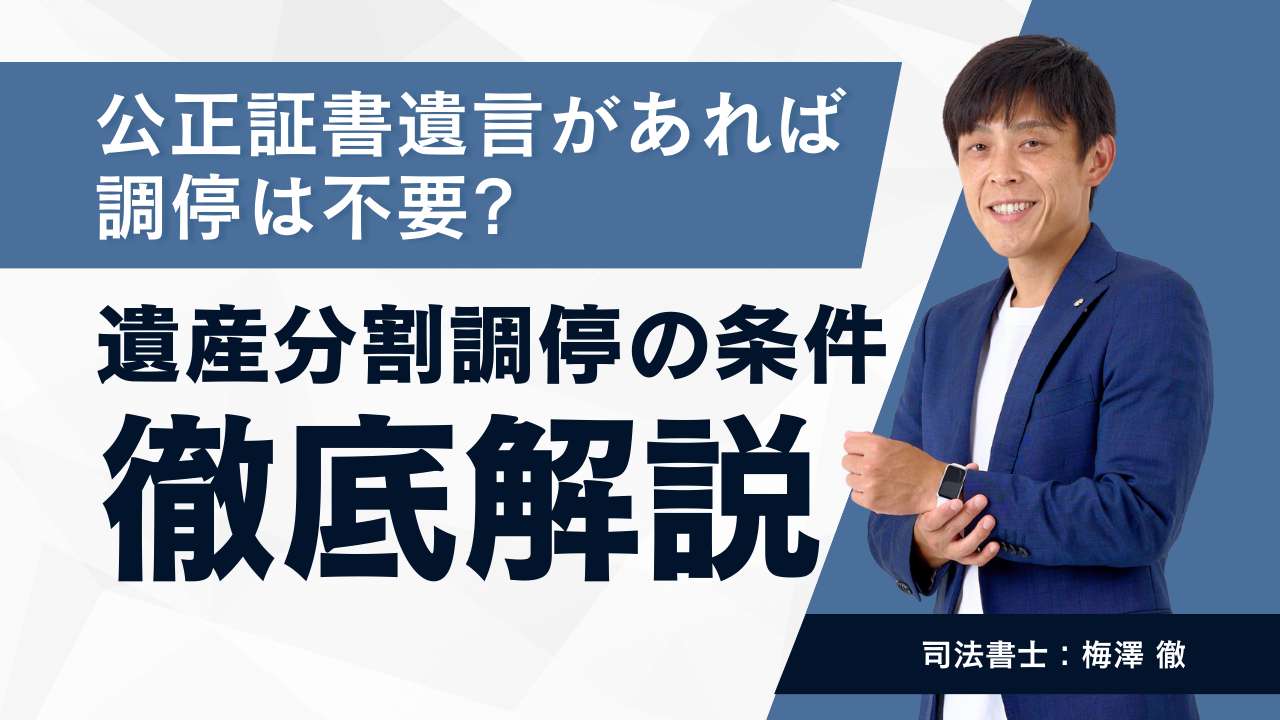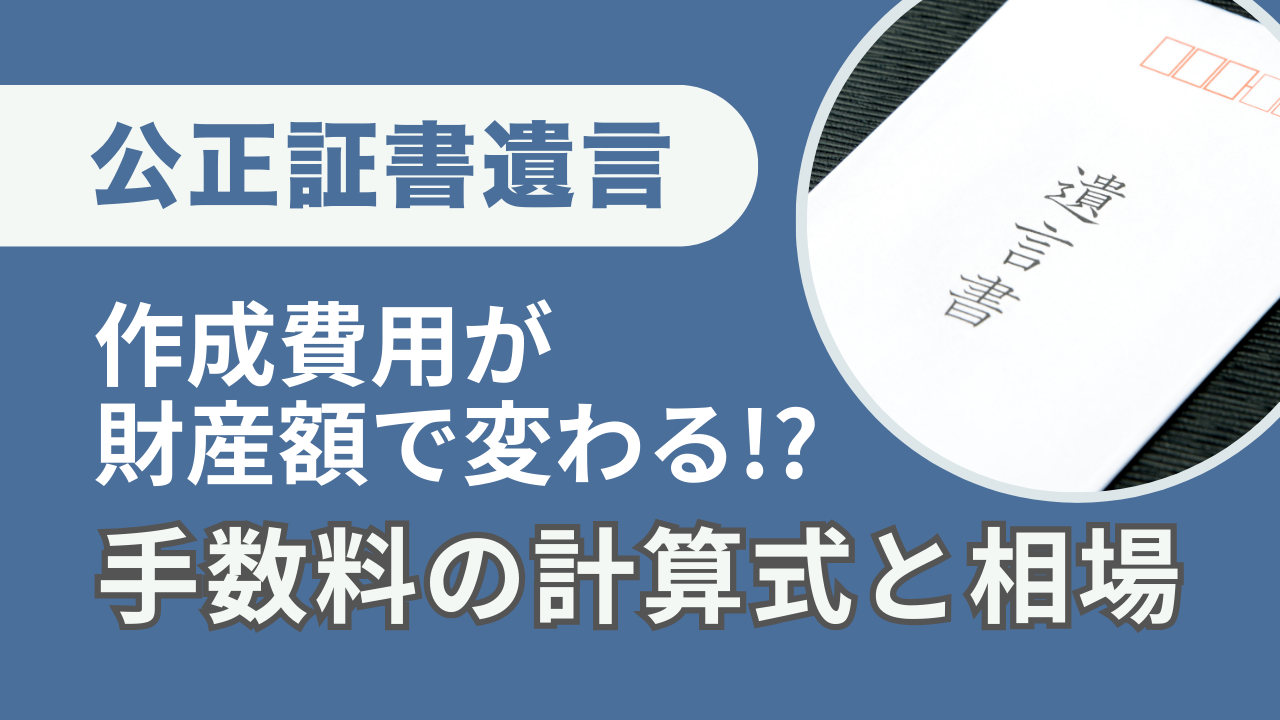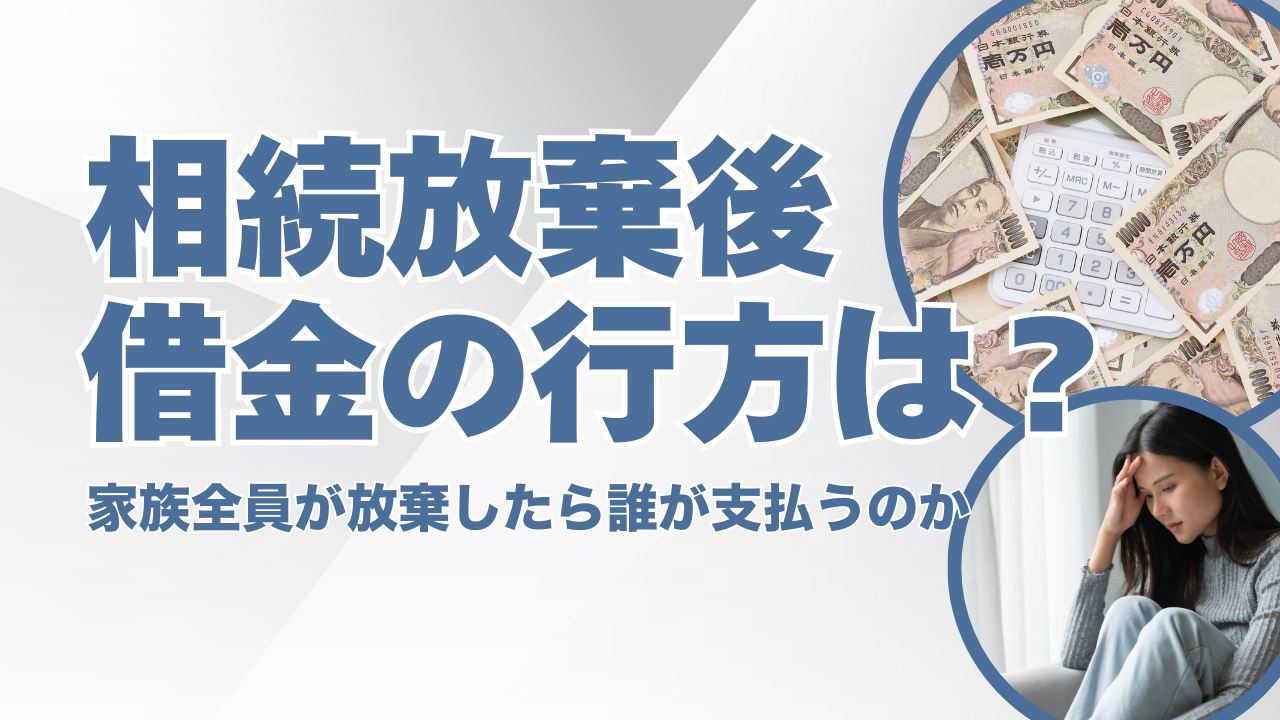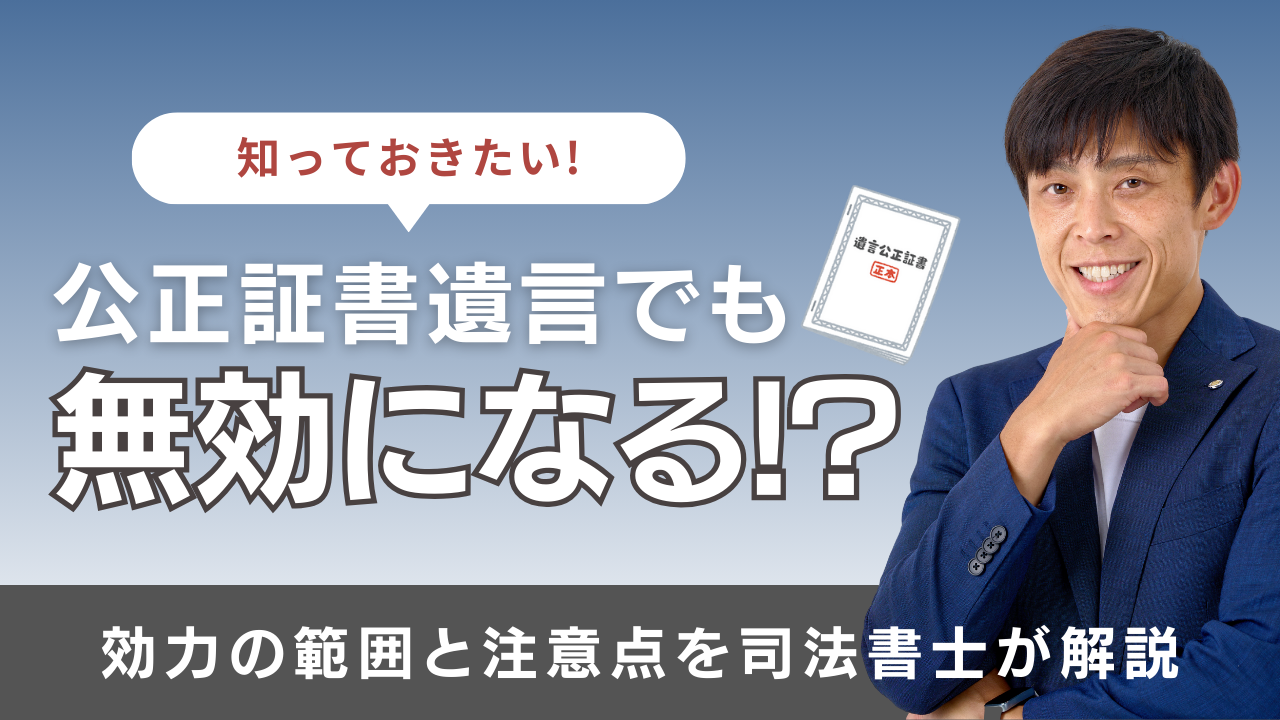この記事を要約すると
- 実家の固定資産税は居住用で6分の1、非居住用で満額課税となる
- 住宅用地特例や小規模宅地特例で大幅な税負担軽減が可能である
- 保有・売却・活用の判断は10年間のコストと収益で総合的に決める
親から実家を相続すると、毎年発生する固定資産税の負担が気になりますよね。
「一体いくらかかるの?」「税金を安くする方法はないの?」といった不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。そのお気持ち、本当によくわかります。
この記事では、実家相続における固定資産税の計算方法から、
具体的な軽減措置、そして実家を保有するか売却するかの判断基準まで、専門的な内容をわかりやすく解説します。
記事を読み終えた頃には、固定資産税の仕組みを理解し、
ご自身の状況に最適な節税対策を選択できるようになります。
この記事はこんな方におすすめ
- 実家を相続して固定資産税の負担が心配な方
- 固定資産税の具体的な計算方法を知りたい方
- 実家の税金負担を少しでも軽減したい方
- 実家を売却するか保有するかで迷っている方
実家相続の全体の流れについては以下の記事で解説していますので、参考にしてください。
目次
実家相続で固定資産税はいくらかかる?基本の計算方法を解説
実家を相続した際の固定資産税は、土地と建物それぞれの評価額に基づいて計算されます。
まずは基本的な仕組みを理解しましょう。
固定資産税の計算式と評価額の確認方法
固定資産税の計算式は以下の通りです。
固定資産税額 = 固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)
参考:固定資産税 – 総務省
固定資産税評価額(※市町村が決定する土地・建物の税務上の価値)は、
市町村が3年ごとに見直しを行い、実勢価格の約70%程度に設定されています。
評価額の確認は、毎年4月頃に送付される「固定資産税納税通知書」で行えます。
実勢価格とは、実際に取引が成立した価格のことでいわゆる売値です。
相続した実家の評価額がわからない場合は、市役所の固定資産税課で
「固定資産評価証明書」を取得できます。
手数料は300円程度で、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)が必要です。
居住用と非居住用で変わる税額の違い
実家の固定資産税は、居住の有無によって大きく異なります。
理由としては固定資産税は、人が住む家屋が建つ土地(住宅用地)に税額を大幅に軽減する「住宅用地の特例」があるからです。
この特例は、国民の居住安定を図る目的と、
土地の有効活用を促す目的から設けられた国の政策的優遇措置です。
居住用の場合(住宅用地特例適用)
- 200㎡以下の部分:評価額が6分の1に軽減
- 200㎡超の部分:評価額が3分の1に軽減
非居住用の場合(空き家など)
- 軽減措置なし:評価額の満額で課税
- 管理不全の空き家は「特定空き家」に指定される可能性あり
例えば、150㎡の土地で評価額が1,200万円の場合、
居住用なら年間2.8万円、非居住用なら年間16.8万円と、6倍もの差が生じます。
実際の負担額をシミュレーション【具体例付き】
「実際にいくらぐらいになるのか、具体的な数字で知りたい」という方も多いでしょう。
そこで、よくある実家のケースを例に、実際の固定資産税がどれくらいかかるか計算してみました。
【事例】築25年の一戸建て実家
- 土地:200㎡、評価額1,500万円
- 建物:評価額500万円
- 所在地:東京都郊外
居住している場合の年間固定資産税
- 土地:1,500万円 ÷ 6 × 1.4% = 3.5万円
- 建物:500万円 × 1.4% = 7万円
- 合計:10.5万円
空き家の場合の年間固定資産税
- 土地:1,500万円 × 1.4% = 21万円
- 建物:500万円 × 1.4% = 7万円
- 合計:28万円
これを見ると驚きませんか?同じ実家でも、住んでいるか空き家にしているかで、年間17.5万円もの差が出てしまうのです。
10年続けば175万円にもなりますから、見過ごせない金額ですよね。
特に住宅用地特例の適用要件は複雑で、個別具体的に回答が異なるため、まずは無料相談をお申し込みください。
FAQ
Q. 固定資産税の計算式は?
A. 固定資産税評価額×1.4%で計算されます。
Q. 居住用と空き家の税額差は?
A. 住宅用地特例により最大6倍の差が生じます。
Q. 評価額の確認方法は?
A. 固定資産税納税通知書または評価証明書で確認できます。
実家の固定資産税を安くする主要な軽減措置と特例制度
ここまでの計算例をご覧になって、固定資産税の負担の大きさを実感された方も多いのではないでしょうか。
しかし、実は固定資産税には複数の軽減措置や特例制度が設けられており、
これらを適切に活用することで税負担を大幅に軽減することが可能です。
特に実家の相続では、住宅用地特例や小規模宅地特例など、有効な制度が複数用意されています。
これらの制度を理解し活用することで、年間数十万円の節税効果を得ることも珍しくありません。
どのような制度があるのか、具体的な適用条件とともに詳しく解説していきます。
住宅用地特例で6分の1に軽減する条件
住宅用地特例(※住宅が建っている土地の固定資産税を軽減する制度)は、
固定資産税を大幅に軽減できる最も重要な制度です。
適用条件
- 居住の用に供する家屋が建っていること
- 毎年1月1日時点で住宅として使用されていること
- 別荘や一時的な居住は対象外
軽減率
- 小規模住宅用地(200㎡以下):課税標準額が6分の1
- 一般住宅用地(200㎡超):課税標準額が3分の1
注意すべきは、家屋を取り壊すと住宅用地特例が適用されなくなることです。
「古い建物だから壊そうかな」と思われるお気持ちもわかりますが、
築年数が古く使用しない建物でも、税額軽減のため残しておく方が有利な場合があります。
小規模宅地特例の相続税軽減効果
相続税の負担軽減を考える際に、ぜひ知っておいていただきたいのが小規模宅地特例です。
固定資産税の制度ではありませんが、実家相続では非常に大きな節税効果を発揮する重要な制度となっています。
特定居住用宅地等の要件
- 面積:330㎡まで
- 軽減率:評価額の80%減額
- 要件:被相続人の居住用宅地で、配偶者または同居親族が取得する場合
例えば、評価額6,000万円の土地の場合、特例適用により1,200万円まで圧縮され、相続税を大幅に軽減できます。
最高裁判所の司法統計によると、遺産分割事件の約40%が不動産に関するものとなっており、実家相続では適切な手続きが重要です。
ただし、この特例を受けるには相続から10か月以内の申告が必要です。
空き家特措法適用前に知るべき増税リスク
管理不全の空き家は「特定空き家」(※倒壊の危険や衛生上の問題がある空き家)に指定され、住宅用地特例から除外される可能性があります。
特定空き家の判定基準
- 倒壊等の危険性がある状態
- 衛生上有害となる恐れがある状態
- 適切な管理が行われていない状態
- 景観を損なっている状態
特定空き家に指定されると、固定資産税が最大6倍に増額されます。
総務省の調査によると、全国の空き家率は13.6%となっており、相続による空き家の増加が社会問題となっています。
定期的な管理や清掃、必要に応じた修繕を行い、指定を回避することが重要です。
FAQ
Q. 住宅用地特例の条件は?
A. 住宅が建っており1月1日時点で居住用であることが必要です。
Q. 小規模宅地特例の効果は?
A. 相続税評価額を最大80%減額できます。
Q. 特定空き家のリスクは?
A. 住宅用地特例が除外され固定資産税が6倍に増額されます。
実家を残すか売るかの判断基準と節税の最適タイミング
実家の処分方法は、税負担と活用価値を総合的に判断して決定しましょう。
あなたの実家は、どのような状況にありますか?
立地や建物の状態を踏まえて考えてみましょう。
10年間の固定資産税累計額と維持費の総合比較
実家を相続したものの、「このまま持ち続けるべきか、それとも売却した方がいいのか」と迷う方は少なくありません。
家を売る機会はそう多くはありません。
だからこそ、相続した時が一番の決断のタイミングです。
なんとなく持ち続けるのではなく、売却するか、明確な理由をもって保有するかを、
この機会に決めることをお勧めします。
判断の材料として最も重要なのは、長期的なコストを把握することです。
実家を保有し続けた場合、固定資産税だけでなく、管理費用や保険料なども継続的に発生します。
まずは10年間でトータルでどのくらいの費用がかかるのか、具体的に試算してみましょう。
【保有コスト例】
- 固定資産税:年間15万円 × 10年 = 150万円
- 管理費(掃除・修繕等):年間20万円 × 10年 = 200万円
- 火災保険:年間5万円 × 10年 = 50万円
- 10年間の総費用:400万円
一方、売却した場合は初期費用(仲介手数料等)が発生しますが、継続的な維持費用は不要です。
実家の資産価値と維持費用を比較し、どちらが有利かを検討することが大切です。
相続から3年以内の売却で使える特別控除
相続した実家を売却する際は、3年以内であれば特別控除が適用できる場合があります。
被相続人の居住用財産の特別控除
- 控除額:最大3,000万円
- 適用期間:相続開始から3年を経過する年の12月31日まで
- 要件:昭和56年5月31日以前に建築された家屋など
この特例により、譲渡所得税を大幅に軽減できます。
ただし、適用には細かい要件があるため、専門家への相談をおすすめします。
実家活用で固定資産税を収益でカバーする方法
実家を活用して収益を得る方法もあります。
| 活用方法 | 月額収入目安 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 賃貸住宅 | 8-12万円 | ・安定収入 ・住宅用地特例維持 |
・入居者管理が必要 ・修繕費負担 |
| 民泊・ゲストハウス | 5-15万円 | ・高収益の可能性 ・季節調整可能 |
・運営の手間 ・近隣トラブル |
| 駐車場・倉庫 | 2-5万円 | ・管理が簡単 ・初期投資少 |
・収益性低い ・住宅特例対象外 |
年間の固定資産税が15万円の場合、月額1.3万円以上の収入があれば税負担をカバーできます。
ただし、賃貸経営には修繕費やリフォーム費用も発生するため、収支計画を慎重に検討しましょう。
FAQ
Q. 実家を保有する費用は?
A. 固定資産税・管理費・保険で年間40万円程度が目安です。
Q. 3年以内売却の特別控除は?
A. 最大3,000万円の譲渡所得控除が適用できます。
Q. 実家活用で税金をカバーできる?
A. 月1.3万円以上の収入があれば固定資産税負担をカバー可能です。
まとめ:実家相続の固定資産税対策は早期の情報収集と専門家相談が重要
実家を相続した際の固定資産税は、住宅用地特例の適用により大きく変わります。
居住用では評価額の6分の1に軽減される一方、空き家では満額課税となり、年間数十万円の差が生じることもあります。
重要なポイントは、住宅用地特例の維持、小規模宅地特例の活用、特定空き家指定の回避です。
実家の処分については、10年間の維持費用と資産価値を比較し、相続から3年以内の特別控除も考慮して判断する必要があります。
実家相続は、固定資産税・相続税・譲渡所得税が複雑に関係する問題です。
個別の状況により最適解が異なるため、専門家による適切なアドバイスが不可欠です。
あいりん司法書士事務所では、実家相続に関する無料相談を承っております。
固定資産税対策から相続登記まで、総合的にサポートいたします。お気軽にご相談ください。
この記事の監修者

遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。