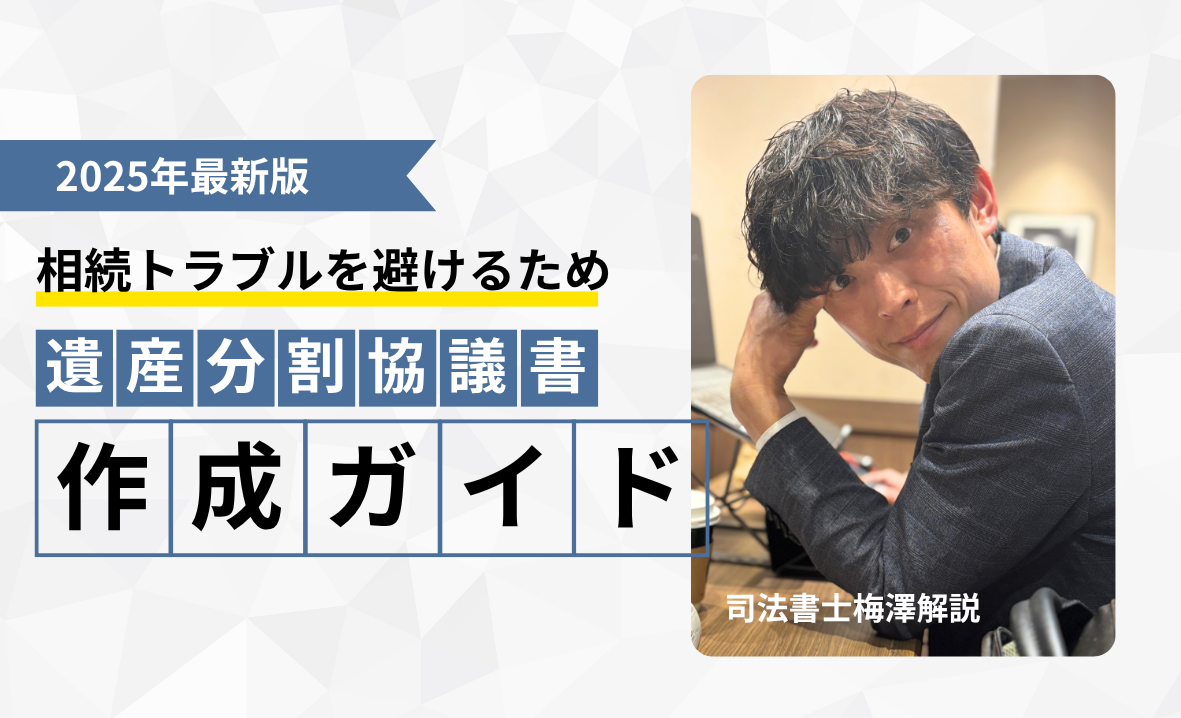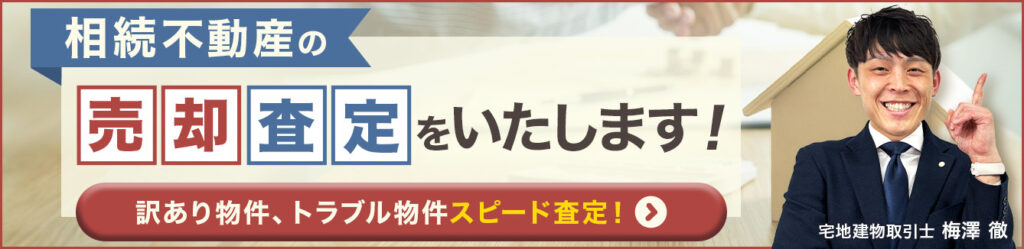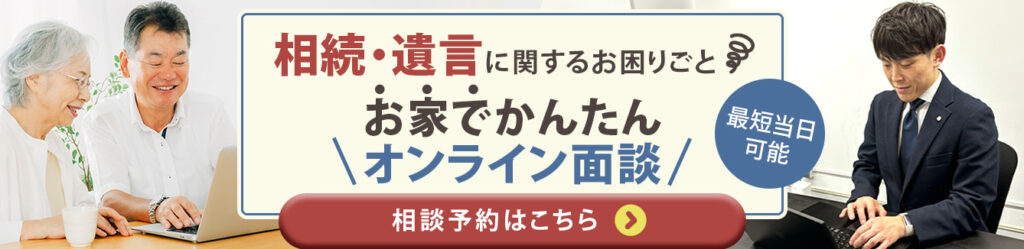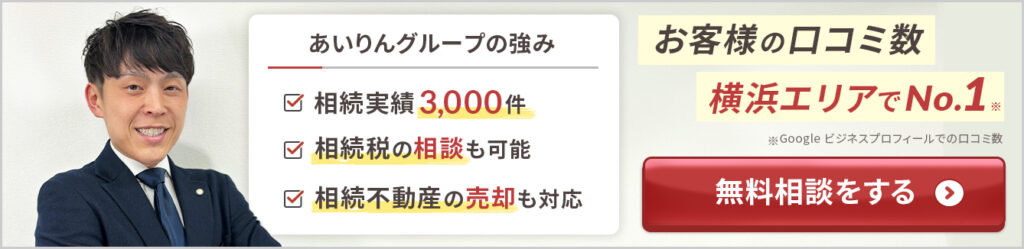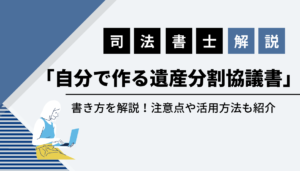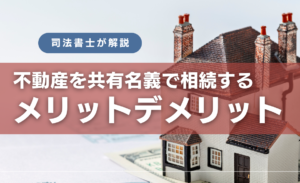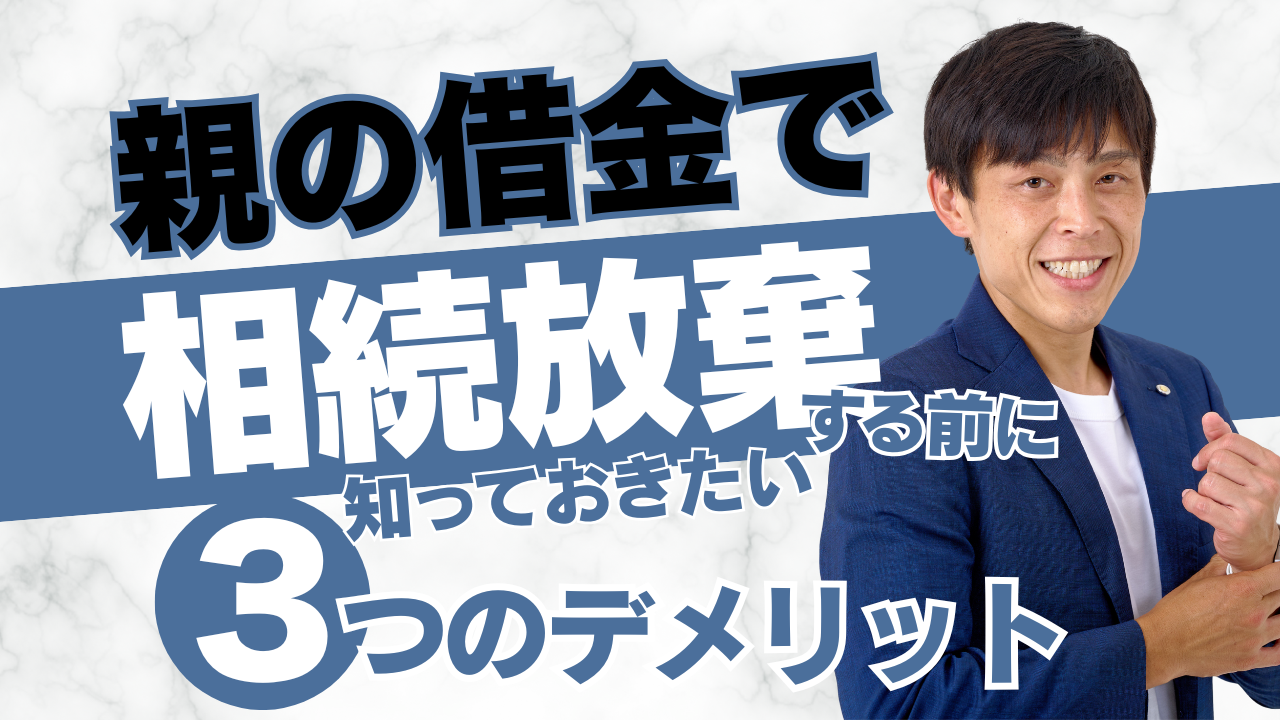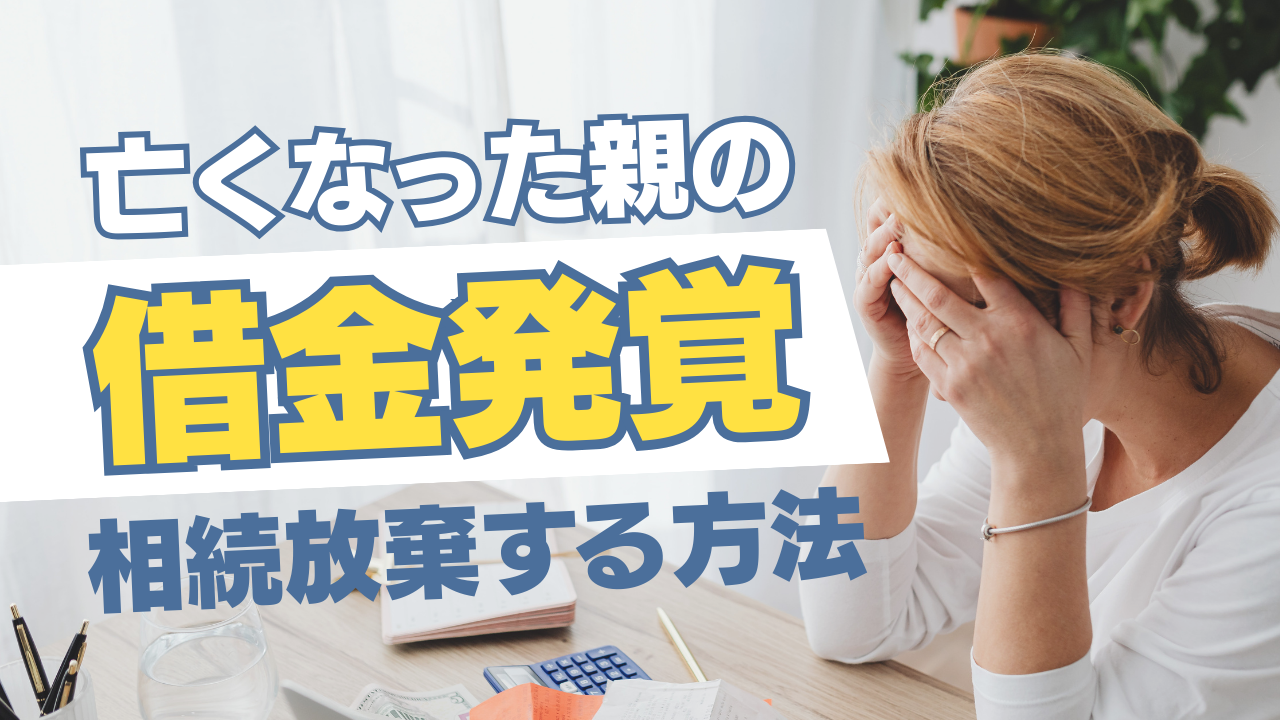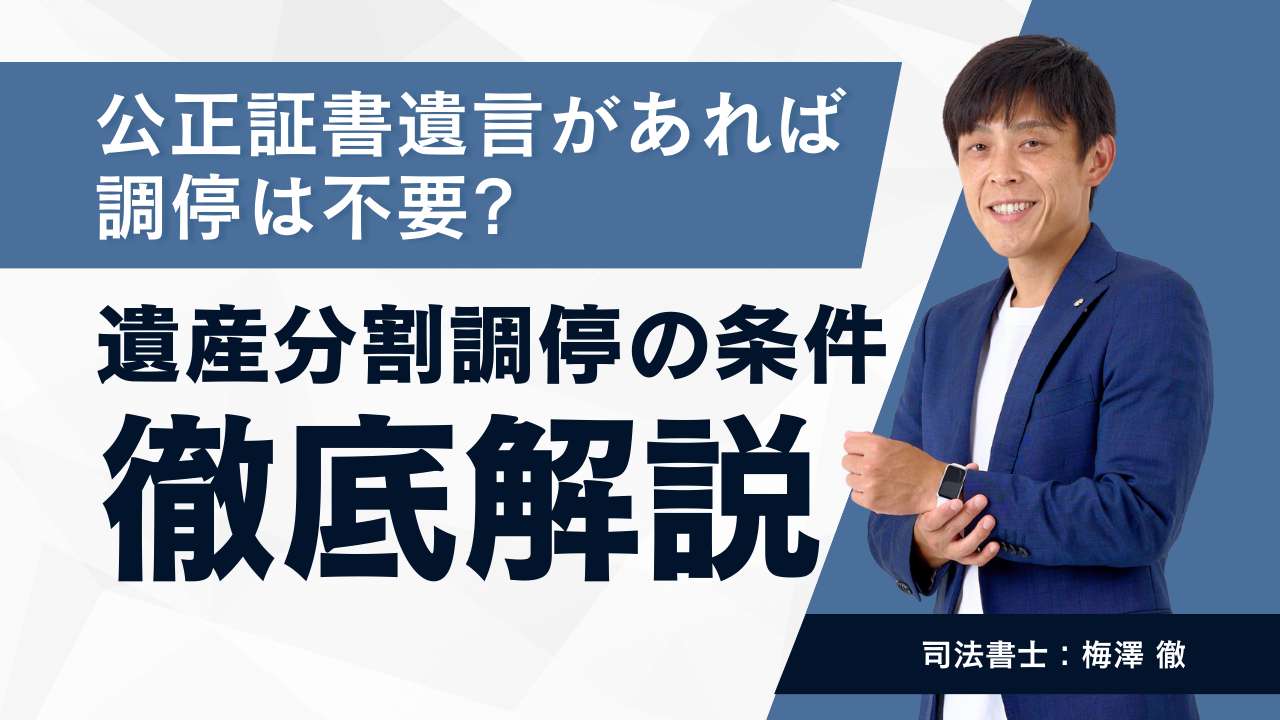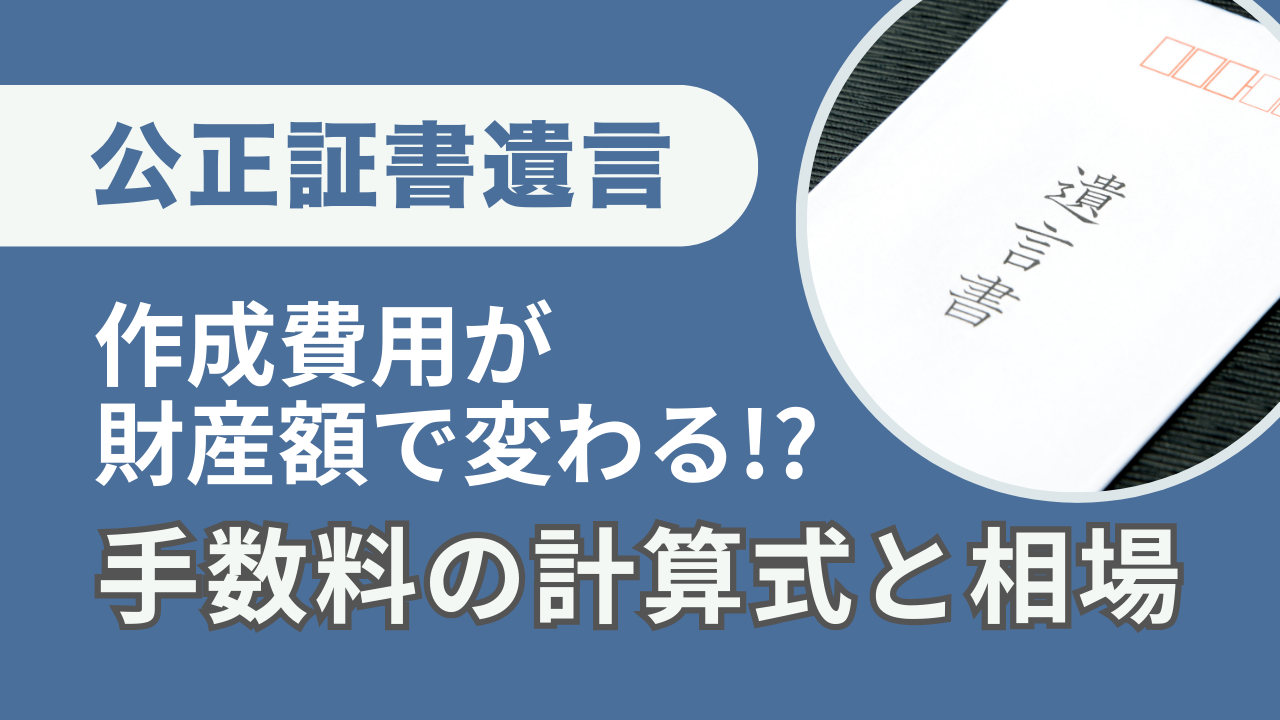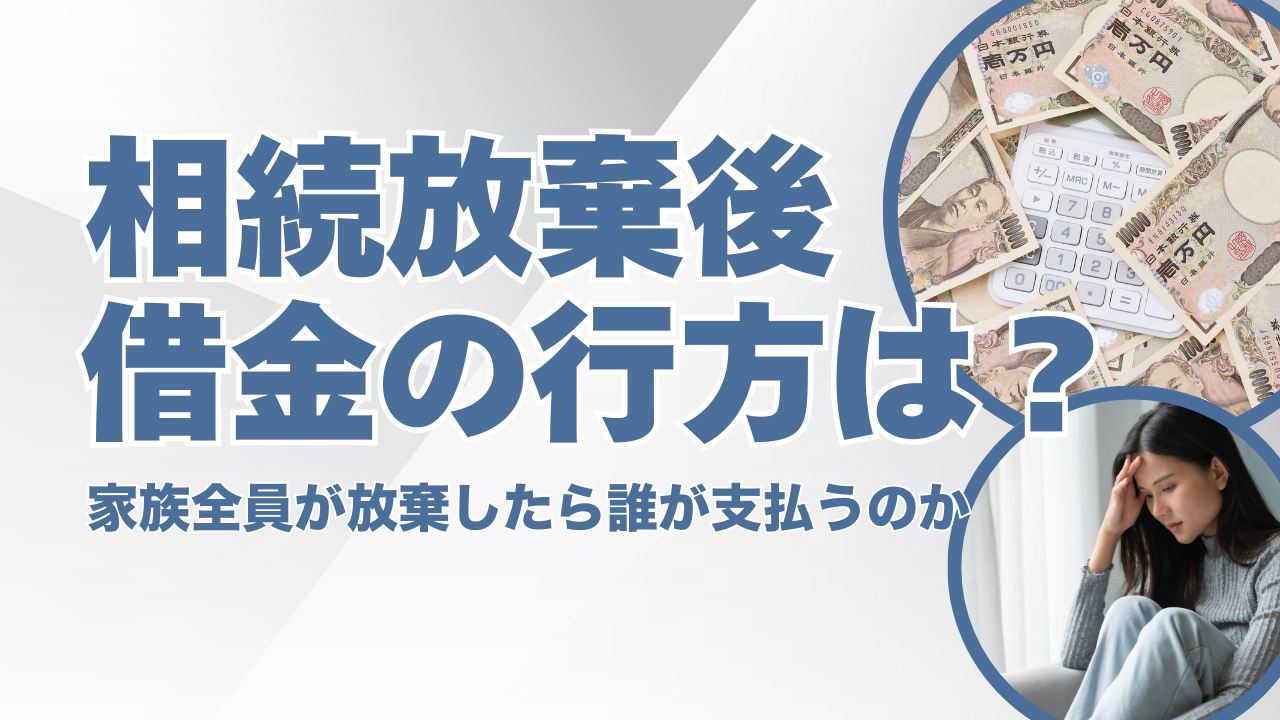この記事を要約すると
- 不動産を含む相続では、遺産分割協議書の適切な作成が円滑な手続きの鍵
- 不動産評価額の正確な算定、相続人全員の合意形成、登記に必要な事項の完全記載が重要なポイント
- 現物分割、代償分割、換価分割の選択や税金対策も考慮し、最適な分割方法を決定しよう
相続が発生すると、遺産の分け方で家族間のトラブルが起こる…なんて話を聞いたこともあるのではないでしょうか。
相続は人生で何度も経験することではないため、多くの方が「何から始めればいいのか分からない」と不安に思うかと思います。
この記事では、遺産分割協議書の正しい作成方法から不動産相続の手続きまで、専門家監修のもと最新情報をわかりやすく解説します。
読み終えた後は、安心して遺産分割協議書を作成し、円滑な相続手続きを進められるようになります。
この記事はこんな方におすすめ
- 不動産を含む相続手続きを控えている方
- 遺産分割協議書の作成方法がわからず困っている方
- 相続登記の義務化に対応したい方
- 相続トラブルを未然に防ぎたい方
目次
不動産の遺産分割協議書作成時の3つの注意点
不動産を含む遺産分割協議書を作成する際は、特に慎重な対応が必要です。
不動産は高額で分割が困難なため、適切な手続きを踏まないと後々大きなトラブルの原因となります。
その中でも特に気をつけておくべきポイント3つをまとめました。
不動産評価額の正確な計算と分割方法の決定
不動産の評価額は、固定資産税評価額、路線価、実勢価格の3つの基準があります。
相続税申告では路線価を基準とした相続税評価額を使用しますが、遺産分割では実際の市場価格に近い実勢価格を参考にすることが一般的です。
不動産評価額が正確でないと、相続人間で不公平が生じる可能性があります。
そのため、複数の不動産会社に査定を依頼し、適正な評価額を把握することが重要です。
評価額に大きな差が出ることも珍しくないため、客観的な判断基準を持つことが大切です。
評価額が確定したら、それに基づいて現物分割、代償分割、換価分割のいずれかを選択する必要があります。
相続人全員の合意と署名捺印の必要性
遺産分割協議書(※相続人全員で遺産の分け方を決める書面)は相続人全員の同意がなければ無効となります。
一人でも反対する相続人がいる場合は、家庭裁判所での調停や審判が必要になります。
協議書には相続人全員の署名と実印による捺印が必要で、印鑑証明書の添付も求められます。
トラブルを防ぐためにも、署名捺印の前に、協議内容について相続人全員が十分に理解し、納得していることを確認しましょう。
不動産登記に必要な記載事項の完全チェック
相続登記を行うため、遺産分割協議書には不動産の詳細情報を正確に記載する必要があります。
登記簿謄本に記載された所在地、地番、家屋番号、構造、床面積などを一字一句間違いなく記載するように気を付けましょう。
例えば、住居表示と地番が異なる場合があるので注意が必要です。
また、被相続人の氏名、相続人の氏名と住所、相続する不動産の特定、相続の割合なども明記します。
記載漏れや誤記があると登記申請が受理されないため、出戻りを防ぐ意味でも、司法書士に確認してもらうことをおすすめします。
司法書士からのアドバイス
遺産分割協議書の作成と相続登記は、個別具体的に回答が異なります。正確な登記のためにも、まずは無料相談をお申し込みください。
FAQ
Q:不動産評価額はどこで確認できるの?
A:固定資産税評価証明書で確認できます。
Q:相続人が県外にいても協議書は作れる?
A:郵送で署名捺印を進めることが可能です。
Q:登記申請で記載ミスがあったらどうなる?
A:申請が却下されるため再申請が必要です。
遺産分割協議書で不動産を相続する手続きの流れ
不動産相続の手続きは複雑で、多くの書類と時間が必要です。
法務省の統計によると、2023年の相続登記件数は約127万件で、前年比105%と増加しています。
2024年4月から相続登記が義務化されたため、期限内に適切な手続きを進めることが重要です。
相続人調査から不動産評価まで必要な書類一覧
相続手続きでは、まず相続人の確定から始めます。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と住民票、印鑑証明書が必要です。
不動産関係では、登記簿謄本、固定資産評価証明書、地積測量図、建物図面などを取得します。
その他、被相続人の住民票の除票、相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)も準備が必要です。
これらの書類収集には1〜2か月程度かかることが多いため、早めに準備を始めることが大切です。
遺産分割協議書作成から法務局提出までの期間
必要書類が揃ったら、相続人全員で遺産分割の協議を行います。
協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印します。
協議書の作成から署名捺印の完了まで、通常1〜3週間程度を要します。
その後、相続登記申請書を作成し、法務局に提出します。
登記申請から完了まで約1〜2週間かかるため、全体で2〜3か月の期間を見込んでおくことが重要です。
相続登記の義務化対応と期限内手続きのポイント
2024年4月から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過去の相続についても義務化の対象となるため、放置している相続登記がある場合は早急に対応が必要です。
期限内に遺産分割が困難な場合は、相続人申告登記(※相続人であることを簡易に登記する制度)という制度を利用できます。
簡易的な登記で、遺産分割成立後に本格的な相続登記を行うことができます。
FAQ
Q:相続登記義務化の期限はいつ?
A:相続開始を知った日から3年以内です。
Q:書類収集にはどのくらい時間がかかる?
A:通常1〜2か月程度の期間が必要です。
Q:相続人申告登記とは何?
A:簡易的に相続人であることを登記する制度です。
不動産相続で失敗しない遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書の書き方次第で、相続手続きがスムーズに進むかどうかが決まります。
特に不動産が含まれる場合は、専門的な知識と正確な記載が求められます。
現物分割・代償分割・換価分割の選択基準
不動産の分割方法には3種類あり、それぞれメリット・デメリットがあります。
| 分割方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 現物分割 | ・手続きが簡単 ・登記費用が最小 ・不動産を保有できる |
・評価額に差がある場合の不公平 ・分割が困難な場合あり |
| 代償分割 | ・公平な分割が可能 ・不動産を手放さない ・納得しやすい |
・代償金の用意が必要 ・税務上の手続き複雑 |
| 換価分割 | ・現金化で公平 ・管理責任がない ・分割が明確 |
・売却手続きが必要 ・売却時期による価格変動 ・税金がかかる |
現物分割は不動産をそのまま相続人の一人が取得する方法で、手続きが最も簡単です。
代償分割(※不動産を取得した人が他の相続人に現金で代償する方法)は一人が不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法です。
換価分割(※不動産を売却して現金化してから分ける方法)は不動産を売却して、売却代金を相続人で分割する方法です。
分割方法の選択基準としては、不動産の利用予定、相続人の資力、税務上の影響などを総合的に判断することが重要です。
一般的には、居住用不動産の場合は現物分割、事業用不動産の場合は代償分割が選ばれることが多くなっていますので、参考にしてください。
税金対策を考慮した最適な分割方法の決め方
相続税の節税効果を考慮した分割方法も決める必要があります。
配偶者税額軽減(※配偶者が相続する場合の税金軽減制度)や
小規模宅地等の特例を最大限活用できる分割方法を検討すると良いでしょう。
居住用不動産については、配偶者が相続することで小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減額)が適用できます。
事業用不動産の場合は、事業を継続する相続人が取得することで特例の適用が可能です。
また、将来の二次相続も考慮し、トータルでの税負担を最小化する分割方法を選択することが重要です。
計算が難しい場合は、専門家と連携して、シミュレーションを行うこともお勧めです。
司法書士からのアドバイス
税金対策を考慮した遺産分割の方法選択は、各家庭の資産状況や相続人の関係性により最適解が異なります。
個別具体的に回答が異なるため、まずは無料相談をお申し込みください。
FAQ
Q:現物分割と代償分割の違いは?
A:現物分割は現物のまま、代償分割は代償金を支払います。
Q:小規模宅地等の特例はいくら減額される?
A:居住用不動産で330㎡まで80%減額されます。
Q:司法書士への依頼費用はいくら?
A:相続登記で5〜10万円程度が相場です。
司法書士への依頼タイミングと費用相場
司法書士への依頼は、遺産分割協議書の作成段階から相続登記完了まで対応してもらうのが一般的です。
費用相場は、相続登記で5〜10万円程度、遺産分割協議書作成で3〜5万円程度です。
不動産の価額や件数によって費用は変動しますが、登録免許税(不動産価額の0.4%)は別途必要です。
司法書士に依頼することで、書類作成ミスや手続き漏れを防ぐことができます。
期限は決まっていないものの法的に不安定な状態なので複雑な相続や期限が迫っている場合は、早めに専門家に相談することが重要です。
相続登記で遺産分割協議書がない場合の3つの対処法
すべての相続で遺産分割協議書が必要というわけではありません。
状況に応じて適切な手続き方法を選択することが重要です。
法定相続分での相続登記申請の手続きと注意点
遺産分割協議が成立していない場合は、法定相続分での相続登記が可能です。
配偶者と子が相続人の場合、配偶者が2分の1、子が残りを人数で等分します。
最高裁判所の統計によると、家庭裁判所での遺産分割調停件数は2022年に12,188件となっており、年々増加傾向にあります。
法定相続分での登記は相続人の一人からでも申請でき、他の相続人の同意は不要です。
ただし、共有名義となるため将来の売却や活用に制約が生じる可能性があります。
また、後から遺産分割が成立した場合は、改めて登記の変更が必要になります。
遺産分割協議書の作成が不要なケース5選
以下のケースでは遺産分割協議書の作成が不要です。
1つ目は相続人が一人の場合で、単独相続となります。
2つ目は法定相続分で相続する場合で、協議書は不要です。
3つ目は遺言書がある場合で、遺言の内容に従って相続します。
4つ目は家庭裁判所の調停調書や審判書がある場合です。
5つ目は相続放棄により相続人が一人になった場合です。
これらのケースでは、それぞれに応じた必要書類を準備して相続登記を行います。
ご自身が当てはまるケースはありますでしょうか?
遺言書がある場合の相続登記手続きの流れ
遺言書がある場合は、原則として遺言の内容に従って相続登記を行います。ただし、形式によって条件などが変わってくるので、下記を参考にしてください。
まず、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きが必要です。 公正証書遺言の場合は検認不要で、そのまま登記申請に使用できます。
遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が登記申請を行う必要がありますが、
遺言の内容が不明確な場合や、相続人全員が遺言と異なる分割に合意する場合は、遺産分割協議書が必要になることもあります。
遺言書の内容を十分に確認し、適切な手続きを選択することが重要です。
FAQ
Q:法定相続分での登記は単独でできる?
A:相続人の一人からでも申請可能です。
Q:遺産分割協議書が不要なのはどんなとき?
A:相続人が一人の場合や遺言書がある場合です。
Q:公正証書遺言は検認が必要?
A:公正証書遺言は検認不要で使用できます。
まとめ
不動産を含む相続では、遺産分割協議書の適切な作成が円滑な手続きの鍵となります。
不動産評価額の正確な算定、相続人全員の合意形成、登記に必要な事項の完全記載が重要なポイントです。
2024年4月からの相続登記義務化により、期限内の手続き完了がより重要になっています。
現物分割、代償分割、換価分割の選択や税金対策も考慮し、最適な分割方法を決定しましょう。
複雑な手続きが多いため、司法書士などの専門家に相談することで、安心して相続手続きを進めることができます。
相続トラブルを避けるためには早めの準備と適切な対応が不可欠です。当事務所では、遺産分割協議書の作成から相続登記まで、相続手続きのすべてをサポートしています。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
この記事の監修者

遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。