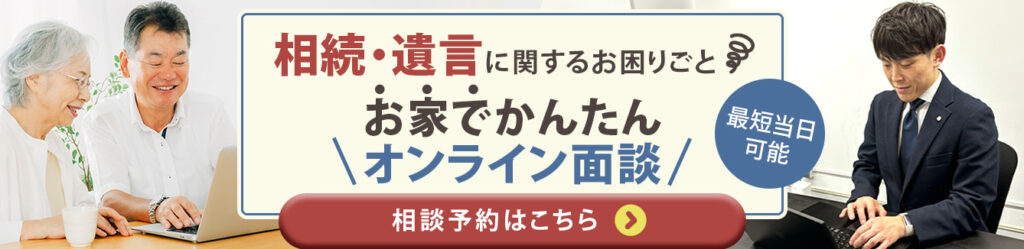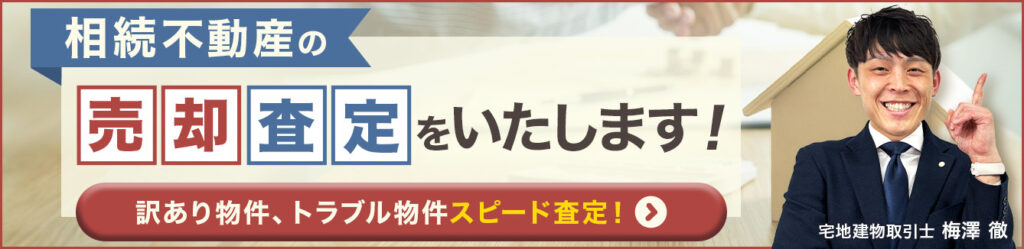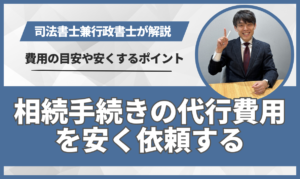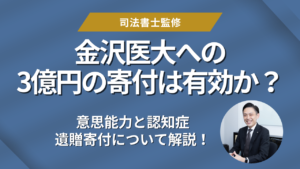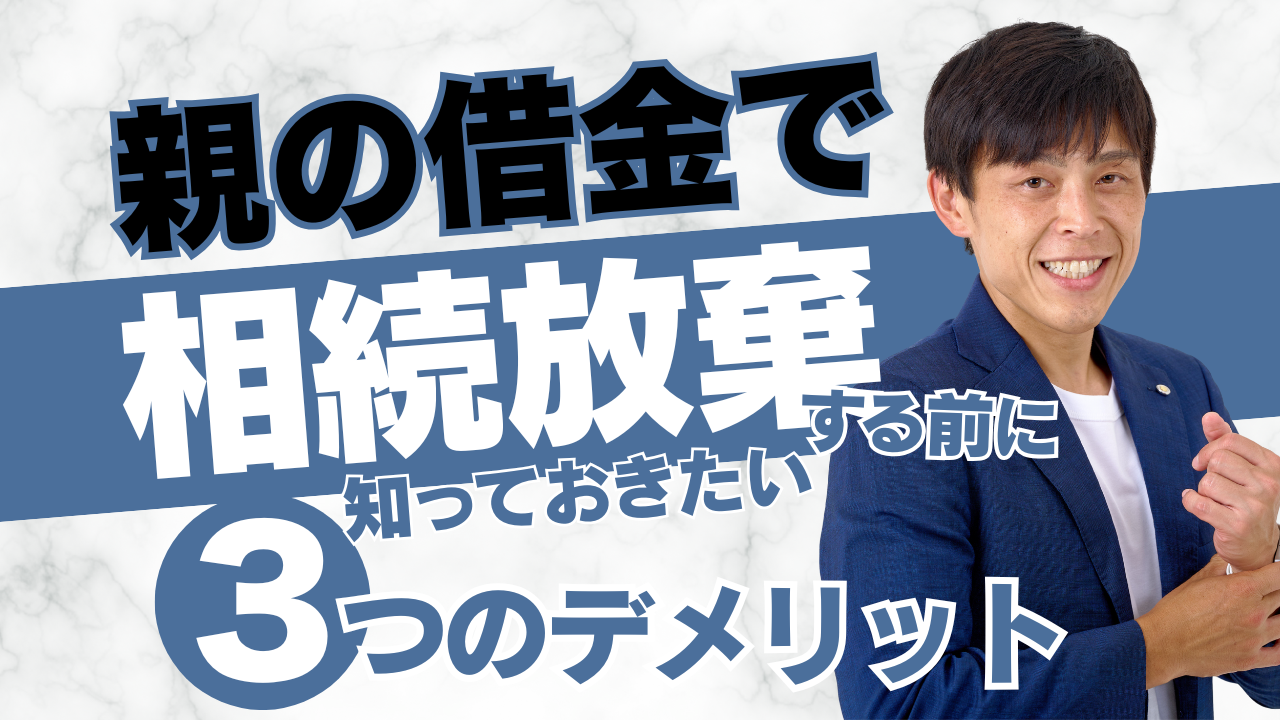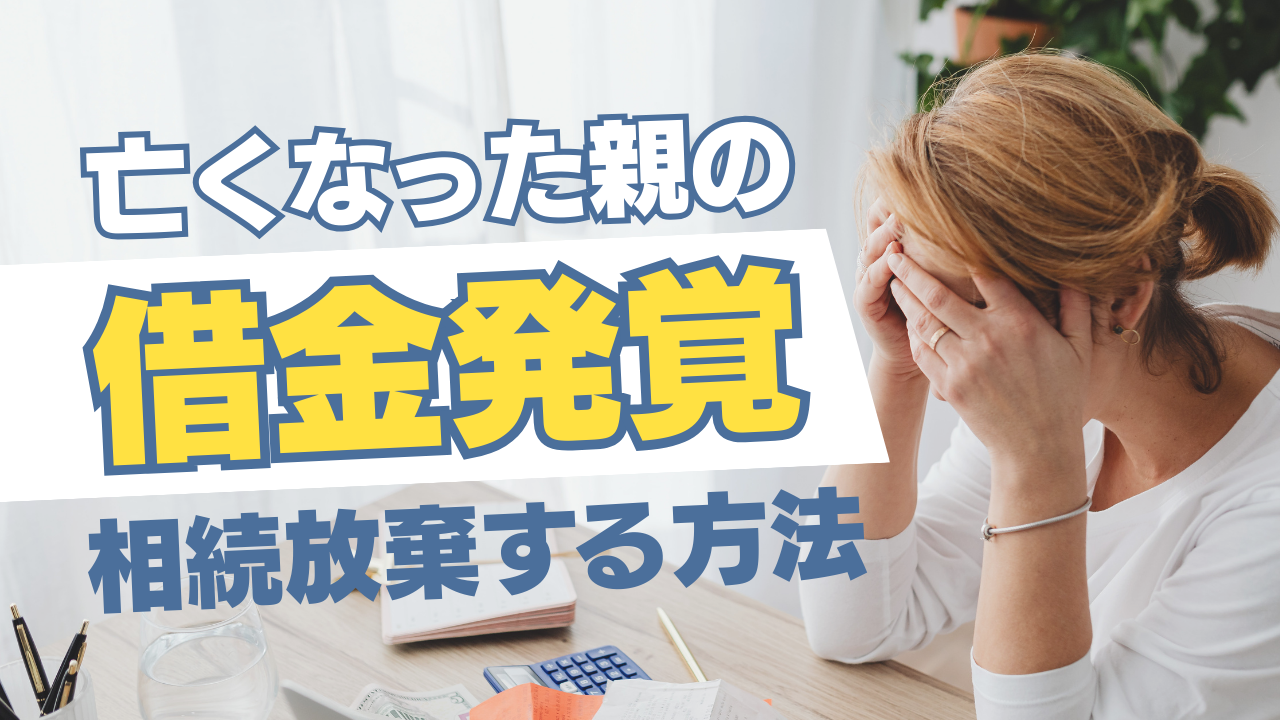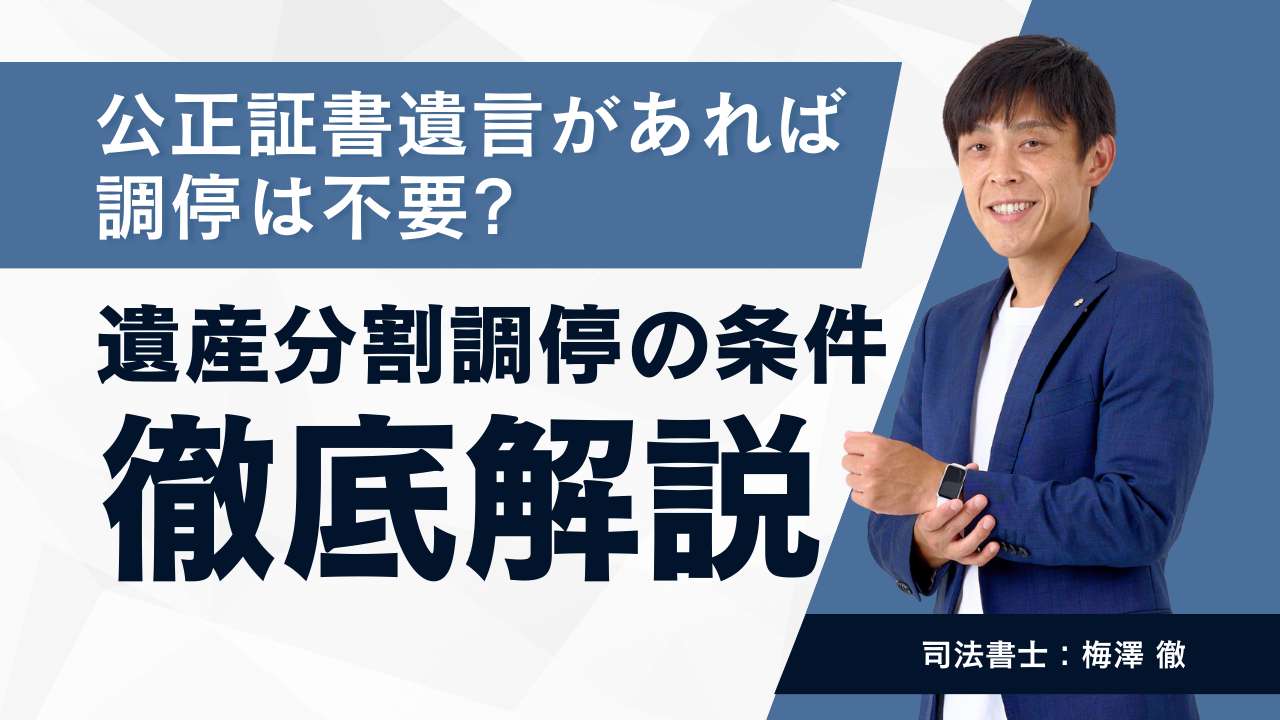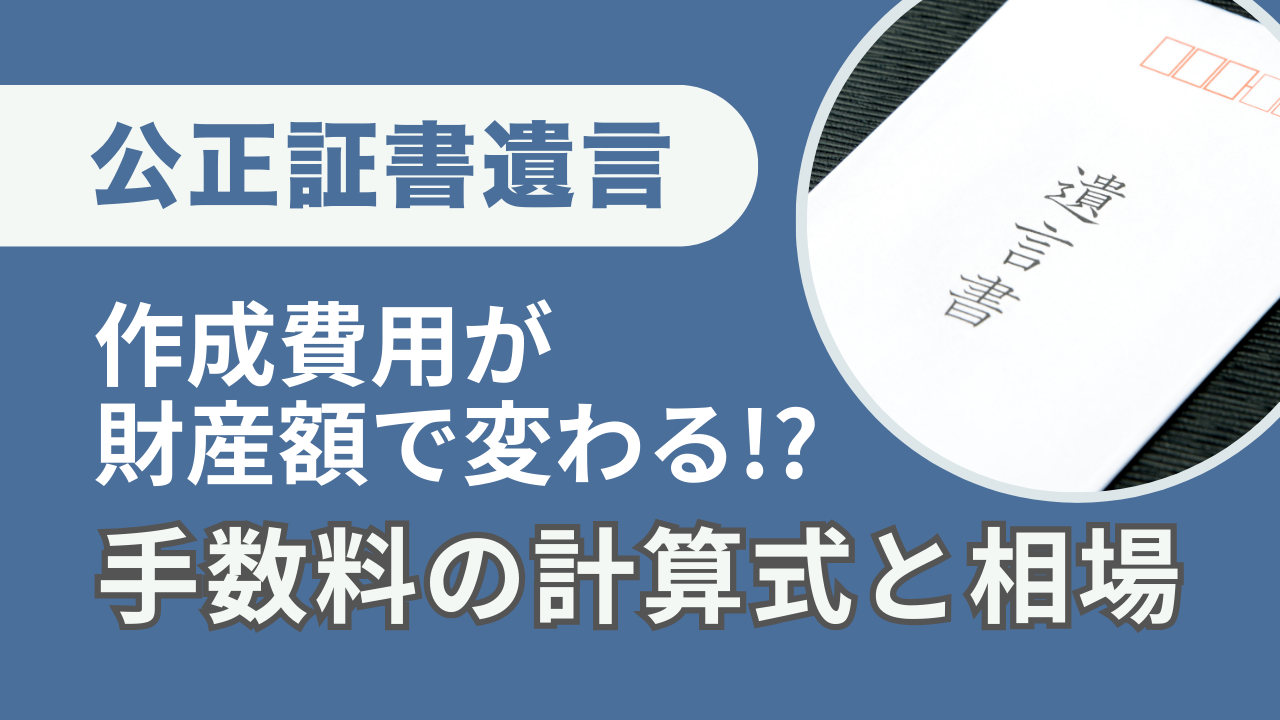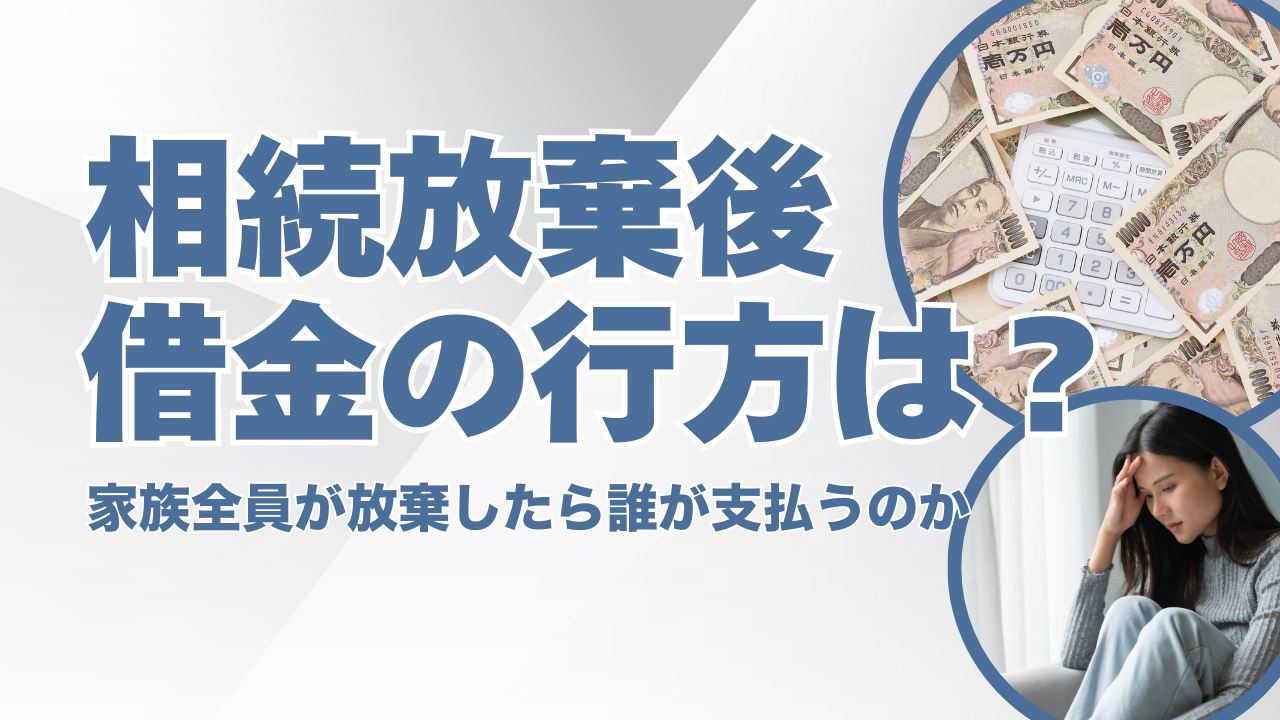この記事を要約すると
- 法定相続分は、遺言書がない場合に、法律で定められた相続人ごとの取り分の割合
- 相続には廃除・代襲相続・遺留分など、法定相続分を制限・補う制度がある
相続は人生で何度も経験するものではありませんが、いざ直面すると法律や制度が複雑で戸惑う方が多くいます。中でも「法定相続分」は、遺産分割の基準となる重要な考え方です。
本記事では、法定相続分の基本パターンから、相続人の廃除・代襲相続・相続登記の可否、さらに最低限の取り分を保証する遺留分制度までを、専門家の視点でわかりやすく解説します。
これを読めば、相続の全体像と注意点がスッキリ理解できるはずです。
法定相続分とは
遺産の分割割合は、被相続人(亡くなった方)が遺言書で決めることも、相続人同士での話し合い(遺産分割協議)によって決めることもできます。
しかし、遺言書がない場合や、協議がまとまらない場合には、民法で定められた「法定相続分」を基準に分けることになります。
つまり、法定相続分とは法律で定められた、相続人ごとの取り分の割合のことです。
法定相続人の4パターン
民法では、配偶者の有無や同順位の相続人の構成によって、次のような割合が定められています。
① 配偶者のみが相続人の場合
相続人が配偶者だけの場合は、遺産のすべてを配偶者が相続します。子どもや親、兄弟姉妹など、他に相続人がいないケースです。
② 配偶者と子が相続人の場合
遺産は配偶者と子が半分ずつ相続します。子が複数いる場合は、その半分をさらに人数で等分します。実子と養子の扱いは同じで、均等に分けられます。
③ 配偶者と親(直系尊属)が相続人の場合
配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。親がすでに亡くなっている場合には祖父母が相続人となります。
④ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分けます。
※同順位の相続人が複数いる場合は、その順位ごとの取り分を等しく分けます。
実際には、不動産や預金の分け方は法定相続分どおりではなく、「土地を相続する代わりに現金を多めにもらう」など、話し合いで柔軟に調整するケースが多くあります。
相続人を廃除できる場合
相続人の中に、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を行った者がいる場合には、その人の相続権を奪うことができます。これを「廃除」といいます。
廃除を行うには、被相続人が家庭裁判所に申立てをするか、遺言書で廃除の意思表示をする必要があります。
家庭裁判所で認められると、その相続人は直ちに相続権と遺留分を失います。
なお、廃除された相続人の子は代襲相続により相続人になる場合があります。
また、廃除の対象となるのは遺留分を持つ相続人(配偶者・子・直系尊属)です。兄弟姉妹には遺留分がないため、「遺産を与えない」という遺言だけで対応可能です。
法定相続分の細かい取り扱い
相続分は、相続人の構成によって次のようになります。
-
配偶者と子の場合:配偶者が2分の1、子が2分の1(複数の子は均等)
-
配偶者と直系尊属の場合:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1(均等)
-
配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(均等)
非嫡出子(婚姻関係にない父母の子)の相続分は嫡出子の2分の1となります。
また、異父母兄弟姉妹(父または母の一方のみ同じ兄弟姉妹)の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。
代襲相続の場合の法定相続分
代襲相続とは、相続人がすでに亡くなっている場合に、その子や兄弟姉妹の子が代わって相続することをいいます。
代襲相続人は、本来相続するはずだった人(被代襲者)の相続分をそのまま引き継ぎます。
例えば、配偶者と死亡した子の代襲相続人A・Bが相続する場合、死亡した子の相続分(1/2)をAとBで折半し、それぞれが1/4を相続します。
法定相続分の登記を共同相続人のうちの1人ができるのか?
共同相続人中の一人が、単独でその人の持分の相続登記を申請できるのでしょうか。
相続人は単独相続、共同相続関わらず、遺産分割前に相続人ごとの不動産の共有関係を公示するため、相続を登記原因とする所有権移転登記を申請することができます。
また、この登記は相続人が複数いても単独で申請することができます。
法定相続分による相続の場合には、遺産分割までの間であれば、少なくとも相続分に応じて共同相続人全員の共有になります。従って相続全員が申請人になれますし、そのうちの一人が保存行為として相続登記を申請することもできます。
一方で共同相続人の一人が自分の相続持分だけ相続登記を申請することはできません。死亡した方とその相続人の共有された状態を一瞬でもつくることは登記技術的に不可能だからです。
法定相続分を守る制度「遺留分」
遺留分は法定相続分の一部を保証することで法定相続人の権利を守る制度です。配偶者・子・直系尊属に認められ、兄弟姉妹にはありません。
たとえ遺言で財産の大部分が他人に渡されても、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求によって取り戻すことができます。
しかし、一方で相続制度が残された家族の生活保障や遺産形成に貢献した遺族の目に見えない持分の清算などの機能を持っていることを考えるとこの正当な利益を軽んじていいわけではないです。
よって、遺留分は亡くなった方の財産処分の自由と相続人の保護、相対立する要請の調和を図るための制度です。
ここで遺留分制度を見ると次のような内情があります。これは遺言によっては相続人の地位を奪うことはできないということです。そして遺留分は法定相続人である子や直系卑属、直系尊属や配偶者に対して認められているわけですが、これらの相続人の廃除を遺留分喪失とを直結させています。
まとめ
法定相続分は、遺言書や相続人同士の協議が整わない場合に、遺産をどの割合で分けるかを示す法律上の基準です。配偶者や子、親、兄弟姉妹といった相続人の構成によって割合は変わり、さらに廃除や代襲相続といった制度が絡むことで権利関係は複雑になります。
最低限の取り分を保障する遺留分制度もあり、被相続人の意思と相続人の保護とのバランスを取る役割を担っています。
相続は家族関係や法律が複雑に絡むため、疑問があれば早めに司法書士や弁護士などの専門家に相談することが重要です。
この記事の監修者

遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。