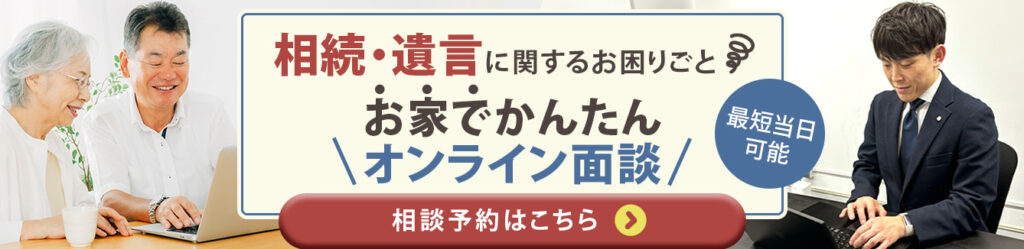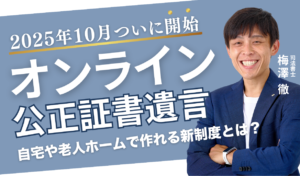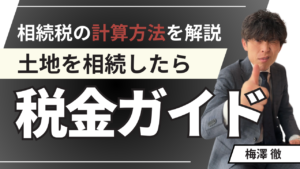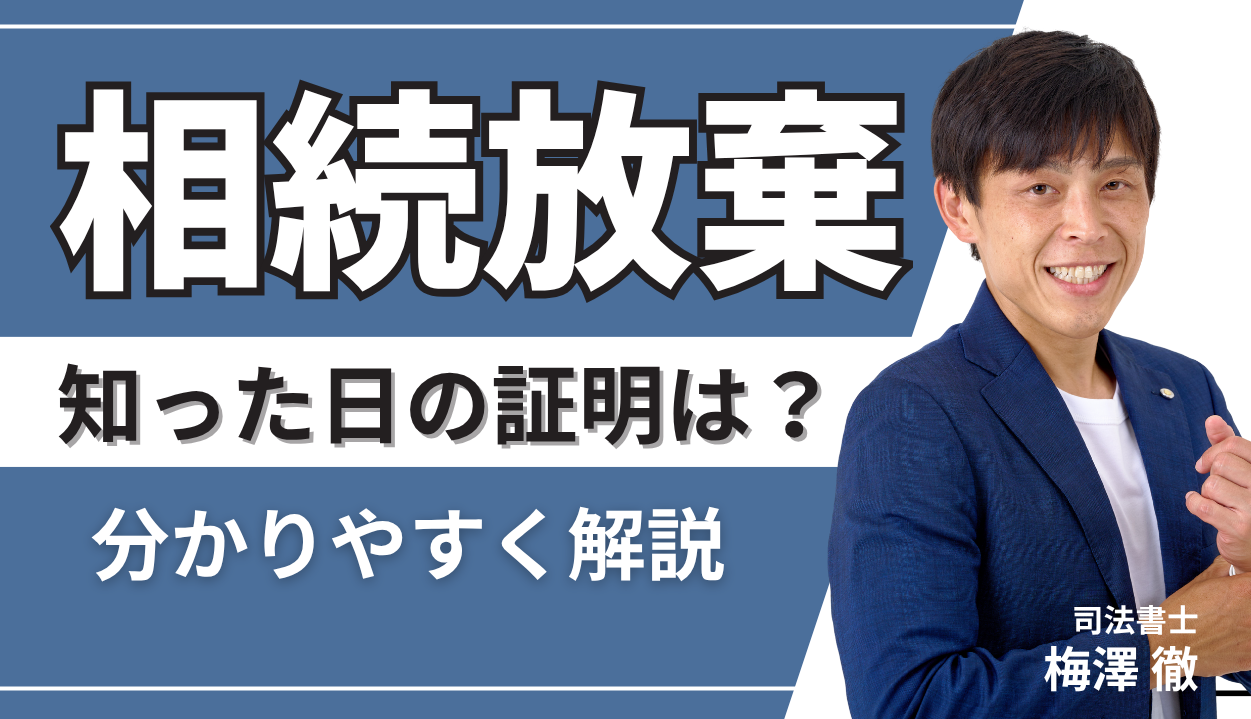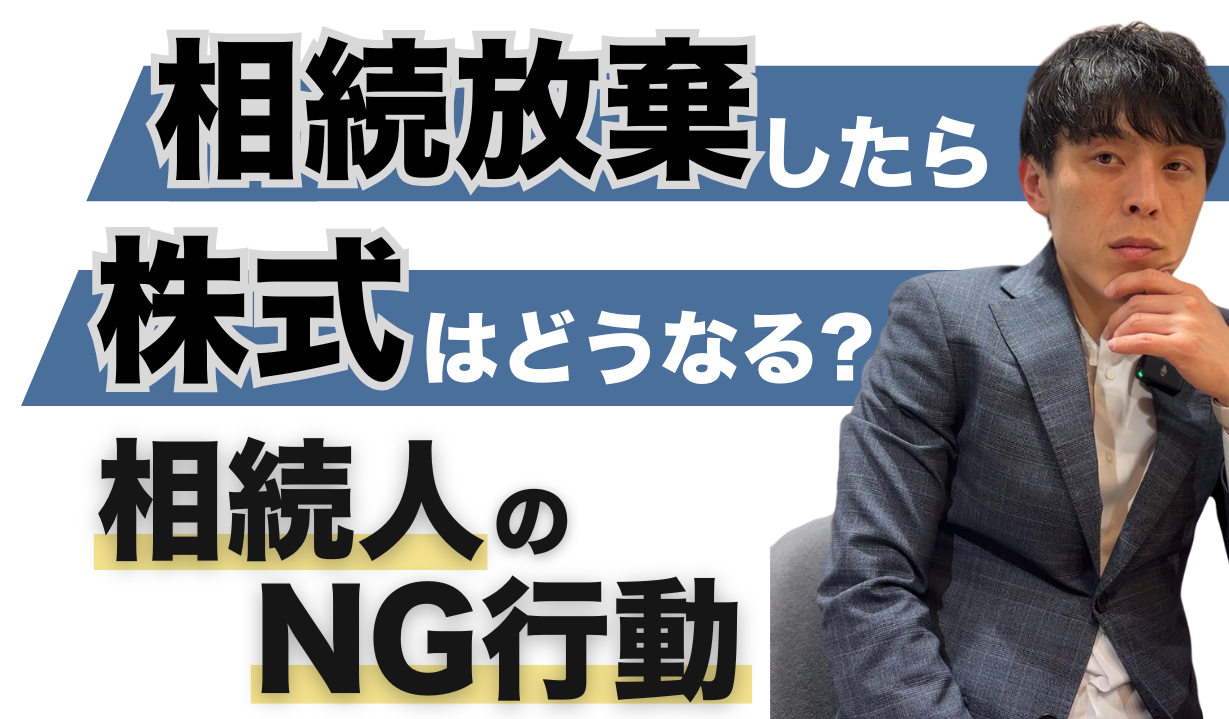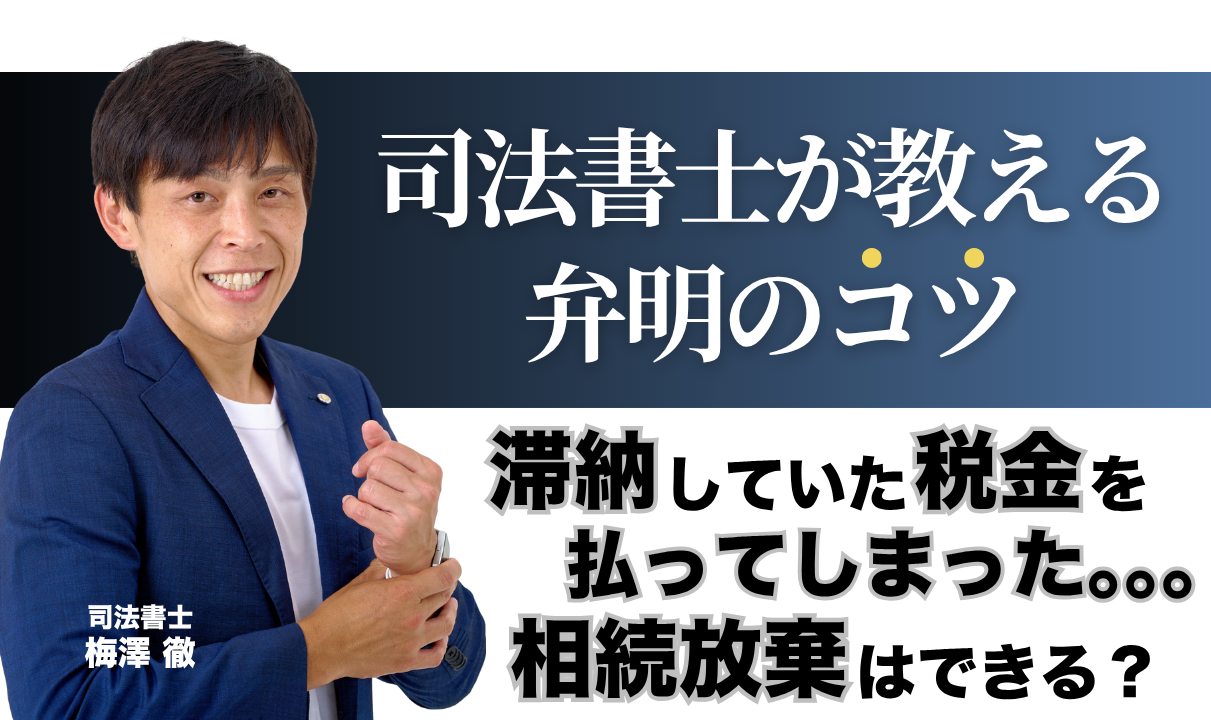この記事を要約すると
- 孫への土地相続は代襲相続・遺言・養子縁組の3つの方法がある
- 孫への相続は原則2割加算だが小規模宅地特例で最大80%減額可能
- 遺留分トラブル回避と生前贈与との比較が重要で専門家への相談が必須
祖父母が所有していた土地を孫が相続するケースは、一般的な親から子への相続とは異なる特別なルールが適用されます。
通常、孫は法定相続人※ではないため、祖父母の財産を直接相続することはできません。
しかし、代襲相続や遺言書の活用、養子縁組など、いくつかの方法で
孫への土地相続を実現できます。
この記事では、孫が土地を相続する3つの方法と
孫特有の相続税2割加算ルール、節税に活用できる特例制度について
司法書士が詳しく解説します。
記事を読み終えるころには、孫への土地相続の仕組みと
手続きの流れ、税負担を軽減する方法が理解でき、適切な相続対策を選択できるようになります。
※法定相続人:民法で定められた相続する権利を持つ人のこと
この記事はこんな方におすすめ
- 祖父母が亡くなり、孫が土地を相続できるのか知りたい方
- 孫に土地を相続させる方法と税金について理解したい方
- 代襲相続や遺言による相続の違いを把握したい方
目次
孫が祖父母の土地を相続できる3つのケース
孫が祖父母の土地を相続する方法は、大きく分けて3つあります。
それぞれの方法には異なる要件と税務上の取り扱いがあるため、状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。
ここでは、代襲相続、遺言書による遺贈、養子縁組
という3つの方法について、詳しく解説します。
| 相続方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 代襲相続 | ・相続税2割加算なし ・法律上当然に発生 ・特別な手続き不要 |
・親が先に死亡している必要 ・戸籍書類の収集が複雑 ・相続割合が決まっている |
| 遺言による遺贈 | ・自由に財産を指定できる ・生前に準備可能 ・孫の年齢不問 |
・相続税2割加算あり ・遺留分トラブルのリスク ・遺言書作成が必要 |
| 養子縁組 | ・基礎控除600万円増 ・法定相続人になる ・世代スキップ相続 |
・相続税2割加算あり ・養子数に制限あり ・戸籍に記載される |
代襲相続で孫が法定相続人になる条件と相続割合
代襲相続※1とは、本来相続人となるべき人が既に亡くなっている場合に、その子(孫)が代わりに相続する制度です。
例えば、祖父が亡くなった時点で、本来相続人である父がすでに死亡していた場合、孫が父の相続分をそのまま引き継ぐことになります。
祖父母より先に親が亡くなることは誰にでも起こりうることで、こうした状況で孫が相続する権利を持つのは当然の流れですよね。
代襲相続が発生する条件は、相続開始時点で被相続人の子が死亡、相続欠格※2、相続廃除※3のいずれかに該当している場合です(民法887条2項)。
相続割合は、亡くなった親が受け取るはずだった相続分と同じになります。
仮に祖父の相続人が配偶者と子3人だった場合、子1人あたりの相続分は6分の1ですが、その子が既に亡くなっていて孫が2人いる場合、孫はそれぞれ12分の1ずつを相続します。
代襲相続は法律上当然に発生するため、特別な手続きは不要ですが、相続登記の際には代襲相続を証明する戸籍謄本が必要になります。
参考:民法(相続)- e-Gov法令検索
※1代襲相続:本来の相続人が相続開始前に死亡等した場合、その子が代わりに相続すること
※2相続欠格:故意に被相続人や先順位相続人を死亡させた場合など、相続権を失うこと
※3相続廃除:被相続人への虐待や重大な侮辱があった場合に、家庭裁判所の審判で相続権を剥奪すること
遺言書による遺贈で孫に土地を渡す方法と注意点
遺言書を作成することで、孫に直接土地を遺贈※1することができます。
遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲り渡すことで、相続人以外の人にも財産を渡すことが可能です。
祖父母が「孫の○○に自宅の土地を遺贈する」という内容の遺言書を
作成すれば、代襲相続の条件を満たさなくても孫に土地を相続させることができます。
ただし、遺言による遺贈には注意すべき点があります。
まず、他の相続人の遺留分※2を侵害しないよう配慮する必要があります。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された
最低限の相続分のことで、配偶者や子には遺産の2分の1の遺留分があります(民法1042条)。
孫への遺贈が他の相続人の遺留分を侵害すると、遺留分侵害額請求をされる
可能性があるため、事前に遺産全体のバランスを考慮することが重要です。
また、遺言書は法定の方式に従って作成しないと
無効になるため、公正証書遺言の利用をおすすめします。
※1遺贈:遺言によって財産を無償で譲り渡すこと
※2遺留分:法律で保障された相続人の最低限の取り分のこと
孫を養子にして相続人にする節税メリットと制限
祖父母が孫と養子縁組をすることで、孫を法定相続人にする方法もあります。
養子縁組をすると、孫は祖父母の子としての地位を得るため、他の子と同じように相続権を持つことになります。
養子縁組による相続には、相続税の節税効果があります。
相続税の計算では、法定相続人の数が多いほど
基礎控除額※が大きくなるため、養子を1人増やすことで基礎控除が600万円増加します。
また、孫養子は相続を1回飛ばすことになるため、世代をスキップした
財産移転が可能になり、長期的な相続税対策として有効です。
ただし、養子縁組には制限があります。
相続税の計算上、実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は
養子2人までしか法定相続人として算入できません(相続税法15条2項)。
また、孫養子が相続する場合は、後述する相続税の2割加算の
対象となるため、必ずしも節税になるとは限りません。
養子縁組は戸籍に記載される法律行為であり、簡単に解消できないため、慎重に検討する必要があります。
※基礎控除額:相続税がかからない金額の範囲で、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算される
代襲相続、遺言、養子縁組のどの方法が最適かは個別の状況によって異なるため、まずは無料相談で専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
FAQ
Q. 代襲相続とは何ですか?
A. 親が先に亡くなった場合に孫が代わりに相続する制度です。
Q. 孫への遺贈の注意点は?
A. 他の相続人の遺留分を侵害しないよう配慮が必要です。
Q. 養子縁組のメリットは?
A. 基礎控除が600万円増え相続税の節税効果があります。
孫への土地相続で知っておくべき相続税と特例制度
孫が土地を相続する場合、通常の相続とは異なる税務上の取り扱いがあります。
特に重要なのが相続税の2割加算ルールで、孫が相続する場合は税負担が増加します。
一方で、小規模宅地等の特例などの節税制度を活用することで、税負担を大幅に軽減できる可能性もあります。
税金の話は複雑で難しく感じるかもしれませんが、知っているかどうかで数百万円の差が出ることもあるため、しっかり理解しておくことが大切です。
ここでは、孫への土地相続における税金の仕組みと、利用できる特例制度について詳しく解説します。
代襲相続と遺言による遺贈のどちらに該当するか、把握しておくことをお勧めします。
孫への相続は税額2割加算|具体的な計算例で解説
孫が祖父母から相続する場合、原則として相続税額が2割加算されます。
この2割加算は、世代を飛ばした相続による税負担の軽減を防ぐために設けられた制度です(相続税法18条)。
2割加算の対象となるのは、被相続人の配偶者、子、父母以外の人が相続した場合で、孫はこれに該当します。
ただし、代襲相続により孫が相続人となった場合は、2割加算の対象外となります。
具体的な計算例を見てみましょう。
祖父の遺産総額が1億円、相続人が配偶者と子2人(うち1人は遺言で孫に遺贈)の場合を考えます。
基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)なので、課税遺産総額は5,200万円です。
孫が1,000万円の土地を遺贈された場合、孫の相続税額は約80万円となりますが、2割加算により約96万円に増額されます。
一方、代襲相続で孫が相続人となった場合は、同じ1,000万円の相続でも2割加算はなく、約80万円で済みます。
このように、孫への相続方法によって税負担が大きく変わるため、事前の試算と対策が重要です。
小規模宅地等の特例で土地評価額を最大80%減額
小規模宅地等の特例※は、一定の条件を満たす土地について、相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
この特例は孫が相続する場合でも適用できる可能性があり、大幅な節税効果が期待できます。
特例が適用される主なケースは、居住用宅地(特定居住用宅地等)と
事業用宅地(特定事業用宅地等)です。
居住用宅地の場合、330平方メートルまでの部分について評価額を80%減額でき、事業用宅地の場合は400平方メートルまでが対象となります(租税特別措置法69条の4)。
孫が特例を受けるための要件は、配偶者や同居親族が相続する場合と基本的に同じです。
居住用宅地の特例を受けるには、孫が祖父母と同居していたこと、相続税の申告期限まで引き続き居住し所有し続けることが必要です。
ただし、配偶者や同居している子がいない場合は、別居している孫でも「家なき子特例」により適用を受けられる可能性があります。
例えば、評価額5,000万円の土地に特例を適用すると、評価額は1,000万円に減額され、相続税の大幅な節税につながります。
特例の適用要件は複雑なため、専門家に相談して正確に判断することをおすすめします。
※小規模宅地等の特例:一定要件を満たす宅地について相続税評価額を減額できる制度
未成年の孫が相続する場合の税額控除と代理人制度
未成年の孫が土地を相続する場合、未成年者控除※という税額控除を受けることができます。
未成年者控除は、相続人が18歳未満の場合、18歳に達するまでの年数1年につき10万円を相続税額から控除できる制度です(相続税法19条の3)。
例えば、10歳の孫が相続した場合、18歳まで8年あるため、80万円(10万円×8年)を相続税額から差し引くことができます。
ただし、孫への相続で2割加算が適用される場合は、加算後の税額から未成年者控除を差し引くことになります。
未成年者が相続する場合、遺産分割協議には特別代理人※の選任が必要になるケースがあります。
親権者である親も相続人となる場合、親と子(孫)の利益が相反するため、家庭裁判所に
特別代理人の選任を申し立てる必要があります(民法826条)。
特別代理人は通常、孫の祖父母や叔父叔母など、利害関係のない親族が選任されます。
また、未成年者が相続した土地の管理や処分には親権者の同意が
必要で、売却する場合は家庭裁判所の許可が必要になることもあります。
未成年の孫が相続する場合は、法的手続きが複雑になるため、早めに司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
※未成年者控除:18歳未満の相続人に対する相続税の控除制度 ※特別代理人:親権者と子の利益が相反する場合に家庭裁判所が選任する代理人
特に未成年の孫が相続する場合は、特別代理人の選任など法的手続きも複雑になるため、相続発生前から専門家に相談し、最適な対策を講じることをおすすめします。
FAQ
Q. 孫への相続税2割加算とは?
A. 孫が相続する場合、相続税額が1.2倍に増額される制度です。
Q. 小規模宅地特例の要件は?
A. 孫が祖父母と同居し相続税申告期限まで居住継続が必要です。
Q. 未成年の孫が相続できる?
A. 可能ですが特別代理人の選任など特別な手続きが必要です。
孫への土地相続手続きと失敗しないための対策
孫への土地相続を実現するには、適切な手続きと事前の対策が欠かせません。
代襲相続の証明、遺言の作成、生前贈与との比較など、それぞれの方法に応じた準備が必要です。
ここでは、孫への土地相続の具体的な手続きと、トラブルを避けるための実践的な対策について解説します。
代襲相続の場合に必要な戸籍書類と相続登記の流れ
代襲相続により孫が土地を相続する場合、相続登記には通常の相続よりも多くの戸籍書類が必要になります。
まず、被相続人(祖父母)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、相続人を確定します。
次に、代襲原因を証明するため、本来の相続人(親)の出生から死亡までの戸籍謄本も必要です。
さらに、代襲相続人である孫の現在戸籍も準備します。
これらの書類を揃えるには、複数の市区町村に戸籍請求をする必要があり、通常1か月程度の期間を要します。
相続登記※の申請書には、「代襲相続」と明記し、登記原因を「年月日相続(代襲)」と記載します。
相続登記には登録免許税※がかかり、税率は固定資産税評価額の0.4%です。
例えば、評価額2,000万円の土地であれば、8万円の登録免許税が必要になります。
相続登記は2024年4月から義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があるため、早めの手続きが重要です(不動産登記法76条の2)。
手続きが複雑で不安な場合は、司法書士に依頼することで、書類収集から登記申請まで一括して対応してもらえます。
※相続登記:相続により不動産の所有権が移転したことを登記簿に記録する手続き ※登録免許税:不動産の登記をする際に国に納める税金
遺言で孫に土地を渡す際の遺留分トラブル回避策
遺言書で孫に土地を遺贈する場合、他の相続人の遺留分を侵害しないよう配慮することが重要です。
遺留分とは、法律で保障された最低限の相続分で、配偶者や子(直系卑属)、父母(直系尊属)に認められています。
例えば、祖父の遺産総額が5,000万円で、相続人が配偶者と子2人の場合
配偶者の遺留分は4分の1(1,250万円)、子1人あたりは8分の1(625万円)です。
このケースで、評価額3,000万円の土地を孫に遺贈すると、子の遺留分を侵害する可能性が
高く、遺留分侵害額請求※をされるリスクがあります。
遺留分トラブルを避けるには、事前に遺産全体の評価額を把握し、遺留分を侵害しない範囲で遺贈する内容を決めることが大切です。
また、生前に相続人全員と話し合い、孫への遺贈について理解と同意を得ておくことも有効です。
遺言書には、孫に土地を遺贈する理由を付言事項として記載することで、遺言者の意思を明確に伝えることができます。
公正証書遺言※を作成する際には、公証人が遺留分への配慮についても
アドバイスしてくれるため、専門家の助言を受けながら作成することをおすすめします。
万が一、遺留分侵害額請求をされた場合は、遺贈された土地以外の財産で金銭を支払うか、土地の一部を譲渡するなどの対応が必要になります。
※遺留分侵害額請求:遺留分を侵害された相続人が、侵害額に相当する金銭の支払いを請求すること ※公正証書遺言:公証人が作成する法的に確実性の高い遺言書
生前贈与と相続の税負担比較|どちらが有利か
孫に土地を渡す方法として、相続ではなく生前贈与※1を選択することも可能です。
どちらが有利かは、土地の評価額、孫の年齢、他の財産状況などによって変わります。
生前贈与の場合、年間110万円までの基礎控除があり、この範囲内であれば贈与税はかかりません。
また、直系尊属から成年の子や孫への贈与には、相続時精算課税制度※2を利用でき、2,500万円まで贈与税が非課税になります(相続税法21条の9)。
ただし、相続時精算課税を選択すると、贈与者が亡くなった際に贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算するため、結果的に税負担が変わらないこともあります。
一方、相続で土地を取得する場合は、小規模宅地等の特例により評価額を最大80%減額できる可能性があります。
例えば、評価額5,000万円の土地を生前贈与すると、贈与税は数百万円かかりますが、相続で取得して
特例を適用すれば、評価額は1,000万円となり、相続税は大幅に軽減されます。
ただし、孫への相続は2割加算の対象となるため、代襲相続以外の方法では税負担が増加します。
生前贈与と相続のどちらが有利かは、個別の状況によって異なるため、税理士に試算を依頼し、最適な方法を選択することをおすすめします。
また、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されるルール※3があるため、贈与を検討する場合は早めの実行が重要です(相続税法19条)。
参考:贈与税 – 国税庁
※1 生前贈与:生きている間に財産を無償で譲り渡すこと
※2 相続時精算課税制度:贈与時に贈与税を軽減し相続時に精算する制度
※3 相続財産に加算されるルール:2024年(令和6年)1月1日以降の贈与から、この加算期間が段階的に延長され、最終的に7年間(贈与のあった年を基準として、相続開始前3年が4年に、その後3年間で7年に)になります。
FAQ
Q. 相続登記の期限は?
A. 相続を知った日から3年以内に申請が義務化されています。
Q. 遺留分侵害のリスクは?
A. 孫への遺贈が他の相続人の遺留分を侵害すると請求されます。
Q. 生前贈与と相続どちらが得?
A. 土地の評価額や家族状況により異なるため専門家への相談が必要です。
まとめ:孫への土地相続は専門家への早めの相談が重要
孫が祖父母の土地を相続する方法には、代襲相続、遺言による遺贈、養子縁組の3つがあります。
代襲相続の場合は相続税の2割加算が適用されませんが、遺言や養子縁組の場合は2割加算の対象となるため、税負担が増加します。
一方で、小規模宅地等の特例を活用すれば、土地の評価額を最大80%減額でき、大幅な節税が可能になります。
孫への土地相続を実現するには、相続登記に必要な
戸籍書類の収集、遺留分への配慮、生前贈与との比較検討など、様々な準備が必要です。
特に未成年の孫が相続する場合は、特別代理人の選任など法的手続きも複雑になります。
手続きや税務の判断は専門的で複雑なため、早めに司法書士や税理士に相談し、最適な方法を選択することが重要です。
当事務所では、孫への土地相続に関する無料相談を実施しております。
相続方法の選択、税負担のシミュレーション、手続きの代行まで、トータルでサポートいたしますので、お気軽に無料相談をご利用ください。
この記事の監修者

遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。