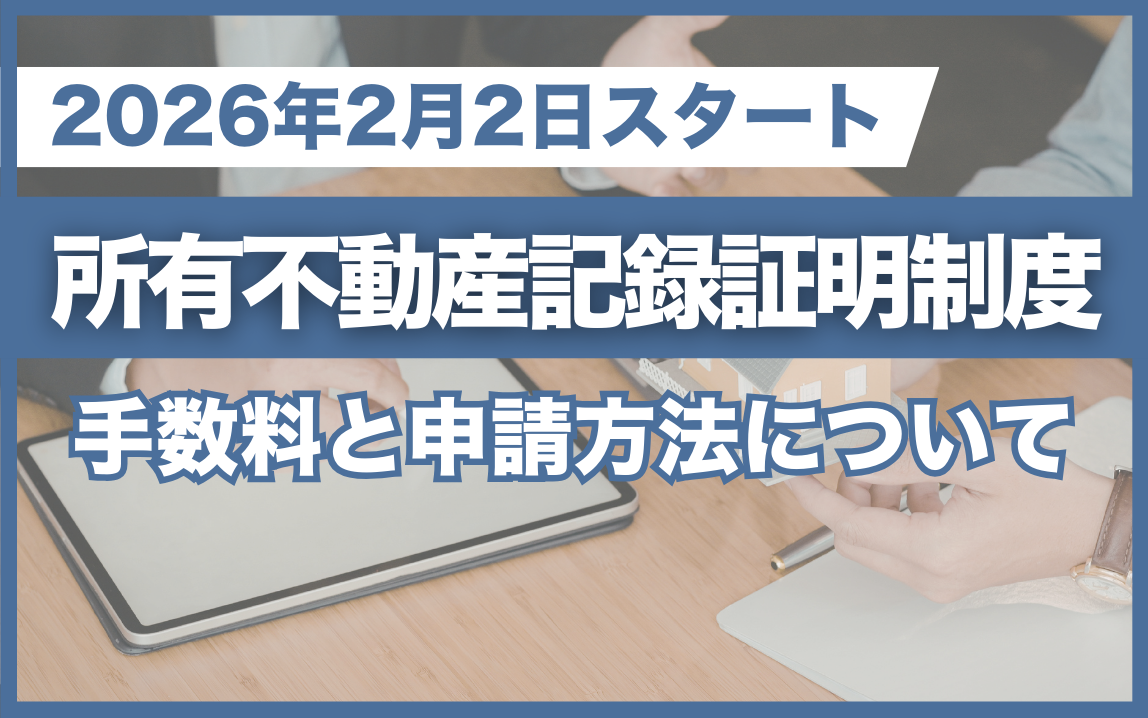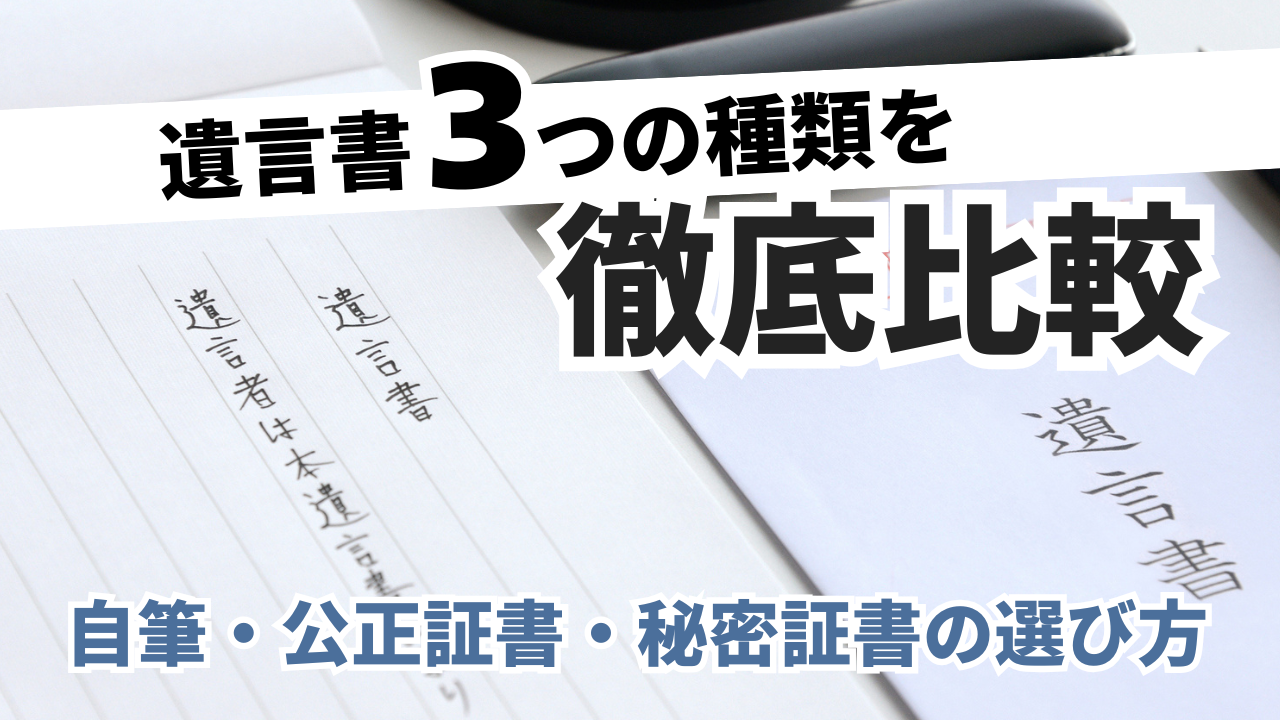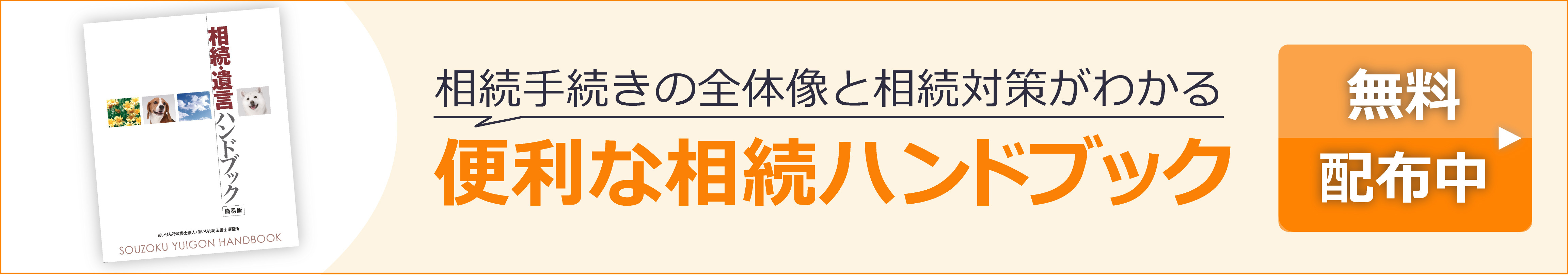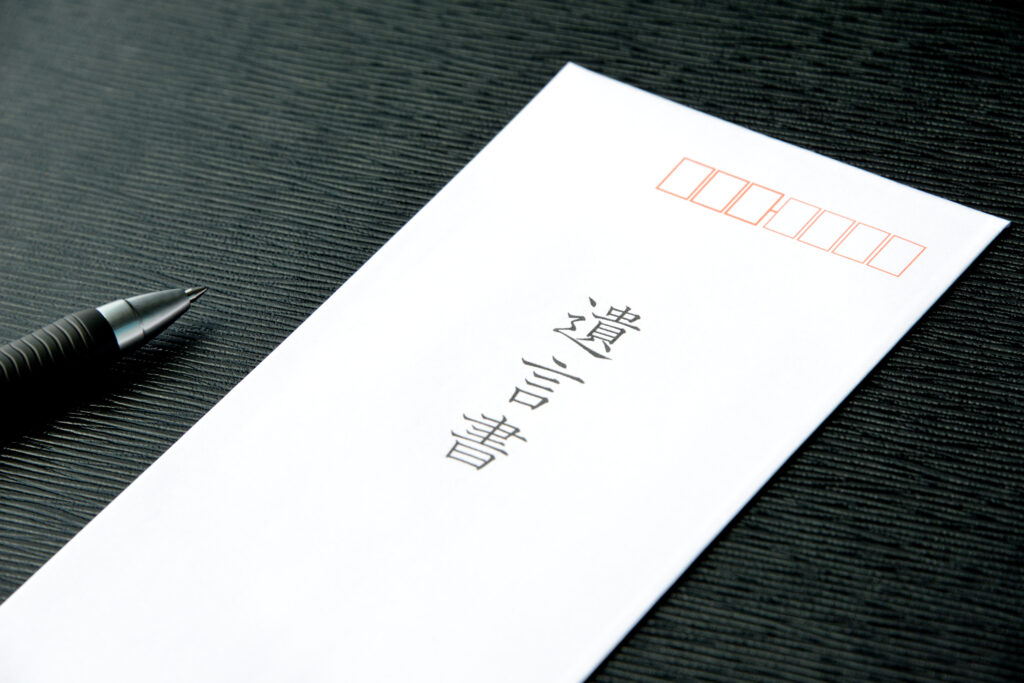
人が死亡すると所有していた財産は相続人に承継されます。「民法」という法律の中で各相続人が承継する割合が決められています。これを「法定相続分」といいます。ただ、必ずしも法定相続分どおりに遺産を分配しないといけないというわけではありません。例えば、亡くなった人(被相続人)の最後の意志は尊重すべきであり、相続人全員で合意して分配方法を決めることは問題ありません。
今回は、被相続人の最後の意志を財産承継に反映させる「遺言」について説明した上で、遺言などによる不利益を調整するための権利である「遺留分」について解説していきます。まずは、民法に定められている法定相続分の割合をみていくことにしましょう。
法定相続分とは?
法定相続分とは、どのくらいの割合で相続人が財産をもらうか法律で決められています。
相続人の属性ごとに詳しくご紹介していきます。
①配偶者
配偶者がいる場合は、必ず相続人となります。
配偶者の相続分は配偶者の他にどのような続柄の相続人がいるかによって変わります。
②子供がいる場合
配偶者と子供がいる場合は、配偶者が2分の1、子供が2分の1の割合で相続します。
例えば、配偶者と子供3人がいる場合に、被相続人が600万円の遺産を残しているケースでは、配偶者が2分の1の300万円、子供3人で300万円を承継します。
子供1人あたりでは100万円となるでしょう。
(民法第900条第1号)
③子供がおらず親(祖父母)が存命の場合
子供はおらず、配偶者と被相続人の親(両親ともに死亡しているが、祖父母が存命の場合は祖父母)がいる場合は、配偶者3分の2、親3分の1の割合で承継します。
例えば、遺産全体の額が600万円である場合は、配偶者が400万円、親が200万円となるでしょう。
両親ともに存命であれば、一人100万円ずつとなります。
(民法第900条第1項第2号)
④子供も親(祖父母)もいない場合
子供もおらず、親(祖父母)も全員死亡している場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
例えば、遺産全体の額が600万円の場合は、配偶者が450万円、兄弟姉妹が150万円となります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、150万円を兄弟姉妹の頭数で分割することになります。
(民法第900条第3号)
遺言書の効力
(民法第985条)
遺言とは、前述のとおり被相続人の最後の意志を遺産承継に反映させるものです。
遺言は、原則として遺言を作成した人(被相続人)が死亡した時に効力が生じます。
以前書いた遺言を書きかえたいと思った場合は、何度でも書きかえることが可能です。
後の遺言がその効力を持ちます。
遺言を作成するにあたっては、以下の2点が注意点です。
①遺言の作成方式が民法の規定に違反していないこと。
②遺言者に意思能力があること。
この両方に当てはまらないと無効になります。
ここでは、普通の遺言方式である3種類を説明します。
遺言書の種類
遺言書の種類は、以下の3つになります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
①自筆証書遺言(民法第968条)
自筆証書遺言は、一番簡単に作成できる方式の遺言です。
ただし、民法の中に自筆証書遺言の作成上のルールが規定されており、ルールを間違えると無効になる場合があります。
とはいえ、さほど難解なルールが規定されているわけではありません。
誰に何の財産を残したいかを自筆で書き、最後に作成した日付と氏名を自署し押印する、というのが基本ルールです。
例えば、日付を書き忘れると無効になります。
必ず自筆でなければならず、パソコンなどで作成したものも自筆証書遺言としては無効となります。
ただし、本文とは別に財産だけをまとめて「財産目録」の別ページとして作成する場合は財産目録のみパソコンで作成可能です。
財産目録のページ下部の余白などに氏名を自署して押印します。
押印は実印である必要はなく、認印でかまいません。
令和2年7月10日に自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる新しい制度が施行されました。
自筆証書遺言を法務局へ持っていき、法務局で保管してもらう制度です。
自筆証書遺言の紛失を防ぐことができます。
保管申請の際には、法務局で形式上の不備をチェックするため、書き方のルールに反して無効になることはありません。
遺言者の死亡後50年間は原本を保管してもらえるため紛失や偽造などの心配もありません。
手数料は3,900円ですからリーズナブルな制度となっています。
自筆証書遺言の法務局保管制度に関しては、法務省のホームページをご参照ください。
この保管制度を利用するとデメリットとされていた形式上だと無効になるという点をカバーできます。
しかし、法務局では遺言者の意思能力の有無は審査しないため、後に相続人から意思能力をめぐる争いが起きる可能性は否定できません。
なお、自筆証書遺言は遺言者の死後に家庭裁判所にて検認手続きをしないといけませんが、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した場合は検認手続きは必要ありません。
②公正証書遺言(民法第969条)
公正証書遺言は、もっとも確実な方式の遺言です。
各地に「公証役場」があり元裁判官や元弁護士などの法曹界で活躍した公証人が常駐しており、公証人に作成してもらう遺言です。
公正証書遺言は、公証人に事前に遺言の内容を打ち合わせします。
具体的な日時や場所を決めて、2人以上の証人の立ち会いの下、あらかじめ公証人が作成した遺言書を読み上げて遺言者にその内容を確認します。
法律家である公証人が作成することにより作成方法を誤ることはありません。
遺言者の意思能力を確認した上で作成するため、後に争いが起きる可能性は極めて低くなります。
公証人役場には遺言の原本を遺言者が120歳に達する年まで保管されるため、紛失する心配もありません。
さらに、寝たきりであるといった場合でも公証人が出張してくれるため、意思能力さえあればどのような状態でも基本的に作成が可能です。
公正証書遺言のデメリットとしては、費用がかかる点のみといってもよいです。
③秘密証書遺言(民法第970条)
秘密証書遺言は、自分で遺言を作成して封をしてから公証人役場に持っていきます。
公証人と証人2人以上が立ち会い、その遺言が自分の遺言書であることを申述して公証人がそれを証明します。
遺言書は封をして持参するため、公証人も証人も内容を見ることはできません。
秘密証書遺言の作成は、自筆でもパソコンでもかまいません。
秘密証書遺言の制度を利用する目的は、内容を誰にも知られることなく、遺言書が自分のものであることを公証人に証明してもらい、公証人役場に記録してもらう点にあります。
メリットとしては誰にも遺言内容を知られないという点です。
一方で、公証人の証明があっても、内容自体に法的な不備がないかは確認できないため、そこは大きなデメリットであり、利用者数の少ない方式といえます。
公正証書がオススメ
以上のとおり普通方式の遺言は3種類あります。
しかし、せっかく最後の意志として作成したにもかかわらず、法律的に無効になったり争いの原因となっては意味がありません。
費用はかかりますが、その他のデメリットをすべてカバーできる公正証書遺言を利用することをおすすめします。
遺言書を破棄などの罰則
遺言書は検認手続きを経ずに勝手に開封すると5万円以下の過料が課せられる場合があります。
自分に不都合な遺言であるからといって、隠したり破棄したりした場合には、相続欠格という相続権を失う結果になるため注意しましょう。
(民法第891条第5号)
遺言を作成した方がよい場合
遺言はどのような場合に作成した方がよいのでしょうか。
作成した方がよいケースについて紹介します。
相続人間で争いが起こりそうな場合
相続人同士の仲が悪いため、自分の死後に遺産をめぐる争いが起こることが予想されるような場合があります。
その場合は、遺言を残すことにより相続人同士が話し合いや裁判などで争うことを避けることができます。
子供も親(祖父母)もいないため、兄弟姉妹に相続分があるが、配偶者に残したい場合
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合には、配偶者にすべてを残して、自分が亡き後の生活に役立ててほしいと思う場合も多いでしょう。
そのような場合には遺言の作成が必要なケースといえます。
特にお世話になったなど、特別の想いがある場合
生前に特別にお世話になった人がいる場合に、その人に遺産を残したいと考える場合にも遺言の作成は欠かせません。
相続人や親族でなくても、遺産を残すことができます。
遺留分とは?
遺留分という言葉の意味や目的が分からない人も多いでしょう。
そのため、遺留分の意味や目的について詳しく紹介し、遺留分の割合をケースごとにお伝えします。
意味・目的
遺留分は、法定相続人に最低限保証された権利です。
例えば、遺言で全財産をある相続人にすべて相続させると書かれていた場合は、他の相続人は1円ももらえないことになってしまいます。
しかし、これではあまりにも不憫なため最低限受け取れる権利を保証し、その分を取り戻すことを規定するものです。
遺留分の割合(民法第1042条)
では「最低限保証された権利」とはどれぐらいのものでしょうか。
遺留分は、兄弟姉妹が相続人となる場合には遺留分はありません。
つまり、遺留分をもつのは、配偶者、子供、親(祖父母)が相続人となる場合です。
遺留分の割合についてケースごとに説明していきます。
①「直系尊属のみが相続人である場合」
3分の1が法律の規定となります。
これは、相続財産の3分の1が遺留分の額を算定する基準となる、という意味です。
例えば相続財産が3,000万円である場合には、その3分の1である1,000万円が遺留分の基準となります。
さらに、直系尊属ですから被相続人の父母共に存命であれば、一人あたりの遺留分額は500万円となります。
②「直系尊属以外が相続人の場合」
2分の1が法律の規定です。
こちらも①と同様に考えます。
例えば、相続人が被相続人の妻と子供2人で相続財産が3,000万円の場合、その2分の1が遺留分算定の基礎となるため1,500万円です。
これに相続人それぞれの法定相続分を掛けます。
すなわち、妻は2分の1、子供は1人4分の1ずつなため、それぞれの遺留分額は妻750万円、子供は1人325万円となります。
遺留分侵害額請求とは?(民法第1046条)
遺言などにより上記の遺留分さえも受け取れない場合には、多くもらった人に対し遺留分との差額を返してもらうよう請求できます。
これを「遺留分侵害額請求」といい、遺留分侵害額請求は請求しなければ取り戻すことはできません。
請求するかどうかはそれぞれの相続人に委ねられています。
消滅時効と除斥期間
遺留分侵害額請求について詳しく理解するためにも、消滅時効と除斥期間の2つについて知りましょう。
消滅時効 (民法第1048条前段)
民法では、「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する」と規定されています。
遺留分侵害額請求をされるかどうか不明なままいつまでも不安な状態になり、被相続人が遺言を残した意味がないからです。
この時効の規定は「知った時から1年」となっているため、主観的な要件が入ってきますが、もうひとつ主観的な要件が入らない規定があります。
除斥期間(民法第1048条後段)
「相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする」と時効の規定に続いて記載されており、知ったかどうかにかかわらず、相続開始すなわち被相続人が死亡してから10年経過すると遺留分侵害額請求はできなくなります。
これを除斥期間といいます。
上記の時効かまたは除斥期間のどちらかが到来すれば、遺留分侵害額請求権は消滅します。
遺言で遺留分を排除できるか
遺言で遺産を残したにもかかわらず、後で取り返しの請求をされるとすれば、被相続人としての想いは十分に叶えられないことになります。
しかし、遺留分は遺言で排除したりはできません。
遺留分侵害額請求をされないためには、各相続人が遺留分に相当する額を受け取れるような内容の遺言にすることが対策として考えられます。
結果的にはあげたい人の取り分が減ることにはなりますが、後で遺留分侵害額請求をされることを考えれば、精神的負担は少ないといえます。
まとめ
今回は、遺言と遺留分について説明してきました。
遺言を作成する場合には法的に不備がないようにしなければ、せっかく残した最後の意志が叶わない結果になります。
遺留分に配慮した遺言を残すことを考えると、法律知識と複雑な計算を要する場合もあります。
遺言作成をされる場合は司法書士や弁護士に相談しながら進めるのがよいでしょう。
遺留分侵害額請求の際は請求額の算定が難しいため、専門家の知識を借りることをおすすめします。
あいりん行政書士法人でも遺言のご依頼を受けております。
まずはお気軽に、無料相談をご利用ください。