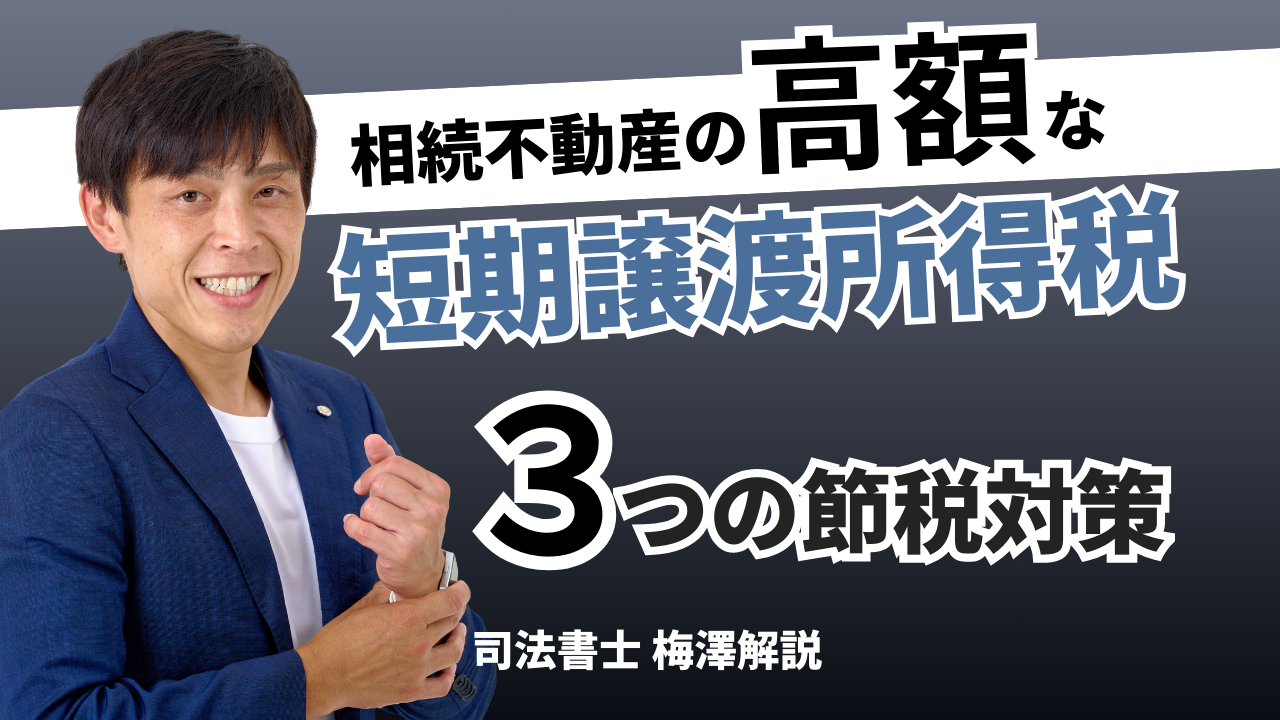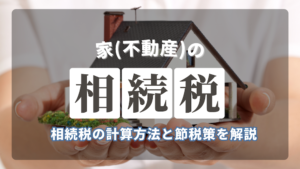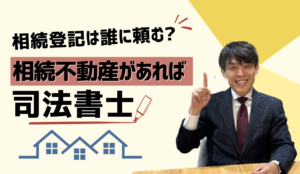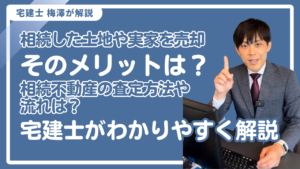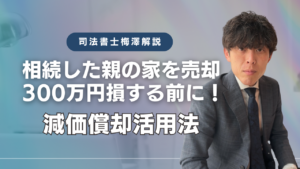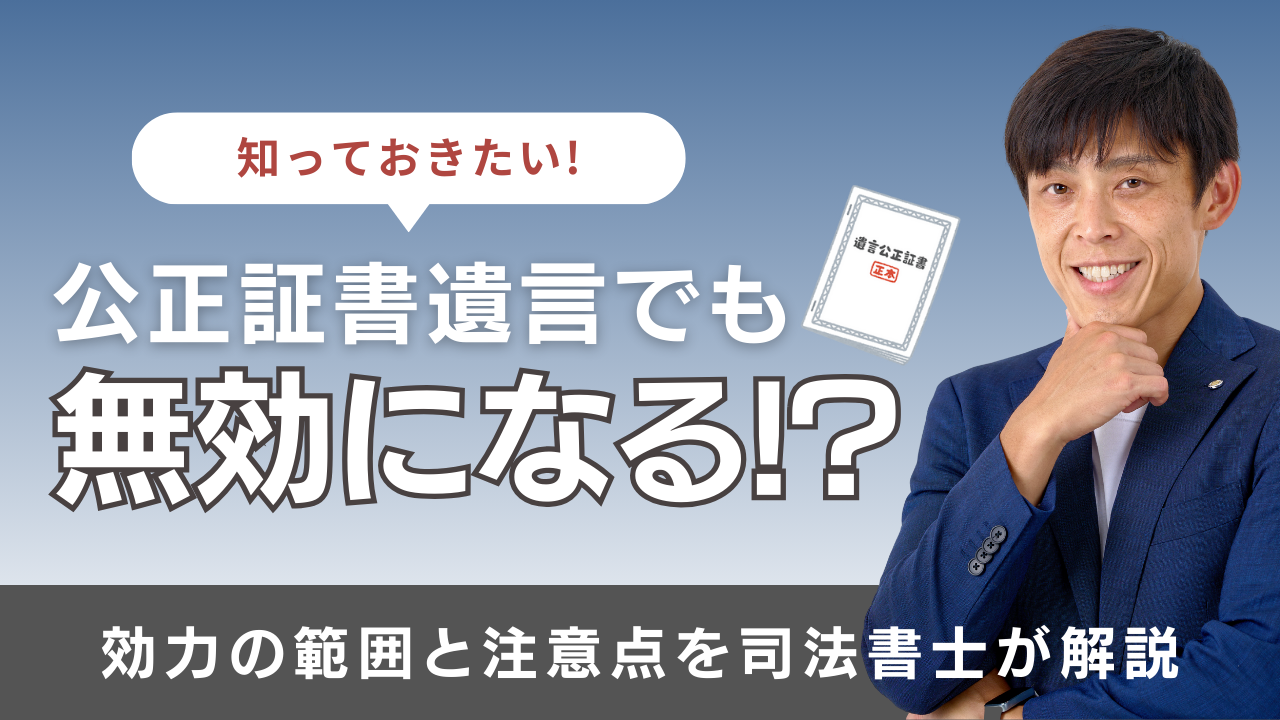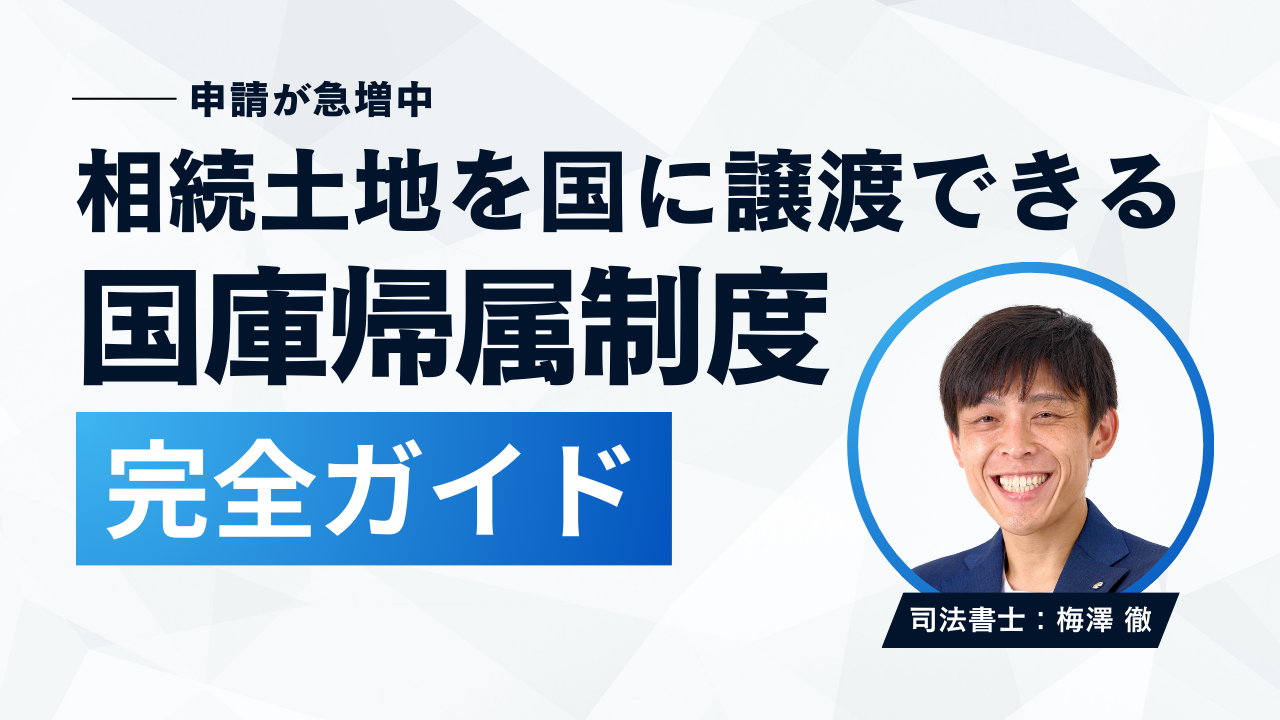この記事を要約すると
- 短期譲渡所得の税率39.63%は長期譲渡の約2倍で相続では被相続人の取得日を引き継ぐ
- 居住用財産3,000万円控除と相続税取得費加算特例で短期譲渡でも大幅な節税が可能
- 相続登記義務化と取得費証明と特例適用漏れが短期譲渡の3つの落とし穴で要注意
相続した不動産を早めに売却したいと考えているものの、短期譲渡所得税の39.63%という高い税率を知って驚いた方も多いのではないでしょうか。
しかし、適切な特例を活用すれば、短期譲渡でも税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
この記事では、相続不動産の短期譲渡における税制のしくみと、実務で使える3つの節税対策を司法書士が分かりやすく解説します。
この記事はこんな方におすすめ
- 相続した不動産を5年以内に売却しようと考えている方
- 短期譲渡所得税の39.63%という高い税率に驚いて対策を探している方
- 相続不動産の短期譲渡で使える特例や節税方法を知りたい方
目次
相続不動産の短期譲渡とは|税率39.63%が適用される条件
相続した不動産を売却する際、所有期間によって税率が大きく変わります。
短期譲渡所得※に該当すると、39.63%という高い税率が適用され、長期譲渡所得の約2倍の税負担が発生します。
ここでは、短期譲渡所得の基本的なしくみと、相続不動産特有のルールについて解説します。
短期譲渡所得の定義|所有期間5年以内で税率2倍に
不動産の譲渡所得は、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以内の場合は短期譲渡所得(税率39.63%)、5年を超える場合は長期譲渡所得(税率20.315%)に分類されます。
例えば、2020年3月に取得した不動産を2025年2月に売却した場合、2025年1月1日時点ではまだ5年に達していないため、短期譲渡所得となります。
短期譲渡所得の高い税率は、主に投機的な取引を抑制する目的で設けられていますが、相続不動産の売却でも適用されるため注意が必要です。
相続不動産は被相続人の取得時期を引き継ぐ特例ルール
相続した不動産の所有期間は、相続人が相続した日からではなく、被相続人(亡くなった方)が取得した日から計算するという特例(所得税法第60条)があります。
例えば、父親が30年前に購入した実家を相続後すぐに売却した場合でも、父親の取得時期を引き継ぐため長期譲渡所得として扱われます。
この特例により、多くの相続不動産は長期譲渡の低い税率が適用されます。
ただし、被相続人が取得してから5年以内に相続が発生し、その後すぐに売却する場合は短期譲渡所得となります。
売却前に、被相続人の取得時期を売買契約書や登記簿謄本で必ず確認しておきましょう
参考:相続又は遺贈により取得した資産の取得費及び取得の時期 – 所得税法第60条
短期譲渡と長期譲渡の税額差|1,000万円で約200万円の違い
譲渡所得が1,000万円の場合
短期譲渡所得では約396万円(1,000万円×39.63%)、
長期譲渡所得では約203万円(1,000万円×20.315%)
の税金がかかり、その差は約193万円にもなります。
所有期間の判定が短期か長期かによって、税負担が数百万円単位で変わるため、売却時期の選択は慎重に行う必要があります。
※譲渡所得:不動産を売却したときの利益で、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額
FAQ
Q. 短期譲渡所得の税率は?
A. 所得税30.63%と住民税9%の合計39.63%です。
Q. 相続不動産の所有期間の計算は?
A. 被相続人が取得した日から計算するため相続日ではありません。
Q. 短期と長期の税額差は?
A. 譲渡所得1,000万円で約193万円の差が生じます。
相続不動産の短期譲渡で使える3つの特例と節税効果
短期譲渡所得の高い税率は大きな負担ですが、一定の要件を満たせば税負担を大幅に軽減できる特例があります。
| 特例 | 控除額・効果 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 居住用財産3,000万円特別控除 | 最高3,000万円控除 | 短期・長期とも適用可能、譲渡所得2,500万円以下なら税額ゼロ、相続開始から3年以内なら適用可能 | 住宅ローン控除と併用不可、売却する相続人の居住要件あり |
| 相続税の取得費加算特例 | 相続税の一部を経費化 | 相続税と譲渡所得税の二重課税を緩和、短期譲渡では節税効果大、相続税500万円で約198万円節税 | 相続税申告期限から3年以内の売却が条件、相続税を納付していることが必要 |
| 長期譲渡への切り替え | 税率が39.63%→20.315% | 譲渡所得1,000万円で約193万円節税、1年待つだけで大幅節税、確実な節税方法 | 保有期間中の固定資産税・管理費負担、不動産価格下落リスク、すぐに売却できない |
居住用財産3,000万円特別控除で短期譲渡でも税額ゼロに
参考:居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例 – 国税庁
マイホームを売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
この特例は短期譲渡所得でも長期譲渡所得でも適用可能です。
特に、相続した実家を売却する場合、相続人が住んでいた場合、または被相続人が亡くなる直前まで住んでいた家(空き家特例)を相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば適用可能です。
例えば、短期譲渡所得が2,500万円の場合、3,000万円の特別控除を適用すれば課税対象となる所得はゼロとなり、税金は一切かかりません。
これは短期譲渡の税率39.63%で計算した場合、約991万円もの節税効果があります。
ただし、この特例を適用すると住宅ローン控除との併用ができないため、慎重な判断が必要です。
相続税の取得費加算特例|短期譲渡3年以内なら相続税を経費化
相続によって不動産を取得し、相続税を納付した場合、その不動産を相続税の申告期限から3年以内に売却すれば、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例です。
これは、相続税と譲渡所得税の二重課税を緩和するための制度です。 短期譲渡所得(39.63%)に該当する場合、この特例の活用は非常に重要です。
【節税効果の具体例】
例えば以下の場合を考えてみましょう。
• 不動産売却により課税対象となる譲渡所得が1,500万円
• 特例により取得費に加算できる相続税額が500万円
この場合、課税対象となる譲渡所得は1,500万円 – 500万円 = 1,000万円に圧縮されます。 税率39.63%で計算すると、約198万円の節税効果が得られます。
この特例は期限があるため、短期譲渡を検討している場合は必ず活用すべき制度です。
短期譲渡を避けて長期譲渡にする売却タイミング戦略
被相続人の取得時期から5年を超えていない場合、売却を少し待つことで短期譲渡所得から長期譲渡所得に切り替えることができ、大幅な節税につながります。
譲渡所得が1,000万円の場合、1年待って長期譲渡(20.315%)に切り替えることで、約193万円の節税効果が得られます。
ただし、売却を待つ間の固定資産税や維持管理費、不動産価格の下落リスクなども総合的に考慮し、判断する必要があります。
節税効果が待機コストを上回るかどうかを計算することが重要です。
個別の状況により最適解が異なるため、まずは無料相談で専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
FAQ
Q. 3,000万円特別控除の適用期限は?
A. 被相続人が居住していた家は相続開始から3年以内の売却が条件です。
Q. 相続税の取得費加算特例の期限は?
A. 相続税の申告期限から3年以内に売却することが必要です。
Q. 短期から長期に切り替えるには?
A. 売却年の1月1日時点で取得から5年超が条件です。
相続不動産を短期譲渡する際の3つの落とし穴と対策
短期譲渡する際には、高い税率以外にも手続き上の注意点があります。
短期譲渡でも相続登記は必須|義務化で10万円以下の過料
2024年4月から相続登記※が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続不動産を売却する際、買主への所有権移転登記を行うためには、前提として売主(相続人)への相続登記が必要です。
実務上は、売買契約後、決済日までに相続登記を完了させ、決済日に買主への所有権移転と同時に行うことが一般的です。
短期譲渡を予定している場合は、売却活動と並行して、相続発生後すぐに司法書士に相談し、決済日に間に合うよう相続登記の手続きを開始することが肝心です。
登記が完了していない状態では決済・引渡しができないため、早めの対応が必須です。
※相続登記:相続によって不動産の所有者が変わったことを法務局に届け出る手続き
短期譲渡の税額計算ミス|取得費不明で税負担が2倍以上に
譲渡所得を計算する際、取得費(購入時の価格や購入にかかった費用)を売却価格から差し引くことができます。
相続した不動産の場合、古い契約書などが見つからないことがよくあります。
取得費が不明な場合、売却価格の5%を概算取得費※として計算することになり、これが実際の取得費よりもはるかに少ないと、譲渡所得が大きくなり税負担が増加します。
特に短期譲渡所得では39.63%という高い税率が適用されるため、影響が深刻です。
例えば、5,000万円で売却し概算取得費(250万円)を適用した場合、実際の取得費が3,000万円だった場合と比べて、約693万円もの税金が増える計算になります。
通帳の記録や固定資産税の評価額の推移など、取得費を立証できる資料を徹底的に探すことが重要です。
※概算取得費:取得費が不明な場合に、売却価格の5%を取得費として計算する方法
短期譲渡の確定申告|特例適用漏れで数百万円の損失リスク
不動産を短期譲渡した場合、売却した年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があります。
居住用財産の3,000万円特別控除や相続税の取得費加算特例は、確定申告で適用を申請しなければ自動的には適用されません。
これらの特例適用を漏らすと、本来は税金がかからなかったはずが、数百万円単位の納税が発生するリスクがあります。
例えば、短期譲渡所得が2,000万円で3,000万円特別控除を適用し忘れた場合、約793万円の税金を支払うことになってしまいます。
手続きが複雑で不安な場合は、必ず税理士に相談し、期限内に正確な申告を行うことが重要です。
※確定申告:1年間の所得と税額を計算して税務署に申告する手続きで、譲渡所得がある場合は必須 参考:確定申告書の提出期限 – 国税庁
手続きの漏れや誤りで数百万円の損失を出さないよう、まずは無料相談で専門家のサポートを受けることをおすすめします。
FAQ
Q. 相続登記の期限は?
A. 相続を知った日から3年以内で違反すると10万円以下の過料です。
Q. 取得費不明の場合は?
A. 売却価格の5%を概算取得費として計算しますが税負担が大きくなります。
Q. 確定申告の期限は?
A. 売却翌年の2月16日から3月15日までです。
まとめ:相続不動産の短期譲渡は特例活用で税負担を大幅軽減
相続した不動産を短期譲渡すると、39.63%という高い税率が適用されますが、「居住用財産の3,000万円特別控除」や「相続税の取得費加算特例」などを期限内に活用することで、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
短期譲渡の落とし穴としては、相続登記の早期着手、取得費の証明資料の確保、確定申告での特例適用漏れがあり、これらを適切に処理しないと数百万円単位で損をする可能性があります。
最適な売却タイミングや特例の適用判断は個別の状況によって異なるため、まずは専門家に相談することをおすすめします。
この記事の監修者

遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。