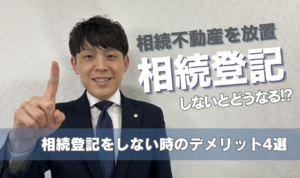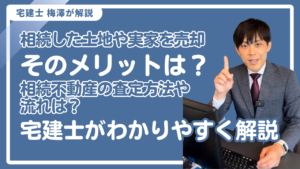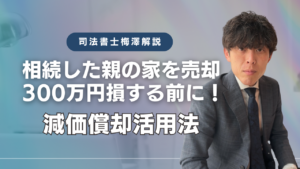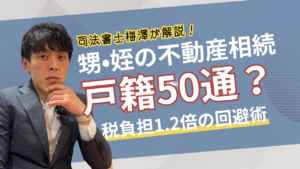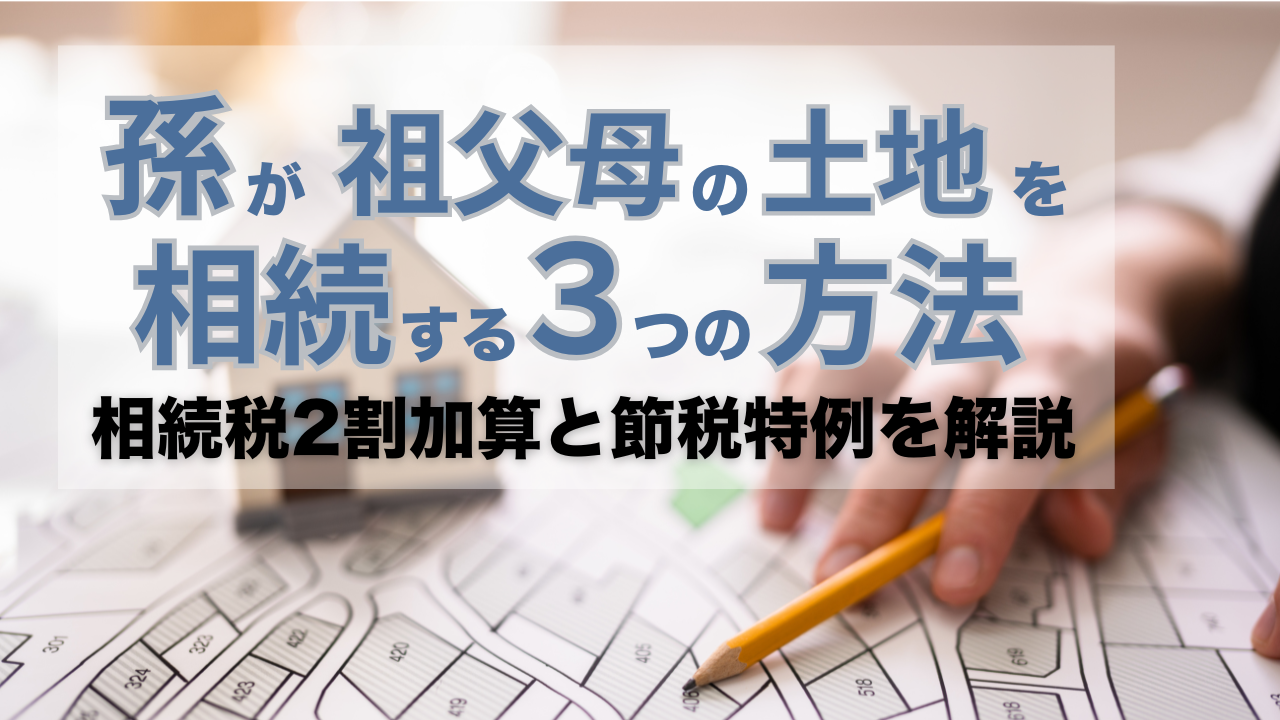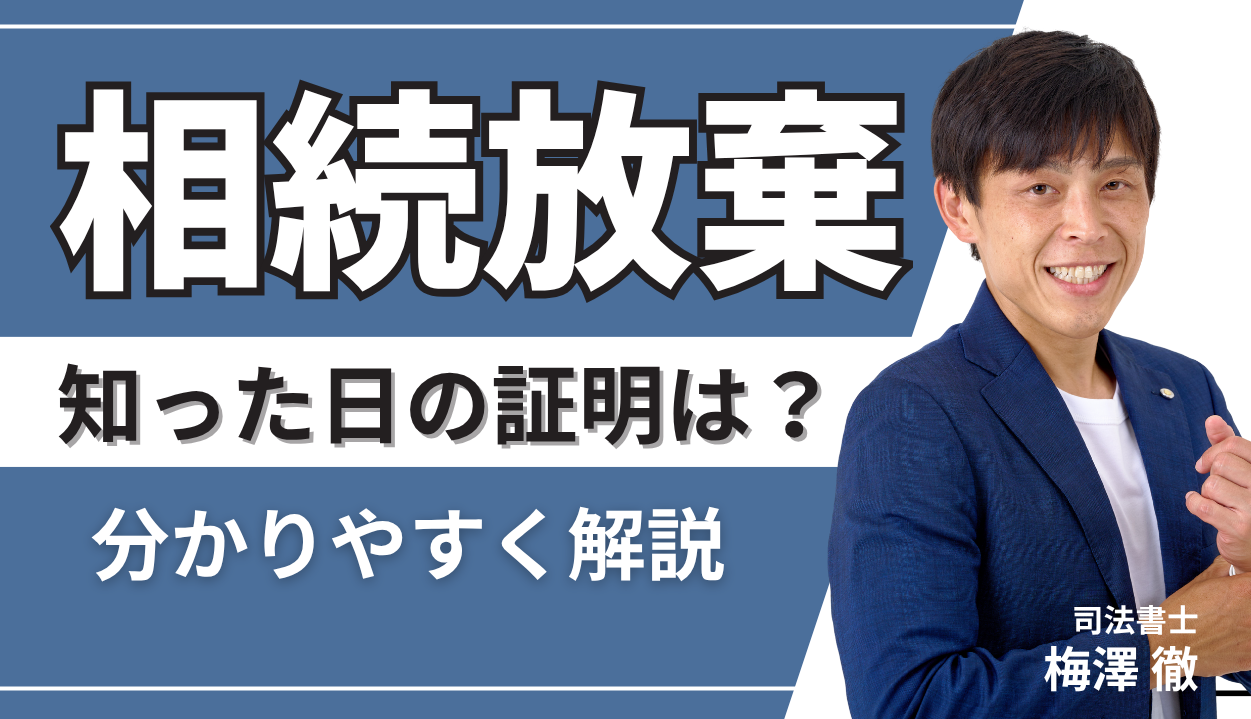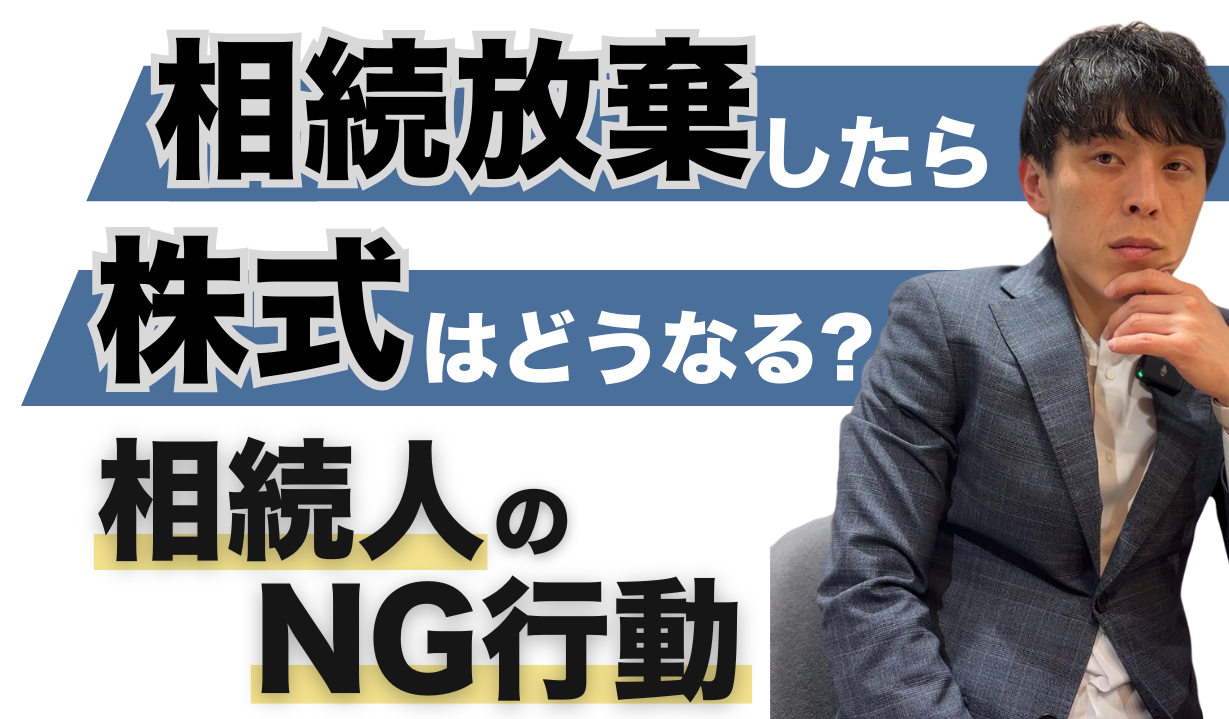この記事を要約すると
- 相続不動産の中間省略登記は原則不可、数次相続のみ例外的に認められる
- 相続した不動産をすぐに売却する場合でも、登録免許税が二重に発生する。
- 取得費加算の特例や同日申請で中間省略以上の費用・期間削減が可能
相続した不動産をすぐに売却する場合、「相続登記を省略して直接買主名義にできないか」と考える方は少なくありません。
この記事では、中間省略登記が相続では原則認められない理由と、例外的に可能な数次相続のケース、さらに費用を抑える実践的な対策まで詳しく解説します。
この記事を読めば、中間省略登記の正確な知識と、相続から売却までの適切な手続き方法が理解できます。
この記事はこんな方におすすめ
- 相続した不動産をすぐに売却する予定で、登記手続きを簡略化したい方
- 中間省略登記で登録免許税を節約できるか知りたい方
- 相続登記を省略して売買登記だけできないか検討している方
目次
中間省略登記とは?相続と売買における適用可否を解説
中間省略登記の基本概念と不動産登記の原則
中間省略登記とは、不動産の所有権が複数回移転する際に、中間の所有者の登記を省略して、最初の所有者から最終的な所有者へ直接登記する手続きのことです。
たとえば、A→B→Cと所有権が移転する場合、通常はA→BとB→Cの2回の登記が必要ですが、中間省略登記ではA→Cと1回の登記で完了させることを指します。
不動産登記法では、「登記の連続性」という重要な原則があります。
これは、不動産の権利変動を正確に公示するため、所有権の移転過程をすべて登記簿に記録しなければならないという考え方です。
この原則があるため、中間省略登記は原則として認められず、各段階の権利移転をすべて登記する必要があります。
ただし、後述する数次相続など、例外的に認められるケースも存在します。
相続では中間省略登記が原則不可!数次相続のみ例外
相続によって不動産を取得した後にすぐ売却する場合、相続登記を省略して直接買主名義に登記することは原則としてできません。
これは不動産登記法の「登記の連続性」の原則により、被相続人から相続人への所有権移転(相続)と、相続人から買主への所有権移転(売買)は、それぞれ別個の法律行為であるため、両方とも登記する必要があるからです。
ただし、数次相続の場合のみ、例外的に中間の相続人の登記を省略できます。
※数次相続とは、最初の相続が発生した後、その相続手続きが完了する前に、相続人の1人が亡くなり、さらに次の相続が発生することです。
たとえば、祖父が亡くなり(第1の相続)、その相続手続き中に父が亡くなった(第2の相続)場合、祖父から直接孫への相続登記が認められます。
これは、中間の相続人(父)が相続をする権利は取得しているものの、自己名義への登記を経由する前に次の相続が発生したため、登記記録の連続性を維持しつつも、中間者の登記を経由しない形式が例外的に認められているからです。
ただし、この数次相続の中間省略が認められるのは、あくまで相続と相続の連続した場合のみで、相続と売買の組み合わせでは認められません。
売買での中間省略登記と数次相続の中間省略の違い
売買取引における中間省略登記は、平成17年の不動産登記法改正以降、原則として認められなくなりました。
以前は、A→B→Cと売買が連続する場合に、中間のBを省略してA→Cと直接登記することが慣行的に行われていましたが、現在では登記の真正を確保するため、各段階の登記が必須となっています。
ただし、一定の要件を満たす場合に限り、「第三者のためにする契約」という特殊な契約形態を用いることで、実質的に中間省略と同様の効果を得ることは可能です。
一方、数次相続の中間省略登記は、売買の中間省略とは性質が大きく異なります。
数次相続では、中間の相続人が実際に所有権を取得する前に亡くなっているため、「省略」というより「経由しない」ことが法的に正当化されます。
相続から売却への流れで中間省略登記ができないのは、相続と売買が異なる法律行為であり、相続人は一度確実に所有権を取得しているためです。
つまり、数次相続の例外は、相続同士の連続にのみ適用され、相続と売買の組み合わせには適用されません。
通常の相続から売却への流れか、それとも数次相続に該当するケースなのかを把握しておいてくださいね。
数次相続に該当するかどうかの判断も含め、まずは無料相談で専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
FAQ
Q. 中間省略登記とは何ですか?
A. 複数回の所有権移転で中間の登記を省略し最終所有者へ直接登記する手続きです。
Q. 相続から売却で中間省略登記は可能ですか?
A. 原則不可能ですが数次相続の場合のみ例外的に認められます。
Q. 数次相続とは何ですか?
A. 相続手続き中に相続人が亡くなりさらに次の相続が発生することです。
中間省略登記ができない場合の費用負担と期限
相続登記を省略できないことによる二重の登録免許税
相続した不動産をすぐに売却する場合でも、相続登記を省略できないため、登録免許税※1が二重に発生します。
費用を少しでも抑えたいと考えるのは当然のことですよね。
たとえば、固定資産税評価額※2が3,000万円の不動産を相続してすぐに売却する場合、相続登記で12万円(3,000万円×0.4%)が必要になってきます。売買登記でも60万円(3,000万円×2%)の登録免許税が必要ですが、これは買主側の負担になるケースがほとんどです。
もし中間省略登記ができれば、相続登記分の12万円を節約できると考える方もいますが、法律上これは認められていません。
さらに、令和6年4月1日から相続登記が義務化されたため、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記を省略して売買登記だけを行うことは、この義務化の規定にも違反することになります。
結果として、相続から売却の流れでは、二重の登録免許税負担は避けられず、適切に両方の登記を行うことが必須です。
※1登録免許税:不動産の登記を申請する際に国に納める税金で、相続登記の場合は不動産の固定資産税評価額の0.4%、売買による所有権移転登記の場合は2%(令和8年3月31日まで)が課税されます。
※2固定資産税評価額:市町村が決定する不動産の価格で、税額計算の基準となる金額
中間省略不可による登記費用の具体的な計算例
中間省略ができないということで、実際にどれくらい費用がかかるのか気になりますよね。
それでは、中間省略登記ができない場合の実際の費用負担を、具体例で確認してみましょう。
【ケース1】固定資産税評価額2,000万円の土地を相続後すぐに2,500万円で売却
- 相続登記の登録免許税:2,000万円×0.4%=8万円
- 売買登記の登録免許税:2,000万円×2%=40万円
- 司法書士報酬(相続登記):約5万円〜8万円
- 司法書士報酬(売買登記):約3万円〜5万円
- 戸籍謄本等の取得費用:約1万円〜3万円
- 合計:約57万円〜64万円
【ケース2】固定資産税評価額5,000万円のマンションを相続後すぐに売却
- 相続登記の登録免許税:5,000万円×0.4%=20万円
- 売買登記の登録免許税:5,000万円×2%=100万円
- 司法書士報酬(相続登記):約8万円〜12万円
- 司法書士報酬(売買登記):約5万円〜8万円
- 戸籍謄本等の取得費用:約2万円〜5万円
- 合計:約135万円〜145万円
このように、評価額が高い不動産ほど登録免許税の負担が大きくなります。
中間省略登記ができれば相続登記分の費用を節約できますが、法律上認められていないため、これらの費用は必要経費として受け入れる必要があります。
ただし、後述する取得費加算の特例などを活用すれば、税負担を軽減できる可能性があります。
相続登記義務化で中間省略の期待は完全に消滅
令和6年4月1日から施行された相続登記の義務化により、中間省略登記への期待は完全に消滅しました。
この制度では、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律で義務付けられています(不動産登記法第76条の2)。
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
この義務化の目的は、所有者不明土地の発生を防ぐことにあります。
国土交通省の調査によると、所有者不明土地は全国で約410万ヘクタール(例えると、九州の面積を上回る規模)に及び、経済的損失は年間約1,800億円と推計されています。
参考:相続登記が義務化!所有者不明土地を解消する不動産・相続の新ルールとは?
相続登記がされないまま放置されると、誰が真の所有者なのか分からなくなり、公共事業や災害復旧、不動産取引などに支障をきたすためです。
仮に「すぐに売却するから相続登記は不要」と考えても、法律上は必ず相続登記を経由しなければなりません。
手続きが煩雑で大変に感じるかもしれませんが、義務化されている以上、避けて通ることはできません。
売却が決まっている場合でも、まず相続人名義に相続登記を行い、その後に買主への売買登記を行うという二段階の手続きが必須です。
また、相続登記の義務化には過去の相続も含まれます。
令和6年4月1日より前に発生した相続についても、同日から3年以内(令和9年3月31日まで)に相続登記を申請する必要があります。
相続登記を省略して中間省略登記を試みることは、法律違反となり過料の対象となるため、必ず適切な手続きを踏むことが重要です。
相続発生から3年以内の申請期限を守りつつ、売却のタイミングも考慮した計画的な手続きが必要です。無料相談で最適なスケジュールを確認しましょう。
FAQ
Q. 相続登記の期限はいつまでですか?
A. 相続を知った日から3年以内に申請が義務付けられています。
Q. 登録免許税はいくらかかりますか?
A. 相続登記は評価額の0.4%、売買登記は2%が必要です。
Q. 相続登記しないとどうなりますか?
A. 正当な理由なく期限を過ぎると10万円以下の過料が科されます。
中間省略登記の代わりに費用を抑える3つの実践方法
これまで解説してきたように、中間省略ができない事で費用は掛かってきますが、以下の方法を取り入れることで費用を抑えることができます。
| 方法 | メリット | デメリット | 節約効果 |
|---|---|---|---|
| 取得費加算の特例 | ・相続税の一部を取得費に加算可能 ・譲渡所得税を大幅に削減 ・中間省略以上の節税効果 |
・相続開始から3年10ヶ月以内限定 ・相続税を支払っている必要あり ・税務申告が必要 |
約50万円〜100万円以上 |
| 同日申請 | ・手続き期間を半分に短縮 ・登記の連続性を維持 ・買主の早期要望に対応 |
・相続人全員の協力が必要 ・事前の綿密な準備が必須 ・同日中の申請調整が必要 |
期間短縮2週間程度 |
| 司法書士一括依頼 | ・重複作業の削減 ・窓口の一本化 ・全体の流れを把握可能 |
・事務所選びが重要 ・セット割引の内容は事務所次第 |
約1万円〜3万円 |
取得費加算の特例で中間省略以上の節税効果
例えば「相続税の取得費加算の特例」を活用すれば、登記費用以上の大きな節税効果が得られます。
取得費加算の特例とは、相続で取得した不動産を一定期間内に売却した場合、支払った相続税の一部を譲渡所得の計算上の取得費に加算できる制度です。
この特例を適用するには、相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に不動産を売却する必要がありますのでこの点はご注意ください。(相続税法第39条)。
【具体的な節税効果の例】
- 相続財産総額:1億円
- 相続税額:1,000万円
- 相続した不動産の評価額:5,000万円
- 売却価格:6,000万円
通常の計算では、譲渡所得は1,000万円(6,000万円-5,000万円)となり、約200万円の※譲渡所得税(不動産を売却した際の利益に対して課される税金)がかかります。
しかし、取得費加算の特例を使うと、相続税1,000万円のうち不動産に対応する部分(約500万円)を取得費に加算できるため、譲渡所得が500万円に減り、税額は約100万円に削減されます。
この特例による節税額(約100万円)は、相続登記の登録免許税(20万円)を大きく上回るため、中間省略登記で登記費用を節約するよりも、はるかに大きなメリットが得られます。
相続した不動産を売却する予定がある場合は、必ずこの特例の適用を検討しましょう。
相続登記と売買登記の同日申請で期間短縮
相続登記と売買登記を同日に申請することで、手続き期間を大幅に短縮できます。
通常、相続登記を申請してから完了まで1〜2週間かかり、その後に売買登記を申請するため、全体で3〜4週間程度の期間が必要です。
しかし、相続登記と売買登記を同時に準備し、同日に連続して申請すれば、登記所での処理が並行して進むため、全体の期間を2週間程度に短縮できます。
【同日申請の流れ】
- 相続登記に必要な書類(戸籍謄本、※遺産分割協議書(相続人全員で遺産の分け方を決めた合意書)など)を準備
- 売買契約を締結し、売買登記に必要な書類を準備
- 午前中に相続登記を申請
- 相続登記の受付後、同日午後に売買登記を申請
- 両方の登記が並行して審査され、約1〜2週間で完了
この方法では、登記の連続性は維持されつつ、実務上の期間を最短化できます。
特に買主が早期の登記完了を希望している場合や、金融機関の融資実行のタイミングがある場合に有効です。
ただし、同日申請を行うには、相続人全員の協力と事前の綿密な準備が必要です。
司法書士に依頼する場合は、同日申請を前提としたスケジュール調整を依頼しましょう。
司法書士一括依頼で中間省略並みの費用削減
相続登記と売買登記を同じ司法書士に一括して依頼することで、報酬の総額を削減できます。
通常、相続登記と売買登記を別々に依頼すると、それぞれの司法書士が個別に調査や書類作成を行うため、重複する作業が発生し、報酬も別々に発生します。
しかし、一括依頼することで、以下のようなコスト削減効果が得られます。
【一括依頼のメリット】
- 登記簿調査や権利関係の確認が1回で済む
- 戸籍謄本などの書類を両方の登記で共用できる
- 相続人との連絡や書類の受け渡しが効率化される
- 司法書士が全体の流れを把握し、最適なスケジュールを組める
【費用削減の具体例】
- 相続登記を司法書士Aに依頼:報酬7万円
- 売買登記を司法書士Bに依頼:報酬5万円
- 合計:12万円
↓一括依頼の場合
- 相続登記+売買登記を司法書士Cに一括依頼:報酬10万円
- 削減額:2万円
報酬の削減幅は事務所によって異なりますが、一般的に1〜3万円程度の節約が期待できます。
また、窓口が一本化されることで、手続きの負担も大幅に軽減されます。
相続した不動産をすぐに売却する予定がある場合は、最初から「相続登記と売買登記をセットで依頼したい」と司法書士に相談することをおすすめします。
多くの司法書士事務所では、セット割引プランを用意しています。
個別の状況に応じた最適な方法を選択するため、まずは無料相談をご利用ください。
FAQ
Q. 取得費加算の特例の期限は?
A. 相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に売却する必要があります。
Q. 相続登記と売買登記を同日申請できますか?
A. 可能です。同日申請により手続き期間を約2週間に短縮できます。
Q. 司法書士に一括依頼するメリットは?
A. 重複作業が削減され報酬総額を1万円〜3万円程度節約できます。
まとめ:中間省略登記は原則不可!正しい手続きで費用と期間を最適化
相続不動産の中間省略登記は、不動産登記法の「登記の連続性」の原則により原則として認められません。
例外的に数次相続の場合のみ認められますが、相続から売却への流れでは相続登記と売買登記の両方が必須です。
令和6年4月からの相続登記義務化により、3年以内の申請が法律で義務付けられ、違反すると過料が科される可能性があります。
中間省略登記はできませんが、取得費加算の特例(相続開始から3年10ヶ月以内)、相続登記と売買登記の同日申請、司法書士への一括依頼により、費用と期間を最適化できます。
特に取得費加算の特例は、登記費用以上の大きな節税効果が得られます。
相続不動産の売却に関する手続きや税金対策についてお悩みの方は、お気軽に無料相談をご利用ください。
当事務所では、数次相続の判断から取得費加算の特例適用、同日申請のスケジュール調整まで、相続登記から売却までの一連の手続きをトータルでサポートいたします。
この記事の監修者

遺産相続の無料相談
横浜市の相続・遺言に関するご相談ならあいりん司法書士事務所へ。
相続のご相談は完全無料です。【横浜駅徒歩4分】 横浜市内で財産・不動産の相続・相続放棄・終活にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
横浜での相続に精通したプロチームが、相続法務から税務にいたるまでお客様をフルサポートします。